オリフレのやつです。
px
#
埋め込み先の背景色と馴染まない場合に指定して下さい。通常は埋め込み先の背景色をそのまま利用します。
px
wikiwikiスタイルでは文字サイズやフォントが自動的に調整されます。
次のコードをWIKIWIKIのページに埋め込むと最新のコメントがその場に表示されます。
// generating...
おしらせ
タイトル背景・アイコン募集中
🐉
フレンズピックアップ企画
週間フレンズ+月刊けものを統合し、総合ファンスレとしてリニューアル
詳しい事はスレで
秋イベント
けもがたり
変則隔週日曜日 22:00~23:00 けもがたりの場所
11・12月の予定 🐸<もう今年も終わりでありますなぁ
11/3 黄色い生き物の話 モンキチョウ、キビタキ、ウデフリツノザヤウミウシなど
11/17 赤い生き物の話 アカゲザル、タンチョウヅル、ベニザケ(繁殖期)など
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
12/1 緑・青色の生き物の話 ミドリムシ、ウグイス色のメジロ、アオツラカツオドリ、マルタタイガーなど
12/15 雪と氷と生き物と ユキヒョウ、ニホンザル、アザラシ、ワカサギなど
12/29 これまでのけもフレとこれからのけもフレ プロジェクト10周年!
けもがたり保管庫
(けもがたり過去ログまとめ)
内部リンク
外部リンク
日記
2024/9/9
久々の日記更新。この前三次コラボに行ってきました。親になると子供目線で施設を見たり色々と気付きが出てきますね。
2024/12/15
熱中症になった
タグリスト
けものフレンズ (399) ユーザー参加型 (230) ネタ (183) たのしースレ (159) 雑談 (136) 二次創作 (133) 画像 (113) 協力 (109) クソスレ (107) 動物 (105) 神スレ (98) ファンスレ (91) 自然 (91) 誰得 (91) 考察 (88) けものフレンズ3 (87) どうしてこうなった (86) けものフレンズ2 (85) 豆知識 (83) イラスト (81) 楽しい地獄 (79) 癒し (78) SS (73) 動画 (73) 優しい世界 (71) ココスキ (70) アニメ (68) 歴史 (68) ゲーム (66) アプリ (63) 元動物 (59) 投稿主はIQ30以下 (59) 笑い (57) クロスオーバー (54) 質問 (51) 相談 (47) 総合 (43) 感想 (41) 音楽 (41) けものフレンズぱびりおん (33) 閲覧注意 (33) イベント (32) コラボ (32) 安価 (30) 公式コンテンツ (29) みんみ教 (26) 日記 (24) 技術 (20) 声優 (18) けもV (16) オリフレ (16) 管理用 (16) アンケート (13) ジャガーマンシリーズ (10) 実況 (10) 書籍 (10) ちくたむ (1)


ゴイシシジミに鬼ごっこで負けたあの日から3日がすぎた今日まで、私は彼女と常に行動をともにすることを余儀なくされていた。
でも今は一人。彼女の姿はない。
まだ太陽が上り初めて間もない早朝。
眠ったままのゴイシシジミの元からこっそりと抜け出してきたのだ。
でもそれは逃げるためではない。
逃げても無駄なことは、この数日間で嫌という程思い知らされた。
だから私が今一人で森の中を歩いている理由は、束縛からの解放などではなく、もっと単純な理由。
私は空腹を満たすために、未だ眠りから覚めきらぬ森の中を彷徨っていた。
「この辺のはダメかぁ……」
辺り一面に青々とした草が生い茂っているが、これらは食べられない。
毒に汚染されているからだ。
毒の有無を見分けるのはそう難しくはない。
キラキラとした光を纏っている草は間違いなく有毒だ。
一見なんの変哲もない草も、毒草の周辺に生えているものは危険性が高いから、食べない方がいい。
毒が身体に及ぼす害が大したことなければ、わざわざこんな風に歩き回って余計にお腹を空かせたりはしない。
でもこの毒は、死に至るほどの強力なものだ。
それを食べてしまったら最後、高熱で三日三晩苦しんだ後に死んでしまうという。
本当に恐ろしい話だ。
……それほどまでに致命的な毒が故に、ゴイシシジミが毒のある草を当たり前のように食べ始めた時は驚愕した。
誰も食べようとしない死の塊を、顔色一つ変えずに食べる彼女が信じられなかった。
悪食なんて言葉で言い表すことの出来ない、常軌を逸した食性。
それは明らかに……異常だった。
「食性……」
ふと嫌なことを思い出しそうになったが、今は無理にでも忘れておくことにする。
今は自分の食料の調達が先決だ。
私はより、感覚を研ぎ澄まし、注意深く毒の及ばない清浄な草を探して歩く。
そうして無心で足を動かし続けた。
気づけばそこは知らない場所。
…光の届かない暗緑の森。
どうやら、いつの間にかだいぶ森の奥の方まで来ていたらしい。
私は足を止める。
「……」
辺りはしんと静まり返っている。
木々が風に吹かれて揺れる音すら聞こえない。
ここには一切の風が届かないのか。
「それに……」
夏といえど、朝は少しだけ肌寒い。
でも今感じている寒気は、そういったものとは別の寒気。
例えるならそれは、一人で雨の中歩いていて、ふと後ろに気配を感じた時のようだった。
「……!」
なんだか既知感のある例えをしてしまった私は、慌てて辺りを見回したが、ゴイシシジミの姿は見えない。
私は少し安心した。
…だがその安心はすぐに不安に包まれる。
…………。
あまりに不気味な雰囲気に多少の恐怖心を抱き、一瞬引き返そうかとも思ったが、その考えは無情にもお腹の音に却下される。
背に腹は変えられない、ということか。
「……いこう」
私は覚悟を決めて歩き出したが、足どりは重くとても進んでいるとはいえない。
そこで私は、今感じている厄介な感情を克服するために、一人の少女のことを思い出すことにした。
それはゴイシシジミのこと。
よくよく考えたら、彼女以上に恐ろしい存在なんて他にないのだ。
もちろんセルリアンも少しだけ怖いが、倒すべき敵である以上、恐怖心よりも戦意が上回る。
だけどゴイシシジミはフレンズで、一応私の守るべき対象だ。
……だから殺すことは出来ない。
その事実が彼女への恐怖心を増長させているのは確かだが、それを除いても、彼女にはセルリアンをはるかに凌ぐ恐ろしさがあった。
ゴイシシジミに比べたらこんなの全然怖くない。
だから、……大丈夫。
「……あ…れ?」
そこで、自分がおかしなことを考えているのに気づいた。
私はゴイシシジミのことを散々怖い怖いと言っているが、今は恐怖心を押しとどめ一歩を踏み出す為の、……心の拠り所にしようとしているのだ。
……なんだか、いろいろと矛盾しているような気がする。
でも、彼女のおかげでこうして恐怖心が薄らいだのは事実で……。
……。
私は、ゴイシシジミに感謝しても良いものかと頭をひねらせる。
彼女のせいで新たな悩みができてしまったが、足取りの方は軽くなっていた。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
あれからどれだけ歩いたのだろう。
さっきまでとあまり変わらない景色から、そんなに歩いてはいないのではないかと予測する。
私はいつの間にか再び足を止めていた。

一度は収まった恐怖の感情が再発したから、というわけではない。
誰かが私をミていた。
私はただ、その視線に釘付けにされていたのだ。
同意の目。…好奇の目。……殺意の目。
それらのどれにも当てはまらない……無感情な眼。
それは、私が心に抱いていたもやもやを全て消し去ってくれた。
「ぇ……ぇ…?」
バックリと大きく開かれた、目らしき部位は、信じられないくらい真っ暗で、吸い込まれそうになる。
私は、……こんな目をしたひとを知っている。
「……ゴイシシジミさん?」
私は、瞬きひとつしないそいつに呼びかけた。
違う。違うんだ。そんなのは分かっている。こいつが彼女ではないのはわかっている。
だってこいつは……。
「……せ…セルリアン……」
こちらを捉えて離さない、無機質な眼光。
それはフレンズの天敵、セルリアンのものだった。
それを完全に理解した私は、今自分が置かれている状況も理解して青ざめる。
私は何を呑気にセルリアンと見つめあってるんだ。
……こんなに接近するまでセルリアンの存在にも気づかないだなんて。
それは、死に至りうる程に危険な油断。
今までにこんなことは一度も無かった。
本能が警告をしてくれていたから。
にもかかわらずこんな状況に陥ってしまったのは、本能が警戒を怠ったからだ。
私はここのところ、常にゴイシシジミと行動を共にしていた。
本能が拒むキケンな少女と、四六時中一緒だったのだ。
ずっと警戒を続けるなんて、そんなことは出来っこない。
私の彼女への警戒心は、段々と薄れつつあった。
最初のうちはその事実を否定し続けていたが、今では認めざるを得ない程に手遅れなことになってしまっている。
……つまり、私の本能はゴイシシジミのせいでバカになってしまったのだ。
「ゴイシシジミさん……」
私はあなたを恨みます。
ここで死んだら、もっと怨みます。
そして、もし生きて戻ったのなら文句を言ってやります。絶対に。
私はそうかたく決意し、ナイフを強く握りしめた。
まず私がすべきことは、敵を観察すること。
相手の弱点や、攻撃方法、その範囲が分かれば、こちらの勝率はぐっと上がるはずだ。
しかし、私の観察眼はあまり優れてはいない。
その理由は、今までの私の戦闘スタイルにあった。
それは、相手を敵だと判断した次の瞬間に突撃、攻撃をするというもの。
以前はそれでもなんとかなっていたが、今はこの身を守る硬質がほとんど砕け落ちてしまっていて、脆い部分が露出してしまっている。
本来鎧に守られるべきであったであろうそこを狙われてはひとたまりもない。
だから私は慎重にならざるを得なかったのだ。
私は生き残るために、未習熟な観察眼をもってして敵を観る。

セルリアンの大きさは、ゴイシシジミの身長の2倍くらい。
形状は、地面から突き出した1本の柱の上に、眼を有した頭らしきものが付いている、というもの。
頭からは触手のようなものが2本垂れていて、その先端は鋭い刃物のようになっている。
それは、敵を攻撃する以外の用途が思いつかない程に凶悪な形状だった。
…あの触手を伸ばして攻撃をするのだろう。
だとすると、今私が立っている位置はセルリアンの攻撃範囲内ということになる。
ざり……
私は、セルリアンから視線を外さず、一歩後ずさる。
セルリアンもまた、こちらを観ているのか動かない。
一歩……もう一歩。
そのようにして、ジリジリと距離を開いていく。
あと二、三歩で敵の攻撃範囲から出れるだろうと言うところで、背後に気配を感じた。
しまった、挟み込まれた……?!
私は最初、背後から感じる禍々しい気配の正体をセルリアンかと思ったが、彼女の第一声ですぐにそうではないと分かる。
「こんなところにいたのね」
それは、私のよく知る声。
その声を聞いた私は安心したと同時に、恐れを抱いてしまった。
セルリアンのほうがまだマシだと思える程に、彼女が怖い。
それは、ゴイシシジミに初めて会った時に感じた恐怖とはどこか違う。
……とにかく、私は彼女がこの場にいるということが、どういうわけか怖くてたまらないのだ。
怖いと思った時にはもう遅い。
一度恐怖に屈してしまった私は、恐怖に対して負の耐性が付いてしまっていた。
ゴイシシジミによって再びもたらされた恐怖は、あの日と同じように私の身体を縛り付ける。
体が動かない。
手足を動かそうと試みたが、やはりびくともしない。
私は、恐怖と焦りでどうにかなってしまいそうな心を無理やりに落ち着ける。
こんな時こそ冷静にならなければならない。
セルリアンは……まだ動く様子はない。
それなら、セルリアンが動き出すよりも早くこの呪縛を解けばいいだけのことだ。
私は目を閉じ、考えをめぐらせる。
私は前に一度、ゴイシシジミの縛りを自力で打ち破ったことがあったはず。
あの時はどうやって動けるようになった……?
……………………うまく思い出せない。
そもそも、何も特別なことはしなかったはずだ。
ただ動けるような気がして、そうしたら本当に動けた。それだけ。
……でも今は、それがない。
動ける気がしないどころか、絶対に動けないとさえ思ってしまいそうになる。
どうやらこの方法は望み薄のようだった。
……でも、万策が尽きたわけではない。
もうひとつだけ策が残されている。
本命はこっちの方だ。
私が常日頃から考えていた、対ゴイシシジミ用の秘策。
……それは、恐怖の原因を突き止めて、それを解消するというもの。
怖くなくなれば、自然と体の硬直も解けるはず。
実に単純な考えではあるが、その効果は絶大…のはず。
…確実性の有無について考えているほど時間に余裕はない。
私はセルリアンが活動を開始するまでに、この呪いを解かなくてはならないのだ。
私は考える。
まず、私がさっき感じたのは間違いなく恐怖だった。
次に、ゴイシシジミの声が聞こえるまで普通に動けていたことから、セルリアンに対する恐怖ではないということがわかる。
私は、ゴイシシジミの何を恐れている……?
私はあの時確か……彼女がこの場にいることが怖いと思ったはず。
彼女の存在そのものより、この状況に恐れを抱いた。
その恐れの形は、ここ数日ずっと彼女といても抱いたことのないものであった。
これまでと絶対的に違う何か。
これは考えるまでもない。
セルリアンだ。
今目の前にいるセルリアンこそが答えだ。
となると……ゴイシシジミとセルリアンが同時に存在していることで起こりうる可能性…私はそれを恐れている、ということになる。
そこまで考えたところで、私はあることを思い出した。
それは、ゴイシシジミがセルリアンとよく似た真っ暗な瞳を持っているということ。
……それは、セルリアンと彼女を見間違えてしまうほどに似ていた。
そして、あの時私は密かに思ってしまったのだ。
………彼女は実はセルリアンなんじゃないかと。
…………。
私は思考がズレ始めてしまったことに気づいた。
これではいけないと思い、本題に戻る。
すると…つまり私は……彼女がセルリアンと結託して襲いかかってくることを恐れている……?
……多分違う。
私はゴイシシジミに心を完全に許したわけじゃない。
だから、常に疑いの目は向けているつもりだ。
寝首をかかれないように、日々警戒の手をできるだけゆるめないように心掛けている。
だから彼女を疑うことなんて、今更怖くもなんともない。
彼女から実際に攻撃を受けたら、疑いかけていた本能を再び信じることが出来て、むしろ喜しいくらいだ。
今の私にはゴイシシジミを疑うことよりも、信じることの方がよっぽど怖い。
……信じることの方が……怖い。
彼女を完全に信用してしまうことによって生じる不利益……それが怖い。
もし私がゴイシシジミのことを信用していたなら、……きっと彼女は、私にとって友達と呼べる存在になっていただろう。
でも、私には彼女と友達になれない理由がある。
友達は作らないという私の信念に反するから、私は彼女とも仲良くできない。
……私が友達を作らない理由。
それは、私が強くないから。
私がセルリアンとの戦いで命を落とすのは、私の中で既に決められていることだ。
私は……自分の弱さのせいで、置き去りにしてしまった大切な友達の人生を、壊してしまうのが怖いのだ。
…………これが……答え?
私の感じている、恐怖の正体……?
でも、でもこれはもしもの話だ。
私はゴイシシジミのことを信用してはいないし、友達だとも思ってないはず……。
なのに……どうして?
私は、恐怖の原因が別にあるのではないかと思い、酷く脆弱な思考回路を再び繋げた。
すぐに頭の中をぐるぐると廻って致命的なエラーの原因を探し始める。
しかし、いくら思考を巡らせても他に答えが見つからない。
……………。
私は……彼女を信じかけている……?
そして、大切だとすら思いつつあるとしたら……。
……薄々は気付いていた。
でも、私は目を背けてしまった。
それを認めてしまったら、もう元には戻れない。
…………認めざるを得ないの……?
すっかり臆病者と成り果ててしまった私は、退路を残して中途半端に事実を認める。
私は彼女のことが……そこまで嫌いじゃないのかもしれない。
……それを認めたからといって、問題が解決される訳ではない。
呪縛から開放されるまでの過程のひとつ。
恐怖の原因を突き止めたに過ぎないのだ。
……私はこれから、どうやってこの恐怖を克服すればいい?
……………………。
私の頭はあまり良くはないのだろう。
秘策だなんて大層なことを言っていたが、一番肝心な恐怖の原因の解消方法がてんでわからない。
私は結局、策と呼ぶにはあまりにも稚拙な手段を選んでいた。
死ぬことなんて怖くない。
残された人の事なんて知るもんか。
そう自分に言い聞かせる。
声は出ないから頭の中で唱える。
ゴイシシジミがセルリアンに殺されることなんて、怖くない。
二度と会えなくなったって……全然構わない。
何度も、何度も言い聞かせる。
……しかし体は動かない。
それどころか、感情で偽ろうとすればするほど、体は心への信頼をなくし、言うことを聞かなくなる。
動け
このまま終わるなんてできない。
だから……
動け
たとえ相手が、自分に非常食の烙印を押すようなひとであろうと、私が兵士である以上守らなくてはならない。戦わなくてはならない。
動け動け動け動け動け動け動け……!
……どれだけ強く念じても、体は動かない。
私はセルリアンの攻撃範囲に入ったままだ。
そして、やつはもう観察を終えたのか既に触手を振り上げている。
身体中の感覚が遮断されたその代わりというように、その姿がより鮮明に映し出されて……。
セルリアンの触手がこちらへと迫ってきている。
それは真っ直ぐと私を捉え、命ごと貫こうとする。
尖ったものが目に飛び込み、私がもうダメかと思った瞬間……
ドンッ
私にかけられた呪縛は打ち破られた。
それも、予想外の形で。
不意に視界が傾く。
不測の衝撃を身に受けた私は宙を舞い、そして地面に叩きつけられた。
「いた……」
私はすぐに立ち上がると、セルリアンを見合った。
が、セルリアンはこちらを全く見ようとしない。
セルリアンの視線の先には……ゴイシシジミがいた。
彼女は地面にうずくまっている。
そして、その傍らには……腕、のようなものが落ちていて、…それを中心に、赤い色が広がっていた。
「そんなッ!!」
私は全ての思考を打ち切り、全力で駆ける。
私の中にはもう、生きるために必要な最低限の恐怖すらもなくなっていた。
今回はちょっと長いので分割して上げてます
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
気がつけば死地の真っ只中。
私はセルリアンとフレンズの間に割って入っていた。
「…………」
背後からは、あの無色透明な笑顔からは想像できないような濁った呻き声が聞こえる。
その声は、血の匂いを纏って痛みを訴える。
熱を持った血の匂いが、理不尽な痛みに身を縮める少女の悲痛な声が、……私を激しく興奮させる。
血が逆流してしまったような感覚。
頭が熱い。
荒くなった私の呼吸が、背後の少女のそれと重なる。
「……」
私はこれら全ての邪魔な感覚を無視する。
……身を滅ぼすような感情はいらない。
私は……この敵に本能だけで立ち向かう。
✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕✕
……それから先のことは、よく覚えてない。
無我夢中だった。
セルリアンは目の前から消え失せ、手に握っていたナイフには黒い液体がべっとりとついている。
「はぁ……はぁ………かった…?」
ふと、足にズキっとした痛みが走る。
私は痛みの方に目をやった。
いつの間にか怪我をしていたらしい。
傷口からは、脈々と血液が流れている。
その一筋の赤い流れが、私に何かを思い出させる。
"キミのためなら……こんな痛み、なんてことないよ。 "
……あるはずの無い記憶。
それは、私じゃない誰かの……痛み。
「……そうだ、ゴイシシジミさん…!」
私はまだ地面に伏せたままの彼女に駆け寄る。
「ゴイシシジミさん、大丈夫ですか……?」
私は、そんな模範的でなんの心もこもらないような、空っぽな言葉で彼女の心配をした。
大丈夫なわけがない。
片腕を失ったのだ。
「ごめんなさい……私が……」
私が次に続けようとした言葉は、目の前の異様な光景を前に霧散してしまった。
彼女は、……ゴイシシジミが…………セルリアンに切断された自らの腕を……食べていた。
一心不乱に、何かにとりつかれたように。
服が血で汚れることなんて気にせず、バリバリ、ガリガリと。
そんな恐ろしいはずの光景を見ても、私の心はなぜか落ち着いていた。
いつだったか、こんな光景をすぐ近くで見たことがあるような気がする。
詳しく思い出そうとしたところで、顔を上げたゴイシシジミと目が合った。
「あの、えっと……」
黙っているわけにもいかず、何か声をかけようとしたけど、なんて言えばいいのか分からない。
そんな私の顔を見るや否や、彼女は顔を伏せた。
「ご、ごめんね。……こわがらせ、ちゃった…わよね」
ゴイシシジミは私に謝罪の言葉を言ったが、そんなのはどうでもよかった。

彼女が顔を伏せる前に一瞬だけ見せたあの表情が、……頭に焼き付いて離れない。
今にも泣き出してしまいそうな…潤んだ瞳。
それは、私が恐れ、嫌ったあの少女のものとは思えないくらいに弱々しいものだった。
「ゴイシシジミさん……、」
「そ、そんなことより! ……あなた意外と強いのね。びっくりしちゃった」
私が言おうとした言葉は、彼女に遮られてしまった。
それは、彼女から私への初めての拒絶。
私は彼女に拒絶されて、……少し安心してしまった。
あのままでは、私はまた心無いことを言っていたかもしれなかったから。
「ぁ……、…………」
彼女の言葉から何も言われたくない、という意思が見えたので、それ以上は何も言えなかった。
……この時私は、なにか言葉をかけてあげるべきだった。
彼女は明らかに傷ついていたのに……。
後悔した私は、これ以上後悔しないようにと言葉を紡ぎ出そうとする。
「あの、腕……」
「…………私は……あなたと同じフレンズよ」
ゴイシシジミは、"両手"でスカートの裾をぎゅっと掴んで言った。
彼女は俯いていてその表情は伺えなかったけれど、見なくても分かる。
さっき一瞬だけ見せた表情。
あの……今にも泣き出してしまいそうな、弱々しい顔。
今の彼女はきっとそんな顔をしているのだろう。
何か言葉をかけなければ。
……でも、こんな時なんていえばいいのか分からない。
あれでもないこれでもないと考えあぐねているうちに時間が過ぎていく。
そうしてようやく思いついた言葉を口にしようと顔を上げた時には、もう…遅かった。
ゴイシシジミはもう顔を上げていて、彼女がいつもそうするように
柔らかく微笑んでいた。
…………ごめんなさい。
ーーーーーーーーーーーーーーー
あの後、ゴイシシジミは無毒な草を探すのを手伝ってくれた。
その間、彼女はいつにもまして口数が多かった。
綺麗な花を見つけた時や、私のお腹が鳴った時。
ことあるごとに話しかけてきた。
私はその度に相槌を打って、笑顔を作ったりしてみた。
そうして、二人で歩いているうちに水の流れる音が聞こえてきた。
音のほうへ行くと、そこは川。
川辺に生えていた草は毒のないものばかりで、私はようやく空腹を満たすことが出来た。
私が食事をしている間、ゴイシシジミは川で服に付いた血を洗い落としていた。
彼女は私が見ていることに気づくと、笑顔を作り、少しだけ手を上げてこちらに振った。
私は同じように手を振り返すと、あまり邪魔するのは悪いと思い、それ以上彼女を見ないようにした。
私が食事を終え、足に付いた血を川で洗い流していると、ゴイシシジミが来た。
どうやら服を洗い終えたらしい。
血で赤く染まってしまっていた部分も、今では元の白さを取り戻している。
それぞれの用事を済ませた私たちは、これからのことについて話し合った。
そして、暗くなる前に南森に戻ろうということになった。
南森とはその名の通り、島の南の方にある森だ。
ゴイシシジミ曰く、南森が一番セルリアンが少なくて安全なのだと言う。
・・・・・・・・・・・・・・・
南森への帰り道。
ゴイシシジミの口数は少しだけ減ったが、相変わらず私に話しかけてくれる。
何にもなくても私の名前を呼んだりする彼女だったが、彼女がいつもしてくる、急に抱きつく等の過度なスキンシップをしてくることはなかった。
それどころか、私が一歩近づくと彼女は一歩離れる。
私が怪訝な顔をしているのに気づいた彼女は、「ほら、これ…臭いから……ね」と言って申し訳なさそうに右の袖を摘んで見せてきた。
そこは、彼女が特に念入りに洗っていた部分。
血の汚れはほぼ完璧に落とされていて、今では見る影もない。
…だけど、うっすらと血の匂いが残っていた。
ゴイシシジミの言葉を聞いて、そんなことか、と思った私は彼女に一歩歩み寄る。

すると彼女がまた身を引こうとしたので、腕を掴んで阻止してやる。
すると、掴んだ右手は少しの抵抗を見せた後、やがて大人しくなった。
私の束縛を受けたゴイシシジミは、何が起こったのか分からず理解が追いつかない、というような顔をしていた。
これで彼女にも、こちらの気持ちが少しは分かるだろうか…?
…………。
何故こんなことをしたのかは自分でもよく分からない。
ただ、そうしたいと思った。
……私の頭はどうかしてしまったのかもしれない。
でもまあ、珍しく動揺するゴイシシジミが見れたから別にいいか……。
「……さ、ささ、ささこ…? これ……なに…?!」
彼女の問いかけに私は答えない。
「早く帰りましょう」
・・★・・*・・★*●・★・・★・*・・*★・・*
私がゴイシシジミの手を引き、南森に着いたのは日が沈んだあとのこと。
こんなに遅くなってしまったのは、ここへ向かう途中、急にゴイシシジミがウトウトとし始めたからだ。
彼女の足取りが急に不確かになったのに気づき、私が振り返るとそこには……立ったまま寝るゴイシシジミがいた。
信じられなかった。
私がこの手を離して一人で帰ったら、一体どうするつもりだったのだろうか…?
結局私は彼女のことを起こすに起こせずに、半ば引ずるようにしてここに戻ってきたのだ。
・・・
あたりはもうほとんど真っ暗だ。
私がゴイシシジミを"いつもの木"の下に寝かすと、彼女はすぐに寝息を立て始めた。
無防備に眠るゴイシシジミの背中が、星明かりに照らされている。
今日は色々あって、疲れたのだろう。
私はその背中をぼんやりと見ながら、今日のことを思い出していた。
…………。
彼女は言った。
同じフレンズだと。
今にも泣きそうな顔で、泣いているような声で言った。
私はその彼女の言葉を疑いはしない。
……だけど、私は一度、彼女のことをセルリアンではないかとまで思ってしまった。
あの言葉を聞いた時、私の心は彼女にとても酷いことをしてしまったという罪悪感でいっぱいだった。
故に、言葉の意味を深くは考えられなかった。
でも今ならなんとなく分かる。
……ゴイシシジミはあの時、私に拒絶されるのが怖かったんだと思う。
私はずっと、彼女の上辺を見て拒絶していた。
彼女のことを得体の知れないひとと称し、恐れていた。
そんな時に、いきなり彼女の本質を見てしまった。
多分あの時私に見せたのが、ゴイシシジミの本当の姿なんだと思う。
私が本当のゴイシシジミを拒絶してしまったら、……彼女はきっと一人ぼっちになってしまう。
……ずっと一緒にいた私だから分かる。
だって、…あんなにも怖いのだ。
彼女の誰よりもやさしい心が見えなくなってしまうほどに……怖いんだ。
……もしかして彼女は、今までずっと、みんなから怖がられて拒絶されてきたのではないか…?
現に、ゴイシシジミと他の誰かが一緒にいるのを見たことがない。
彼女の唯一の友達がいなくなってしまった今、残されたのは……私だけ。
「なんで私なんだろう……」
私はなんの変哲もないただのフレンズ。
特別やさしい訳でもないし、……むしろたくさん酷いことを言った。
でも、彼女は私と一緒にいる。
……。
私は……ただのフレンズ。
彼女の友達に似ていたからって、それは変わらない。
そしてゴイシシジミは……切られた腕が新しく生えてくるだけの、一人のフレンズ。
同じ……フレンズ。
フレンズ……か。
前に、フレンズというのはどこかの言葉で、友達と言う意味があると聞いたことがある。
「友達……」
友達を作るのが怖くて、逃げてしまった私と
決して一人になるまいと、懸命に努力する彼女
なんだ、ゴイシシジミは私なんかよりもよっぽどフレンズらしいじゃないか。
そこでようやく気づく。
ああ……そうか。
逆だったんだ。
普通じゃないのは私の方。
今までずっと、必要以上に他者と関わろうとしなかったから、気づけなかった。
……こんなフレンズらしからぬ私を受け入れてくれるのは、きっと彼女くらいなんだろうな……。
……私が彼女のことを拒絶しなければ、傷つけなければ、……ずっと一緒にいてくれるのかな…?
「ふわぁ……」
ふと、あくびが出て、直前に考えていたことも一緒に頭の外に出ていってしまう。
半分くらいは出ていった気がする。
私は随分と考え込んでしまったと思い、寝る準備を始めようとした。……準備と言っても横になるだけなんだけど。
しかし、まだ眠ることは出来そうにない。
ゴイシシジミの様子がおかしいことに気づいたのだ。
彼女は寝息に混じってうめき声を上げている。
何事かと思い、正面に回り込んで彼女の顔を見ると、どうやらうなされているようだった。
怖い夢でも見ているのだろうか……?
……。
起こした方がいいのかな…?
「…………いか…ないで………」
「!?」
どうしたものかと考えあぐねている時に、急に声が聞こえたものだからドキッとした。
……それはただの寝言だった。
ただの寝言なのに……。
ふいに彼女が晒した彼女の内側は、とても悲しい色をしていて……。
私は無意識に、ゴイシシジミの頭を撫でていた。
すると、一雫の涙が彼女の頬を伝った。
……。
彼女が決して見せようとしなかった涙を盗み見てしまったという罪悪感が胸を刺す。
……………………………………。
……起こすのを躊躇ってしまう。
彼女の寝息を聞いてしまったから。
……やめておこう。
今起こしたところで、どんな顔をすればいいのか分からない。
それに今無理に起こしてしまえば、彼女の見た夢を、彼女自身の記憶に留めてしまうことになりかねない。
夢なんて、目が覚めれば自然と忘れてしまうもの。
どんなに悲しいことも、嬉しい気持ちも、等しく、長くは留まらない。
時には、それが寂しいと感じることがあったりもするけれど、その寂しさもその時限りのものなんだ。
……だから、私は見て見ぬふりをするの……?
だって、私にできることは何もないから。
……本当に私にできることはないのかな?
そんなことを考えながらゴイシシジミをみていると、彼女が微かに震えていることに気づいた。
寝言と涙に気を取られていて、全然気が付かなかった。
「寒いのかな…?」
それなら、と思い私はゴイシシジミの背中側に回り、横になった。
そして、彼女の背中に自分のそれを重ねる。
…………。
背中を通じて、彼女の体温や震えが伝わってくる。
でもそれは、今だけのこと。
やがて、彼女の体の震えは収まり、やさしい体温だけが残る。
今なら、ゴイシシジミのことを少しは理解出来るかもしれない。
明日からはもっとちゃんと彼女の話を聞いて、仲良くなる努力をしよう。
そうすれば、いつか本当の友達にもなれるかもしれない。
私は、これからの彼女との接し方について、あれやこれやとかんがえようとしたけど、でも……だけどいまは、……ただ、……ねむい。
「おやすみなさい……」
・・・・・・・・・・・・・・☀︎・・
……朝日が眩しい。
私が人生で一番の深い眠りから覚めると、まだ背中が暖かい。
私よりも早く寝たはずのゴイシシジミはまだ寝ていた。
「くわぁ〜」
背中の方でモゾモゾ動く気配がする。
私が大きな欠伸をすると同時にゴイシシジミが目覚めたようだった。
「んぅ……何してるのぉ……?」
ゴイシシジミは目をこすりながら、寝起きの、へにゃへにゃな声で私に問いかけた。
「ゴイシシジミさんが寒そうだったので……」
私ががそう言うと、ゴイシシジミもまた、大きな欠伸をした後、少し口元を緩めて言った。
「……あなたがそれを言うの?」
ゴイシシジミはそう言うと、おもむろに自分のマフラーを脱いで私の首元に巻いてきた。
「あの、これ……」
「寒かったんでしょ?」
「いえ、私は全然……」
「遠慮しなくてもいいのよ。私も気になってたから。そんな格好で寒くないわけがないわよね」
私が否定しようとしまいと、彼女には関係ないらしい。
このままでは本当に、この暖かくてモフモフな夢のような物体を押し付けられてしまうかもしれない。
「あの、私ほんとうに…!」
「それに、……貴方が寒さで死んじゃったりしたら、私も困るもの」
言葉を遮られて、最後まで言わせてもらえない。
ちょっとムッとした私は、少し意地悪な返しをすることにした。
「非常食ですか?」
私は、かつて最も恐れた言葉を言った。
でもこの言葉には、もう恐れや敵意の意味は無い。
私はただ純粋に、彼女とのコミュニケーションを楽しんでいた。
「そうよ? それに今貴方が死んじゃったら私、退屈すぎて死んじゃうわ」
ゴイシシジミはそう言って、幸せそうに笑う。
そんな顔をされると、もう要らないだなんて言えない。
…………………………………………。
……私は仕方がないのでこのモフモフを甘んじて受け入れることにした。
「後で返して欲しいって言っても、返してあげませんからね」

尊さが溢れて、感想の語彙が蒸発しそうです
各挿絵からは文章にマッチしたイメージが伝わってきました
緊迫感のある戦闘シーンが二人で苦難を乗り越えての休息の時間を引き立てていて、SS書きとしてもこれ以上ない良い例として勉強になりました
あと、戦闘シーンもそうですが、ササコが自分自身の感情を冷静に分析したのもその後の心理に影響したのかな?と考察もできて、読んでいて非常に楽しめました!
完結まで楽しみです!
いつも感想ありがとうございます
少し時間がかかってしまうかもしれませんが、必ずや完走してみせますので、それまでどうかお付き合いくださいませ
このssがひと段落したら、ダァッたーさんの書かれているssを是非!読ませていただきたいと思うてます🐓
ものすごいテキストの量でびっくしりました セリフ少ないのに心理描写でうまく展開を進めていてすごい
手に汗握るセルリアンとの攻防、そしてササコちゃんの心の中に変化が芽生えつつありますね
今後の展開にも目が離せないぜ👀
お褒めに預かり光栄です
実を言うと、キャラクターのセリフを考えるの結構苦手でして……
なので心理描写をできるだけ詰めて何とか補っているといった感じですね
そして、セルリアンとの戦闘は完全カットです(戦闘描写も苦手科目)
ササコちゃんがこの先どう変わっていくのか、その辺も注目していただければなと思います
あれからというもの、私は一度もセルリアンに遭遇していない。
…危険が無いのはいいことだ。
でも私は、平穏な日々がずっと続いていることに、焦燥を感じ始めていた。
このまま、ゴイシシジミとの安らかな日常に、かまけていていいのだろうか…?
これではいつか、…大変なことになってしまう気がする。
もし、……私が今以上に弱くなってしまったら…。
私は、いつしかゴイシシジミが見せた悲しい顔を思い出す。
私が弱かったから、彼女を深く傷つけた。
それに、……それだけではない。
彼女の、苦痛を纏った呻き声。
地面に散ってしまった、彼女の生きてきた時間。
赤く汚れてしまった、やさしい笑顔。
それら全ては、私の無力によってもたらされたものだ。
……次は、あれだけでは済まないかもしれない。
私は目を閉じ、最悪な未来を想像する。
……真っ赤に染まった視界。
私は、血と吐瀉物の混ざった、汚らわしい水溜まりの中心に立っている。
そして、もう決して元には戻らないであろう潰れた肉の塊を見下ろして、呼びかけるのだ。
何度も。何度も。
喉が潰れて、声が出なくなるまで。
ずっと、ずっと…呼びかける。
そうして、喉が裂けてようやく静かになった時に初めて、彼女のやさしい声を思い出す。
でもそれは、過ぎ去った記憶の断片に過ぎない。
私がいくら涙を流しても、誰もやさしく慰めてなどくれない。
泣いて、泣いて、時間だけが過ぎてゆく。
…それなら、私の涙はいずれ赤く染まるだろう。
そして、赤い涙に呼応するように、真っ赤な雨が降り出す。
その熱い雨粒が、私の大切だったものをどろどろに溶かしてしまうんだ。
そこには、一つを除いて何も残らない。
……そこに残ったのは一本の錆びたナイフ。
私はそのナイフを……。
……そんなのは、絶対に嫌だ。
おぞましい想像をしてしまい、吐きそうになるのをぐっと堪える。
ここで吐くわけにはいかない。
吐いて、スッキリなんてしてたまるか。
最悪の事態の想定は、常に頭の片隅に住まわせておかなくてはならないのだ。
私の吐き気が収まった頃、前を歩いていたゴイシシジミが足を止めた。
……そうだ、私は今彼女に連れられて、新しい寝床を探すために歩いていたんだった。
確か……気分転換がしたいとか言っていた気がする。
私が彼女に、別に今のままでいいと言っても聞き入れては貰えず、結局今こうして歩いていたのだった。
「あ、ちょっと待って」
立ち止まったゴイシシジミはそう言って、私を手で制する。
彼女の顔を見ると、少し強ばった表情で茂みの奥の方、一点を見つめていた。
「ゴイシシジミさん、あっちに何かあるんですか?」
私はゴイシシジミの制止の手をくぐり抜けて、彼女の視線の先を見た。
……茂みの奥の方に、フレンズよりも大きめの影がひとつある。
「……セルリアン、ですか」
「ええ、だから別の道を……」
ここで彼女の提案を受け入れてしまえば、私の想像が現実になる日がいつか訪れてしまうかもしれない。
だったら、ここは彼女の言葉を無視してでも戦うべきだろう。
「私が行って倒してきます」
「だめ!」
私がそう言うやいなや、ゴイシシジミが語気を強めてそれを否定した。
静かな森に、彼女の声が響く。
……そんな不用意な彼女の大声に反応して、セルリアンがこちらの存在に気づいてしまった。
「あなたは下がっていてください」
私は少しだけ言葉に不快感を込めて言った。
だが彼女はそんなの意に介さないという風に、またもや私の言葉を否定する。
「だめよ。あなたも一緒に逃げるの」
ゴイシシジミはそう言うと、セルリアンに背を向け走り出す。
私もその後に続く。
左腕を掴まれていたから、私も走らざるを得なかった。
私が立ち止まれば、彼女も立ち止まるだろう。
もしそうなれば、二人ともみちずれになってしまう。
…仕方がないので、私は走りながら彼女に抗議することにした。
「なんの…つもりですか…! 離してっ…ください!」
「嫌よ…!」
「私は兵士なんです! ……だからっ敵を前にして、逃げるなんて……出来ません…!」
私が言ったのは完全なでまかせだった。
兵士だから戦わなくてはならないと言ったような使命感なんて、本当はもうどこにも残ってはいない。
それはある日を境に、消えてしまったのだ。
「そんなの!…知らないわっ……無駄口叩く余裕があるなら……もっと速く走って!」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「どうして、行かせてくれなかったんですか……?」
私は、両手を膝につき肩で息をするゴイシシジミに問いかけた。
その言葉には、少しだけトゲが含まれていたかもしれない。
「どうして、って……だってあなた、怪我してるじゃない」
ゴイシシジミはそう言うと、私の左足を指さす。
それを知っていたのなら、急に走らせないで欲しい。
そんな私の思いが伝わったのか、ゴイシシジミは少し困ったような顔をした。
「こんな怪我、生きていれば誰だって……」
私はそう言いかけて口を噤む。
私の言おうとしたことが必ずしも正解ではないことは、ゴイシシジミの全身を見ればわかる。
「いい? 逃げられる時は、逃げるの」
「…………」
「返事は?」
急に押し黙った私を見て、彼女は少しだけ口を尖らせてそう言った。
「納得できません」
「納得できないって……。…とにかく、私の言う通りにして」
「……できません」
「あなたが頷くまで、何度だって言うからね」
今日はゴイシシジミが妙に食い下がってくる。
でも、私も考えを改めるつもりはない。
互いに一歩も引くつもりがないせいで、会話はずっと平行線を辿っている。
…このままだと、このあまり楽しくない会話をいつまでも続けることになってしまう。
それは嫌だ。
せっかくなら、私は彼女ともっと楽しい話をしたい。
だから私は、うまく話題をそらせるような一言を考える。
ゴイシシジミは意外と押しに弱く、流されやすいところがある。
だから、そこをつく。
なんとか話題をすり替えて有耶無耶にして、早々に話を切り上げてしまおう。
……しかし、並大抵な話題の転換では、今の強情な彼女には通用しないだろう。
何か、ゴイシシジミが反応せざるを得ないような言葉は……。
私は少し考えて、その言葉を思いついた。
でもこれはちょっと……いや、かなり失礼な一言だ。
でも、これくらい言わないと話を聞いてくれない気がする。
うーん……………。
「…………仕方ないか」
「…? わかってくれた?」
ゴイシシジミの心底安心したような表情が痛い。
私は今から、この柔らかく微笑む無防備な彼女に、ひどいことを言おうというのか…。
……後でちゃんと謝ろう。
私は覚悟を決め、そのとんでもない一言を口にする。
「ゴイシシジミさん、なんか血なまぐさい…です」
「ぇ………………」
一瞬のうちに空気が凍りつく。
言った瞬間、私はしまったと思った。
だけど、もう手遅れ。
口から出た言葉は戻らない。
ゴイシシジミは口の端を不自然に吊り上げ、目を見開き瞬きひとつしない。
彼女はそのなんとも言えない表情のまま、完全に固まってしまっていた。
これは絶対に、私が悪い。
「ご、ごめんなさい! 今のはほんの冗談で……。というか! …そんなに嫌いな匂いじゃないって言うか、…むしろ好きなくらいで……」
私は何を言っているんだ……。
直前の無礼な発言を謝り、なんとか取り繕おうという私の試みは失敗に終わった。
……というか、今の彼女には私の声すら聞こえてすらいないようだった。
ああ、私はなんてことを…。
さっきまで固まったままだったゴイシシジミは、今は少しだけ違った様子。
彼女はわなわなと震え、しきりに瞬きをしている。
これは私の言葉を完全に理解し、怒りに打ち震えているということか。
そんなゴイシシジミの様子を呆然と眺める。
……私は、彼女がかつて私に言ったあの言葉を思い出していた。
"あなた、そんな事ばっかり言ってると、いつか殺されちゃうわよ?"
……これは殺されても文句は言えないな。
というか、もういっそひと思いに殺っちゃってください…!
私が死を受け入れる風なことを口走りそうになった時、顔を赤くしたゴイシシジミが口を開いた。
「も、もう! ひどいこと言わないのっ…! 」
「ぁ、…はい。ごめんなさい」
……怒られた。
彼女は少し眉を吊り上げていたが、それは直ぐに水平になる。
なんだか神妙な面持ちだ。
「…あなたはどうして、そんなに死に急ぐの?」
ゴイシシジミは小さくため息をついて言った。
「私は…死に急いだりなんかしていません」
「そう、自覚がないのね」
「自覚がないも何も、…私は本当に……」
「あなたがそのつもりでも、私には死にたがっているようにしか見えないわ」
「………………」
「あなたが死んで悲しむ人もいるのが分からないの?」
ゴイシシジミが私のことを何もかも分かったかのように言ってくる。
でもそんなのは、ただの勘違いにすぎない。
だから私は断固とした口調で言ってやる。
「いませんよ」
「…何?」
「私が死んでも、悲しむ人なんていません」
「そ、そんなことないでしょ? …きっと誰か……」
「そんなことありますよ? …だって私、友達とか一人もいませんから」
「私は……ん…」
「初めて会った時、言いましたよね? 友達は作らないって」
「それは…聞いたけど……」
ゴイシシジミは少し俯き、言葉を続ける。
「でも、どうして? ……あなたはどうしてそんなにも、…一人になろうとするの?」
「…だって、私は兵士なんです。…兵士に友達なんて、必要ないから……」
自分でも分かっている。
こんなの友達を作らない理由になんかならない。
咄嗟に口から出たでまかせだ。
そのことは彼女にも見透かされているようで、「本当に…?」と言って私の目をじっと見つめてくる。
「兵士だとかそんなのは抜きにして、あなたの言葉を聞きたいわ」
「……………」
なんと言えばいいのか分からず、私が言葉に詰まっていると、ゴイシシジミが小さな声で呟いた。
「…怖いのね」
「……ぇ…?」
私は彼女の言葉を聞いて、ひどく動揺した。
なぜなら、それは本当のことだったから。
「私には、あなたが友達を作ることに怯えているように見えるの」
ゴイシシジミは「違ったらごめんね」と一言付け足して、更に続けた。
「教えて。…死ぬことよりもこわいことって何? 」
彼女は真っ直ぐな目で私を射抜く。
逃げることなんて許さないと言うような、そんな視線。
……いや、違う。
きっとこれは私自身によってもたらされた錯覚。
ここで私が返答を拒んでも、きっと彼女は許してくれる。
でも私の心が、それを望んでいないのだ。
私は、…彼女に本当の私を知ってほしい。
彼女が私の内面を見て、どう思うのかを知りたい。
だから、私は……。
私は、彼女に本心を打ち明けることにした。
「……私は、自分の失敗で誰かが傷ついたり、悲しんだりするのが…こわいんです」
私はぽつりぽつりと話し始めた。
「私は今までに何度もセルリアンと戦ってきました。…時には、誰かを守るために。私は、それが自分の使命だと思っていたし、何も疑問を抱くことはありませんでした。……でも、そんな私の…愚かしい思考停止の日々が、いつまでも続くことはありませんでした。ある日、私は気づいてしまったんです。………私が、知らず知らずのうちに、…みんなを傷つけていたことに。……本当はもっと早くに気づいていたのかもしれませんが……。きっと私は、ずっと見て見ぬふりを続けていたんでしょうね。……私が、目を背けたかったもの…。それは、命を賭して守ったその人の…顔でした。……戦い、傷ついた私を見て、みんな悲しい顔をします。…中には、責任を感じて自分を責める人もいました。…そんなやさしい人たちがもし、…もし私が死んだことを知ってしまったら…? ……想像するだけで、胸が…潰れそうなほど苦しくなりました。……それからです。私が、誰とも上手く話せなくなったのは。……喋り方だって、最初はこんなんじゃ…なかったんです。………次第によそよそしい態度になっていく私に、みんなは今まで通りに、優しく接してくれました。……でも、私はその優しさから逃げてしまったんです」
「……どうしてって、訊いてもいいかしら?」
それまで黙って私の話を聞いてくれていたゴイシシジミが、遠慮がちに質問をしてくる。
「簡単な話ですよ?…私にはその優しさが耐えられなかった。…それだけです。…あ、でも私は後悔なんてしてませんよ。だって、あのまま一緒にいれば……私はきっと、この命が尽きる日までずっと、後ろめたさを感じて生きていくことになっていたでしょうから」
「そんなの……」
ゴイシシジミはどうにも腑に落ちないという顔をしていた。
だから、私は最後にこう言った。
「心に一生消えない傷を負わせる。きっとそれは何よりも罪深いことなんです。だって、…悲しいのは、時にセルリアンよりも厄介なんですよ。悲しみはその人の人生そのものを、不幸なものにしますからね」
「…………」
ゴイシシジミは俯き、何かを考えているようだった。
やがて、何かを思いついたのだろう。
彼女はその言葉を、俯いたまま口にする。
「私には、あなたが自分の手を汚したくないだけの偽善者に見えるわ」
「そうですね。…その通りです」
私はてっきり、ゴイシシジミは私の考えを理解して受け入れてくれると思っていた。
自分でも随分とムシのいい話だとは思う。
でも、彼女ならと期待してしまっていた。
だからだろうか…。
彼女の意見を聞いた時、私は少しだけ落胆してしまったのだ。
「大体ねえ、…拒絶されれば誰だって悲しいの。傷つくの。あなたにはそれが分からないの?」
ゴイシシジミはさっきのように俯きがちにではなく、真っ直ぐとこちらを見て言った。
彼女の表情は誠実そのものだったけれど、言葉の端々には怒りの感情が込められていて、気圧されそうになる。
私もそれに負けじと、声を出す。
「そんなことは分かっています。でも、大切な友達を失った時に感じる悲しみに比べれば、幾分かマシなはずです」
「そんなの……誰かを傷つけていい理由にはならないし、悲しい気持ちに上下を付けるなんてもってのほかよ」
「それは……」
彼女の言い分は至って正しい。
だからこそ、言葉を重ねれば重ねるほどに、私が理屈だと思い込もうとしていたものは紛れもない屁理屈になってしまう。
「じゃあ、私はどうすればよかったんですか?」
ついにどうしようもなくなった私は、投げやりに言った。
それを聞いたゴイシシジミは、ゆっくりと立ち上がると、私の背後に回る。
そして、私を無理やりに立たせ、また正面に回ってきた。
「あなたに今必要なのはお説教じゃないみたいね…。ついてきて。教えてあげるから」
彼女はそう言うと私の前を歩き出した。
今回も分割して上げてます
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「あの子がいいわね。ほら、来て」
「何をするつもりですか…?」
ゴイシシジミの視線の先には、一人のフレンズがいた。
それは見覚えのある姿をしていて、この間私に友達になりたいと言ったあの子だった。
……なんだかすごく嫌な予感がする。
「ほら、行くわよ」
ゴイシシジミはそう言うと、私の腕を引っ掴んでグイグイと引っ張った。
「ち、ちょっと待ってください!」
私はその場に踏み留まろうと、足に力を入れた。
…しかし、その行為が身を結ぶことはなく、靴が地面にすれてザリザリと音を立てるだけだ。
「っとお…!どこが非力なんですかぁ……まって!本当に待ってください…!」
私の抵抗は空しく、とうとうゴイシシジミが立ち止まることはなかった。
…今、ゴイシシジミの背中の向こうにはあの時の少女が……。
「あなた、ちょっといいかしら?」
「わたし?」
「そう、あなたよ」
「わたしに何か…ひゃうっ!」
「どうしたの? 急に素っ頓狂な声なんか出して」
「あ…あのあの…あなたもしかして……ゴイシシジミさん、ですか…?」
「そうよ? 初めまして」
「…た」
「た?」
「たたたたべないでください!!」
「はあ…別にあなたを食べたりなんてしないわよ」
「ぅうわたしなんてつぁべてもおおいしくにゃいれすよぉおお!!!!………へ? たべない…ほんとうに…?」
「ええ、約束するわ」
「よ、よかったぁ〜」
私はゴイシシジミに腕を掴まれていたため逃げることも叶わない。
だから今の私にできるのは、二人の会話に耳を傾けるか、観念したように項垂れるかのどちらかしか無い。
そこで私が選んだのは、それら両方だった。
私は、項垂れつつ二人の会話に耳を傾ける。
「えっと……今日はあなたにお願いがあって来たの」
「お願い?もしかしてたべ…」
「食べないから。…実はこの子と友達になってあげてほしいの」
「ともだち!?もちろん!!いいよ!!」
……なんだか妙に興味深げな視線を感じる。
私が顔を上げると、ゴイシシジミの肩越しにあの少女と目が合った。
「あ、その子…」
少女の見せた残念そうな顔が、あの時の彼女のそれと重なる。
…私はまた、この子をがっかりさせてしまったのだ。
「どうしたの?」
「前に会った時に、友達にはなれないって…」
「あなたねぇ…もうちょっとマシな言い方はなかったの?」
「……」
ゴイシシジミはそう言うと、私を少女の前に立たせようとしたが、私は彼女の背中にしがみつき、抵抗をする。
恥ずかしいからとか、そんなんじゃない。
私の存在が彼女の表情を曇らせてしまっているのだから、このまま隠れていた方がいいと思った。
…本当に、ただそれだけのこと。
「しょうがない子ね…」
ゴイシシジミは、まるで聞き分けのない子供に呆れたというような声色で言った。
「ねえ、貴方に聞きたいことがあるの」
「なぁに〜?」
少女の声から、先程の嬉々とした様子とは打って変わってしゅんと落ち込んでしまっているのが分かる。
…そんな少女にゴイシシジミは、更に気分が落ち込んでしまいそうな質問をぶつける。
「あなたは、もしも仲良しの友達が突然いなくなっちゃったら…悲しい?」
「当たり前だよー」
「だったら、悲しい気持ちになるくらいなら最初から出会わなければいいとか思うかしら?」
「ううん、思わないよ? だって会えなきゃ一緒にお話できないし、一緒に遊んだり、ご飯食べたりも出来ないもん」
「ですって。あなたはこれを聞いてもまだ、自分の気持ちだけを尊重して、友達にならないなんて言えるの?」
「ぁっ……」
気づくと私の眼前には、あの少女が立っていた。
二人の会話に気を取られていた私は、ゴイシシジミの背中にしがみつくのを忘れてしまっていた。
…そのため、私はいとも容易く少女の前に引きずり出されてしまったのだ。
「…………」
私が俯き何も言わずにいると、ふいに誰かに背中を押された。
振り返ると、私の背中を押した犯人であろうフレンズが穏やかな笑みを浮かべている。
私はその顔を見て少し安心した。
……安心したはいいけど、私はこれからどうすればいいの…?
「……えっとね」
私が焦りと緊張でどうにかなってしまうかと思われたその時、声が聞こえてきた。
ゴイシシジミのものとは違う声。……あの少女の声だ。
それはゴイシシジミよりかは落ち着きのない声だったけれど、それでもやさしい声音だった。
…そして、その声は私に向けられたものらしい。
私がそれを認知したのを悟った少女は、更に声を発した。
「ずっと考えてたんだ。何かきみを怒らせるようなことをしちゃったんじゃないかって。…でも、わたしは馬鹿だから、どんなに考えても……何も分からなくて……。……だから知りたいんだ。知って、謝りたい。きみは何にもないって言うかもしれないけど、わたしは……」
「ちょっと待ってください。その、……あなたは本当に……何も悪くなくて………………」
私は慌てて少女の言葉を遮った。
悪いのは私なのに、彼女は私に謝ろうと言うのだ。
それを認めてしまったら、私は本当にどうしようもないやつになってしまう。
……だから、彼女の謝罪の邪魔をしたのに……。
……なのに、それに続く次の言葉が出てこない。
「……ゎ、…わた………は………………」
「わたし、きみとちゃんと話したい。ちゃんと話して、やっぱりきみと友達になりたいよ…」
少女は真剣な目をして言った。
私はその目を見て、彼女の言葉に嘘偽りが無いことを悟る。
……私は、…彼女の期待に応えたい。
あの時の私の選択は間違いだったと、ゴイシシジミが教えてくれた。
…だから私は、今度は間違えないようにと、ちゃんと聞いて考えた。
……それを今から、言うんだ。
私は目を閉じ、深く息を吸い込む。
「…わ、……たし、は、…………ほんと…うは、……たしも、…………あなた…と、と友達…に、…なりたい……」
一息で全部言うつもりだったのに、途中で酸素が足りなくなって、何度も言葉が途切れてしまう。
さらには、声は震えていて、自分でもなんて言ったか分からないほどだった。
……それなのに、彼女には私の言葉がちゃんと伝わったようだった。
「じゃあ、わたしたちはこれで友達だね。わたしはチャコウラナメクジ。チャコちゃんって呼んでくれると嬉しいな」
「…わ…た………ぅ…」
私も自己紹介をしようとしたけど、上手く声が出せない。
それどころか、声のかわりに涙が溢れてくる始末だ。
……私は、泣いてしまっていた。
「わ!…ご、ごめん!……わたし、何かしちゃった…?!……あ…きみ、怪我してる。…もしかして痛むの?」
「い……が…ぁ………」
違う。
あなたのせいじゃない。
傷だって、もう痛まない。
そう言いたいのに…言えない。
声を出そうと開けた口から、大量の涙が入ってくる。
……不味い、泣きたい。
そんな私のあまりの取り乱しっぷりを見かねたゴイシシジミが、助け舟を出してくれた。
「えっとね……多分、あなたのせいじゃないと思うの」
「…本当?」
「ええ。ササコは…あ、この子はササコっていうの。ササコはきっとね、嬉しくて泣いてるのよ」
「ササコちゃん、本当なの? …足も痛くないの?」
ゴイシシジミの言葉を聞いたチャコちゃんは、私に最終確認のための質問をした。
自分でもどうして泣いているのか分からない。
でも、せっかくゴイシシジミが助けてくれたのだから、私は黙って頷くことにした。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
私が泣き止んだのは、あれからしばらく時間がたった後の事だった。
私が気づくとそこは知らない場所。
隣にいたゴイシシジミに、今いる場所について尋ねると、新しい寝床とのことだった。
彼女に聞いた話によるとあの後、私たちがチャコちゃんと別れた後も、私はずっと泣いていたのだという。
そして、ゴイシシジミはいつまでも泣き止まない私の手を引いて、ここまで歩いてきた。
…でも私にはその間の記憶が全然なかった。
まるで眠っている間の事のように頭からすっぽりと抜け落ちてしまっている。
「それにしても……」
ゴイシシジミは少し口を尖らせる。
そして、不貞腐れたように言った。
「私の時はあんなに嫌がってたのに、今度はあっさりと受け入れるのね?」
「なんですか、それ。元はと言えば、ゴイシシジミさんが無理やり引っ張っていったんじゃないですか。それに……」
あっさり、なんて言われてしまうとなんだか釈然としない。
だから私も少し口を尖らせて言った。
「私たちが初めてあった日。…あの時自分が何を言ったか、よく思い出してください」
「あはは……やっぱりあれは微妙だったかしら。」
ゴイシシジミはそう言って目を細めた。
「本当はね? あの時、…私はあなたにこう言うつもりだったの……」
彼女は口元を少し緩める。
…そして、そのまま犬歯を見せるようにゆっくりと口を開く。
私は、生まれて初めて見るその妖しい表情に思わず息を飲んだ。
「今すぐお前を食い殺してやるぞーって!!」
次の瞬間、彼女はバッと両手を大きく広げて、私に襲いかかる動作をした!
…が、全く迫力がない。
「もうその手には乗りませんよ?」
私がそう言うと、ゴイシシジミは「なーんだ」と言って少し残念そうな顔をした。
なんだとはなんだ、なんなんだ?
…四六時中ずっと一緒にいるのに、彼女の考えていることがよく分からない。
たまに猟奇的なことを言ったと思えば、それを聞いた私の反応に何かを期待する。
……もしかして、これが彼女なりのコミュニケーションだったり?
もしそうだとしたら、たまには乗ってあげるべき…なのかな?
「心配?」
私が少し考え込んでいると、突然ゴイシシジミが何か声をかけてきた。
えっと、心配って……まあ、心配かな。
……それって、何が?
彼女は一体、どういう意味合いでその言葉を口にしたのだろう。
……『 本当に食べられちゃわないか、心配? 』
と、そんなところだろうか…?
大まかな予想を立ててみたけど、どうもしっくり来ない。
「大丈夫よ。もしもあなたが死んじゃっても、…あの子はきっと大丈夫。ここの子達はそんなにヤワじゃないからね。どんなに悲しくても、ちゃんと前を向いて歩いて行ける強さをみんなが持っているの」
私が質問に答えるよりも早く、彼女はその言葉を口にした。
そこでようやくあの質問の意味が分かる。
どうやら彼女は、私の絶命後に残されたチャコちゃんの心配を、私がしていると思ったようだった。
すると、つまり……。
彼女は私の話を理解した上であのような行動に及んだ。
そして今私の話を蒸し返して、お説教を完成させた?
…となると、これもまたゴイシシジミの思惑通りということになってしまう。
……やっぱり、納得いかない。
彼女の言葉に上手く言いくるまれない。
だから私は、こちらも彼女の言っていた言葉を蒸し返して反論をしてみることにした。
「それも…誰かを傷つけていい理由にはなりませんよね…?」
私は別に、彼女の意見を否定したいわけじゃない。
にもかかわらず、こんな揚げ足取りをしてしまったのは、どうしても納得しきれない自分への確実な答えが欲しかったからだ。
私は、彼女ならその答えを導いてくれるのではないかといった、漠然とした信頼のようなものを抱いていた。
……しかし、私が意見するとゴイシシジミは「それもそうね」と言ってこちらの反論をあっさりと認めてしまった。
…拍子抜けだ。
私は彼女に、無理な期待をしてしまっていたのかもしれない。
そう…思った時だった。
私は自分の視線が、ゴイシシジミの顔に釘付けになってしまっていたのに気づいた。
それは、またもや初めて見る表情。
彼女の白い顔には、…不敵な笑みが浮かべられていた。
…これは間違いなく勝利を確信した笑いだ。
ゴイシシジミはその表情を崩さずに、その鋭利な言葉を口にする。
「でも、これであなたは簡単には死ねなくなったわね?」
……完敗だった。
彼女は私の心をよく理解した上で、ここまで計算していたのかもしれない。
「それがあなたの狙いですか…?」
「さぁて、なんのことかしら?」
ゴイシシジミはそう言ってはぐらかす。
そんな彼女の涼やかな目を見ながら私は、彼女には敵わないなあと思ったのだった。
イシちゃんのマフラーの下はこうなってました

ササコを変えてしまった出来事がわかったところで即座に行動に出て効果を得たイシちゃんはやり手ですね…
ササコの地の性格がまだ出ていないとすると、兵士を辞めるくらいの変化が無いと変われる気がしないので、これからのイシちゃんの作戦に注目したいです
おまけの絵では、イシちゃんはか弱い女の子という印象ですが、それを護るたくましさがササコに備わるのは少し先になりそうですね………
これからも楽しみです!
コメントありがとうございます
実を言うと、ササコはセルリアンと戦うために「兵士」を持ち出しましたが、この時には既に兵士としての使命感などは消えてしまっています
これからも頑張ります!
目を開けるとそこは、真っ暗闇の中だった。
何も見えない。
地面も空も、…何も無い。
それに自分の姿だって、ぼんやりとしていてよく分からない。
もし今この状況でセルリアンにでも襲われようものなら、何が何だか分からないうちに、私は殺されてしまうのだろう。
そんな危機的状況にありながらも、私の心は落ち着いていた。
不思議と怖さを感じないのだ。
「?」
ここはどこなのだろう。
辺りを見回しても、やはり何も見えない。
私はとりあえず、自分が立っている?ここを地面とし、歩いて行くことにした。
ピチャン、ピチャン…
足を踏み出すと、何やら水音のようなものが聞こえた。
どうやらここら辺は水溜まりになっていて、私はその上に立っている、ということらしい。
ピチャン、ピチャン……
「……?」
歩き出してから数歩で、水たまりを踏む感触が無くなった。
それなのに、水音だけが未だに聞こえている。
私は一瞬だけ立ち止まり、水音の正体について考えようとしたが、やっぱりやめておくことにした。
今は考えるよりも足を動かすべきだと思ったから。
……でも本当は、立ち止まっても聞こえ続ける水音から、目を背けたかっただけなのかもしれない。
ピチャン、ピチャン……
私は歩く。
ただひたすらに。
わけも分からず。
足の痛みなど忘れて、歩く。
そうしてしばらく歩いていると、遠くの方から誰かの声が聞こえた気がした。
私はその声を探してよく耳を澄ませる。
すると、今度は少しはっきりと聞こえた。
声は確かに存在している。
そして、その声は泣いているみたいだった。
その事に気づいた私は、歩くのをやめて走り出した。
私は泣き声の聞こえる方へと走る。
地面を強く蹴る程に、水音もまた強く、ハッキリと聞こえるようになる。
粗くなった水音がベシャベシャと耳にうるさいが、そんなことはどうでもいい。
今はただ、一刻も早くあの子の所へと行かなくてはならないのだ。
私はより一層、足に力を込めた。
速く、もっと速く…!
この声が消えてしまう前に。
私の存在が消えてしまう前に。
私は必死になって走った。
呼吸は止まり、足がもげてしまいそうだった。
それでも走った。
そして、ついに私は声の主の元へたどり着いたのだ。
よかった、ちゃんといてくれた。
私は、暗闇に座り込み一人泣いている少女に歩み寄る。
そして彼女をそっと抱きしめた。
すると少女は驚いたのか、ビクッと体を震わせた。
「大丈夫ですよ」
私は、安心させようと彼女の頭をやさしく撫でた。
しかしこれだけでは、彼女を安心させるには足りないらしい。
暗闇に怯え続ける少女が見ていられなくて、私は嘘をついた。
「私はあなたを助けに来たんです。だから一緒に行きましょう。」
私がそう言うと、少女は手で涙を拭って、こちらの顔をまじまじと見つめた。
私が彼女の顔をよく見えないように、彼女にも私の顔はちゃんと見えてはいなかっただろう。
それでも私は彼女に微笑みかけた。
「…ほら、立って」
私は立ち上がり、いつまでも無言でこちらを見つめる少女に手を差し出した。
すると、彼女はおずおずと手を伸ばし、私の手に重ねる。
確かな感触を感じた私は、その手をぎゅっと握りそのまま一気に引っ張りあげた。
…少女は私が思ったよりもずっと軽かった。
必要以上の力で引っ張ってしまったため、彼女は立ち上がった後もまだ勢いを残していた。
そして勢いそのままにこちらに倒れ込んで来る。
ぽすっ
彼女は軽かったので、私でも易々と受け止めることが出来た。
……なんだか既知感を感じる。
こんなことが前にもあったような……。
私は過去の記憶を辿るべく、目を閉じ視覚情報を遮断した。
……でも、そんな行為に意味などなかった。
何も思い出せない。
こんな真っ暗闇の中で目を閉じたって、不安感を増長させるだけだ。
いくら探したって、過去なんて見つからない。
…それもそのはず。
だって、ここには暗闇しか無いのだから。
「……行くわよ」
私は、私の胸に顔をうずめたまま動かない少女の肩を掴んで、そっと引き離す。
そして彼女に背を向けて歩き出した。
すると少女は直ぐに追いついてきて、私の腕を取った。
「えっと、……これ、なんですか?」
「……」
彼女は無言のまま、私の腕にしがみついて離そうとしない。
こんな所にずっと一人でいたから、心細かったのだろうか。
何も見えない暗闇の中で、たった一人…。
そんな時に、偶然言葉の通じるフレンズが通りがかったのだから、さぞや安心したことだろう。
かくいう私も、彼女のおかげで平静を保っていられるのだが……。
ピチャン……ピチャン……
本来一人で歩くことになっていたはずの道を、二人で歩く。
ピチャン、ピチャン……
一人でいようと、二人でいようと、水音は変わらない。
常に一定の間隔で滴り落ちる。
ピチャン、ピチャン……
私がこの断続的なリズムに苛立ちを感じ始めた頃、ようやく視界に変化が現れた。
遠くの方に、微かに光が見えたのだ。
「ほら、見て」
私がそう言うと、今までうつむいたままだった少女が顔を上げた。
……そして、次の瞬間、私の腕が解放された。
彼女が私の手を離したのだ。
それまで私の少し後ろを歩いていた彼女だったが、いつの間にか私を追い越してずっと先を歩いていた。
「……あ、ちょっと待ってください」
私は彼女を呼び止めようと声をかけた。
しかし、こちらの声が聞こえていないのか、彼女が足を止める気配はない。
私は慌てて彼女に追いつこうと走り出した。
ベシャッ、バシャッ、グチャッ
私は走っていて、彼女は歩いている。
……なのに、彼女との距離がちっとも縮まらない。
「まって!!」
私がいくら叫ぼうが、彼女は後ろを振り返りすらしない。
…もしかしたら、最初から私の声など届いていなかったのかもしれない。
「待っテくらサい! イカナイデ……わたシヲ…ヒトリイヒハイエ……」
なんだか呂律が回らない。
彼女を呼び止める言葉を吐いたつもりだったが、私の声は形をなさない。
……でも、だからといって私は残念に思ったりはしない。
だって、私が呼び止めたかった彼女はもう、光の向こうに消えていってしまっていたから。
「……」
呆然と立ち尽くす。
彼女は私のことを、真に必要とはしていなかったみたいだ。
単に私が勘違いしていただけ…。
足の痛みが全身に広がってゆく。
「もう…いいか」
ピチャン……ピチャン……ズル…ベチャンッ!
ひときわ大きな水音。
音が聞こえた方を見て、ようやく水音の意味を理解した。
私が、水音になっていたのだ。
…そして、今度は腕が腐り落ちてしまったようだ。
……光に近づきすぎた。
身を焦がすほどの、毒々しい七色の光線。
その虹色の光に包まれて、私の体がドロドロに融けてしまう。
痛みはない。
なぜなら、痛みを理解するための頭は、…もうとっくに、失われていたのだから。
もう、私はだめだろう。
薄れゆく意識の中で、私は最期に、既に無い頭が覚えていたであろう名前を、とうに消えてしまった口で呟いた。
「ゴイシシジミさん……」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「……ぅあ」
視界が……ぼんやりとしている。
意識も。
私は確か、……死んで…。
でも、いま……??
両手で顔をぺたぺたと触ってみる。
……ちゃんとある。
頭も、腕もなくなったりはしてない。
それらの確認が済んで、ようやくぼんやりとしていた意識がはっきりとしてきた。
今なら分かる。
さっきまでのは紛れもなく……
「……ゆ…め?」
そうだ、夢だ。
あんなのは全部、酷い悪夢だ。
「わらし、ねちゃってたんだぁ……」
ゴイシシジミの用事とやらが終わるのを待っているうちに、眠くなって……そのまま……うん。
私は木陰から這い出て空を見上げた。
現在の太陽の位置から推測するに、私が眠っていたのはほんの少しの間だけだと思う。
そんなちょっとした微睡み程度の時間であんな悪夢を見てしまうとは、なんて運が悪い。
あるいは、運なんて不確かなものではなく、他に明確な原因があるのかもしれない。
そして私は、その原因に心当たりがあった。
それはゴイシシジミのこと。
ここのところ、彼女の私への態度が素っ気ない。
前は鬱陶しいくらいだったのに、
最近では彼女の口数が極端に減り、代わりに思いつめたような顔を見せるようになった。
こちらから話しかけても、心ここに在らずといった様子で、以前にまして話す価値がない。
「やっぱり、あれのせい…?」
私には、ゴイシシジミの元気がないことの原因にも心当たりがある。
それは2日前のことだ。
ゴイシシジミが他のフレンズと何やら言い合いをしていた。
話の内容までは聞こえなかったが、二人の表情から察するに、決して楽しい話ではないことが分かった。
その後話を終えて戻ってきたゴイシシジミは、疲れたから寝るとかなんとか言ったっきり、一言も喋らずに、本当にそのまま寝てしまったのだ。
……それからだ。
彼女の表情に度々陰りが見えるようになったのは。
あの時何の話をしていたのかを彼女に訊こうと何度も思ったが、それは今日の今日まで果たせなかった。
それを聞いてしまったら、何かが変わってしまう気がしたから聞けなかった。
……でも、何も訊かなくたって、確実に何かは変わってしまっている。
もう、だめなのかな?
……夢で見たみたいに、…離れていっちゃうのかな。
「しょうがない……のかな」
こんなにも弱気になってしまうのは、きっとこの傷のせいだ。
私の弱さの証は、日に日に深く鋭くなってきている。
私は右足の傷に目を落とす。
「…………」
表面が深く抉れてしまっている。
それは、指が4本入ってしまうほどまでに広がってしまっていた。
こんなにも痛々しい傷なのに、血は一滴も流れない。
そして……。
私は、どうにかこの足を蔽うのに丁度いいものが何かないかと、辺りを見回したが、それらしきものは何もない。
私は膝を抱えて、俯きがちに小さくため息をついた。
…そんな時だった。
ゴイシシジミがくれたマフラーが目に入った。
「ああ、これ……」
私は少し思案してから、それを首から引き離し、足に巻いてみることにした。
……長さも幅もピッタリだった。
せっかくゴイシシジミがくれたものをこんな形で使うのは、なんだか気が引けるけど、仕方がない。
こんなものが露出していては、気になって会話もままならないだろうから。
もっとも、今の彼女には私のことなど見えてはいないかもしれないけれど……。
「…………これでよし」
ひと仕事終えた私は、また空を見上げた。
太陽の位置はさっき見た時とさほど変わってない。
「遅いな……」
体がなんだかだるい。
それに熱っぽい。
風邪でもひいたかな。
……このまま死んじゃうのかな。
さっきから、ろくな思考が出来ない。
一人でいることが、ここまで心細いものだとは思わなかった。
これも、……あの夢のせいだ。
「……いこう」
このままゴイシシジミの帰りを待っていても、思考がどんどん後ろ向きになってしまう。
だから探しに行こう。
私は、ぼやける目を両手で擦り、膝に手をつく。
「よっ!とと……」
ただ立ち上がるだけでも、寝起きの私には辛い。
上手く立てなかった私は、よろよろと木に寄りかかってしまった。
ふと、そんな私の一連の動きを客観的に見た景色を想像してしまう。
そのあまりにも滑稽な姿がなんだかおかしくて、私は苦笑した。
やがて体勢を立て直し、最初の一歩を踏み出そうとした時、私はその一歩の重さを知り、大きく落胆した。
もう、一歩も歩けそうにないのだ。
額にはたまのような汗が浮かび、息が荒くなる。
足はガクガクと震え、立っているだけでもやっとだった。
「…なん…で……?」
その気になればいつでも会いに行ける気でいた。
だからだろうか…?
今それが出来ないと分かった瞬間から、孤独が怖くてしょうがない。
怖くて、悔しくて、泣いてしまいそうになる。
……そんな時だった。
ゴイシシジミの声が聞こえた。
「……ササコ」
幻聴なんかじゃない。
私がずっと会いたかった人が、そこに……。
視界はぼやけきっていて、彼女の表情は分からないけど、きっとやさしく微笑みかけてくれているはず…。
今すぐ彼女の胸に飛び込みたい。
……でも、それは出来そうになかった。
「……私たち、もうお別れしましょうか」
「……………………へ?」
突然彼女から突きつけられた言葉は、あまりにも鋭いくて…。
私が何度も口にしてきたような拒絶で、私の心を深く抉る。
それはまるで、使い古してボロボロになって、切れ味の落ちたナイフのような言葉だった。
刃が欠けていても、ナイフはナイフ。
私みたいなやつを殺してしまうにはそれで十分だ。
「ぁ…あはは、そんな急に……どう…しちゃったんですか?」
私の世界が崩れていく。
視界が歪む。
…もう、立っていられない。
大きく視界がぐらついて、その次の瞬間には……世界が終わっていた。
本当はもうちょっと続くんですが、その続きに少し手こずってまして……
この続きは8話と言うことにしてあげることにしました
ササコの夢で、本当はイシちゃんを必要としているのに近くには居続けられない悲しさがその直後とリンクしてて巧いと思いました
突き放すような言動をとってきたササコが、逆に突き放されることで、これまでの不器用さを払拭するかそれに繋がるといいなとも思いました
次回も楽しみです!
コメントありがとうございます!
実を言うと、あなたの感想を読んで初めて「なるほど、これはそういう事だったのかー」と気付かされることがよくあります
自分で書いていても気づかなかったような彼女達の一面を、こうして知ることが出来て嬉しいです
次回も頑張ります!!
「ねえ、ちょっと! どうしたの?!」
ゴイシシジミは血相を変えて、ササコに駆け寄る。
「ササコ、大丈夫? ……私の声が聞こえる?」
大丈夫かと訊ねたゴイシシジミだったが、どこをどう見ても大丈夫でないことは、彼女にもよく分かっている。
だからこそ、彼女はよびかけ続ける。
……それは、認めたくなかったから。
「ササコ……ねえってば」
ゴイシシジミはササコの体を揺する。
しかし、ササコは息を荒くするばかりで、それ以上の反応を見せない。
ゴイシシジミは途方に暮れてしまった。
彼女が今、どういった状態なのか分からない以上、ゴイシシジミにはどうすることも出来ないのだ。
ゴイシシジミは全てを諦めたように、項垂れる。
──その時だった。
「……ぁ…………」
「ぇ……なに? なんて言ったの?」
不意に、小さく、熱っぽい声が発せられた。
それを聞いたゴイシシジミは、ササコが何かを伝えようとしていることに気づく。
「ごめんね、もういちど、いって?」
ゴイシシジミはササコにちゃんと届くように、ゆっくりと、それでいて簡潔に言葉を伝えた。
その言葉はササコに伝わったようで、彼女の荒い呼吸が少しだけ抑えられる。
ゴイシシジミは、絶対に聞き逃すまいと、ササコの口元に耳を近づけた。
「……ぁ…つぃ…………」
今度はちゃんと聞こえた。
ササコは、暑いと言った。
その言葉を聞いたゴイシシジミは、彼女の全身に目を向ける。
そうして、ゴイシシジミはようやくあることに気づいた。
ササコは身体中に汗をかいている。
見ればすぐに分かることのはずなのに、ササコの言葉を聞くまで気づかなかった。
早々に諦めてしまっていたから気づけなかったのだ。
…でも、それを悔いるのは今じゃない。
後悔するよりも先にすべきことがある。
「ササコ、大丈夫? 服、脱がすからね」
ゴイシシジミはそう言って、ササコの服を脱がし始めたが、直ぐにその手が止まる。
ササコの足に絡まる一枚の布切れが気になってしょうがない。
それはかつてゴイシシジミからササコへと贈られたものだ。
だから、それをどのように使おうが彼女の自由だ。
でも、だからといって、どうしてこれが足に巻かれているのだろう…?
…マフラーが巻かれているのは確か、彼女が怪我をしていた所だ。
だとすると、そこを覆っているのは傷を隠すためなのだろう。
それならそれで別におかしなことなんてない。
見られたくないから、隠した。
たったそれだけのはず。
…でも、どうしてだろう。
ササコのマフラーの下が気になって仕方がないのだ。
なんにせよ、このマフラーを取らないと服を脱がせられない。
ゴイシシジミはマフラーを掴むと、ゆっくりとササコの足からそれを解いた。
「……!」
ササコの隠そうとしていたものを見て、ゴイシシジミははっと息を呑む。
彼女の華奢な足には、小さな少女には不釣り合いな痛々しい裂傷があった。
……そして傷口の周りには、色鮮やかなアザがいくつも広がっている。
『 痛くない?』
そう声をかけようとした時だった。
「……なに……これ……?」
アザが、……動いた。
絶えず色を変え、蠢いている。
「ちょっとごめんね…」
ゴイシシジミは先に謝ると、アザのある部分をそっと触る。
ササコは無反応だ。
今度は軽く押し込んでみる。
アザは押しのけられ、手を離すと元の位置に戻った。
(アザじゃ……ないの?)
ササコの足に蔓延るアザのようなそれは、決してアザなどではなかった。
「さ、ささこ……これ…! ご、ごめ……わた…わたし、どうしたらいいのか……」
ゴイシシジミは気が動転して上手く喋れない。
そんな彼女の頭を冷やし、果ては凍らせてしまうような言葉を……
「……きっ……て」
ササコが、言った。
それは、ササコが何度もうわ言のように言っていた言葉だ。
彼女のあの言葉にはまだ続きがあった。
熱い。足、切って。
「……あ…し………あつ…い。……きって」
ササコは、自らの足を切断してほしいと、そう言っているのだ。
「……そんなこと、出来るわけないじゃない」
ゴイシシジミがそう言うと、ササコはもう何も言わなくなった。
ゴイシシジミに願いが届いたのを悟ったのか。
……あるいは、声を出せないほどに弱ってしまったのかもしれない。
(もう、足を切り落とすしかないの…? …それはだめ。 そんなことしたらササコが死んじゃう。……でも、このままじゃ……)
「ササコ……」
目の前の少女を助ける手立てが何も思いつかない。
こんなこと、一度も経験したことが無かったから。
……もしかしたら、他のフレンズならこんな時どうすればいいかを知っていたかもしれない。
皆と仲良くしていれば…。
あの時、不実な態度をとったりしなければ……。
そうしたら、今頃誰かが助けてくれていたかもしれない。
ゴイシシジミは自らの傲慢さを呪った。
ササコを脅してそばに置いて、それで満足していた。
その罰を受ける時が来たのだ。
……でも、彼女に罪は無い。
ササコは脅されていただけだ。
(私はどうなってもいい。裁かれて当然のことをしたから。……でも、ササコは違う)
「──ああ、そうだ。 私はどうなってもいいんだった」
(行こう…!)
ゴイシシジミは他のフレンズを探しに行く決意をした。
善良なフレンズを助けるためなら、力を貸してくれるかもしれない。
ゴイシシジミはササコを慎重に背負うと、すぐに走り出した。
目的地はここから北の方、以前の寝床周辺だ。
そんなに遠い距離じゃない。
だから、今いる道を真っ直ぐ行けば、そんなに時間はかからないはずだった。
今は一刻も早くササコの足をなんとかしなければならないのだから、立ち止まっている時間なんてない。
しかし、ゴイシシジミは走る足を止めてしまっていた。
セルリアンが道を塞いでいたのだ。
(なんでこんな時に…)
ゴイシシジミはセルリアンに憎々しげな視線を向けた。
だが、セルリアンにとってそんなものは道を譲る理由になどならない。
セルリアンはそのでかい図体で、道の真ん中を陣取っている。
そして、不動のままゴイシシジミ達をただ、じっと見つめている。
相手に戦意がないのなら、面倒な戦いは避けたいところだが、何せ奴らは言葉を話さない。
「……」
いつまでもここで睨み合っている訳にはいかない。
だから、ゴイシシジミは素早く決断をした。
(セルリアンの脇を走り抜ける!)
ゴイシシジミの選択には大きなリスクがあったが、彼女にとってはそれが一番マシな選択だった。
ゴイシシジミはササコを落とさないように背負い直すと、強く地面を蹴った。
一歩、また一歩。
足を前に踏み出す程に、セルリアンとの距離が近づいてくる。
ゴイシシジミは、額に冷や汗を浮かべつつ、……セルリアンの脇をすり抜けることに成功した。
その間もセルリアンは、ゴイシシジミのことをずっと目で追ってはいたが、それ以上の興味を示すことはなかった。
しかし、彼女の背負っている少女を見た途端にその目の色が変わる。
ゴイシシジミがセルリアンとすれ違った次の瞬間、背後で大きな物体が動く気配がした。
(……これは、想定内)
ゴイシシジミは振り向くことなく、走り続ける。
その後を、彼女の何倍も大きいセルリアンが追いかける。
背後からは、ドシドシと重量感のある音が聞こえてくるが、セルリアンの足はそれほど速くはないらしい。
音は少しづつではあるが、遠ざかっている。
だから、そのまま走っていれば容易に振り切れるはずだった。
ガッ
(……え?)
ゴイシシジミの振り上げた足が、
着地するはずだった予定地から大きく外れる。
そしてそのまま、ドサーっという音と共に二人は地面に投げ出されてしまった。
「ぅ……」
地面に伏せったゴイシシジミが小さく呻き声を上げる。
自分が転けてしまったことを自覚した彼女はすぐさま立ち上がろうとしたが、足首が急に痛んだので地面に両手をついてしまった。
どうやら、転けた時に足首をひねったらしい。
「…ササコ…!?」
ゴイシシジミは、さっきまで背負っていた少女の姿が見当たらない事に気づき、咄嗟に周囲を見渡した。
幸い、彼女は直ぐに見つけることが出来た。
ササコはゴイシシジミの前方、数メートル先に横たわっていた。
ゴイシシジミはササコの姿を確認すると、すぐに彼女に駆け寄った。
そして、彼女の顔を覗き込む。
辛そうではあったが、まだ生きている。
「ごめんね。…こけちゃった」
ゴイシシジミはそう言うと少し自虐的に笑った。
…そして、ササコをそっと抱き起こすと、そのままぎゅっと抱きしめた。
すぐ後ろにはセルリアンが迫ってきていると言うのに、何故かゴイシシジミはもう逃げようとはしなかった。
愛おしむような目で、ただ、ササコを抱きしめる。
「大丈夫だからね」
彼女はそう小さく呟くと、固く目を瞑った。
……その次の瞬間、セルリアンが大木のような腕を振り上げた。
ずいっと伸びた大きな影が、二人の小さな影を呑み込んでしまう。
そして、その影よりも更に暗い色をした影の主は容赦なくそれを振り下ろした。
セルリアンの致命的な攻撃が、ゴイシシジミの背中に迫ったその時──。
ガッギィィィンッ!!
──空気を引き裂くような轟音が辺りに響き渡った。
いつまで経っても痛みが来ないことを不思議に思ったゴイシシジミが、恐る恐る目を開け後ろをゆっくりと振り返ると……。
そこには、一人のフレンズが立っていた。
彼女はこちらに背を向け、セルリアンの前に立ちはだかる。
その背中からは、鎖のように長く連なった鎧のようなものが生えていた。
そして、二本の腕と、その鎧のような部位を使って、巨大なセルリアンの腕をその身一つで受け止めていた。
「無事か…?」
少女はそのままの姿勢でそう言うと、ちらりとゴイシシジミ達の方へ視線を向ける。
ゴイシシジミは瞬間的に顔を伏せ、彼女と目を合わせないようにした。
彼女こそが、ゴイシシジミが探していたフレンズに間違いない。
そして、ゴイシシジミが最も会いたくない相手でもあった。
「?」
ゴイシシジミの反応に少女は怪訝な顔をしつつも、セルリアンの腕をしっかりと受け止めている。
突然現れたフレンズに攻撃を受け止められたセルリアンは、腕を引っ込めるでもなく、そのまま押しつぶそうと力を込めた。
その変化を全身で感じ取った鎧の少女は、ゴイシシジミから視線を外すと、再びセルリアンを睨みつける。
「失せろ」
少女は威圧的な声を発したが、威圧的なのはその声だけではない。
彼女の目はギラギラとした赤い光を放ち、全身からは黒い瘴気が滲み出している。
それだけの威圧を受けても、セルリアンは怯むことなく少女を見下ろしている。
「そうか」
少女は吐き捨てるように言うと、セルリアンの戦意に応えるように、彼女もまた両腕にぐっと力を込めた。
彼女の力は強大なセルリアンにも劣らないものだ。
だが、これだけの体格差があっては、彼女の方が明らかに不利に思われた。
……しかし、彼女は圧倒的な力で持ってしてセルリアンの腕を押し返してしまったのだ。
ドオォン!
バランスを崩したセルリアンは地面に倒れ込む。
少女はその隙を見逃さず、すぐさま攻撃に転じた。
彼女は二、三歩助走をつけると、大きく飛び上がる。
そして、空中で身体を捻り、背中の鎧を思い切りセルリアンの胴体部に叩きつけた。
……次に彼女が地面に足をつけた時、既にセルリアンはバラバラに四散していた。
「危ないところだったな」
ゴイシシジミ達をセルリアンから助けた少女が、ゴイシシジミの元へ歩いてくる。
しかし、助けられたゴイシシジミの表情は明るくない。
「ムカデ……」
「……!」
ゴイシシジミがムカデと読んだ少女は、ゴイシシジミの顔を見るなり目を見開く。
それはまさしく、幽霊でも見たような顔だった。
「まさか…本当にお前が! 何故、お前が生きている…?!」
「…………」
ゴイシシジミは無言でムカデを見上げている。
その視線には僅かに敵意が含まれていた。
「おい」
「……」
いつまでも無言でいるゴイシシジミに、ムカデは苛立ちを覚え始めていた。
……やがてムカデの視線は、無言の少女から、彼女が抱いている瀕死の少女へと移る。
「お前、まさかその子に何かしたんじゃないだろうな」
「私は……」
ゴイシシジミは何かを言いかけて、俯きがちに頭を小さく横に振った。
「お前ッ……!」
なかなか言葉を紡ぎ出せないゴイシシジミを見て、ムカデの目は次第に殺気を帯びたものになる。
………………。
しばしの沈黙。
沈黙に耐えかねた少女と、ようやく口にすべき言葉を見つけた少女。
二人は同時に言った。
「今度は確実に仕留める」
「この子を助けてほしいのっ!」
たった今ゴイシシジミに向かって死刑宣告をした少女は、彼女の言葉を聞いて動揺した。
一方、宣告を受けたゴイシシジミの方は、驚きもしない。
ただ、真っ直ぐな目でムカデを見つめる。
「何を…今更そんな……!」
「お願い。…もう私にはどうにも出来ないの」
「だってお前はそんなやつじゃ……」
ムカデはゴイシシジミから視線を逸らす。
彼女の拳は固く握られていた。
「私なら殺してもいいから」
「…お前」
ゴイシシジミはいとも容易くその言葉を口にした。
彼女の放ったその一言がムカデの琴線に触れる。
ムカデはゴイシシジミのすぐ近くまでつかつかと歩み寄ると、片手で彼女の襟を鷲掴みにした。
振り上げられたもう片方の手は、未だ握りこぶしを作ったままだ。
「お前はッ……!」
ムカデはそのままの姿勢で、ゴイシシジミを威圧する。
彼女の眼光には、セルリアンに向けられたものと同じ殺気が含まれていた。
……それでもゴイシシジミは怯まない。
彼女の瞳は真っ黒ではあったが、揺るぎない決意の光が宿っていた。
「お願い」
「………………」
ムカデは複雑そうな顔で、彼女の襟を放すと、振り上げた拳を下ろした。
彼女の目からはもう殺気や敵意などは消え失せていた。
「あまり期待はするなよ。私は…医者じゃないからな」
ムカデはそう言うと、ササコの顔を覗き込んだ。
そして次に、ゴイシシジミの顔をじっと見た。
「えっと……なに…?」
「いや、それじゃあよく見えないだろ」
いつまでもササコを大事そうに抱いたままのゴイシシジミに、ムカデがため息混じりに言った。
「ご、ごめんなさい」
彼女ははっとして、ササコを地面に寝かせた。
ムカデは改めてササコの全身を見た。
彼女が真っ先に気になったのは、やはり足の傷がある部分だった。
そこには白黒のマフラーが巻かれている。
それは、ゴイシシジミによって再度巻かれたものだ。
ムカデはゴイシシジミをちらりと見ると、マフラーを取った。
「これは……毒だ」
ムカデは、ササコの傷周辺に蔓延るそれの正体をあっさりと言い当てた。
「毒?」
それまでササコの診察を黙して見守っていたゴイシシジミだったが、ムカデが聞き慣れない単語を発したため、聞き返した。
ゴイシシジミが聞き返すと、ムカデは信じられないといった顔で彼女の顔を見た。
「お前……まさか知らないのか?! 誰からも……聞いていないのか……?」
「えっと……」
知らないから聞き返したのに、とゴイシシジミは思った。
ムカデの鬼気迫る表情に気圧された彼女は口ごもってしまう。
その様子をみて、ムカデはそれこそがゴイシシジミの答えなのだと認識した。
「そうか……知らなかっのか」
ムカデは苦々しい顔で呟いた。
「お前も見たことはあるだろ。キラキラと輝く、虹のようなものを」
虹と聞いて、ゴイシシジミはぴくんと反応した。
彼女に心当たりがあるのを察したムカデは、更に言葉を続ける。
「あれが体内に入ったら、段々と身体中に広がっていき、最後には………」
彼女はそこで一度言葉を切った。
そして……
「死ぬ……と、言われている」
重々しい口調で言った。
「……」
ゴイシシジミはその言葉を聞く前から、ササコの顔を無言で見ていた。
そしてそれは、彼女の宣告を聞いた今でも変わらない。
そんなゴイシシジミの様子を見たムカデは、思ったことをそのまま口にした。
「妙に落ち着いているな」
彼女の発言は少し無神経だったかもしれない。
でもゴイシシジミはそれで腹を立てたりはしない。
彼女はただ、無感情な目でササコを見つめている。
「……そんな気はしていたの」
彼女は小さな声で呟いた。
そして、ムカデを見た。
「ササ……」
ゴイシシジミはササコの名前を言いかけて、口を噤んだ。
頭を小さく横に振ると、改めて言い直す。
「この子はもう助からないの?」
それは、ちょっとした質問をするかのようにあっさりとした口調だった。
……そしてその声は、どこか他人行儀な響きを持っていた。
誰にでも分かるほどにあからさまなゴイシシジミの態度の変化に、ムカデは眉をひそめる。
「お前は本当に、その子を助けたいんだな?」
なぜ今更そんなことを聞くのか。
ゴイシシジミは、そんな疑問を抱きはしなかった。
なぜなら、彼女の発言は核心に迫ったものだったから。
ゴイシシジミは、ムカデに内心を見透かされ、曖昧な態度を咎められたのだ。
「……ええ」
ゴイシシジミは消え入りそうな声で言った。
俯き前髪を垂らした彼女の表情は伺えない。
「…そうか」
ゴイシシジミの声を聴いたムカデは、少しだけ表情を緩める。
そして、一度は無視した彼女の問いに答えた。
「助ける方法は……ある」
「本当…?」
ゴイシシジミは少し顔を上げると、上目遣いにムカデを見た。
「……ああ、本当だ」
今度はムカデが俯く。
そして、ササコを助けるその方法を口にする。
「毒を取り除けばいい」
彼女は低い声でそう言うと、ササコの毒に汚染された足に目を落とした。
彼女の暗い表情を見て何かを察したゴイシシジミは、恐る恐る訊いた。
「足を……切るの?」
「そ……」
ムカデは一瞬、肯定の言葉を言いかけて口を噤んだ。
そして長い沈黙の末、改めて否定の声を発した。
「……いや、そんなことはしなくていい」
ムカデがそう言うと、先程セルリアンを粉砕したばかりの彼女の鎧が蠢いた。
「何をしているの……?」
ゴイシシジミが怪訝な顔で言った。
「……」
鎧は主であるムカデの手元まで来ると、そこで停止した。
彼女はその先端に両手をそっと添える。
バキンッ
「!?」
──突然、重い金属音が響いた。
ゴイシシジミは音のしたそれに目を落とす。
すると、音の主は真っ二つになってぐったりとしていた。
どうやら先程の金属音は、ムカデが鎧の先端を切り離した時に生じた音だったようだ。
「あ、あなた……何をしてるの?」
「……」
ムカデは心配そうに聞いてくるゴイシシジミのことを無視して、更なる奇行に走る。
彼女は鎧の断面から中に手を突っ込み、何かゴソゴソと弄る。
「……いた」
「?」
やがて何かを見つけたらしいムカデは、それを中から引っ張り出した。
鎧から引き抜かれた彼女の手には、拳ほどの大きさの石のようなものが握られている。
「それ、なに?」
「セルリアン……らしい」
ゴイシシジミの質問へのムカデの返答は衝撃的なものであった。
「せ、せる……?」
ゴイシシジミは、眼前の少女の言葉が上手く理解出来ないといった様子だった。
ムカデはそんな彼女をお構いなしに、奇行では済まされないようなことを平然と続けようとする。
ムカデは何を思ったのか、ササコの足に向かって、セルリアンを持った手を近づけた。
彼女の行動はゴイシシジミには到底理解出来ないものだったが、それでも止めずにはいられなかった。
「待って!」
セルリアンが彼女の傷に触れる寸前で、ゴイシシジミの両手がムカデを引き止めた。
「あ、あなた……本当に何をしてるの…?」
「何って、…チリョウだよ」
ムカデは不快感を露わにして言うと、彼女の手を振り払った。
そしてもう一度セルリアンをササコの足に近づけようとする。
その手を再びゴイシシジミが引き止める。
「ねぇ、あなたちょっと…怖いわよ。……こ、この子に……何をするつもり…?!」
ゴイシシジミはムカデを睨みつけて言った。
しかし、彼女の威嚇はムカデをイラつかせる以外の意味を持たない。
「助けてやるって言ってんだから、…ありがたく受け取れよ」
ムカデはゴイシシジミを睨み返すと、低い声で言った。
「ご、ごめんなさい……」
先程までは親身になってくれていたムカデだったが、今はどこか違う。
今の彼女は、有無を言わせないと言った様子だ。
そんな彼女の変わり様を。
怒りに満ちた鋭い目を。
それら全てをその目で見てしまったゴイシシジミは、すっかり怯えきってしまっていた。
彼女はただ、ムカデの後ろ姿を見ていることしか出来ない。
ムカデは治療と言った。
だが、彼女がやっていることはどう考えても救命処置などではない。
(救命処置じゃないなら……)
──グチャリ。
怪音が鳴った。
その音がゴイシシジミの耳に鮮明に刻まれる。
それは、彼女のよく知る音で……。
「ころすなら…わたしを殺してッ!」
次に彼女の耳に響いたのは、彼女自身の咆哮だった。
突然の大声にムカデはビクッと身体を震わせたが、それでも手を止めるには至らない。
「……」
ゴイシシジミは立ち上がり、ムカデの背後に駆け寄る。
そして、もつれるように彼女の背中に縋り付く。
「お願い……」
ゴイシシジミは懇願するように言った。
しかし、ムカデはその願い諸共彼女を払い除けてしまう。
バランスを崩してしりもちをついたゴイシシジミは再び立ち上がろうとしたが、それをムカデに邪魔される。
彼女は禍々しい鎧の先端をゴイシシジミの喉元に突きつけて言った。
「これ以上私の邪魔をすれば、本当に殺すからな」
「そんな脅し怖くないわ」
ゴイシシジミは凛とした声で言った。
すると、その声に反応してムカデの鎧が蠢いた。
それはゴイシシジミの首から少し横に逸れると、重い金属音を立てながらゆっくりと蠢く。
鎧はゴイシシジミの横をすり抜け……そのままぐるりと彼女の身体を囲んでしまった。
鎧と彼女の間隔が徐々に狭まって行く。
ゴイシシジミはこれから起こる事を悟ったように、ゆっくりと目を閉じた。
─────ぺたん。
「……?」
ゴイシシジミは妙な感触を頭に感じて目を開けた。
そうしてまず彼女の目に飛び込んできたのはムカデの後ろ姿だった。
しかし、その上半分は何かに遮られていて見えない。
彼女とムカデの間はあるもので隔てられていた。
「……な…に?」
それはムカデの鎧の先端だった。
ゴイシシジミの頭に乗せられたそれはゴソゴソと、右へ左へ振れている。
「?」
ゴイシシジミは自分が置かれている状況を理解出来ず、きょとんとしている。
その目には戸惑いの色が滲んでいた。
…それもそのはず。
ゴイシシジミの中では、全身に巻きついたそれは彼女をそのまま締め殺すことになっていたのだ。
それなのにいつまでも経ってもその気配がない。
ムカデの身体を守るための鎧が、ゴイシシジミを緩やかに包み込む。
それはまるで、腕を使わずに抱擁しているようにも見えた。
「あ、安心しろ……して。…大丈夫だ…よ?」
ムカデが言った。
言葉通り、怯える少女を安心させるために言った。
粗暴な口調が隠しきれていないが、それが彼女なりの精一杯の言葉だったのだろう。
彼女の言葉はゴイシシジミへ向けられたものであったが、当の本人はその言葉の意味を理解しかねていた。
言葉の意味自体は理解できるが、なぜムカデがそう言ったのかが全く分からない、そんな様子だった。
ゴイシシジミはムカデの言った言葉の意図について考える。
しかし、ゴイシシジミの思考は直ぐに打ち切られる事になる。
「わひゃあっ! なぁん…何をするッ!?」
突然ムカデが素っ頓狂な声を上げた。
後に続く非難の言葉から、ゴイシシジミにその原因があることが分かる。
考え事に集中していたゴイシシジミは、無意識にムカデの鎧の内側を撫でてしまっていたのだ。
「ご、ごめんなさい」
「まったく……。手元が狂ったらどうするんだ」
ムカデはそう言うとゴイシシジミを解放した。
束縛を解かれたゴイシシジミは、ムカデの傍まで這っていくと、彼女の隣にぺたんと座り込んだ。
「何をしてるの?」
ゴイシシジミはムカデの手元を覗き込み言った。
ムカデの手には、先程彼女がセルリアンだと言った石のような物体が握られていて、彼女はそれをササコの傷に押し当てている。
「こうやって、…毒を身体から取り除くんだ」
「毒を…?」
「ああ、こいつらは毒を食べるからな」
「そう……」
ゴイシシジミはつまらなさそうに相槌を打ったっきり、口を閉ざしてしまった。
「?」
ゴイシシジミの僅かな声色の変化に気づいたムカデは、彼女をちらりと横目に見た。
彼女は俯き、自分の両の手のひらを見つめている。
その姿は、ひどく弱々しく見えて……。
儚げでさえある彼女のことが放っておけなくて、ムカデは声をかけた。
「お前は…さ。…今のお前は……そんなに嫌なやつじゃないよ」
「ぇ…?」
ゴイシシジミは少しだけ顔を上げてムカデの方を見た。
「だから、その……悪かったな。…私はお前のこと、誤解してたと思う。だから…ごめん」
ムカデがそう言うと、ゴイシシジミはまた俯いた。
そして両手でスカートをぎゅっと掴むと、小さな声で言った。
「…私も、…ごめんなさい」
「……うん」
ムカデは複雑そうな表情で頷いた。
それからは、二人がお互いに声をかけることは無かった。
ムカデはササコの毒の治療を続け、ゴイシシジミはそれを見守った。
そうしてしばらくの時間がたった。
ササコの毒のアザはみるみるうちに消えてゆき、最後のひとつが無くなると同時に、ムカデがセルリアンを彼女の足から引き剥がした。
大量の毒を吸収したセルリアンは、ムカデの手の中でまもなく爆散した。
「終わったの…?」
ゴイシシジミが心配そうな声でムカデに聞いた。
「ああ、これで毒の侵蝕は止まった。この傷も直に治り始めるだろう」
ムカデはササコの足にマフラーを巻きながら言う。
それを聞いて、ゴイシシジミはようやく安堵の表情を見せた。
「よかった……」
心底安心する彼女を見て、ムカデが目の端を吊り上げる。
「これからはちゃんと毒に注意しろ。あんなセルリアンは滅多に見つからないからな。次は無いと思え」
「ええ、この子が起きたらちゃんと話すわ」
「……」
ムカデは少しの間黙り込んだ。
難しい顔でゴイシシジミの目を見つめる彼女は、慎重に言葉を選んでいるようだった。
「……お前が、その子のことを本当に大切に思ってるのなら、自分のことはもっと大事にするべきだ」
諭すような目でムカデが言った。
それは、ゴイシシジミのことを心から案ずるが故の忠告だった。
「ぇ…ええ、気をつけるわ」
ゴイシシジミの返事を聞いたムカデは目を細めた。
しかしそれは、望み通りの応えが得られたことに対しての、満足気な笑みなどではない。
かといって、彼女の言葉を疑っているという訳でもなかった。
それは、言い難いことを伝えるべきかを決めかねているような、そんな迷いの表れだった。
やがて……決心がついたのか、ムカデはゆっくりと口を開いた。
「だが、今後その子に何かあった時には……」
神妙な顔で話を始めるムカデ。
ゴイシシジミは彼女の表情から真剣な空気を感じ取り、表情を強ばらせる。
ムカデは少し言葉に詰まっていたようだったが、ゴイシシジミがこくんと喉を鳴らすと、続きを話し始めた。
「その時には、お前にもできることがあると教えておく」
━━━━━━━━━━━━━━━
「それは、本当のことなの…?」
「ああ」
「……そっか」
ゴイシシジミは俯きがちに呟く。
その視線の先には、彼女自身の両手が重ねて置かれていた。
彼女は次に、横たわる少女の顔に目を落とした。
それから自分の両手とササコの顔を見比べると、ゆっくりと目を閉じた。
……数秒後、彼女が再び目を開けた時、その表情は晴れやかなものになっていた。
今の彼女はもう、無力な少女などではない。
ゴイシシジミは顔を上げると、屈託のない笑みを浮かべて言った。
「ありがとう」
感謝の言葉を向けられたムカデは、困ったような笑みを浮かべて返した。
「まさか、お前にお礼を言われる日が来るとはな」
ムカデがそう言うと、ゴイシシジミもまた困ったような顔で笑う。
「いいか、これはあくまでも……」
「分かってるわ」
表情を改め、真剣な顔で何かを言おうとしたムカデを、ゴイシシジミが制した。
そして、曖昧な笑顔を浮かべつつ言う。
「ふふ、あなた本当は優しいのね」
突然好意的な言葉をかけられた彼女は面食らってしまう。
「わ、私は…お前を……」
何かを言いかけて言葉を飲み込むムカデ。
「?」
ムカデは無言で立ち上がると、不思議そうな顔をするゴイシシジミに背を向けた。
「もう行っちゃうの?」
ゴイシシジミが言った。
「ああ、やりたいことがあるんだ」
「…そっか」
ゴイシシジミが残念そうに呟く。
ムカデは、心細そうに眉を下げる彼女に振り返りもしない。
「ここら辺にいれば、多分安全だからさ」
ムカデはそれだけ言うと、真っ直ぐ歩き出した。
「待って」
ゴイシシジミの短い言葉がムカデを引き止める。
「なんだ?」
「……助けてくれて…ありがとう」
ゴイシシジミはムカデに改めてお礼を言った。
ムカデはその言葉をそれとなく受け止めると、また歩き出す。
「ああそうだ……」
ムカデが何かを思い出したように足を止めた。
「その子しばらくは歩けないだろうから、お前がおぶってやれ」
今回はかなり読みづらいかもしれません
三人称視点で書くのって難しい……
百足ッ!?これはとても強そうで頼りになるだろう…と思ったらなんか敵対関係だったみたい……
でも二人ともフレンズ助けをせずにはいられないので自然と馴染んで安心しました
今回はケガの描写に本当にゾッとさせられて、お見事だと思いました
イシちゃんとササコちゃんが数々の苦難を乗り越え、本当の友達に少しずつなろうとしている過程なんだと思ってこれからも応援しますッ!
人知れず改名しましたが、ダアッたーです。
コメントありがとうございます!!
ムカデちゃんは実は作中最強のフレンズですが、その戦闘力は正規のフレンズには若干ゃ劣ります
二人が敵対していた理由に当たる部分もそのうち描写できればと思っています
ケガに関しては、あえてササコ視点では詳細に描写しないようにとかちょっと工夫してみました
これからも頑張りますッ!
改名の件、了解しました👍
ネタばれ注意
鉛色の空の下、二人の少女が見つめ合う。
仰向けになった少女が見るのは、淡く輝く琥珀色の瞳。
その上に覆いかぶさる少女の目に映るのは、深く透き通る黒い瞳。
二人はお互いに目を合わせて、決して視線をそらそうとはしない。
「……ササコ…?」
黒い瞳の少女が恐る恐る呼びかけた。
「……」
琥珀色の少女は応えない。
彼女は無言のままゆっくりと目を細めると、口元を歪めて笑った。
ーーーーーーーーーーーーーーー
「ここをこうして……」
「こう、ですか?」
「あっ、そこじゃないわ」
「えっと…じゃあ、こっち?」
「そうそう……ああ、そんなに強く引っ張っちゃダメよ」
「すみません…」
「いいのよ。だけど今度はもう少しやさしく、ね」
「やさしく……」
今私は、イシちゃんに教わりながら、何かを作っている。
材料は白い花。
長い茎の先端に小さな花がたくさん付いている、変わった形をした花だ。
イシちゃんは確か……シロツメクサとか言っていたと思う。
……あれ?
この花の名前を思い出して、ひとつの疑問が浮かんだ。
もしかするとこれは、花じゃなくて……草なのでは?。
「どうしたの?」
私の手が止まっていることに気づいたイシちゃんが、心配そうに聞いてきた。
この花が本当に花なのかを、彼女に訊いてみようか……?
……。
……やめておこう。
私は、さっきまで抱いていたちょっとした疑問を飲み込むことにした。
それを聞いたところで、きっと答えてはくれないから。
今のイシちゃんは、なんだか意地悪なのだ。
私が何を作っているのかを訊ねても、「内緒」と言って教えてくれない。
「いえ、なんでもないです」
私がキッパリと言うと、イシちゃんは「そう?」と訝しげに言った。
今振り返れば、彼女のいかにも訝しげといった顔が見れるのだろうけど、今はとりあえず我慢しておくことにする。
……それにしても、私は一体何を作らされているのだろう?
「こんな感じですか?」
「うん、いいわね。あとはそれを繰り返して……」
イシちゃんはそう言うと、私の手元の作りかけに、スっと手を伸ばしてきた。

その手には一本のシロツメクサが握られていて、それをぎこちない手つきで作りかけに巻き付けていく。
不意に、彼女の細い指が私の手の甲に触れた。
これ、なんだか…くすぐったい。
「あ、あの……」
「んー?」
私はイシちゃんに抗議をすべく、振り返ろうとした。
しかし、それは出来そうになかった。
というか不可能だった。
私が文句を言うべき相手は今、私の左肩に顎を置いてしまっていて、背中からは彼女の鼓動が伝わってくる。
……それらが意味するのは、私とイシちゃんの距離が物理的にとても近いということだ。
それは、お互いの吐息が聞こえる程に近い距離。
……。
……つまり、つまり、……比較的客観的倫理的合理的に見て…このまま振り返るのは、すごくすごくまずいことなのだ。
…………。
私が今ここで振り返ることによって起こりうるコト。
それは……。
……刺さる。
私のツノが!
イシちゃんの側頭部に!
それもかなりの確率で!!
……はぁ。
私のテンションがどこかおかしくなっている気がするのは、…多分気の所為では無いだろう。
そうだ、イシちゃんの所為だ。
……。
自分でも分かっている。
別に振り返らずとも、一言文句を言うことくらいはできることを。
なのに私はそれを実行していない。
だから、このなんとも言えない感情の原因は私にもあるのだ。
……というかむしろ私の感情なんだから、大体私が悪い。
結局私は、イシちゃんに文句を言うのを諦め、黙って耐えることにした。
私の中で渦巻いている、この正体不明の感情の説明をするよりも、このまま何もしない方がきっと早く終わる。
私は目を閉じ、この色んな意味でのくすぐったさに耐える姿勢に入った。
失われる視覚情報。
研ぎ澄まされるいくつかの感覚。
増幅される……くすぐったさ。
どうせすぐに終わる。
だから我慢……。
我慢……がまん……。
心の中でそう何度も唱える。
こんなものでも、気休めにはなるはず…。
こうして何かに集中していればぁ…………あ! ほら、終わっ……ん?
一度は離れたくすぐられるような感覚が戻ってきた。
私は、嫌な予感がして目を恐る恐る開けた。
「ふんふんふーん♪」
「ぁ……」
私の目に飛び込んできたのはさっきと全く同じ光景。
瞼が上がりきる前に見えてしまった、非情な現実。
イシちゃんの手には一本のシロツメクサが握られていて、それをぎこちない手つきで作りかけに巻き付けている。
……同じ動作で、同じ不器用さで。
さっきと違う点をあげるとするならば、私の持つ作りかけが、シロツメクサ一本分だけ華やかになっていたこと(勘違いじゃないことを願わずにはいられない)くらいだ。
……いや、もう一つだけあった。
草が一本増えたとか減ったとかそんな不確かなものでは無い、明らかな違いが。
「ふふんふんふふーん♪」
「た、楽しそうですね……」
「ええ、とっても楽しいわよ?」
イシちゃんはそう言うと、心底楽しそうに笑った。
うぅ……私は今それどころじゃないのに…。
そんなふうに笑われては、全部許してしまいそうになる。
「ふふんふふふふーん♪」
イシちゃんは少しの間手を止めていたが、私の二の句が無いのを確認すると、また鼻歌交じりに作業を再開した。
こんなにも楽しそうな彼女の邪魔をするのはとても忍びない。
だが、そんなことを気にしている余裕が私に無いのは確かだ。
やはりここはなにか一言言ってやらねば。
「あの!」
「なぁに?」
返事はすぐに返ってきた。
それはもう、瞬間的に。
私から声をかけられるのを待っていたと言わんばかりの素早い応答。
それに驚いた私は、咄嗟に言うつもりだった言葉を飲み込んでしまった。
今から新しく言葉を紡ぎ出すことも出来ず……
「なんでもない、です」
私は渋々直前の発言を取り消したのだった。
ーーーーーーーーーーーーーーー
「なんですか、その輪っかは」
私はちょっとムスッとして言った。
するとイシちゃんは、ちょっとだけ不機嫌な私とは対照的に、ご機嫌な様子で笑った。
「これはねぇ……」
イシちゃんはゆっくりとした動作で、シロツメクサの輪っかを天高く掲げると、そのままそれをこちらに向けて振り下ろす。
スポッ
「……え?」
何も見えない。
私の視界が唐突に奪われた。
「クク……」
どこからともなく笑いを堪えるような声が聞こえる。
「これは、……目隠し?」
「クク…ふふふ……」
私が思ったことをそのまま口にすると、笑いを堪えるような声がただの笑い声になった。
これは間違いなくイシちゃんの声だ。
もしかして私はからかわれているのでは?
私が困惑している間も笑い声は止まらない。
止まる気配がない。
「なんですかこれはぁ!?」
「ふ、…ごめん…ね。ふふっ」
イシちゃんは笑い半分で謝ると、頭の輪っかを外してくれた。
ようやく戻った視界には、やはり楽しそうに笑う少女の姿があった。
そんな彼女を見ていると、なんだか怒る気も失せてしまう。
「それで、なんですかこれ?」
「これはね」
イシちゃんは輪っかから数本のシロツメクサを抜くと、先程よりも一回り小さな輪を作った。
そして、もう一度私の頭に被せようとしてくる。
一瞬、頭を動かして避けるという考えも浮かんだが、彼女の表情からは悪意が感じられなかったので、私はそのまま受け入れることにした。
……。
頭に再び被せられたそれは、先程のように私の視界を奪ったりはしなかった。
「花かんむりっていうのよ」
イシちゃんが言った。
花かんむり。
私はその名前に心当たりがある。
「それって、王様とかが頭に乗っけているアレですか?」
「うーん……コレはどっちかと言うと、お姫様っぽいわね」
「お姫様……」
「そう、お姫様。とっても似合ってるわよ?」
私は頭の花かんむりを取り、イシちゃんに差し出した。
「私よりあなたの方が似合うと思います。なので、これは……」
「ダメよ、それはあなたのものだからね。……でもどうしてもって言うなら、貰ってあげてもいいわよ」
イシちゃんはさらに言葉を続ける。
「ただし、それはあなたが別の花かんむりを用意出来たらの話よ」
イシちゃんはそう言うと、数本のシロツメクサを差し出してくる。
私がそれをおずおずと受け取ると、彼女は満足気に目を細めた。
そしてその表情のままその場にしゃがみ、手のひらで地面をポンポンと叩いた。
そこに座れと言うことだろうか?
少し考えて、今立っているこの場に座ることにした。
私が腰を下ろすのと入れ違いに、しゃがんでいたイシちゃんが立ち上がる。
そして、何事も無かったかのようにこちらまで歩いてくると、私の背後に座った。
「なんですか?」
「ふふん、教えてあげるわ」
「いや、でもさっき……」
「うん?」
教えるも何も、ついさっき間近で作るのを見ていたので、花かんむりの作り方は知っている。
「大体の要領はつかめたので、もう一人で出来ます」
私がそう言うと、イシちゃんは「そう?」と残念そうに言って、私の手元に視線を落とした。
「……じゃあ、見てるだけ」
「まあ、見てるだけなら……」
私は花かんむりを作り始めた。
たしか、…最初は二本だけ持って……。
「じー……」
そこに別の一本を巻き付ける。
「じぃぃー……」
「む……」
あとはこれを繰り返して……。
「じぃぃー……!」
「見すぎです」
「気のせいよ」
「そう…ですか?」
「じっ!」
「もう! あなたはそこの木陰でお昼寝でもしててください!」
「え〜? でも私、眠くなんてないわ」
「むー……」
私はイシちゃんの目をじっと見て、無言の圧力をかける。
「ま、まあそうね。ちょっとは眠いかもしれないわね」
イシちゃんが視線を逸らして言った。
もうひと押しだ。
「じぃー……」
「……分かったわ」
イシちゃんはそう言って私から離れると、木陰に向かってとぼとぼと歩き出した。
途中、名残惜しそうに何度も振り返る。
……ちょっと悪いことをしたかもしれない。
「分からなくなったら呼んでね」
少し遠くからイシちゃんが言う。
これが終わったら、存分に構われあげよう。
そして、彼女の好きな遊びに付き合うんだ。
私は来るはずの無い未来に思いを馳せる。
そうと決まれば、これを手早く完成させてしまおう。
ーーーーーーーーーーーーーーー
数分後
「とはいったものの……」
私は花かんむりを作る手を止めてしまっていた。
半分くらいを作り終えた所で、なんだか眠くなってきたのだ。
眠たい目をこすり、空を見上げる。
それで少しは目が覚めるだろうと思っての行動だったが、未だ私のまぶたは重い。
…………。
青く澄み渡る空は、どこまでも高くて。なんだか寂しい気持ちになる。
私は空に手を伸ばした。
決して届くことがないのは分かっている。
それでも私は……。
「静かだな……」
ふと思い立って振り返ってみると、イシちゃんは横になって目をつぶっている。
どうやら寝ているようだった。
眠たくないとか言ってたの。
仕方なく作業を再開したが、あまり捗らない。
「お姫様か……」
ふと、イシちゃんの言葉を思い出した。
花かんむりが、お姫様が身につけるようなものなら、それを被ったイシちゃんはさぞや綺麗なんだろうな。
そう思った私は、後の楽しみを損ねない程度にぼんやりと想像してみることにした。
白い肌に、緩くウェーブのかかった綺麗な髪。
瞳は深い黒色をしていて、イシちゃんの雪のように白い肌を際立てている。
そんな彼女が身に纏うひらひらも、調律の取れた白と黒で色づいている。
それだけでも十分すぎるほどに綺麗なのに、花の輪っかをかぶせたりしたら、かえって邪魔にならないだろうか…?
少し心配だが、物は試しという。
私は完成した花かんむりを、イシちゃんの頭にそっとかぶせる。
……。
すると……そこには、お姫様がいた。
一度も見たことはないが、イシちゃんは私の想像の中のお姫様そのものだった。
イシちゃんがお姫様なら私は……騎士?
うーん……私につとまるかな?
だってそんなに強くないし、かっこよくもないしな……。
騎士がダメなら……
……王子様…とか。
・・・
そんなのもっとダメだ。
私じゃイシちゃんと全然釣り合う気がしない。
でも……いいなあ、王子様。
…………。
ううん、別に王子様じゃなくたって、ただ一緒にいられればなんだっていいんだ。
たとえ一般兵だって構わない。
むしろ私らしいとも言えるし。
イシちゃんの唯一無二に慣れないのは残念だけど、彼女を守って死ねるのならそれで……。
「……あれ?」
素敵な想像していたつもりが、いつの間にか変な妄想をして、勝手に落ち込んで……。
挙句の果てに、これは……涙?
……。
「よしっ」
私はもう一度、眠たい目をこすった。
まぶたは重いままだ。
早く作らないと。
そんなに難しい事じゃないはず。
イシちゃんなんか、ほとんど片手だけで完成させたんだ。
だから、私にだってできるはずなんだ。
一本、もう一本とシロツメクサを絡めていく。
段々と動悸が激しくなる。
「もう少し……」
あとは、最後の仕上げ。
輪っかを作って……。
……ダメだ。
「…………」
白い花のかんむりモドキは赤く汚れてしまった。
せっかくここまで紡いできたのに、全部台無しだ。
せっかく、頑張って作ったのにな。
こんなの被せちゃったら、イシちゃんは怒るかな。
「ご…め……」
急に息苦しくなって、出かかっていた言葉が掠れて消えてしまった。
お腹に違和感。
違和感の正体を手を当てて確かめようとしたけど、それは途中で遮られた。
何かに触れたのだ。
本来そこに無いはずの何かに。
不思議に思い、私はぼんやりと視線を落とした。
……え?
鋭利な赤色が突き出していた。
まるで、土の上に花が咲くみたいに。
あ、そういえば私のお腹も土の色と似てるな……。
ふと、そんなことを思った。
でもこれは花じゃない。だったらなんだろう?
よく見てみようと屈もうとしたが、上手く屈めない。
違和感と痛みが強くなるばかりで、体はちっとも曲がらない。
痛み……?
私が当然の疑問を浮かべたところで、突然花のような何かがずいっと茎を伸ばした。
これならよく見える。うん。
私は、何だか焦点の定まらない目でそれをまじまじと見つめる。
赤くて、尖っている。
それを見て、私はなあんだと思った。
それは私がよく知る形だったから。
もっとも、私が知っているそれは赤くなんかなかったけど。
疑問がひとつ晴れて私がほっとしたのもつかの間、大きな疑問が残されていることに気づく。
どうして私のお腹にナイフが刺さっているの……?
考えたところで分かるはずがない。
なぜなら、いつの間にか、気づいたら刺さっていたのだ。
さっきまで*****を作っていたのに。
お腹に***が刺さって気づかない訳が無い。
こんなに痛いのだから絶対に気づく。
でも、これって…………え?
何が起きているのか分からなくて、イシちゃんの方を見る。
だが、答えは得られなかった。
彼女は口元を不気味に歪ませるだけだ。
いつか見たあの表情。
恐ろしい程に色の無い、あの顔。
だけどその顔もすぐに掠れて消えていく。
……。
今では、あの無色透明な色でさえも恋しい。
前半と後半で文体がかなり違うのは、書いた時期が違うからです
一応直そうとはしたのですが、直そうとするほど変な感じになってしまって……
結局そのままで上げています。
原っぱで花冠作り……ゆっくりと時間が流れている………
もう、イシちゃんのことを思うと涙が出るほど別れたくなくなってきちゃったんですね……
と、いう夢から覚めそうなほどの衝撃が………
これこそ夢だと思いたい………夢であってくれっ………
最後の文で一気に一話の雰囲気に近くなってるように感じました👍
この段階でもう既に、ササコはイシちゃんのことを本当に大切に思っているんですよね
いつの間にか呼び方も変わっていたりして、色々と違和感を覚えたかもしれません
でも、今はそれでいいのです。ちょっとくらいもやもやっとしてた方が、次回からの展開を受け入れやすくなる……はず……だといいな、です
ササコの身に起こったことについて
後半の脈絡のない不自然な展開を見るに、全てを現実ととらえるのは難しいかもしれませんね
最後の一分は一話を投稿した当時から考えていたものでして……
これはいつか絶対に入れよう、と思っていたので、そこに注目してもらったのは結構嬉しかったりします
あ!もちろん、コメントを頂けること自体がありがたき幸せです
感謝してます!
*致命的なネタバレは避けているつもりですが、あんさん喋りすぎやでという場合は遠慮なく「ネタバレやめれ!」とおっしゃってください。自嘲しますので
それは、とある夏の日の昼下がりのこと。
一人の少女が鮮血の海の中心に横たわり、狂ったように笑い声を上げる。
この世の全てを嘆くようなその響きは、時に自分自身の首を絞めあげるようにねじれ、掠れる。
その狂ったような笑い声が、どのような感情から湧き上がったものなのかは誰も知らない。
彼女自身さえも。
複雑化しすぎた彼女の心は、きっと誰にも理解しえないだろう。
───────────────
「ざまぁみろ」
私は憎々しげに小さく呟いた。
これは、私を殺そうとした彼女への悪態。
私はまだ生きている。ざまぁみろ。
思いっきり憎悪を込めて吐き出したはずなのに、心はちっとも晴れない。
「……」
……本当は分かっているはず。
彼女は、ムカデは何も悪くない。
彼女はあの子を守りたかっただけ。
だから、そんな彼女にこんな憎悪が向けられるのは間違っている。
それを理解した途端に、行き場を失った黒い感情が全て私に帰ってきた。
この醜い感情も、当然の痛みも、全部そのままの形で受け入れよう。
それだけが、今私に出来る唯一の償いのフリなんだ。
「……ざまぁみろ」
今度は間違えない。
これは、悪事がバレて懲らしめられた馬鹿な私自身への、嘲りの言葉だ。
「……ざ…まぁ……みろ」
涙が込み上げてくるのを感じる。
私はそれをぐっとこらえると、鼻をすすった。
泣くわけにはいかない。
もしここで泣いてしまったら、今以上に惨めな気持ちになってしまいかねないから。
立ち上がるために、地面に両手をつく。
身体のあちこちが痛むけど、いつまでもこんな所にはいたくはない。
「っ……」
私は立ち上がると、空を見上げた。
このままではまた泣いてしまいそうだったから。
悲しみを諦めに変えてくれる、灰色の空。
今日も、雲の切れ間からは憎々しげな視線が私を覗いていた。
「ん……」
ふいに、鼻につんとした痛みを感じた。
あんなに大嫌いだったこの痛みも、今ではなんだか可愛く思えて……。
「あはは……」
自然と笑みがこぼれた。
よし、その調子。
ポジティブなだけが私の取り柄だったはずだ。
それすらも無くなってしまったら、今度こそ本当に死んでしまうかもしれない。
それは、…ダメだ。
少しだけ元気になれたところで、ようやくまともな思考回路を取り戻せた。
そして私は、今までの自分の不用心さに気づき、青ざめる。
「血、洗わないと……」
今、私の服は自分の血で真っ赤に汚れてしまっている。
こんな、全身血まみれの姿で歩き回っているのを誰かに見られでもしたら、もう二度と自分の足で歩けなくなるかもしれない。
もしそうならなかったとしても、良くない噂が立つことは目に見えている。
これだけの血を流して、平然と生きているなんてありえない。
だから私を見たフレンズはこう思うだろう。
───私が、誰かを食い殺したんだって。
でもそれは仕方の無いことだ。
だって、これは誰が見たって返り血にしか見えないから……。
目を落とし、服の汚れ具合を再度確認する。
これだけ汚れてしまっては、雨水だけでは綺麗にならないだろう。
雨なんかよりも、もっと沢山の水が必要だ。
「そうだ、川……」
川、それは沢山の水が絶えず流れる場所。
そこへ行けば、この服もある程度は綺麗にできるはず。
「私にしてはいい考えだね」
自分を元気づけようとして言ったはずの言葉が、胸に突き刺さる。
痛い。苦しい。……悲しい。
これではまるで馬鹿みたいだ。
「……そんなの、分かってるよ」
諦めるように呟くと、心がたちまちに軽くなった。
「よし、行こう」
私は酷く軽いこの心が、再び重さを取り戻してしまう前に、川へ向かうことにした。
誰にも出会わないように、あえて危険な道を通って。
───────────────
草の根をかき分け、何とか無事に川にたどり着くことが出来た。
少し時間はかかったものの、想定していたよりもずっと早く着いた。
早速、川の前にしゃがみこんで手を水に浸してみた。
すると今度は嬉しくない想定外が……。
「うぅ……つめたい」
川の水は思っていたよりもずっと冷たかった。
そのあまりの冷たさに、さっき頑張って堪えた涙が、再び滲み出してくる。
「……」
川の水を少し手ですくって、何度かスカートにかけてみたけど、ちっとも綺麗にならない。
私は少し考えて、この冷たい水の流れに足を踏み入れることにした。
ちゃぷん
静かに、ゆっくりと片足を水に沈める。
この川はそれほど深くはなく、すぐに川底に足がついた。
「冷たいけど、我慢……」
次に、スカートを持ち上げてもう片方の足を踏み出す。
二度目ということもあってか、今度は冷たさがそんなに気にならなかった。
両手をスカートからぱっと離すと、重力に従って水面にふわりと乗り、やがて水を吸って重たくなった。
私は、水中でヒラヒラと泳ぐそれをぼんやりと眺める。
「…………」
…………違う。
私が本当に見ていたのはその向こう側だ。
川底に沈む自分の面影だ。
そいつは、とても凶悪な目付きでこちらを睨みつけていた。
ぱしゃん!
私は水面を蹴った。
でも、消えない。
踏みつけても、踏みつけても、そいつは一時的に形を歪めるだけだ。
「ハァ……ハァ…………ふっ」
やつが口元を不気味に歪め、目を細めた。
その次の瞬間───。
バッシャン!
私は、冷たい水に全身を沈めていた。
ゴポゴポ……
……冷たい。
ゴポ……ゴポ……
……痛い。
ゴポッ………………
苦しい。
………………
このまま、もう少し。
……………。
ざっばぁん!
「げほっ、げほっ!…………けほっ」
冷たい水を吐き出す。
……。
少し…体温が下がったのかもしれない。
雨水が温かく感じられるから。
絶え間なく落ちてくる熱い粒が、私の全身を包み込んでいた痛みを奪って行ってしまう。
「もうちょっとだったのにな……」
無意識にそんな言葉が零れた。
これは……違う。
「もう少しで楽になれたのに」とか、そう言うのでは決してない。
本当に違うから。
誰にともなく言い訳をする。
「……どう違うの?」
それは……。
…………。
私は嘆いたんだ。
ありとあらゆる可能性を失い、最後の最後に残されたたった一つの希望をかけた、その計画の失敗を。
もう少しで、上手くいったのに。
私がやったのは、見つかれば叱られるような悪いことだったかもしれない。
だけど私には、素直に叱られて全部終わらせるなんてことは出来なかった。
突然の計画の終わりを予感して、強い焦燥にかられた私は、叱られるだけでは済まないことを言ったんだ。
目を閉じ、失敗の記憶を思い出す。
私は名前も知らないあの子を両手で抱いていた。
あの子は震えていた。
怯えていたんだと思う。
その様子を間近で見て、私は微笑む。
とても満ち足りた気持ちだった。
……そんな時だった。
背後から声をかけられた。
私が振り返るよりも早く、腕の中の少女が震える声で言った。
「ムカデちゃん、…たすけ…て」
私は振り返り、ムカデと呼ばれた少女を見た。
目を吊り上げ私を睨む彼女は、とても怒っているようだった。
お前のことは知っているだとか、その子を解放しろだとか、そんなことを言っていた。
その時、私はムカデになんて言ったんだっけ?
確か……
「あなたには関係ないでしょ?
この子はもう私の物なんだから、何をしたって私の自由。
あなたはいらない。だから、何処かに行って」
こんな感じのことを言ったと思う。
……。
これは…まあ、誰がどう見ても私が悪いだろう。
何をされても文句は言えない。
実際、罪を認めずに変に開き直った私は、酷い(当然の)仕打ちを受けている。
「……」
でも、私は懲りない。
……懲りる訳にはいかない。
今の私には、もうこれしか無いから。
途中までは上手くいってたんだ。
だから、だから……
「だから…」
…………。
今度はもう少し優しくしよう。
優しくして、仲良くなろう。
そうすれば、みんなからも本当の友達みたいに見えるはず。
友達になったら、たくさん助けてあげるんだ。
……そうして、全ての役目を終えた時、きっと私はあなたと同じ所へ行ける。
「そうだよね、…アメちゃん」
あなたの代わりになると決めたあの日から、いつか来る最期の日まで。
それまで私は、立派にあなたの人生を生きていくよ。
服を洗い終えて川から上がると、さっきまでの寒さが嘘のように消えてしまった。
今は、近くにあった木の下で服を乾かしているところだ。
……………………。
これだけびしょ濡れでは、いつまで経っても服が乾くことは無いだろう。
……でも、そんなことはもうどうでもよかった。
「何がダメだったんだろう……」
意識的に口に出したのは、そんな言葉。
それはこの上なくわざとらしい響きを持っていた。
こういうことを言っていいのは、何の後ろめたさも持たない純粋な心の持ち主が、自らが考えうる最善の努力をした時だけだ。
残念ながら、私はそのどちらにも当てはまらない。
最悪な企みをダメなことと知っていながら実行した私に、その言葉を口にする資格はなかった。
だから、本当はこう言うべきなのだ。
「どうすれば、もっと上手くいったのかな」
好意的な言葉は無駄だと知った。
だから、わざと怖がらせるようなことを言ったのに。
「……」
最初は上手くいってたんだ。
恐怖は相手を束縛するのには最適だった。
逃げようとするのは、生きようとする意思があるからだ。
だから、それを奪ってしまえばいいと思った。
生きるのを諦めさせる程の恐怖を与えれば、と。
罪悪感はあった。
でも、それもいつかは無くなるものと信じこもうとして……。
最初の間違いで味をしめた私は、気の弱いあの子に、毎日のように恐ろしい言葉を浴びせかけた。
何度も、何度も、同じ罪を重ねていって……。
……そうして、今に至る。
恐怖はあの子を拘束する以外の意味を持たなかった。
過度な脅かしが、あの子と私を永遠に隔ててしまったんだ。
──ぴしゃん!
……落とした視線の先に、あまりに邪悪な顔が写っていたものだから、反射的に水たまりを蹴ってしまった。
「………………」
最初のうちは、本当に上手くいっていた……と思う。
しつこいようだけど、何度も失敗を経験してきた私が言うのだから、間違いは無いはず。
……。
私は、今回の失敗から学ばなければならない。
こんなことをまだ続けるのかと、誰もが思うだろう。
でも、どうか、安心して欲しい。
次で最後だから。
……何となく分かる。
こんなこと長くは続かないって。
もし次も失敗してしまったら、私はきっと、全部を諦めてしまえるから。
だから、最後にもう一度だけチャンスをください。
……そうは言っても、次の私の被害者には安心どころじゃないのかもしれない。
だったら、私が謝らなくてよくなるほどに、たくさん優しくしてあげるから……。
私に残された時間の全てを、あなたのために使うから……。
だからどうか、許してほしい。
「きっと、うまくいくよ」
後ろ向きになりそうな思考を、前向きな言葉で遮った。
これからどうすればいいのかは、もう分かっている。
私は、足元の水溜まりで素敵な笑顔の練習をしてから木陰を飛び出した。
短く、ストーリーがあまり進展しない
前回のかさましのような11話です
これからはイシちゃん視点で進むのかな?
突然姿を消したササコ…
自暴自棄になって溺れかけるなんて、独りじゃなければ助けてもらえるのに…
自分の不器用さを身にしみて嫌っているのがわかる…
ムカデでもだれかがいればいいのに、と思います
チェック頻度がさがってて10話とまとめての感想になってしまいましたが、楽しませてもらいました
ご明察の通り、ここからはイシちゃんの視点で書いていきます
ササコ視点の時よりも読みづらく、感情移入もしづらいかもしれませんが、どうにか形にするつもりです
ササコやムカデも不器用ですが、イシちゃんはそれ以上に不器用かもしれません。
いちいちチェックしないと更新されているかわからないのは面倒ですよね
投稿期限を決めるというのも考えましたが、期限を守れる気がしなくて……
見ての通り、あまり更新頻度は高くないので、ふと思い出したときにでも見に来てもらえればという感じになっておりますすみませぬこめんとありがとうございます
「……見つけた」
木々の隙間から確認できた姿は、間違いなくフレンズのものであった。
全身傷だらけで、見るに堪えないようなその少女の姿を見た私は、心の内で喜んでいた。
そして、「彼女しかいない」と思った。
私は彼女の姿を見た瞬間、本能的に見下して、選択をしたんだ。
自分より弱そうな彼女になら返り討ちにあう心配はないと、そう思ったのだろう。
それは最低な私の、最悪な打算だった。
「……」
自分がどれほど卑劣かなんて、今更もうどうでもいい。
今を逃してしまえば、もう二度とこんな機会はないのかもしれない。
こんなところを一人で、それも俯きながら歩くような不用心なフレンズは、彼女くらいのものだ。
この幸運を逃すまいと思った私は、彼女に近づくことにした。
……私にとっての幸運も、これから私と出会う彼女にとっては、間違いなく不運だと言えるだろう。
そう思うと、急に足が重くなって……。
「……ごめんね」
誰にも届かないくらいの声で謝罪の言葉を呟くと、少しだけ心が軽くなった気がした。
ーーーーー
雨粒を蹴飛ばしながら、名前も知らないフレンズのあとをつける。
最初はあまり近づき過ぎないように、一定の距離を保ちながら歩いていたのだが……。
「…………」
一人の時に背後から急に話しかけられたら、誰であろうと驚いてしまうだろう。
それならばと、私は相手から自然に存在を認知してもらえるように、少しずつ距離を詰めていった。
しかし、一向にこちらの存在に気づく気配がない。
そして私は、ついに、彼女の真後ろと呼べるであろう距離まで近づいてしまっていた。
……それでも彼女は気づかない。
もしかして、知らない子の後ろにぴったりとくっついて歩いている今の私は、とんでもなく怪しいやつなのでは……?
「うん、そうだよ」
「!?」
目の前の少女が唐突に言った。
その言葉の意味がうまく理解できない。
『うん』
これは、肯定の言葉。
『そうだよ』
これも……肯定を意味する言葉だ。
この二つがあわさっても、反対の意味になったりはしない。
それどころか、お互いの意味を強め合い、より確実な肯定の言葉となっている。
…………。
でも、それなら彼女は誰に向かってその肯定の言葉を言ったのだろうか?
この場には彼女と私の二人しかいない。
それなら、私に言ったというのが自然だろう。
だけど、それはない。
私は何も口にはしていない。……はず。
そうなると、やっぱり彼女が言ったのは独り言ということになるわけで……。
バシャバシャッ!
突然の大きな水音。
気づくと、傷だらけの少女は私から距離を大きくとっていた。
急に走り出したのだ。
私が慌てて後を追おうとした時、彼女がばっと振り向いた。
驚いたように目を見開く少女。
だが、その目はすぐに訝しげな表情の一部となる。
「あの、……どうしてついてくるんですか?」
丁寧な口調で、問いかけてくる。
「どうして」と聞かれると、どう答えていいか分からない。
「さて、…どうしてかしら?」
咄嗟に答えが思いつかず、質問をそのままの形で返してしまった。
これを聞いた少女は、一層疑わしげな視線をこちらへ向ける。
彼女はそのまま少しの間、私の目を、見張るように見つめていた。
そして、ようやく視線を外すと、「用がないならいいです」と言って、こちらに背を向けてしまった。
「せっかく出会ったんだもの。仲良くしましょう?」
彼女を引き止めるために放った咄嗟の一言は、調子はずれなものだったけど、そんなに悪くはなかったはずだ。
それでも、無視されたりしないかと少し不安だったので、私は言葉の最後に「ね?」と同意を求めるように付け足した。
「…それは、できません」
彼女は言った。
当然のことを口にするように、きっぱりと断られた。
「あら、どうして?」
平然とした態度で言ったつもりが、少し声が震えてしまった。
私の悪評を知らないみたいだったから好意的に接してみたけど、やっぱり、それは間違いだったのかもしれない。
「どうしてって……」
目を逸らして言いよどむ。
私は、彼女が見せたこの一瞬の隙に、空いていた距離を一気に詰めた。
これでもう、逃げられない。
「ねえ、どうして?」
改めて、もう一度質問をした。
これは、最終確認。
彼女の次の一言で、私のことを知っているかどうかを判断する。
別に知ってるなら知ってるで、構わない。
その時は、今まで通りにするだけだ。
……ああ、でも、……今まで通りじゃダメだったんだっけ。
「私、……友達は作らないって……決めてるんです」
「ふーん、そう……」
これは……難しい。
もしこれが、私の機嫌を損ねず逃げるために吐いた嘘なら、なかなかよくできた嘘だ。
でも、もし……本当のことだったら…?
私はもう一度、好意的な言葉で繰り返してみることにした。
「仲良くしましょう?」
言ったあとに気づいた。
彼女が本当のことを言っていたとしても、その先には同じ拒絶があるのだ。
「その、だから……」
少女は困ったような顔をした。
私のことを、理屈が通じない我儘なヤツだと思っているのだろうか。
……でも、その通りだから仕方ない。
「……はぁ」
もう、ダメだ。
これ以上問答を続けても無意味だ。
やっぱり私には、真っ当な方法で友達を作るなんてできなかった。
それだけの事。
私は少女の頬に両手を添えて、彼女の目を覗き込んだ。
綺麗な琥珀色の瞳に影が差す。
「あなたは私の言う通りにしておけばいいの。だってあなたは私の暇つぶし兼、非常食なの。
……あなたがどう思おうが、絶対に逃げることは許さない。…あなたに拒否権はないわよ」
私は、足りない頭で精一杯考えた脅し文句を言った。
今度は無闇に怖がらせ過ぎないようにと、できるだけの優しい口調と笑顔を心がけたのだけど……。
私のそんな配慮は、無駄なものだったのかもしれない。
少女は私が今までに見てきたどんな顔よりも、怯えた表情を見せた。
見開かれた目は、焦点が定まらないのかどろんとしている。
それでいて、私と目を合わせないようにと、必死に視線をそらそうとして蠢く。
瞳を直接覗き込んでいるのにも関わらず、全く目が合わないのは、彼女の無意識下の努力が報われた証拠なのかもしれない。
ぱちゃん
私が手を離すと、少女は地面にへたりこんでしまった。
余程怖かったのだろう。
そんな他人事みたいな言葉が浮かんだ。
ぜんぶ、私のせいなのに。
そこまで考えたところで、ようやく、心に小さな罪悪感が芽生えた。
これは、大事な感情だ。
今日まではずっと、邪魔だとしか思えなかった、とても大事な感情。
ずっと目を逸らして、邪険にして……。
そして、いつしかそれを抱くことはなくなっていって……。
……でもそれは大きな間違いだった。
誰かを傷つけたら、その罪に見合うだけの苦しみを味あわなければならない。
じゃないと、また傷つけてしまうから。
何度だって、際限なく繰り返してしまうから。
だから私は、二度と間違えないために、精一杯苦しまないといけない。
……やっと気づけたんだ。
もうこの芽を摘むようなことはしたくない。
この罪悪感は、絶対に忘れないようにしよう。
私は罪悪感が示す通りに、何とか怯える少女を安心させる術を探した。
…………。
……頭を撫でれば、少しは落ち着くだろうか…?
私は少女の頭に手を伸ばそうとした。
───その時。
「……っ!」
頭が……痛い。
突然ひどい頭痛に襲われて、差し出しかけていた手を引っ込めてしまった。
頭の中で、なにかよくないモノが這いずり回っている。
……ああ、そういえば今日はまだ、虹草を食べてないな。
今日は色々あったから……それで食べ損ねたんだ。
辺りを見回しても、あるのは真っ赤な草ばかり。
虹色に光る草はどこにもない。
探しに……行かないと。
虹草は、そんなに珍しいものではない。
少し歩けばすぐに見つかるはずだ。
私は、地面にへたりこんだままのソレに背を向け、元来た道を引き返す。
一歩、二歩。
遠い。まだつかない。
三歩、四歩。
胸が苦しい。
視界も既に、赤色に侵食し始めている。
……そうだ。
五歩目を踏み出したところで、ふと、背後の少女のことを思い出した。
ゆっくりと振り返る。
……横たわる彼女の顔を見て、私は息を呑んだ。
赤く染りゆくその顔は、私のよく知る人物にそっくりだった。
(黄金に輝く瞳は、瑞々しい、まるで禁断の果実のようね。
それに……彼女の真っ白な頬には、本物の赤がとってもよく似合うはずよ)
誰かの悪意が木霊する。
頭の内外から戯言を吐き続けて、私に思考を放棄させようとする。
だけど、私はそんなの認めない。
私は流れ込む衝動を喰い殺し、たった一言を絞り出した。
「またね」
ムカデの容姿
ササコやイシちゃんよりもさらにちっちゃい(身長)
友達をどうしても作りたくてササコに接近したけどどうしてもうまく接することができなくて警戒されていたと………
たまたま会って友達になろうとするのは険しい道だけどイシちゃんなりの苦悩が伝わってきました
イシちゃんは一度まっとうなやり方を諦めてしまているので、どうしても良くない方法を選ぶ傾向にあります
それは選択肢の一番上に「脅す」があるような状態で、
それでも、なんとかササコとちゃんと仲良くなろうとするのですが……
好意的な態度での成功経験のなさゆえか、脅すような言い方をしないと不安で仕方なくなってしまうようです
多分この子が一番人に近しい精神を持っていますが、その心の弱さゆえの苦悩も多いのかもしれません
物音に気がついてふと目を覚ました。
いつの間にか寝てしまったらしい。
「……?」
ここは…何処だっけ?寝起きで頭が上手く回らない。
辺りを見回すも、視界はまだぼんやりとしている。
「ん……」
そろそろだ、と思った。
視界が段々と鮮明になっていく。そこでようやく物音の正体を視認できた。
あれは…私だ。
私がいる。
こちらに背を向け、一心不乱に何かを貪っているみたいだ。
くちゃくちゃ、くちゃくちゃ。
ぴちゃぴちゃ、ぴちゃぴちゃ。
ぴちゃん、ぴちゃん。
何かが滴る音がする。
私の口の端から涎と混じった赤い汁のような物がたれている。
まったく、なんてはしたない。
ふとそんな事を思った。
ぴちゃん、ぴちゃん、ぴちゃん
水音の間隔が段々と小さくなっていく。
そして────
グシャッ!
……何かが落ちた。
それに目をやると、赤黒い…木の実のようだった。
ぼんやりとソレを見詰めていると、目が合った。
「え…?」
理解し難い出来事に、なんとも間抜けな声が出る。
目が合うなんて、そんなことはありえない。
だって、木の実に目なんてある訳が無いのだから。
でも、……目はあった。
だったらこれは…果物ではない。
それが何かを理解する前に、口が動いた。
「ひ、ひとごろし」
奥歯がガチガチと音をたてているのを感じる。
そう、これは恐怖だ。
心の底から怯えている。
目の前の狂人に次は自分が殺される。
それに怯えている。
殺人鬼に出会った者が抱く、ごく自然な感情だ。
だから私は狂ってなんかいない。正常だ。
頭の中で、私が恐怖を感じる理由をなんとも言い訳がましく積み上げていく。
『信じてたのに』
『どうしてこんなことをしたの?』
潰れた木の実が憎々しげに言う。
潰れた声で、潰れた眼差しで私を責め立てる。
違う、私じゃない。
だって、私はここで見ていただけだ。
そんな私に恨み言を吐くなんて、なんて身勝手なやつだ。
「違う」
木の実が言った。
何が違うものか。
これを身勝手と言わずしてなんと言う。
「違う」
まただ。
うるさいやつめ。
いっその事、もう二度とその口が利けないように、完全に潰してしまおうか?
「違う」
「……」
三度目でようやく、何が違うのかに気づいた。
やつは、私が感じている恐怖の理由を、見透かしていたのだ。
私はなんてことをしてしまったのだろう。
自分のした事がこわくてたまらない。
もう元には戻らない、取り返しがつかない。
"私は大切な友達を……この手で、殺してしまった"
私が殺した正義の味方が今こうして、裏切り者のとってもとっても悪い私を、殺しに来たんだ。
それならしょうがないよね。
死ぬのは恐いけど、これは当然の報い。
受け入れるしかない。
……でも待って、おかしいよ?
だって、あの子は死んじゃったんだよ?
なのに、どうして。
そこでようやく気づく。
ああ、そうか。
これは夢だ。
よくあるただの悪夢だ。
「ふっ……」
それに気づいたら、眼前の光景がなんだか馬鹿らしく思えた。
夢なら目を覚ませばいい。
そして二度と思い出せないように、永遠に記憶の奥底に沈めてしまおう。
いつもみたいに。
目を覚まそうと、意識を集中させる。
次第に目の前の悪夢が滲んで見えなくなる。
私はこれから目を覚ます。
そう思った時…
『ワスレルナンテユルサナイ』
────────────────────
「ッ!」
呪いの言葉で目を覚ました。
それは、私の記憶に鮮明に刻まれてしまったようで、目覚めの前に聞いたのか、それとも後なのか、それすらももう分からない。
「また……」
いつからだろうか。
私は毎晩、悪夢を繰り返し見るようになっていた。
だからこの目覚めはもう慣れっこだ。
だけど、あの悪夢だけはどうしても慣れない。
「でも…今日のはそんなに怖くなかったかな……」
今回の悪夢は、比較的マシな方だった。
今までで一番怖かったのは、赤黒い液体で満たされた空間の中で、赤や白のおぞましい何かが浮き沈みを繰り返すのをずっと見せられる、というものだった。
そんな、見方によっては幻想的に見えなくもないような悪夢は、手足を捥がれるよりも、殺されるよりも、ずっと恐ろしいものだった。
思い出すだけでも、頭がどうにかなりそうな血なまぐさい夢。
思い出したくなかったのに、思い出してしまった。
「はぁ……」
頬に伝う雫を指で掬い、目の前に持ってくると、それは赤かった。
私は次に、視線を少しずらした。
すると、目に映るものが何もかもが赤く見える。
……これでは、汗か血の判別もつかない。
「…………」
目は覚めたはずなのに、まだ赤い。
私は今もまだ、あの赤黒い箱の中にいるのかもしれない。
だから、この景色は悪夢の延長。
私はまだ眠ったまま……。
「それなら、早く起きないとね」
皮肉混じりに呟き、体を起こす。
そして、近くにあった硬い木のようなものにもたれかかった。
「まずは、ごはん……」
足元を見ると、たくさんの草っぽい何かが生えていた。
私はその中のひとつ、虹色に光るものをちぎり、目の前に持ってくる。
「食べないとだめだよね……」
何もかもが赤くなった世界で唯一赤くない色を持つそれは、私にとって、なくてはならないものだ。
これには、食べるとおかしくなった世界を元に戻す効果がある。
……正確には、おかしくなった私自身を治す効果と言うべきだろう。
これがなければいずれ、私は私でなくなってしまう気がする。
……ほかにも、少しの間意識がぼんやりとして上手く物事を考えられなくなる、という効果もある。
でもこれは、効果というより、副作用と言うべきかもしれない。
意識が朦朧としている時にセルリアンに襲われたりしたら、逃げることも難しくなる。
だけどそれも、食べすぎなければさほど問題はない。
再び意識が明瞭になった時には頭が少し軽くなり、気分もよくなるので、デメリットよりもメリットの方が遥かに多い。
……実を言うと、唯一のデメリットであるはずの効果も、私にとっては結構嬉しい。
安心して眠ることも出来なくなった今、何も考えずにいられる時間はとても貴重だ。
……となると、この草を私が食べることで得られる効果には、有益なものしかないということになるけれど……。
しばしの間、絶え間なく変色し続ける草を睨みつける。
それを見ていると、段々と動悸が激しくなり、さらには息苦しくなってくる。
私は目を閉じ、深く息を吸った。
そして、目を瞑ったまま草を口元まで持ってくる。
……ゆっくりと口を開け……僅かに開いた隙間から草を強引に押し込み、最後に両手で蓋をした。
まずいなんてもんじゃない。
もしゃもしゃ……もしゃ…………
ゆっくりと、吐き出さないように注意しつつ噛み潰していく。
もしゃ…………………………
…………………………………………ごくん。
「…………はぁー…………ぅッ」
少し安心したところで、強い嘔吐感に襲われる。
お腹の中で何か、熱いものが蠢いているような感覚。
「きもちわるぃ……」
いつも、今日は大丈夫なんじゃないかと期待をする。
今日は、気持ち悪くはならないんじゃないかと。
期待して、……そして、裏切られる。
……でも、日に日に感じる嘔吐感が薄れていっているから、このまま行けば、いつかは感じなくなるのかもしれない。
「………………」
しばらくの間、黙って吐き気が治まるのを待つ。
………………………………。
待っていると、次第に吐き気は弱くなっていき、……やがて治まった。
今日はいつもよりも早く終わった気がする。
そう感じた私は前回までを思い出そうとしたが、上手く記憶をだどれない。
それで、
思った。
もう、始まっていると。
────────────────────
虚無に身を任せること数分間。
私が再び目を開けた時には、世界はすっかり元の色を取り戻していた。
心は、いつもよりちょっぴりだけ晴れやかだ。
実際の空は、いつも通りの雨降りだけど、そんなことは気にしない!
今の私はとても機嫌がいいのだ。
木陰から這い出し、空を見上げる。
こんな良く雨が降る日には、誰かと鬼ごっこでもして遊びたい。
私に友達がいれば、すぐにでも追っかけ回していたところだ。
「友達……」
ふと、昨日あったフレンズのことを思い出した。
全身に傷を負った、琥珀色の目をした少女。
私は彼女に仲良くしようと言い、そして断られた。
何とかならないかと少し粘ってみたけど、答えは同じ。
しょうがないので実力行使に出ると、少女はひどく怯えた様子を見せた。
これは、私の脅しが最初の頃よりも洗練されつつある、ということだろうか。
あそこまで怖がらせるつもりはなかったんだけど……。
いくら「慣れ」ようが、不測の事態は起こるものだ。
だけど、今回のことに関しては、「慣れ」が事態を引き起こしたように思える。
相手が感じる恐怖の大きさを把握しきれていなかった私は、少しばかり対応を間違えてしまったのかもしれない。
「んーっと……あれ?」
ちょっとさじ加減を間違えただけで、私の作戦は何も失敗してないのでは…?
というか、あんなの間違いの内に入らないよ。
取り返しのつくうちは、何をしたって大丈夫。
いくら傷つけようが、最終的にその傷を癒してあげられればいい。
まだなんとかなる。
まだまだこれから。
なんかいろいろと難しく考えてた気がするけど、そんなのは全部余計なことだ。
考えた結果、後ろ向きな思考になってしまうのなら、考えない方がいいに決まってる。
前向きに生きれば、前向きに死ねるはずだから。
「よーし……」
今一度、気合いを入れ直す。
昨日、あの子は友達は作らないと言った。
どんな理由があるのかは知らないが、それでも独りは寂しいはず。
……それに、あんなに傷だらけになっても誰も助けてくれないのは、独りで生きてきたからだろう。
それなら、やっぱりこのまま彼女を一人にはしておけない。
私が傍にいて守ってあげないと。
「そうと決まれば!」
私は勢いよく立ち上がると、大きく伸びをした。
目を瞑り、深く息を吸う。
そしてそのまま、
「いつまでも孤独でいられると思うなよー!」
と、高らかに宣戦布告しようとしたが、恥ずかしいのでやっぱりやめた。
心の中で呟く程度に止めておくことにする。
「よし、行こう!」
私は雨の降り頻る森の中を、濡れることも気にせずに意気揚々と歩き出す。
────────────────────
今の私はあまり気分がいいとは言えない。
生温い雨粒が全身にまとわりつき、湿った空気が肺を満たしている。
それらの不快感が、体の内外から溶け込むように、私の質量を確かに増していく。
私の足取りは、段々と重くなっていった。
「はぁ……」
雨に濡れた髪が頬にぺったりと張り付いて鬱陶しい。
私は前髪を指でかき分けながら、今日何度目か分からないため息をついた。
何も考えずに飛び出してきたけど、そう簡単に会いたい人に会えるというわけではない。
そんなこと、分かりきっていたはずだ。
この無数の木々が隔てる森の中で、人探しをするのは困難だということも。
……だから、絶対に逃がさないようにと脅しをかけたのに。
うかつだった。
虹草なんていつでも食べられた。
それなのに、私は作戦を中断してまでそちらを優先した。
もう少し時間をかければ、全部上手くいっていたかもしれないのに、楽な方へと倒れてしまった。
あれは仕方のないこと、やむを得ない事だったと言い訳をしてみても、あの後再びあの子を探しに行かなかった事の言い訳にはならない。
とりあえず今は、昨日あの子と会った辺りに向かってはいるけど…。
あれから一晩たってるんだ、今はもう遠くに逃げてしまっているだろう。
だけど、それでも……私はわずかな期待を完全に消しされずにいた。
もしかしたら、まだあの辺にいるかもしれないとか。
なんなら、逆に私のことを探してたりするかもしれないとか。
そんな、自分に都合のいい夢を見る。
そうでもしないと、私はここに立っていることもままならなくなってしまうから。
……ダメで元々。
あの子が見つからなかったら、別の子を探せばいい。
まだ大きな失敗はしてないから、まだやり直せるはず。
怖がらせるだけ怖がらせといて、そのまま放置というのは酷い話だけど、またいつか会えた時に、あれは冗談だったとでも伝えられればいい。
そういった、ダメだった時のための慰め言を考えながら歩く。
そうして歩を進める内に、昨日あの子と会った辺りまで来た。
私は、諦めと慰め言の準備を始める。
もう既に、昨日私たちが立っていた場所は見えているけど、私は足を止められずにいた。
あと一歩進めば、あの子の頭のてっぺんが見えるのではないかと、期待する。
あの子は小さいからなあ…。
すぐ近くまで行かないと見えないかも。
まあ、私も大概だけどね。
そんな独り言を小さく呟く。
今歩いている道は勾配皆無の平坦な道で、身長なんて関係ない。
いたら見えるし、いなければ見えない。
私はそんなことにも気づけないほどに、心身ともに疲れきっていた。
諦める準備に疲れた。
今に期待を裏切られると身構えるのは、とても苦しいことだった。
だから私は期待し続けることにした。
馬鹿みたいに、何の根拠のない期待を続ける。
これは、いわゆる逃げ、なのだろう。
期待を裏切られる瞬間を先延ばしにして、徐々にこの感情が薄れていくのを待つ。
そして、淡い期待が透明になって見えなくなった頃、私は歩き疲れて、落ち込む気力さえ失っているだろう。
もしそうなったら、虹草でも食べて横になろう。
そして、健全な意識を取り戻す前に、眠りについてしまおう。
そうすればきっと、期待を抱いていたということ自体を、夢の中での痛みのように忘れてしまえる。
……そんな風なことを、頭のどこかで考える。
それは少しでも心を傷つけたくないがための、完全な逃避だった。
……期待を捨てないと思ったら、ダメだった時のその先のことを考えている。
さっきから、プラスとマイナスの感情変化が激しい。
私の情緒が安定しないのは安定のことで、自分でも何を考えているのかよく分からないのもよくあることだ。
でも、少なくとも今の私が前向きな思考ではないことは明白だった。
ずっと、後ろ向きな理由で期待し続けていたけど、そろそろそれにも疲れてきた。
心の確かな疲労を認めた時、自分がいつの間にか俯きながら歩いていたのに気づいた。
これでは、見つかるものも見つからない。
……いや、最初から見つかるはずがなかったのだろう。
私は顔を上げた。
眼前に広がる見慣れない景色。
もう既に、私が歩いているのは記憶に無い道となっていた。
私は足を止める。
すると、ようやく止まった孤独な足音とともに、悲しい雨音も止んだ気がした。
辺りに静寂が訪れる。
自分の呼吸音も、何も聞こえない。
音のない世界で残されたのは、……私一人だった。
ぴちゃん
「……?」
その時、私は音を聞いた気がした。
それは、水が跳ねる音。
音のなくなった孤独な世界でただ一つ、私の耳に届き得る響き。
…それは足音のように聞こえた。
自分以外の、小さくて……孤独な足音。
私は、音の聞こえた方へ向かった。
ぴちゃん、ぴちゃん
これは、私の足音じゃない。
自分の足音なんて聞こえない。
ぴちゃん、ぴちゃん
……これは、さっき聞いた音とおなじ。
何度も、何度も繰り返し聞こえる。
ぴちゃん、ぴちゃん
私の頭の中でだけ響くその音は、どうやら記憶の中に残る一音を繰り返し聞かせているだけみたいだった。
私はそれだけを頼りに歩く。
ぴちゃん、ぴちゃん。
音が止むのと私が足を止めたのは、同時だった。
目の前には一本の木が、何かを隠すように立っている。
私はゆっくりと、その裏に回り込んだ。
するとそこには、昨日会ったあの子が居た。
身体中の傷はもうほとんど消えていたけど、あの傷だらけだった少女に間違いないと思う。
彼女は地面にしゃがみこんで、顔を伏せている。
その姿を見つけた時、ようやく世界に音が戻った。
「何をしてるの?」
何の気なしに質問をする。
私は声をかけた後で、「しまった」と思った。
急に声をかけられたら、びっくりさせてしまうかもしれない。
それなのに私は、この子を見つけられたのが嬉しくてつい、挨拶もなしに話しかけてしまった。
私の声を聞いたであろう少女がゆっくりと顔を上げる。
見たところ、驚いたような様子は無かった。
先程の心配は無用なものだったのかもしれない。
「……」
少女は無言で私の顔をただ見上げている。
その琥珀色の眼差しは、昨日見たのと同じ色をしていた。
「…………」
……少し待ってみたけど、返事はない。
仕方ないので、こちらから何か話すことにする。
話す、と言ってもなんでもいいというわけではない。
無視されてしまっては元も子もないので、相手が反応しやすいような話題を見つけなくてはならない。
………………。
何かいい話題は無いかと考えているところでふと、疑問に思った。
そもそも、彼女はこの木陰で何をしていたのだろう?
何をしていたか。
普通なら、雨宿りをしていたと考えるのが自然だろう。
それなら、「隣いいかしら?」と何気なく聞いてみるのもいいかもしれない。
それが今の私の思いつく限りの最善の振る舞い。
でもそれは、この子が本当に雨宿りをしていたらの場合に限る。
……私は、彼女がただ雨宿りをしていたとは思わない。
さっきから感じているこの違和感が、違うと言っている。
この子が選んだ木は、どうやら雨避けには不向きらしく、彼女の足元には水溜まりができている。
それはつまり、溜まりになるほどの雨粒が、枝や葉に弾かれることなくその場に降り注いでいるということだ。
雨宿りをするならもっと適した木がある。
なのに何故、彼女はこの木の下にいるのだろう。
何か……やむを得ない事情があったとか?
仮にそうだとしたらそれは何だろうと、透き通る水溜まりをじっと見つめて、頭をひねらせる。
…………。
少しして、考えたところで何も分からないと気づき、視線を上に戻した。
少女の全身が目に入る。
……私は、水溜まりの上でしゃがむ彼女の姿に既知感を覚えた。
その既知感の正体に気づいた瞬間、一つの可能性が頭に浮かび、凍りつく。
人目を避けるように木陰に隠れてすることなんて決まってる。
これはつまりそういうこと。
さっきの水音も、……そういうこと?
……もし、これらの品性のかけらもない想像が全て当たっていたとしたら。
視線を再び下へと戻す。
この水溜まりはまさか……。
ふと、少し前に私がそれをじっと見つめていたことを思い出す。
彼女はそんな私を、どんな目で見ていたのだろう。
恐る恐る視線を上に……。
……少女の表情をうかがうと、やはりというかなんというか、怪しいやつを見る目をしている。
「…………」
なんだかとても恥ずかしい場面に直面してしまった気がする。
……そんな場で私がとった行動は、気を使ってこの場から離れるでもなく、留まって、……じっと彼女の足元を見て……。
状況を整理していくうちに、先程までの悠長な態度はどこへやら消え去り、急に焦りが出てきてしまう。
とりあえず、何か言わないと……!
このままでは、この子に間違いなく嫌われてしまう。
そんな何をいまさらという感じだけど、やっぱり嫌われる要素は少ない方がいいに決まっている。
こんな出来事は、この先仲良くなる上で邪魔にしかならない。
怖い言葉で脅かしても、頑張れば警戒を解くことはなんとか出来そう。
でもこれは…?
下手をすれば、他者を意図的に恥ずかしめて喜ぶ嫌なやつだと思われてしまうかもしれない。
どうしよう……!?
できることなら、今ここで私と会ったこと自体を忘れさせたい。
でも、記憶を消すことなんてできない。
悲しいことに私はその術を持たない。
出来もしない願望を形にするために、時間を浪費してしまう。
私は、すぐ横道に逸れてしまうどうしようもない頭を、可能な限り高速回転させて、思考をする。
早く何か言わないと!…早く…早く!
「だっ、…大丈夫?」
そうして、やっとこさ発したのはそんな言葉。
「私は何も見ていない!」という強い意思を込めて声に出した。
…いや、本当に何も見ていないんだけど、何かの間違いで自分が覗き魔か何かだと思われるのはすごく困る。
だから私は、なんとか相手の警戒をときつつ、状況が何も理解出来てない風を装うために、相手を気遣うような言葉をかけたのだ。
それらしい言葉を並べてはみたけど、私が考えに考えてようやく口にしたそれは……単なるとぼけだった。
雨音がうるさい。
声を持たない彼女は、私の決めつけからの態度や言動を否定も肯定もしない。
なのに、私の存在は否定する。
絶え間なく視界を横切るその一粒毎が、まるで意志を持ったかのように私の頭上に降り注ぐ。
私は、それらが頬を伝う度に、自分が泣いているような錯覚を覚える。
本来私が流すはずだった涙に取って代わられてしまったような気さえする。
『私が代わりに泣いてあげる。
あなたの悲しみを代わってあげるから、それ以外も全部、私にちょうだい』
そんな風に言われている気がする。
私はその声なき思いを聞く度に思うのだ。
雨粒にだってできることなんだな
、と。
なんなら、私よりも上手くできるのかもしれない。
泣いたり、笑ったり……
友達を作ったり。
それはとてもとても素敵なことだ。
彼女と代わった自分を想像すると、なんだか幸せな気持ちになる。
ずっとなりたかったものにようやくなれたような、そんな幸福感を感じられる。
……だけどそれと同時に、酷く虚しい気持ちにもなるんだ。
劣等感……なのかな。
私の涙は無数の雨粒、そのひとつにも及ばない。
私のことを鬱陶しく思う人がいても、誰かを助けてやることなんてできない。
そんな事実を突きつけるように重くのしかかる。
降って、降って、降られて。
そうして──
歪に育った私の心を、平坦になるまで解かしきってしまう。
…………。
偶然、花を見つけたとする。
草に見えなくもない、小さな花だ。
私はその花がとても気に入って、何度も何度も見に行った。
それはもう毎日のように通いつめた。
……でも、ある日突然、大雨が降るんだ。
私はその日雨宿りをする。
そうなると、当然花は見に行けない。
翌朝、私が目覚めて直ぐに花を見にいくと……それは死んでいた。
周りの草ごと枯れてしまっていた。
根腐れしたんだ。
どうしようもないことだった。
……悲しくはある。
でも、涙は流れない。
そこでようやく、私は足元のそれがただの花だと知る。
取るに足らない、数あるうちの一つなんだって。
放っておけばいつかまた生えてくる。
だから悲しむほどの事じゃない。
……私は、ただの花を忘れられずにいた。
それからも、毎日のように雨は降る。
大雨じゃない、普通の雨。
ある日、新しく花を見つけた。
やさしい色をした、これもまた小さな花。
私はもう一度この花を見守ろうと思った。
……だけどそれはもう既に枯れつつある。
まだ小さく未成熟なそれは、根腐れをしていた。
この雨続きだ、緩慢に枯れていったのだろう。
せめて、完全に枯れてしまうまでは見届けたい。
そう思った私は、今度は決して離れないようにとそこに居座った。
髪が、服が、雨に濡れる。
それでも私は見守った。
するとどうだろう。
それは急速に枯れていった。
…………。
これは自分のせいなんじゃないかと思う。
私がちゃんと雨宿りをしていたなら、枯れなかったのかもしれない。
私は雨雲を睨みつけた。
自分が悪い。
だけどもっと悪いのは、絶えず雨をふらせ続ける雨雲の方だ。
だって、
……………………。
せっかく芽生えたはずのやさしい気持ちも、これでは直ぐにダメになってしまう。
綺麗に整えられた頭の中では、
感情なんて育たないから。
……これで二回目だ。
また
枯れて、腐って、溶けてしまった。
それが確かにあったはずの場所をを見て落ち込む私に向かって、ようやく声らしきものが聞こえる。
その声は、そんなものは不必要と、私には相応しくないのだと。
だから、捨ててしまえという。
嫌だ。そんなのは認められない。
だって、これを捨ててしまったら本能しか残らない。
唯一残ったそれは、私の存在を肯定し、一番の間違いさえも否定しないだろう。
……ただ死ななければいいなら、それもいいのかもしれないが、それこそ私には相応しくない。
私にはどうしてもやりたいことがあって、それは私のしなきゃいけないことでもある。
それは違う、と雨粒が言う。
違わない。
私は彼女の否定を否定した。
そもそも、雨粒に耳を貸すこと自体が馬鹿らしい。
『……いいわ、もう少しだけ待ってあげる』
雨粒はさらに言葉を続ける。
『あなたが役目を終えるまでは、私は何もしないと約束してあげる。その代わり、その時が来たら……』
何を言っているの?
『何って、私なりの慈悲よ。私の人間らしい優しさでもってして、あなたに情けをかけてあげたの』
あなたは、人なの?
『…………』
まるで話が通じない。
『どこにいたって見ているからね。逃げても無駄よ』
あなたに何ができるって言うのよ。
『その口調、一体誰のマネかしら?』
…………。
意思の疎通なんてできるわけがない。
『まあいいわ。とにかく、その時が来たら、こっちからお迎えを向かわせるからね』
お迎え……。
『最後にひとつだけ教えておいてあげる。あなたの白々しい態度があまりに滑稽で、見るに耐えなかったからね。これも慈悲というやつかしら』
……。
『その子、あなたから隠れていたみたいよ? きっと、あなたのことが怖くて仕方がないのね』
その子…?
不意に視線を落とした。
すると、怯えた目がこちらを見ていた。
……ああ、そうだ。
私がこの子にこんな表情をさせているんだ。
きっと私が近くにいるだけでも怖いのだろう。
そんなことにも気づかずに、妄想を疑わず、挙句の果ては自分の潜在意識にそれを正されて。
一連の思考はとても正常なものとは思えない。
虹草の副作用がまだ抜けていないのだろうか?
……いや、それは違う。
むしろその逆だと思う。
酷く落ち込んでしまうこの気持ちは、長時間虹草を食べずにいた時の精神状態に近いように思える。
さっき食べたばかりなんだけどな。
もしかするとさっき食べたのは、周辺の草の中でも、特別輝きが弱いものだったのかもしれない。
もしそうなら直に視界が赤みがかってくるだろう。
それは数分後か、それとも1時間あとのことか。
何れにしても、緊急じゃないから無理に今食べることはない。
何より今は別に優先すべきすることがある。
「こんなとこで、何をしてたの?」
私は、こちらを見上げる少女に向かってもう一度問いかけた。
「……」
「もしかして、何かから隠れていたとか」
「………」
少女は答えない。
でも、言葉がなくてもわかることはある。
私が言った白々しさ全開の一言を聞いた瞬間、彼女のまぶたがぴくんと動いた。
この反応から、私の予想が見当外れなものではなかったことが分かる。
「そっか。……それで、……なんで隠れてたの?」
「…………」
この沈黙を勝手に自己解釈して話を進めると、ただ怯えていただけの目に、何か言いたげな色が混じる。
私は構わず質問を続ける。
「もしかして、私に会いたくなかったのかしら?」
そう言った後、別に怒っているわけじゃないということを伝えるために、からかうように笑って見せた。
「んー?」
「……………」
みるみるうちに青ざめていく。
別に追い詰めたいわけじゃない。
否定でも、肯定でもいい。
なんならそれ以外でも、何か言葉を話してほしい。
一方的に話しているだけじゃ、仲良くなんてなれないから。
このままだとあなたの沈黙は全部、私の粗末な頭で理不尽に解釈されることになるんだよ?
「…………」
………………。
少し待ったけど、返ってきたのは沈黙だけだった。
このままでは、この会話(…と呼んでいいのか分からないけど)はいつまでも平行線を辿ってしまう。
でもだからといって焦ることはない。
既に視界が赤みがかってきている気がするけど、何も慌てることなんてない。
眼前の少女は確実に追い込まれつつあるのだ。
それは私の本意ではないけど、言葉を交わせないのであれば何かしらの行動を起こしてもらう他ない。
命の危機に陥った時には、回避不可能な選択を誰もが迫られることになる。
逃げて命を続けようとするか、生きるのを諦めて死を受け入れるか。
一か八か、敵に襲い掛かるという場合も少なくはない。
もし逃げられたら追いかければいいし、受け入れてくれたなら、これからゆっくりと仲良くなれる。
万が一、この子が逆に襲いかかってくるようなことがあってもそれで構わない。
実際、追い詰めた相手から返り討ちに合うことも少なくはなかったし、その度に私はことごとく負けている。
昨日は彼女のことを自分よりも弱そうだと勝手に評価したけど、実際のところは分からない。
……とにかく、恐怖の対象を力でねじ伏せられることが分かればこの子も少しは安心できるだろうし、私にとっても悪い話じゃないはずだ。
出来ればこの子の手を汚させるようなことはしたくないけど、今の私は彼女にとってセルリアンと同じ外敵だから、やむを得ないことと思おう。
彼女が戦う意思を見せてくれれば、それが何よりなのだ。
戦いを通じて芽生える友情…みたいな?……そんな物語もあったかもしれない。
さっきから自分が負けることが前提なのは、こちらから攻撃してこの子が実際に怪我をするようなことがあれば、信頼を得るのは難しくなるからだ。
だから私は、彼女の私に対する印象の悪化を防ぐために手を出さない。
痛いのは嫌だけど、未来の友達のためだもん。
きっと私は耐えられる。
……ああ、でも…仮にそんな事態になったとして、私はこの子に何をされても平然としていなきゃダメなんだ。
腕を折られても、首を絞められても、平気な顔をしなくてはいけない。
精神的な弱さは決して見せてはいけないから。
私が口程にもない少女だと悟られれば、相手の心を繋ぎ止めておくための一番有効的な手段を失いかねない。
もしそうなってしまったら、お話がきっと得意じゃない私は何も出来ずに終わってしまう。
そんな最悪な事態を避けるための強がりを、私はあらかじめ用意していた。
瀕死の重傷を負った私は、あまりの痛みに泣いてしまいそうになるのを我慢する。
そして、包容力と不気味さを含んだ微笑みを浮かべて、「気は済んだかしら?」って言うんだ。
その後は何事も無かったかのように起き上がる。
……何があったって私はきっと無事だから。
そんな私を見て、この子は不気味に思うだろうけど、別にそれでも構わない。
それこそが狙いなのだから。
…………。
私にもできるだろうか…?
いくら強がったって、うめき声ひとつあげないのは難しいかもしれない。
………………。
でもまあ……これは万が一の場合だから、ね。
あらかたの事態を想定し終えたことを確認する。
あんまり悠長にしすぎて時間切れになったりしては困るので、こちらから仕掛けることにした。
「ねぇ」
少しだけ声を低くして圧力をかける。
すると、少しの時間がたった後、ようやく声が聞こえた。
「…………だ」
「……? いま、なんて……」
上手く聞き取れなかった。
せっかく何かを伝えようとしてくれたのに聞き逃してしまった。
これは全部、雨のせい。
雑音をならし続けて、意思の疎通さえ図らせない。
私は再三嫌い続けてきた自然現象を今一度呪った。
「…………」
彼女が声を発してから、この場の空気はかわりつつある。
私はその変化に気づいた。
最初はただ怯えるだけの少女だったが、自分が置かれている状況の理不尽さに気づいたのだろうか。
その目からは段々と怯えが薄れていって、明確な敵意が宿り始めている。
その視線は自らの生命を害する敵に向けられるものになっていた。
……それでいいんだよ。
その手で私を─────
瞬間、突然強い風が吹いた。
私の右手が無意識に動き、髪を抑える動作をした。
これは本来髪が乱れるのを防ぐための動きのはずだけど、頭からつま先までの全てが水浸しの私には不必要な動作だ。
不必要な、…無駄な行いのはずだった。
だけど、なんの意味も持たないかと思われたその行為は、本来の目的とは別の意味で作用した。
それは私が大きな隙を見せたこと。
髪を抑える私の視界は暗く閉ざされていて、それは私が目をつぶっているからだ。
私は気づく。
今の自分が如何に隙だらけかを。
目は見えていないから、今目の前にいるはずのこの子が攻撃をしてきたら避けられない。
彼女に殺意や害意があったとして、私はそれをこの身体で受けるしかないし、両手がふさがっているので反撃できない。
右手は髪を、左の手はスカートを押さえるのに忙しいのだ。
…………。
やるなら今しかないよ。
なにかするなら今のうち。
あなたの命懸けの奇襲はきっと成功する。
別に逃げてもいいけど、もし追いつかれてしまったら……。
ここで仕留めておかないと、あとが怖いよ?
……そんなことを頭の中でひっそりとつぶやく。
そそのかすように、寄り添うように、…声なき想いを滴らせる。
風はまだ止んではいない。
─────バシャッ
その時、一際大きな水音と共に小さな気配が動いた。
私は頬を弛めた。
次の瞬間───
ぽすっ
……ぎゅー。
……?
何が起きたかわからなかった。
水音が合図をしてまもなく、胸の辺りに衝撃を受けた。
私は、これから友達になろうとしている少女のことを思い描いた。
すごく気が弱そうに見えたけど、本当はやればできる子なんだ。…そんな風なことを思った。
そして、直に襲ってくるであろう痛みに備えて、私は固く目を瞑った。
それなのに、いつまで経っても痛みを感じなくて。
死刑宣告を待っているような気分で、永遠にも感じられる時間の終わりを今か今かとびくつきながら、ただ待っていた。
…だけど、そんな心臓に悪い時間が永遠に続くことはなかった。
やがて私は気づく。
痛みの伝達遅れにしては長すぎる時間にようやく違和感を覚えたのだ。
私はゆっくりと目を開けた。
「…………?」
本当に、何がなんだかわからない。
私のことを心から恐れ、敵意の宿った眼差しを向けてきた少女が、私の胸に顔をうずめていた。
分からない。
彼女がどうしてそんなことをするのか、全然分からない。
髪とスカートを押さえていたはずの自分の両手が、いつの間にか少女の身体を捕まえるように抱きとめていた。
なんでそんなことをしたのか、自分のことも分からない。
……でも、なんだろう…。
不思議と心が満たされるような幸福感を感じる。
……もう、何も分からなくたっていい。
今はただ、このまま……。
私は少女の頭を撫でようとした。
今度は無意識じゃなくて、自分の意思で、そうしたいなって思った。
左手をそっと持ち上げる。
そして、彼女の真っ白な髪に触れようとした時、その手が止まった。
同時に、呼吸も止まる。
段々、と動悸が、激しくなる。
焦点の定まらない目が、真っ赤に濡れた私の左手を見ていた。
そんな……もう…ダメなの…?
せっかく、せっかく仲良くなれそうだったのに。
仲良く……そうだ、私たち、もう、打ち解けたんだ。
私は目を閉じ、見たくないもの全てを視界の外へ追い出した。
そしてもう一度、大好きな友達を抱きしめた。
今度は二度と離さないように、強く。
辛いのを全部忘れてしまえるくらいに強く。
このまま絞め殺してしまうくらいにもっと強く。
もっと、もっと……。
……?
……気づくと私は、誰も抱きしめてなんかなかった。
私はあの優しい体温を、また見失ってしまった。
どこに行ったの?
私は暗闇に手を伸ばした。
何にも当たらない。
……目なんて開けたくない。
でも、このまま会えなくなるのはもっと嫌。
私は目を開けた。
すると、そこにあの子はいた。
変わってしまった世界で、変わらずここにいてくれた。
ゆっくりと、彼女の頬へと手を伸ばす。
もう少し……もう少しで届く。
……もう少しだったのに。
少女は私の両手をすり抜け、背を向けてしまった。
「なん…で…?」
かすれる声で問いかけた。
でも、とどかない。
聞こえてすらいないみたい。
一瞬視界が揺らいだかと思ったら、あの子の背中が少しだけ遠くなった。
彼女が駆け出す。
段々と遠のく。
遠く、離れていってしまう。
其の後ろ姿を、脈打つ視界で、ぼんやりと、眺める。
………。
「待って!!」
咄嗟に私は叫んでいた。
少女が足を止める。
今度はちゃんと届いたみたい。
私は彼女の背中に歩み寄る。
一歩を踏み出すごとに粘っこい音が足に絡みつき、血なまぐさい匂いが全身を包み込んだ。
彼女の背後に立つ。
そして私はもう一度、彼女を抱き締め───
「私から逃げようとしたのね?」
え……?
そいつは言っていた。
意識的に、私の無意識を介して、世迷言を私の友達に吹き込む。
何を言っているの…?
そんなわけない。
私とこの子は友達なのに。
逃げるなんておかしい。
「そんな、こと……」
ほら、彼女も違うと言っている。
そんなことを言い出した私がどうかしてるんだ。
……あれ?
私はどうかして……?
………………………………
……そうだ。
私は頭がおかしくなっているんだ。
だから変な勘違いを起こすんだ。
私はこの子と友達なんかじゃなかった。
少なくとも、今は違う。
だったら……だから、今喋っているのが、本当の私なんだ。
じゃあ私は誰なの?……頭が痛い。
早く、虹草を食べないと…。
「いいわよ」
「……え?」
「逃げてもいいわよ」
私の意志とは無関係に、話が進んでいく。
でも、……これでいいんだ。
事実をちゃんと受け止めている、比較的まともな方の私がきっとうまくやってくれる。
だから、私は何もしなくていい。
「でもその前に、私の遊びに付き合ってもらうけどね」
私は少女の正面に回り込みながら言った。
「……遊び……?」
「鬼ごっこって知ってる? 誰かが鬼とかいうのになって、他のひとが逃げるの」
「……」
「あなたが私から逃げ切れたら、そのまま見逃してあげる」
「…に、……逃げきれなかったら……」
「そうね……じゃあ、こういうのはどうかしら? あなたが鬼に捕まったら……足を一本、もがれるの。あなたが二度と逃げられないように…ね」
「そんなのって……」
そんなのってない。
ここまで黙って聞いていた私だったけど、さすがにこれはやりすぎだと思う。
はっきり言って、彼女は異常だ。
この子が自分に怯えていることを知っていながら、こんな暴力的な言葉で脅すなんて……。
「嫌ならしなくてもいいのよ? 私はあなたとずーっと一緒にいられれば、それで満足なんだから」
彼女はそう言って楽しそうに笑う。
私には理解ができない。
目に見える事実すらねじ曲げてしまった私には、彼女の歪で不健全な、正常であるはずの心がまるで解らない。
「わかりました。……その条件で構いません」
「ぅ……じゃあ、私が…今から十秒数えるから、その間に逃げてね」
私は、この子がそんな遊びには付き合えないと言ってくれることを期待していた。
どうやらそれは頭のおかしな遊びを提案した私も同じだったらしく、彼女が動揺しているのが分かる。
だったら最初から言わなければいいと思ったが、彼女なりの考えがあったのだろう。
……異常な思考回路を持った正常な私と、少しだけ分かり合えた気がする。
でも、もう直ぐにお別れをしなくてはならない。
私は十秒を数えて遊び相手を逃がしたあと、虹草を食べて正常になる。
この先の不安はあるけど、いつまでもこのままではいられない。
私は少女が走り出すのをのを確認してから十秒を数え始めた。
「いーち、にーい、さーん……」
ゆっくりと数える。
「しー……」
もういいか。
あの子の後ろ姿はもう見えない。
私は足元に視線を向けた。
そこには辺り一面に生い茂る草があった。
その一本一本が絶え間なく変色し続けている。
まるで生きているみたい。
それはとてもおぞましく見えた。
気味が悪くて、目にも悪い光景。
それをぼんやりと眺める。
…………。
私が虹草に手を伸ばすのを躊躇っていると、周囲の草の輝きが段々と薄れ始めてくる。
そして、輝きが弱いものから順に、赤色に飲み込まれていく。
このままでは、虹草と普通の草の区別もつかなくなってしまう。
私は慌てて手を伸ばした。
「痛っ」
突然、指先に鋭い痛みを感じて手を引っ込めた。
引っ込めた手のひらに目を落とす。
真っ赤に濡れる手のひらには、一際赤い一本の跡が出来ていた。
それを辿り、指の先へと。
先ほど痛みを感じた部分には、小さな切り傷があった。
どうやら、手を伸ばした先でなにか鋭いものに触れたみたいだ。
私は草をかき分け、それを拾い上げた。
まじまじと見る。
ひらべったくて、先端が尖っている。
そして、尖っていない方、もう片方の端は手で持ちやすい形をしている。
私はこの形状に心当たりがある。
これは……ナイフ?
ナイフ。
それは私たちが生まれながらにして持っている武器。
フレンズがセルリアンに立ち向かうための、唯一の力。
ムカデなんかはナイフがなくても強いらしいけど、そんなのは彼女くらいのものだと思う。
特別な力を持たない私たちは、この武器に頼るしかない。
かくいう私も持っていたのだが、以前セルリアンから逃げる際にうっかり落としてしまっている。
それなら、今こうしてナイフを拾うことができたのは幸運と言えなくもない。
でも、今拾ったこれは酷く錆び付いていてあまり使い物になりそうにないし、そもそも私が落としたものでもない。
だから勝手に持っていくのは悪いように思う。
私はこの錆びついたナイフを元の場所に戻しておくことにした。
ちょっと名残惜しいけど、……でもまあ別に武器があってもなくても、あんな恐ろしい相手に立ち向かうなんてこと、臆病者の私にはできっこないし……。
………………。
さっきから、私は何をしているのだろう。
今はこんなことをしている場合じゃないのは、私だってわかっているはずだ。
……でもどうしてだろう。
私はこのナイフから、目が離せずにいる。
いつまでも、ナイフの先端の方をじっと見つめているのだ。
こうしているとなんだか頭がざわついて、…何かを思い出しそうになる。
「うみ……」
私が小さく呟いた。
知らない文字列。…聞きなれない響き。
それなのに、どこか懐かしさを感じてしまう。
愛おしくもおぞましい響き。
このたったの2文字が頭の中で反響し、何度も何度も繰り返される。
脳を貫き、頭蓋にぶつかる度に分裂し、2文字は4文字、4文字は8文字となり頭の中を駆け巡った。
やがて、増えすぎた文字がぐちゃぐちゃになってしまう。
私はこれらを頭の中から締め出そうと足掻いた。
そうして外に引きずり出されたのは、全く別のものだった。
無機質な声が頭の中で重く響く。
『 もしオマエが……其の、紛い物の手を汚すことを躊躇うのなら……ここに、海に連れて来るがいい 』
「そうすれば、…あとは、ワタシが……」
どこで誰から聞かされたかも分からない、他人事のような言葉。
感情のない声で、私じゃない誰かに向かって言っている。
…………。
私が聞き取れたのはここまで。
他にも、数多の言葉が色んな声音で話されたけど、何重にも重なって声と呼べないくらいに濁ってしまっていて理解ができない。
その音の集合体は今もなお増大を続けている。
頭がどうにかなりそう。
既にどうにかはなっているとか、そんな声すら今は聞きたくない。
「うぅ……」
あまりの爆音と頭痛に耐えきれず、私はその場に倒れ込んでしまった。
手に持っていた殺害のための道具が投げ出される。
『──から……もう─────』
────音が止んだ。
「……え…?」
突然、頭の中で鳴っていた音がピタッと止まった。
私はその音が止む直前に偶然聞こえた声を、言葉を認識して青ざめる。
『ここは危ないから、もう近づいちゃダメよ 』
言葉の意味を理解した瞬間、血の気が全て引いた。
こんなのは、なんてことのない、ただの雑音の内の一つに過ぎない。
でも、私には理解ができてしまった。
……彼女は忠告をした。
断崖に立って。
ここには海があるから、危ないと言った。
海は、とても危険な場所。
その危険な海へと向かう道には、私の知っている景色が含まれていて……。
「……」
起き上がり、前を見据える。
記憶の映像と自分の視界が重なる。
色は違えどとてもよく似ている。
森の中なんてどこも同じ景色だから、気にする事はないはず。
でも、私の直感がそうだと言っている。
この道こそがあの海沿いの崖へと続く道なのだと。
出処不明の記憶と、頭のおかしな私の直感、その両方を信じるというのなら……。
「この先には、……っ!」
私は今すぐにあの子を追わなくてはいけない。
何かの勘違いならそれでいい。
頭のおかしな私が見たただの妄想でもいい。
考えたって真偽なんて分からないのだから。
最悪な事態を想定している暇があるのなら、最善の努力を真っ先にするべきだ。
私が今できる最善は走ること。
誰よりも早く走って、あの子に追いつかなくちゃいけない。
足に力を入れて立ち上がる。
その時、視界が大きく脈打った。
立ちくらみとは違った感覚。
世界が逆さまになってしまったかのような違和感が全身を駆け巡る。
……急がなくちゃいけない。
真っ赤な恐怖が私たちを満たしてしまう前に、あの子を捕まえないと。
切り詰めたようなこの切迫感は、私と彼女の間で隔てられることはなかった。
共通の目的意識を持った二人の心が一致する。
一人は大切な友達を救うために。
もう一人は、未来の友達を守るために駆け出す。
赤白い空の下、乖離しかけていた意識が、今ひとつになった。
「絶対に追いつく…!」
救われるべきはゴイシシジミ、それを追いつめているのもゴイシシジミ……
そんな状況から抜け出さんがための覚悟が友達のもとへと駆ける!という回でした
あのナイフ…まさか…
コメントありがとうございます!
気になっているみたいなのでナイフについての情報を軽くまとめてみました
ゴイシシジミ達がフレンズとして生まれた時に所持している武器
その形状は様々だが、一人につき一本必ず持っている。
私は走った。
走って、追いついた。
随分と時間を無駄にしたけど、なんとか追いつくことができた。
もしかすると私は足が早いのかもしれない。
長いことセルリアンから逃げ続けていたからだろうか。
私の逃げ足は知らず知らずのうちに鍛えられて、洗練されている。
その洗練された逃げ足が本当の意味で役に立ったのは、これが初めてのことだった。
……追いかけていたのだから、逃げ足とはちょっと違うのかもしれない。
でも、やっぱり……私は今日も逃げていたんだ。
無数の気配から。
見えない、存在しないはずの誰かから。
どうせこれもただの幻覚。
それを頭で理解していても、怖いものは怖かった。
振り向くことさえゆるさない程の恐ろしい何か。
私はそれに決して追いつかれないように走った。
そうして気配がどんどん離れていって、ここに着いた頃には既にそれはいなくなっていた。
私は後ろを振り返らずに言う。
皮肉を込めて…。
「助かったわ。ありがとう」
声なんてかけるんじゃなかった。
私は直ぐに後悔した。
バシャンッ!!
「!?」
……背後に無数の気配を感じたかと思ったら、大きな水音と共にそれらが一斉に弾けた。
恐る恐る振り返る。
「…………」
地面に赤い液体がぶちまけられていた。
それを見て私は、もう時間があまりないことを自覚する。
私はあの子のいる方へと向き直った。
まだ少し遠くて分からないけど、
あの子はきっと私を見てる。
ゆっくりと歩を進める。
だったら、どんな顔で私のことを見ているんだろう。
急がなくちゃいけないはずなのに。
……というか、どうして立ち止まっているのだろう。
間に合わないかもしれない。
もしかして、私から逃げる時に転んで……怪我をして……。それで、走れなくなっちゃった、とか……?もし、間に合わなかったら……?それか……気が変わった、なんてことは……ないよね。きっともうまにあわない。
…………。
思考がめまぐるしく変わる。
川の流れのように緩やかな変化は、彼女に近づくほどに激しくなる。
それはきっと目を背けたかったから。
心の平静を保つためには決して見るべきではない。
でも、目が離せない。
だから私は、せめて理解ができないようにと自らの思考を妨害した。
……でもそんなのは虚しい抵抗だった。
私の眼前に広がるそれは、目を背けるにはあまりに大きすぎたから。
たたずむ少女の背後から、雲の向こうまで続く程の、大きな大きな赤い溜まり。
それはいつか夢で見た光景に似ていた。
これが……海…?
断崖に立つ彼女の姿が、いつかの夢の自分と重なる。
あそこから落ちた後私は、……身体がバラバラになって溶けてしまった。
……それはあくまで夢の出来事だ。
………。
もしあの子が海に落ちるようなことになったら、何もかもが終わるだろう。
でも、そんなことは絶対にあってはならない。
いざという時には、この身を犠牲にしてでも彼女を救ける。
絶対に。
決意と呼ぶにはあまりにも軽い自己犠牲の精神に、自分でも嫌悪感を抱いた。
「あなた……それ……」
私は立ち止まっていた。
海を背にして立つ少女の手にはナイフが握られている。
「ここで足を失うくらいなら、私は全生命をかけてでも抵抗します。…私が死ぬ気で戦ったら、あなたも無傷ではいられないはずです」
手に凶器を持つ彼女の目は怯えていた。
彼女の瞳に宿る決意の光よりも、怯えの方が強く出ている。
……それなのに、どうしたらそんな風に立ち向かえるの?
「あれは…ほんの冗談よ。……非力な私に、あなたの足…を、どうこうできるわけないわ」
「……非力…あなたが? それこそ冗談じゃないですか…?」
「……ねぇ、あなたのそれも…冗談、なんでしょ……? それ、あんまり面白くないわよ?」
「冗談なんかじゃありません」
「あ、あんまりしつこいと怒るよ…?」
「それはこわいですね。きっと私なんかは、すぐに殺されちゃいますね」
「そんなこと……」
私は確信する。
この子は強い。
今まで必死に生きてきたであろう彼女が私より弱いなんて、そんなことがあるわけなかった。
戦い方の一つも知らない私なんかより、ずっと強い。
それなのにまだ私が無傷でいられるのは、彼女が心に恐怖心を抱いているからなのだろう。
傷つけるのが怖い。
返り討ちにあうのが怖い。
数歩引き下がるだけで死んでしまえる、この場所が怖い。
……。
あなたが今抱いているであろう恐怖の数々。
私がその内の一つを、今から取り除いてあげる。
だから……
「そこから……動かないでね」
それだけ言って、彼女の立っている崖際に向かって歩き出す。
私は彼女をこれ以上追い詰めることがないように、伏し目がちに歩いた。
私は自分でも分かるくらい目つきが悪いので、こうでもしないと余計に怖がらせてしまう。
私に近づかれることに対する恐怖が海に落ちる恐怖に勝ってしまえば、彼女は崖から飛び降りてしまうかもしれない。
それだけは絶対に防がないといけない。
「こ、これ以上近づいたら、宣戦布告とみなします……!」
そう言って、ナイフをこちらへ向ける。
「私は……本気です。」
付け足すように彼女が言った。
それでいいよ。
それであなたが怖くなくなるなら、私を好きにすればいい。
そのかわり、一度私に触れたなら、絶対に私のことを好きになってもらう。
そして二度と私から離れられなくしてやる。
それがこの遊びの決まり。
実際に足を取ったりはしないけど、私から逃げる足はちゃんと奪わせてもらう。
「あ!!」
「…?」
ナイフを持つ少女が、素っ頓狂な声を上げた。
私は立ち止まることなく彼女の様子を伺う。
「私に近づけば……あ、あなたの友達も無事では済まないかもしれませんよ……!」
「……」
「うぅ…! …み、みなごろしです!! あなたのせいでこの世界中のみんなが悲しむんです。……あれ? みんな死んじゃったら、誰も悲しまない……」
「そうね」
「そう…ですよね。……あああ! そもそも……どうしてそんなに目つきが悪いんですか!? おかしいですよ……あなたは……」
「私のこと、ちゃんと見てくれてるのね。…嬉しい」
「もう、怖いんです! 来ないでください!!」
「そっか。……あなたの気持ち、もっと聞かせて」
「わたしこ、ここから飛んでやりますよ! それできっと、あなたは毎晩夢の中でその光景を見るんだ。……良かったですね? これで毎日一緒ですね?!」
少女はそう捲し立てると海に飛び込もうとする。
でも、今更そんなことをしてももう遅い。
既に手を伸ばせば届く距離まで近づいている。
迷わず私に刃を突き立てていれば、そんなことしなくて済んだのに。
そう心の中で呟き、両手を差し伸べる。
そこには僅かな迷いもなかった。
彼女の手元へ向かって真っ直ぐと手を伸ばす。
……両の手がナイフをすり抜けた。
私の身体には傷一つ付いてない。
ここまで追い詰められても、あなたはそれを使わないんだね。
私の指先が、……少女の手の甲に触れた。
何本かの指を伝って、彼女の心の怯えを確かに感じる。
私はその手を包み込むように捕まえた。
「つかまーえたっ。……いこ、ここは危ないわ。」
今回はちょっと短めです
長らく更新が滞っており、すみません
少し古い記録から読める形になっているものを2つばかし引っ張り出してきたので載せておきます
多分、エピソードゼロ的なやつです。
私は走っていた。
逃げていたのだ。
何故こんなことになっているのかを思い出そうとしたが、上手く思い出せない。
脳に酸素が十分に行き渡っていないからか、恐怖という名の液体が頭蓋を満たしてしまっているからか、あるいはその両方か。
私の僅か1メートル後ろにそいつはいる。
ドスドスと大袈裟な音を立てながら追いかけてくる。
走っても走っても距離が広がらない。
心臓が悲鳴をあげ、肺が潰れそうになりながらも、必死に足を動かす。
こんなことになるんだったら、もっと体力をつけておくんだったと今更ながら後悔する。
後悔先に立たず、だ。
だからたった今自分の身に起こった出来事も後悔したって仕方がない。
仕方がないのだが、私はまたも後悔してしまっていた。
いつの間にか視界が大きく傾いていた。
多方石にでもつまづいたのだろう。
ああ、余計な事を考えながら走っているからこんな事になるんだ。
しまったと思った。
無駄な後悔をしている暇があるなら、コケないように体勢をたてなおすべきだった。
あ、また後悔。
(もういいよ…)
コンマ1秒後には強い衝撃が私を襲うのだろう。
願わくば、その瞬間に強く頭をぶつけて気絶でもしてしまいたい。
今感じている以上の恐怖を感じながら死んで行くなんて真っ平御免だ。
ドシャァァ
「いったぁ……」
私はコケた。盛大に。
こんなに綺麗にコケたのは生まれて初めてかもしれない。
もしも今のコケ方に点数がつくのなら、100点満点中90点位はついたのだろうか…?
そんな馬鹿なことを考えているうちに追跡者は目と鼻の先まで迫ってきていた。
そいつの姿を一望する。
一望とはおかしな表現かもしれないが、それ程にやつは大きな体をしていた。
「は、はは…」
自然と乾いた笑いが出る。
きっと今の私は随分と青ざめた顔をしているのだろう。
自分では見れないのがちょっと悔しい。
今更立ち上がったってどうせ逃げきれないし、そもそも腰が抜けて立てない。
私は生きることを諦めざるを得ない状況になっていた。
・・・・・
あれからどれだけの時間が経ったのだろうか。もしかすると、1秒にも満たない間の事だったのかもしれない。
奇妙な事が起きていた。
目の前の化け物は一向に動こうとしない。
まるで時間が止まっているみたいだった。
今のうちに逃げられるんじゃないか?
そう思った次の瞬間、やつは大木のように太い腕を振り上げた。
咄嗟に目をぎゅっと瞑り、まもなく自分の身に降りかかるであろう痛みに備える。
しかし待てども待てども、痛みを感じない。
恐る恐る目を開けると…。
目の前の景色は目を瞑る前とは打って変わっていた。
世界は常に変化し続けているとは言うが、こんなにも早く変わるものなのか?
ふと足元を見ると地面がない。
かと言って、落ちることもない。私は宙に浮いていたのだ。
私は死んでしまったのか?なんて呆気ない。
痛みを感じなかったのが不幸中の幸いと言ったところか。
このまま雲の上まで昇っていくのかと思いきや、ある程度まで上昇すると一定の高さを保ち続けた。
「あれ?」
(どうしよう。こういう時ってどうすればいいの?死んだことなんてないから分かんないよ…。)
途方に暮れて上を見上げると、そこには私が今まで見た事のない程美しい、透き通った瞳をもつ少女がいた。
「天使様…?」
無意識のうちに口のはしから声が漏れた。
その言葉が彼女の耳に届いたのか、少女の可愛らしい顔がこちらへ向いた。
そして優しく微笑んで、肯定するでもなく否定するでもなくこう言った。
「大丈夫?」
私は今、絶対絶対の大ピンチに陥っている。だからといってピンチを脱するために今私にできることは何一つとして無いので、何故こうなってしまったのか、事の発端を思い出してみることにする。
陽射しの強い午後。一人の少女が地べたに這いつくばり、頭に疑問符を浮かべていた。
それはとある夕暮れ時のことだった。
いつものように、好物の葉っぱを食べていた時に事件は起きた。
なんと空から石のようなものが落ちてきて、私に直撃したのだ。
自分の体よりも一回り大きなそれに、私はいとも容易く押しつぶされた。
一瞬の出来事で、死を覚悟する暇もなかった。
すぐに意識が途絶え、次に気がついた時には世界を……見下ろしていた。
あまりにも唐突な出来事に私は愕然とした。
そこで私はとりあえず状況の確認をしようと思い、周囲を見渡してみることにした。
視界は先程よりも鮮明になっていて遠くまで見渡せた。
上を見上げると、空がとても近く感じる。周囲を一通り見終えると、視線を下に落とした。
「……へ?」
ふと、奇妙な音を聞いた気がした。
「なに?……これ……?」
今度ははっきりと聞こえた。
この音は、自分のすぐ近くから……というよりも、自身が発している音のようだった。
だが今はそんな事よりも先に、自分の身に起きた変異について深く考えるべきだろう。
視線を下に向けて初めて気がついた。
私の体は大変な変化を遂げていたのだ。
体からは棒状の謎の物体が4本伸びており、それらは全て5本に枝分かれしていた。
5本に分かれた物体は、それぞれが個別の生物のように動き、気味が悪かった。
どうやらこの物体は体の一部で、自分の意思で自由に動かせるらしい。
それからしばらくの間体を動かす練習をしていると、先程よりもさらに珍妙な音と共に強い空腹感に襲われた。
「お腹すいたぁ……」グゥ
このままではいけないと思い、私は食事を再開することにした。
「にがっ」
口に入れた葉っぱはにがかった。
「にがい」が何かは分からないが、ただそう感じたのだ。
刺激的な感覚ではあったが、だからといって悪いという気はしなかった。
私は食事を終えるとまた周囲を見渡した。
するとやはり、鮮明になった視界で見る世界は美しく、見ていると心が不思議な感情で満たされるのを感じた。
私はその感情の意味を探すべく、世界を見て回ることに決めた。
「よっ…と…ほっ…と」ズルズル
早速4本の棒状の物体を駆使して地面を這い始める。
するとどうだろう、これまでよりも早く動けるではないか。
多少の不安はあったが、これなら何とかなりそうだ。
「よーし、どんどん行くよー!」
ズルズル…ズルズル…ズルズル…ズルズル…
ズルズル……ズルズル……ズルズル…………
ズル……ズル……ズル…………ズル…………
ズル…………………ズル…………………………
しばらく這った所で、景色がまるで変わっていないことに気づいた。
遠くまで見えているのになかなか進まないというのはなんだか焦れったい。
それにこの体で移動するには、思っていたより体力を使うようだった。
このままのペースで行けば、次の餌場にたどり着けずに、待っているのは……
死
「あはは……今からでも引き返そうかな……」
だんだんと思考が後ろ向きになって来る。
「あの……大丈夫ですか?」
地面に伏せて悩んでいると、また奇妙な音を聞いた。
だが今までのものとは何かが違う。
なにか、こう……意味を持っているような……誰かに何かを伝えようとするような、そんな感じがした。
「え……?」
「立てますか? もしかしてどこか怪我とか……」
私は直感で、この音は自分に向けられたものだと解った。
そして、私を心配しているという事も。
だから私も音に応えようと、音のする方へ顔を上げた。
するとそこには、私と同じ姿をした生物がいた。
一つ、明らかに違う点があるとするなら、4本の棒の内の2本を器用に使って、移動しているらしい事だ。
私にも出来るのだろうか?
そんな事を考えてぼんやりと見ていると、ある事に気がついた。
目の前にいるこれとは別に、ひとまわりもふたまわりも大きな生物がこちらを見ているではないか。
ずっとこちらを見ているにも関わらず1度も音を発さないそれに、私は恐怖を覚えた。
本能、だったのかもしれない。
私の直感は叫んでいた。
「後ろ!」
「…っ!」
私が発した音を受け取ったのか、後ろを振り返り、そして次にこう発した。
「セルリアンです! 逃げてください!」
「せるりあ…?」
「いいから、早く逃げてください!」
「う、うん!」
私はその音を聞いて、セルリアンと呼ばれた生物から背を向け、這い出す。
ズルズル…ズルズル…ズルズル…ズルズル…
ふと、私に警告した者の事が気になり後ろを振り返った。
次の瞬間、私は目の前の光景に驚き、目を見開いた。
私にセルリアンからの逃避を促したあの子が、自分の体の何倍もある相手に勇敢に立ち向かっていたのだ。
傷だらけになりながらも戦う彼女はとても勇ましく、そして……
「……あれ?」
急に目が回り出したかと思った時にはもう、私の意識は途切れていた。
・・・・・
…………きて……………おきて…………
音が聞こえる。私を呼んでいる。そういえばあの子は……はやく、起きないと。
「あ、目が覚めましたか?!」
「……ぁ゙…う…ん」
「大丈夫ですか?私に何か出来ることはありますか?」
「……み……ず…………」
「水ですね?ちょっと待っててください」
そう言って、茂みの中に消えていく少女。
焦点が上手く定まらない。
それに、酷い頭痛と嘔吐感を感じる。
あの子が戻って来るまで意識を保っていられる自信がない。
そんなことを考えていると、先程彼女が向かった茂みの方から、こちらへ近づいて来る足音が聞こえた。
あの子が戻って来たのか…?
それにしては早すぎやしないか?
私は少し警戒した。
警戒した所で何かができる訳でもないけれど……。
「お待たせしてすみません」
私はその音を聞いて安堵した。
「これどうぞ」
少女は歩行に使っている棒とは別の2本で、大きめの葉っぱを器用に持ち上げている。
そしてその上には、私に今一番必要なものがあった。
私はぼやけた目で少女の顔をちらと見る。
そして、差し出された葉っぱに頭を近づけて水を飲んだ。
「んく…んく…んく………ぷはぁ」
その水はほんのり甘くて、今まで飲んだどの水よりも美味しく感じられた。
「もう大丈夫そうですね」
「あっ」
私はこの子に2度も助けられたんだ。
一度目はあの怪物に襲われた時、そして今。
この子に感謝の想いを伝えたい。いや、伝えなくてはいけない。
難しい事じゃないはず。
今まで通り、本能の赴くままに心を音に乗せれば、きっと伝わる。
「さっきは助けてくれて……ありがとう」
「あ、はい。どういたしまして」
「それと!水も、ありがとう」
「それも、どういたしまして」
よかった、ちゃんと伝えられた。
「あの、ちょっといいですか? あなたに話しておかなければいけない事があって……」
「はなし?」
「はい。セルリアンの事も知らないみたいだったので」
私の恩人である少女は、懇切丁寧に色んなことを教えてくれた。
私たちはフレンズと呼ばれる存在で、とある物質に触れることで体が変化し、このような姿になったのだということ。
それと、フレンズの天敵であるセルリアンの存在についても聞いた。
あのまま地面を這っていたら、飢餓状態に陥る前にセルリアンに食べられていたかもしれない。
私はこの子に出会えて本当によかったと思った。
そして最後に、私が音と呼んでいたものは声というらしい事も教えて貰った。
この子ともっと話したい。仲良くなりたい。
そう思った私は早速声を発した。
「あのね、お願いがあるの」
「なんですか?私に出来ることなら尽力します」
「わたし、きみともっとお話したい。……だからわたしと友達に…」
しかし、私の願いはいとも容易く拒否されてしまった。
「それは出来ません」
「……ぇ?」
「あなたと友達にはなれません」
「あの、えっと……」
突然のことで言葉に詰まってしまった。
そこで初めて断わられるなんて想定していなかったことに気がついた。
私は、目の前の少女の親切に甘えていたのだ。
「ごめんなさい」
私の顔を見るやいなや、少女は謝罪の言葉を口にした。
よっぽど顔に困惑の色が出ていたのだろう。
お願いしたのは私の方なのに、この子が謝るのはおかしい。
罪悪感を抱くべきは、彼女の優しさにつけこんで願いを叶えようとした私の方だ。
「えっとね、きみは悪くないよ。わたしも無理言ってごめんね」
次に上げるのは17話です
7割くらいは書き終えているので、次の投稿までそんなに期間が空くことはないと思います
しばしお待ちを……
どうしたら、彼女ともっと上手く話せるのだろう?
私は頭を捻り、思考を巡らせる。
色々と考えてみてはいるのだけど……。
「んん……」
結構……苦戦している。
考えたところで、ずっと失敗続きだった私には正しい会話の仕方が分からない。
いくら誰かの口調を真似ようと、その口から発せられたであろう言葉までは簡単に真似出来ない。
………………。
もっとたくさん話せていればなにか違ったかもしれないけど、それは無理な話だ。
だって、あの子はもう居ない。
私が彼女の未来を奪ってしまったんだ。
「…………」
(あなたがここにいてくれれば、私が生きる必要はなくなる。
もしそうなったら、私が苦しまなくちゃいけない理由もなくなるのかな?)
……………。
いつの間にか思考が数日前まで逆回りしている事に気づく。
これではいけないと思い、何とか思考軌道の修正を試みる。
ここ数日のことについては思い出したくなんかなかったけど、今の私は既に記憶の水たまりに片足を突っ込んでいる状態なのだ。
"どうせ"なら全身を海に沈める位の気持ちで、色々と思い出してしまおう。
そしてその過程で役に立つ情報を見つけられたら、ついでにそれを利用する。
辛いこと、悲しいこと、何を思い出したっていい。
今後のためになるのならそれが何よりだ。
それに、何があったって、これ以上に気持ちが落ち込むことなんてないだろうから。
……やっぱり、"どうせ"というのは非常に私らしくてなんか嫌だ。
だから私は"せっかくなので"と思うことにした。
私は早速、冷たい水底に意識を沈める。
………………。
確か……何日か前に、たくさんお話ができた日があったはず。
その時のことを詳しく思い出してみよう。
……あの日も、今日と変わらずに雨が降っていた。
私の隣には名前も知らないフレンズがいた。
その子は無口なのか、私が何を話しても声を出さなかった。
何度話しかけても、ただ何かを悟ったような視線をこちらへ向けるだけ。
そんな彼女に向かって、私が言う。
『あなた、つまらないわね。……もういいわ。今…楽にしてあげる』
私はそう言って彼女の首に両手を添えた。
そして、ほんの少しだけ力をこめる。
そこまでしても彼女は声を出さなかった。
目を細め口角を少し吊り上げたその表情は、まるで死を受け入れようとしているように見えた。
それを見てどう思ったのか、私はさらに強く彼女の首を絞めつけた。
……数秒後、もうその子は何も反応してくれなくなった。
虚ろな目で私の心を見透かすような真似も止めたようだった。
私はより強く、手に力を込めた。
━━その時だった。
小さな呻き声が聞こえた。
私が手を離す。
それから…………。
気がつくと、右手に鋭い痛みを感じていた。
ぼんやりとそこを見た。
さっきまで首を絞められていた少女が、私の手に噛み付いていた。
私は彼女を引き剥がし、突き飛ばした。
『そんなに死にたいなら……今すぐ殺してあげる』
震える声で私が言った。
それを聞いた少女が、ようやく言葉を発した。
彼女がなんと言ったのか上手く思い出せない。
でも、なんのための言葉だったのかは分かる。
その懇願するような声を。
それらが形作る願いを聞いた私は首を横に振った。
それを見た少女がまた何か言った。
私はまたその願いをはねのける。
その後も、何度も同じ言葉が繰り返されている。
段々と二人の声にノイズがかかり始めてくる。
……そして最後にはノイズだけが残った。
耳障りな雨の音だけが。
「…………」
私はとんでもない思い違いをしていた。
そのことに今ようやく気づいた。
あんなのはお話なんかじゃない。
ただの脅しと、命乞いだ。
別の記憶を探しても、同じようなものばかり。
今の今まで脅しなしでは何ひとつとして上手くいかなかったと思っていたけど、それは違ったのかもしれない。
(私が上手くできたことなんて一度もなかったんだ。)
「……」
私は誰にも聞こえないくらい小さなため息をつくと、向かいの木にもたれかかっている少女に目を向けた。
俯いたまま、黙り込む彼女に。
(今はとても落ち着いているみたい……)
あの後、私が彼女の手を引いて海から離れここまで歩いてくる間中、彼女はずっと泣いていた。
きっとそれは「悲しい」とか「怖い」みたいな感情から出た涙じゃない。
彼女自身が与りしれぬところで起こったのだろうと私は思う。
無意識的なものなのだろうと。
ただ手を引かれて歩くだけだった彼女に、突然手を振り払われた。
でも次の瞬間には、私の背中に顔を埋めて泣いていた。
そんな彼女の頭を私が撫でて慰めた。
……泣かせたのは私なのに。
きっと彼女はパニックに陥って、どうすればいいのか分からなくなったんだと思う。
彼女は自分に命の危険が迫っていても、私に危害を加えなかった。
とても優しい心を持っているのか、突き抜けた怖がりなのかは分からない。
でも、至近距離に迫った死を受け入れることしか出来ないのは、きっととても恐ろしいことのはずだ。
そんなのは絶対に本能が拒絶するはず。
でも彼女はそれを許してしまった。
自分の本能に背いた結果、どうすることも出来なくなって、最後にはただ涙を流すことしか出来なくなった。
…………。
でももしかすると、…それが、外敵に捕まってしまった少女にできた精一杯の抵抗だったのかもしれない。
何の意味も無いようなその抵抗は、私には有効だったから。
彼女のほんの数滴の涙に、私は心を揺さぶられたのだ。
今さら自分のことを慈悲深いだなんて思わない。
今まで何人ものフレンズを自分の意思で傷つけたのだから。
そんな私に誰かの特別になる資格なんて無いのかもしれない。
でも、その時だけは……。
世界でたった一人、彼女を慰めてあげられる誰かでありたかった。
だから私は彼女のことを抱きしめて、頭を撫でたんだ。
自分の罪を改めて自覚した。
せめてもの償いをと優しく抱きしめた。
それなのに……。
彼女は私に感謝の言葉を言ったんだ。
涙混じりの声で、「ありがとう」って。
それは本能が無意識に喋らせた心無き音だったのかもしれない。
でもその声を聞いた時、私は罪悪感を感じると同時に、自分を泣かせた悪いやつにまでお礼を言ってしまうような女の子のことを、とても愛おしく思ったのだ。
(また昨日みたいに話してくれないかな……)
昨日あった崖際での攻防を思い出す。
私の言葉を聞いた少女は慌てふためき、何やらおかしなことを口走った。
私はそれを受け止めて、次の言葉を紡いだ。
……それは単なる時間稼ぎ。
大した意味を持たない空っぽな言葉だった。
でも、それは私の心からの言葉でもあった。
深く考えずに発した声。
屈折した思考も打算もない、思ったままの言葉。
それは、私が長らく忘れてしまっていた私の本当の声だった。
(彼女の声に応えた動機は、打算的と言えなくもないけどね……)
もし昨日みたいに思ったことをそのままの形で伝えたら、もう一度声を聞かせてくれるだろうか?
「……」
目を閉じて心を落ち着かせる。
次の言葉はもう思いついている。
でも、それを言おうとすると鼓動が早くなる。
本当にコレでいいのかな?
余計に嫌われないだろうか?
そんな不安が雨音となって降り注ぐ。
私はそれらを振り払う言葉を探した。
しかしそんなものは見つからない。
私の思いつく言葉はどこか危なっかしくて、どうしても不安が残ってしまう。
……上手く言い出せない。
こうしている間にもどんどん鼓動が早くなる。
早くなった鼓動が私を急かす。
私は背中を押されて足がもつれるように口を開いた。
そして、両手を広げて酷く歪な言葉を紡ぎ出す。
「また……抱きしめてあげよっか?」
「…………?」
私の言葉を聞いてしまったであろう少女が、ジトっとした視線をこちらに向ける。
心底『何を言っているんだこいつは』みたいな視線がつらい。
(まあ……反応してくれるだけマシ…なのかな?
あっ、目そらされた……)
……もう既に若干後悔している。
こんな頭に浮かんだことを何の審査にも通さず直接口に出すようなのは、今後は控えるべきだろう。
ちゃんと考えて言葉を選ばないと、また誰かを傷つけてしまうかもしれない。
今回は私一人の心がかすり傷を負った程度で済んだけど、こんなことを続けていたらいつか盛大にやらかしてしまうだろう。
もうこれ以上罪を重ねるわけにはいかない。
「今の…は、忘れて。…ね?」
変に思われると困るので、とりあえず直前の発言を取り消しておく。
彼女が本当に忘れてくれるかは分からないけど、これでこの会話はまた振り出しに戻ってしまったことになる。
まあこれといって何か進展があったわけではないけれど。
(どうしたもんかなぁ……)
今度は前もって会話の内容を頭の中でシミュレートしてみようか?
上手くいく気はしないけど、それでも何も考えないよりかはいいはず。
客観的に自分を見て何かに気づければそれでいい。
私は早速これを試してみることにした。
『ねぇあなた、お腹すいてないかしら?』
『……』
『あなたは私のこと嫌い?』
『………』
『あなたに私は見えてないみたいね』
『…………』
「……………」
だいたいの予想は出来ていたけど、想像の中でも無言のままでいられると……つらい。
視線を向けるだけとかでもいいから何か反応を示して欲しい。
……というか、想像上での私もどこかおかしい気がする。
一言一言に微妙な違和感があるのだ。
(あなた、あなたって……これじゃまるで……)
どこかおかしな想像が更に変な方向へと向かい始める。
わざわざ名前で呼ばなくても通じ合える程の距離。
とても近くて……近い。
お互いの息がかかってしまうほどのきょり。
それは友達以上の━━━
「━━━なまえ」
私の想像……もとい妄想は、私自身の声によってかき消された。
(そうだ……私はまだ彼女の名前も知らないんだ)
だからこんなにも私の彼女に対する呼び方が限定されてしまっているんだ。
もうずっと誰かと名前で呼び合うことがなかったから忘れてしまっていたけど、名前は本来とても大切なもののはず。
大切な友達の名前も知らないなんて話は聞いたことが無い。
お互いの名前を知ればもう友達……という訳では無いけど、心の距離は大きく縮まるはずだ。
(これはなんとしてでも聞き出さなければ…!)
ようやく自然な話題を見つけることができた喜びを感じつつ私は口を開いた。
「私の名前はゴイシシジミ」
またやってしまった。
あまり深く考えずに実行に移った結果、やけに簡潔な自己紹介になってしまった。
自分の名前を言いきった直後に間違いに気づき、「イシちゃんって呼んでもいいのよ?」と付け足したのは我ながら機転が利いていた…と思う。
ちょっと馴れ馴れしすぎた気がしなくもないけど、今は気にしないことにする。
重要なのはこの後なのだ。
「あなたは?」
「…………」
つい自分の名前を答えてしまいそうな自然な流れを作ったつもりだったけど、帰ってきたのは沈黙だけだった。
……無理に喋らせる方法はある。
でもそれはあまりに強引かつ非人道的だ。
それ無しでは今のこの状況を作り出すことも叶わなかったことは分かっている。
でも、もうそんなものに頼るわけにはいかないんだ。
私にとって一番だった本法を封印した今、自分にできることがあまりに少ないのを実感する。
今の私は無力な子供同然だ。
自分でそれを認めてしまったら、私はもう子供らしいやり方でしか目的を達成できなくなってしまう。
(……別にそれでもいいか)
どんな方法を使ったって、目的を果たせるならそれでいい。
私はとある方法、ある種の強引さを持った稚拙極まりないやり方で彼女の名前を聞き出すことにした。
「あなたの、名前は?」
「……」
「教えてほしいなー?」
「……」
「お・な・ま・え、わかるかなぁ?」
「………」
━━仕方ない。
「教えてくれるまで何度も訊くよ? 四六時中あなたに話しかけるよ? あなたが私を刺して殺したくなるまでずぅっっっと言い続けるよ? 私はしつこいからね。
教えてくれたら少しは大人しくなるかもしれない」
「ぅ……」
私が一息に言い終えると、目の前の少女が小さくうめいた。
そして━━
「ぅわたし…は、……ササコナフキ*******、…です」
「ぇ……?」
(今のは……彼女の名前? ササコナフ……?)
彼女の口から零れた名前らしき文字列は以外にも長く、一度聞いただけでは理解ができない。
ようやく口を聞いてくれたという喜びと、名前を上手く聞き取れなかったというやってしまった感が頭の中で渦巻いている。
慣れない言葉詰めで軽い酸欠を起こしていたからちゃんと覚えられなかった?
……いや、もし万全の状態だったとしても、きっと覚えきれなかっただろう。
私はあまり物覚えがいい方ではないから。
(まずいなぁ……)
とても長い名前だったのは覚えてる。
それと、あとは最初の数音だけ。
私はせめてそれだけは忘れまいと口を開いた。
「ササコノフ……?」
とりあえず自信のあるところまでを声に出して、少女の方をちらりと見る。
すると……。
「・・・・・」
返事はなかったけど一応の反応はあった。
━━━蔑むような目。
その目を見た瞬間、背筋にゾクゾクとしたものが駆け抜けた。
咄嗟に顔を伏せる。
(もしかして私……間違えちゃった……? )
私が声に出したのはササコノフ。
そう聞こえたから声に出した。
でもよくよく考えたらササコネフだったような気がしなくもない。
「ササコネフ……?!」
私は恐る恐る顔を上げた。
「……」
諦めたような顔。
彼女の表情を見るに、私はまた間違えてしまったのだろう。
何度も名前を間違えた上に呼び捨てみたいになってしまった。
このままでは、いい加減なやつだと思われてしまう。
なんとか軌道修正をしなければいけない。
「これは、ほら……あれよ。……ぁ愛称! 親愛なるあなたへ私からのプレゼント!」
もうだめだ。
馴れ馴れしい上に恩着せがましい。
……どう足掻いても私は変な人になってしまう。
これでは、危ない人のレッテルを貼られるのは免れられないだろう。
(上手くいかないな……)
「━━━━……ササコって呼んでいい…?」
私は半ば諦めがちに訊いた。
「……どうぞ。……っ!」
「……ぇ?」
少女は一言返事をすると、しまったというような顔をした。
「いいの?」
「……」
「……ササコ」
「…………」
彼女がそれを了承した。
愛称で呼ぶことを許してくれた。
たとえそれが、反射的に口をついた不本意な言葉だったとしても、私は嬉しかった。
だから━━━
「よろしくね、……ササコ…!」
そう言って左手を差し出した。
ササコがその手を取ることはなかったけど、それでも……。
この時の私は、きっとだらしない顔をしていたと思う。
私は今日も夢を見る。
いつものように、また、悪夢を見ている。
それを自覚しているのに、目を覚ますことが出来ない。
起きようと意識を集中させても、舌を噛み切ってみても、目の前の景色が変わることはなかった。
「……」
私は途方に暮れて辺りを見回した。
…………。
……仄暗くてよく見えないけど、ここが閉鎖空間ということだけはなんとなく分かる。
「…………」
真っ暗ではないということは、どこかから光が入り込んでいるのかもしれない。
私は光の源を探して見ることにした。
ぽふ
「……?」
一歩足を踏み出してみると、足が地面に沈みこんだ。
妙な感覚だった。
靴越しにふわふわとした感触が伝わってくる。
なんだろう、と思った。
こんな寝心地の良さそうな地面には心当たりがない。
それなのに、ここがどこなのかは今の一歩で理解出来てしまった。
ここは……繭の中なんだ。
誰かがヒトリで眠りにつく為の、特別な空間。
とても私がいていい場所なんかじゃない。
それなら一刻も早くここから出なければいけない……はず…?、。
なんだかぼんやりとした焦燥感を胸に、私はさらに歩を進めていく。
もふ、もふ……
もふもふもふもふ、
もふ…………もふ……
…………もふ。
私の足取りは足元から伝わるこの感触ほど軽くはなかった。
ただでさえ眠くて体が重いのに、一歩進む度に耐え難いほどに眠気が増幅されていくのだ。
もふもふに足を数もふcm沈めるだけで、意識が融けてしまいそうになる。
この眠たくて仕方ないのを何とかするべく、頬をつねってみる……。
が、あんまり痛くない。
こんなので眠気をどうこうしようなんて言うのは夢のまた夢だ。
仕方ないので、私は自分の舌を噛み切ることにした。
口を開けてめいっぱい舌を伸ばす。
目を瞑り、喉を鳴らす。
そうしてようやく覚悟が決まったら、一気に歯を食いしばる。
一気に!
「──ッ!………………?」
……痛みを感じない。
頬を指で摘んだ程度の痛みすらないのだ。
私は舌を思い切り噛めば、重く鋭い痛みがすぐにやって来るだろうと予想していた。
でも実際には違った。
重たいどころか私の舌はとても軽かった。
それも少しの質量も感じさせないほどに。
これはどういうことかと不思議に思った私は、客観的に自分を見て確認することにした。
私は妙になれた手つきで左の目玉を取り出す。
そして、少しべたつくそれを親指といずれかの指とでころがし、自分の方へと視線を合わせた。
私の左目に上下逆さまの自分が映る。
恐る恐る口を開けて中を覗き込む……。
────ない。
咄嗟にしまった、と思った。
さっき一度舌を噛んだ時に、勢い余って噛みちぎってしまったのを忘れていた。
これでは目を覚ませない。
「……」
(……とりあえず、眼は元の位置に戻しておこうかな……)
私は手に持っていたそれを右の窪みに押し込み、ぱちぱちと瞬きをした。
「……?」
なんだか視点が微妙に…右にズレている気がする。
私はそのズレを修正するべく、左目へと手を伸ばした。
………………。
しかし、指先が触れたものは、さっきまで私の手の中にあったものとは違った感触をしていた。
眼よりもずっと柔らかい何か。
私はそれを引っ張り出してみた。
(これは……石?)
所々角張ったそれは、……石のようだった。
それを理解した瞬間、
「……っ!」
空を切りながら薄闇に溶けて行く石ころ。
私は、何食わぬ顔で自分の体に紛れ込んでいたそいつにひどく腹が立った。
だから思い切り遠くへと投げ捨ててやったのだ。
「…………」
なんとも言えない、喪失感のようなものが私の心を満たしている。
そうだ、そういえば舌を無くしたんだった。
とても残念……。
噛み切るための舌をどこかへやってしまった。
(……あれ?)
そもそも、舌はどうして必要なんだっけ。
なんで無くなったら『残念』なんだろう。
別になくてもそんなに困らない気がする。
むしろ、味覚を感じなくて済むなら、無い方がいいに決まってる。
それなのに私は、そんなものにいつまでも執着している……。
どうしてだろう?
噛み切るための舌。
噛み切って、……痛みに身を縮こませるための────。
そうだ、思い出した。
今の私に必要なのは不味い味を感じさせる舌でも、つらい現実を映し出す目玉でもない。
目を覚ますための痛みが必要なんだ。
ここは夢だから。
私が大嫌いな痛みを許容しているのも、自らのおぞましい行動に目を瞑っているのも、全部、ここが夢の中であるからこそだ。
(これだけ理解できてれば、……十分だよ。)
右腕を顔の前まで持ってくる。
そして、彼女が逃げられないように、残されたもう一本の手で拘束した。
これでもう逃げられない。
肘の内側辺りに歯を突き立てると、そのまま右腕を力任せに引きちぎった。
断面に耐え難い痛みを感じる。
……いや、実際には耐えられる程度の痛みしか感じてはいないのだろう。
まともに思考できているのがその証拠だ。
この程度、私があの子に与えたものには遠く及ばない……。
私はいつの間にか手段が目的に成り代わっているのに気づいた。
元々は眠気に耐えるための行いだったはずだ。
なら、本来の目的は達成出来ただろうか?
その答えは考えずとも分かる。
痛みによる意識の鮮明化はあまり効果が無かった。
でも、私は間違いなく目的を果たせたのだと実感している。
今は血の気が引いて、眠いどころではない。
取り返しのつかない事をしてしまったと青ざめているのだ。
断面から溢れ出す血なまぐさい液体は、繭の色を真っ赤に染め上げてしまった。
最初のうちは私の足元だけに留まっていた色は、今では全体に広がってしまっている。
もう取り返しがつかない。
「っ!?、っ?!っ──……………?」
半ばパニック状態になりながら、何とか流れる血を止めようとする中で、ふと、私は不思議なことに気づいた。
あんなに暗かったのに、血の赤色だけはやけにはっきりと目に映るのだ。
私は少し考えて、そして理解した。
この身体に流れる液体、私の血液は発光していたのだ。
なるほど、道理で気分が落ち込むはずだ。
私は悪態をつきたくなるのをぐっとこらえた。
血が光るからと言って、悪いことばかりではないはずだ。
目がチカチカして安眠出来ないかもしれない。
偶然誰かに見られて不気味がられるかもしれない。
でも、今はどうだろう。
ここには私しかいないし、ここでぐっすり眠るつもりもない。
それに、ほら─────。
俯いた視線を遠くへと向ける。
さっきまでは暗くてほとんど何も見えなかったのに、今では空間全体が赤く照らし出されていて、遠くまで見渡せた。
思いの外広かった繭の内側には、目印になるものが何も無く、ひどく殺風景だ。
何も見えなかったのはそういう事か、と納得する。
(えっと、出口は…………あそこかな?)
周囲を注意深く見渡していると、遠くの方に一際強い光を見つけた。
しかし、そこは私が向かっていたのとは逆方向だった。
…………。
数歩分の徒労で済んだだけ良かったのかもしれない。
もし、あと五、六歩くらい離れてしまっていたら、もう光は永遠に見えなくなっていたかもしれないのだから。
(よし────っ!)
私は気を取り直して、光ある方へと足を向けた。
もふ、もふ、もす、ぽふ
ぱふ、ばす、がす、ばち
めき、めき、ぼき、ぶち
がつ、ざく、ざく、ぴしゃん
地面に足を埋める度、不気味な音が辺りに木霊する。
そのどれもが不吉で、痛みや別れを想起させるものばかりだ。
でも、不思議と恐怖を感じることはなかった。
きっと、自分でもわかっていたんだと思う。
私にとっての痛みと別れは、これから始まるのだと……。
私は躊躇しつつも前へと進む。
背後には小さな気配がひとつ、いつの間にか着いてきていた。
振り返ってはいけない、歩みを止めてはいけない。
この身には不釣り合いなほど優秀すぎた本能が告げる。
それならと、私は前へ前へと進んだ。
つき動かされるように。
本能は決して裏切らないから。
彼女はいつだって、私がより苦しむ選択を導き出す。
だから盲目的にでも信じられるのだ。
…………………………。
そうして歩いていると、次第に、正体不明の不快音が聞こえなくなってくる。
その代わりなのだろうか。
今、ようやく静かになったはずの頭の中で、パチパチという音が鳴っている。
燻るように、小さな音で。
不安に思いつつも立ち止まることは出来ない。
なにかに取りつかれたように足を前へと、前へと。
近づけば近づくほど視界が鮮明になっていく。
……音の正体と光の正体。
その両方が、残された片方だけの目に痛く鮮明に焼き付いた時、私はようやく足を止めることが出来た。
さすがにこれだけ近づけばこれが何かはわかる。
周囲を照らしていたもの。
それは火だった。
直径十センチほどの、炎にも満たない小さな灯り。
私はその小さな灯りに誘い出されたのだ。
(なんだ、出口じゃなかったんだ。)
その場でしゃがみこんでぼんやりと火を眺める。
手をかざすとほんのりと熱を感じた。
(あったかいな……)
無駄足だったのかもしれない。
でもこうしていると、悪態のひとつをつきたくなる感情がみるみるうちに溶けていく。
とっても、心が安らぐ……。
バサバサっ。
ふと、火の中に何かが飛び込んだ。
なんだろう。
不思議に思いまじまじと見つめていると、何かは動いた。
もしかすると、火のゆらめきと見間違えたのかもしれない。
私は目を擦り、もう一度それを見た。
「────っ…………」
見間違いなんかじゃなかった。
小さな火の海にのまれて苦しんでいる。……私と同じような、小さな虫けらが。
きっともう助からない……。
とても小さな炎だった。
それでも、彼女が死んでしまうには十分なのだろう。
灰に成りゆく命を前に、私にできることは何も無かった。
火中のムシが脚やハネを必死に動かす姿をただ見つめる。
パチッ
小さな破裂音と共に、黒焦げのお腹が爆ぜた。
それでもまだ動いている。
六本の足が、ピクリ、ぴくりと。
そのさまをぼーっと見届けていると、先程の眠気がまた込み上げてくる。
ふわーっとあくびをして目を細める。
目をこすり、もう一度火の中を見た。
ぴくり……。
もう少しだけもがいたあと、やがてそれは動かなくなった。
私は何故か手に持っていたコップの水を、未だ燻っている亡骸にぶちまける。
(可哀想に……。自分から火に飛び込むなんて。
きっと本能には抗えなかったんだね。)
そんなことを思った。
『何をしているんですか』
「───ッ!」
だんだんと怪文書じみてきたので、一度ちゃんと文章の作り方を勉強するべきかもしれない
突然、後ろから誰かに声をかけられた。
私はビクッと飛び上がり、恐る恐る振り返る。
今度は本能も止めなかった。
「……」
後ろに立っていた少女と半分だけ目が合う。
彼女は私の欠落したもうひとつのことなんて気にもとめず、もう一度同じ質問を繰り返した。
今度はさっきよりも強い口調だったけど、全然怖くない。
私はもう既にこれが夢だと気づいているし、そもそもそんな優しい顔で怒られても迫力なんて全くといっていいほど無い。
(これで何回目だろう。)
赤く汚れてしまった借り物の繭の中で、本来の持ち主に出会った。
何度か繰り返された出会い。
これは数回目の再邂逅。
『答えてください』
(─────え?)
先程とは違う険しい表情で私を問い詰める少女に違和感を覚える。
彼女とは夢の中で何度も会ってきた。
でもこんな風に厳しい表情を見せたことはこれまでに一度たりともなかった。
彼女はあくまで写しなのだ。
だからこの責めるような目も、やけに丁寧な口調も、私には違和感でしかない。
ずっとあの子とは別人だと割り切ってきた。
夢子とかいう安直な名で呼び、差別化を図っていた。
でもこんなにもはっきりとした差を持っているのは絶対に変だ。
これはどういうことだろうかと考え込んでいると、ふと脳裏にあるものがよぎった。
思い出したのは真新しい記憶。
新しい友達(?)のササコが私に見せた敵意に満ちたあの目だった。
そういえば、ササコの口調もこんな風に丁寧な感じだった気がする。
(所詮は夢、かぁ……)
姿だけこれまで通りなのは、私がまだササコのことをちゃんと記憶できてないということだろうか。
もしそうでないとしたら、それは間違いなく未練なのだろう。
いつまでも現実を受け入れられない子供な私が、夢に希望を見出そうとしている。
もし本当にそうだとすれば、それはまあ馬鹿みたいな話。
……でも、こんなふうに考えていられるのもきっと今だけだ。
いつかはこの声や目の輝きも変わってしまうのだろう。
そう思うとなんだか急に寂しくなった。
だけど、どれだけ感傷的になろうとしても結局は夢。
だからわずかな悲しみも生まれない。
寂しいどまりだ。
『聞こえてますよね』
「……」
このまま全てが順調に進んであの子の写しと二度と会えなくなった時、私はようやく役目を終えることが出来る。
そんな気がする。
(もう十分……。早く目を覚まさなきゃ─────)
私は今度こそと、目覚めるために意識を集中させた。
薄れゆく赤色。
徐々に体の感覚が失われていく。
今度はちゃんと起きられる。
そう思った時。
『あなたが殺したんですよね』
「…………」
夢子が腕を掴んできた。
このまま逃してはくれないようだ。
さて、どうしたものか……。
試しに少し微笑んで首を傾げてみる。
すると、『しらばっくれないでください』と余計に気分を害したようだった。
しらばっくれるなと言われても、なんのことだか分からない。
そのまま彼女と見つめあっていると、だんだんと不機嫌そうな表情になってくる。
その目が不機嫌を通り越してゴミを見るような目になった時、ようやく腕を離してくれた。
もう触れていたくないということだろう。
『本当に分からないんですか…?』
「……?」
『さっきからあなたが頑なに見ようとしない、彼女のことですよ』
そう言うと視線が少し横に逸れる。
それは私の肩を抜け、その先を見ていた。
私は首だけ動かして後ろを見た。
そこには小さな火溜りが落ちていた。
パチパチと耳障りな音を立てて揺らいでいる。
(えっと……ああ、あれのことか)
火は消したと思ったんだけど、なんでまだ燃えているのだろう。
そんなことを考えるのは馬鹿げているかもしれない。
『なんですか……その表情は───っ!』
ササコモドキがまた何か言っている。
今度はなんだろう。
私の目つきが悪いとか言い出すのだろうか。
……もし本当にそう言われたらどうしよう。
(うーん……別にどうするもなにもないか。)
ここで再び目つきの悪さを指摘されたところで、私が意外と気にしいだったということが発覚するだけだ。
でもまあさすがの私も夢にまで見る程根に持ってはいないはず……。
『────ああ、そうですよね。"そんな目じゃ"、ちゃんと見えないですよね』
そう言って何か一人で納得すると、急に押し倒してくる。
私の心臓は高鳴ったりはしなかった。
その代わりかどうかは分からないけど、火が燃える音がとても近くに感じた。
(───……というか、本当に目の事だったんだ。しかもそんな目って……)
反抗的な目と見つめ合うこと二、三秒くらい。
先に動いたのは夢子の方だった。
片手で私の首を掴むと馬乗りになる。
私に触れたくないのではなかったのか。
彼女の目を見るとなんだか冷めた感じ。
首でも締められるのかと思ったけど、そうではないようだ。
私はまた見つめ合うのかとため息をついた。
その直後だった。
「……っ!?」
私の穴に何かが触れた。
ベタつく液体が縁の部分に垂れている。
(気持ち悪い……)
そこに視線を向けて何をしているのか確認しようとするも、ちょうど視界の外で起きている事態を把握することは不可能だった。
今は首を掴まれていて頭を傾けることすら出来ないのだ。
こうなってしまったらもう為す術がない。
私は右だか左だかの眼の空洞に押し当てられた物体を受け入れるしか無かった。
「……っ」
何かはゆっくりと押し込まれた。
それは音もなくはまると、ズキズキとした痛みを訴え出す。
目が、開けられない……。
痛い。……何も見たくない。
目の奥の方から溢れてくる血か涙かを必死に押し止める。
これが今の私に出来る精一杯の抵抗だった。
それなのに。
『目を開けてください』
それはお願いなんて生易しいものじゃなかった。
これは脅迫だ。
今すぐに目を開けないと恐ろしい目に遭わす。
彼女はそう言っているのだ。
このまま彼女の要求を無視し続ければ、残りの四肢を食いちぎられたりするかもしれない。
でも私は屈しない。
どうせこれは夢なんだ。
夢の中なら何があってもとりあえず死ぬことは無い。
それなら肉体よりも精神を健全に保つことの方が大切だと言える。
だから私は何をされようと絶対にこの目は開かない。
そう固く決意する。
それは勇ましさなんて欠片ほどもない、臆病者の決意だったけど……。
『そうですか……。もう、しょうがない人ですね』
目を固くつむっていると、呆れたような声で誰かが囁いた。
それは優しい声のようにも聞こえて……。
私はその声に不思議と安心感を覚えた。
首に添えられていた手にはもう少しの力も込められてはいない。
それはするりと離れると、そのままどこかへと消えてしまった。
「………………」
それから少しの時間が経って、火が燃える音がすっかり聞こえなくなった頃、私は再び目を開いた。
不自然に広く感じる視界。
目の痛みはとうに消えていた。
頭痛の種である彼女の姿も、…一緒にどこかへと消えてしまった。
……これはきっと私にとって好都合なはず。
それなのに今は、広くなった視界に誰も居ないことがどうしようもないくらい不安で……。
独りでいることは、こんなにも怖いものだっただろうか。
(……起きよう。)
もう目覚めを邪魔する者はいない。
今度こそここから出られる。
一刻も早く起きて忘れるんだ。
(心残りは……ないことも無いけど。)
私は名前も知らない虫だったものを一瞥し─────。
「────っ…………」
私はそれを見て動きを止めた。
これはなんだろう。
たった今鮮明に目に焼き付いたはずのものが、上手く認識できない。
それは燃えていた。
ごうごうと音を立てて真っ赤に揺れている。
下から上へ、川みたいに流れている。
その流れの中で、白かったはずのものが、赤く燃えている。
"あなたが殺したんですよね"
頭の中に響くのはそんな言葉。
責め立てるような声で、反響する。
……うるさい。
『あなたが』
やめて。
『あなたが』
わかってるから、もう黙ってよ……。
「…………」
浅く息を吸うと肺の中が熱い空気で満たされた。
熱に浮かされた本能が、もう認めるしかないのだと私に告げる。
「………………。」
……全部思い出した。
私は責任から逃げるために、彼女に背を向けたんだ。
燃え盛る炎を見て見ぬふりした。
助けられたかもしれないのに何もしなかった。
挙句罪の記憶ごと熱源へと放り込む。
それだけの事をした。
なのに、どうして……?
記憶回路の八割近くを焼き切ってやったのに、どうして今さら思い出したんだ。
これでは知らないフリもできない。
(う……ああ……わたしは……ッ!)
水底のように冷たい心が燃え上がる。
細胞の一つ一つを焦がしながら叫ぶ。
どれだけ本能を欺いたとしても、私はきっとこの中に飛び込むことなんてできない。
だから叫ぶ。
千切れた舌のひどく歪な音で叫ぶ。
これが夢で、全部自分の頭の中での出来事だから大丈夫だってことは知ってる。
でも私は、刻一刻と面影を失って行く彼女を前にして冷静さを保つことなんてできなかった。
一瞬誰の名を呼ぶか迷った後。
「アメちゃん────ッ!」
「ちーがい!ますー! わたしは、はれですっ!」
夢の中での記憶や認識の多くは出鱈目なものなので、あまり気にしても仕方ないです
サブタイトルが付いてなかった話にちゃんとつけ直しました
その過程で話数が1話分ズレてます
気がつくと目が覚めていた。
重たく閉じられた瞼を持ち上げるためにだいぶ苦労したはずなのに、目覚めの瞬間は随分と呆気ない。
もしかしたらまだ夢の中なのかもしれないと疑うも、この開放的かつ閉塞的な空は間違いなく現実のものだった。
灰色の空。
それは僅かな赤みも帯びない、私の見慣れた不純な色だった。
(視界は正常、か。)
それに、目覚めの気分も存外悪くない。
あんな夢を見た後だというのに、心もなんだか冷めていて。
もしかすると、昨夜寝る前に虹草を多めに食べたのが効いたのかもしれない。
(……それなら、これからは眠る前に少し多めに草を食べることにしようかな。)
「…………」
今の私はきっと苦い顔をしているんだろうなと思う。
少し余計に不味い思いをするだけで今後の目覚めが爽やかなものになるのなら、絶対にその方がいいに決まってるのに、私はそれがなんだか良くないことのように思えてならない。
これは別にあるかも分からない防衛本能を理由にして不味いのを回避しようとしているとかそういうわけじゃない。
さすがの私もそこまで子供ではないはず……。
そもそもだ、冷静に考えると虹色に光る草とか絶対に食べちゃダメなやつなんじゃないか。
草じゃなくてもそう。
あんなにおどろおどろしく発光するなんて、明らかに有害な何かを含んでいるとしか思えない。
そんなものを最初に食べようと思った時の私は一体何を考えていたのだろう。
少しの間追想にふけるも、結局何かを思い出すことは出来なかった。
「ふわぁ……」
短いあくびがこのまま起きるか、それともまだ寝るのかと、選択を迫ってくる。
せっかく目を覚ませたのに、このままではまた夢の世界に引き戻されてしまうだろう。
「あふ……」
もうこれ以上無駄なことを考えるのはよそう。
虹草の正体が何であろうと、今更食べるのをやめたりは出来ない。
食べなきゃ健全な心を保つことも出来なくなってしまうから。
私はこれからも、おそらく有害であろう物質を体内に取り込み続けるしかないのだ。
(あれ……? そういえば……)
これから先のあまり健康的とは言えない食生活についての算段を立てていると、ふと、起床直後に誰かの声を聞いていたことを思い出した。
えっと、たしか……晴れがどうとか言っていた気がする。
まあどうせこれも夢か幻聴の類だろう。
早々に考えを切りあげた。
私は目をこすり、大きく伸びをする。
これは朝の日課というやつだ。
目の前の彼女も同じ様に手を組み腕を伸ばしている。
(……え……?!)
目が合った。
それを見た途端、身体が硬直してしまう。
真っ赤な少女がこちらを見ていた。
それもすぐ目の前に座って。
どうして? いつから? あなたは……誰?
当然のような顔でそこにいる少女に対する疑問達が、私の脳を一瞬で支配する。
支配していた……はずなのに。
彼女の左目に宿る異質な光に気づいた瞬間、それらの疑問は全て融けて消えてしまった。
その虹色の輝きは私のよく知るものとよく似ていて、不気味さを感じずにはいられない。
「ぅ……はっ…!……はあ…………はっ……」
毒々しい視線にまっすぐ射抜かれていると、だんだんと呼吸が苦しくなってくる。
息を吸っても、吸っても、変わらず苦しいまま。
きっとこの少女の目から放たれた光線が、私の胸の奥に穴を開けてしまったんだ。
……逃げないと。
私はここにいてはいけない。
いや、もしかするとそれは私の方じゃなくて……。
どちらにせよ、いつまでもこのまま寝起きの顔を知らない子に晒しているつもりは無い。
「お姉さまはあめがきらいです。お姉さまがだい好きなはれも、あめがすきじゃないようです」
私が声を絞り出すよりも早く、少女が言った。
その幼げな声質は起床直後に聞いたものと同じだったけど、声の調子はだいぶ違うような気がする
。
今の彼女からは落ち着いた雰囲気を感じる。
その話し方は落ち着いていて、口調も理性的。
それなのに、何を言っているのか全く分からない。
こちらが言葉の意味を理解しかねているのを察したのか、少女はさらに続けた。
「はれはけっしてあめちゃんなどというおなまえではありません。しんがいのきわみです」
なるほど、少しわかってきた気がする。
どうやらこの子は私に名前を呼ばれたと思ったらしい。
そしてその名前が間違いだったので、こうして文句を言っていると……。
「はれははれです。お姉さまがくれたたいせつなおなまえです」
頬を膨らませて怒るハレ(?)に「しゃざいをよーきゅうします」と謝罪を要求された。
それで彼女がどこかへ行ってくれるなら土下座でもなんでもするけど、ちょっと納得いかない。
「……ごめんなさ───」
「おはよーございます」
私が仕方なくハレの要求に応じようすると、それに被せるように彼女が言った。
「……何?」
「おー、はー、よー、おー! ございます」
「え? …あ、おおはよう?」
どうして急に挨拶をするのか、彼女の意図がわからない。
欲しかった謝罪の言葉を遮ってまでしなきゃいけないことだったのだろうか……?
「うおー……」
とりあえず同じように返したけど、その行いに意味なんてなかったのだろう。
私に朝のあいさつを強要した少女はそっぽを向いていて、その視線の先には一輪の花が咲いている。
ハレはそのありふれた花を興味深そうに見つめていた。
どうやら、彼女はこちらの言動にはとことん無関心なようだった。
「なんですか?! これっ」
「…………」
「わー! なーんなーんでーすかー!? これぇっ!」
他人の言葉には無関心。
そのくせ無視されたらこうしてしつこく粘る。
(まるでここ最近の私みたい……。)
そんな風なことを思ってしまった。
私は周りからはこんな、わがままな子供みたいに見えていたのだろうか?
それは違うと思いたい……。
私は他人の言葉に関心が無い訳ではないし、聞くだけ聞いてはいる。
ただ、都合が悪かったから無視していただけで……。
なおさらタチが悪いと思った。
「タンポポよ」
私が極めて大人的な態度で質問に答えると、ハレは目を丸くした。
何故か無言で詰め寄ってくる。
そんな目で、見ないでほしい……。
「じぃー……」
「な、何……? 私に、なにか用なの……?」
「お姉さま」
「……?」
「おおおーお姉さまっ! お姉さまですよね?! やっとみつかりましたぁ」
「何を言ってるの? …私はあなたの……んむっ?!」
私のことを突然お姉さまと呼び、有無を言わさないといった様子のハレ。
彼女の決めつけるような言葉を否定しようとしたけど、今度は物理的に言葉を遮られた。
片手を頬に添え、そのまま親指を口の中に滑り込ませてくる。
一瞬で果物を何百倍にも甘くしたような味が口の中に広がった。
「うう……うぇっ……」
あまりの甘さに吐きそうになる。
嘔吐いても止めてくれない。
舌で押し出そうにも、指に触れること自体を拒絶するかのように、奥の方へと後ずさってしまう。
そのせいで、甘くなった唾液が奥まで運ばれてまた吐きそうになる。
このままでは間違いなく嘔吐してしまうだろう。
今この体勢で吐いたら悲惨なことになるのは目に見えている。
犠牲者は二人。私と、たった今加害者になろうとしている彼女とだ。
きっとそんなことを理解していないであろう少女が目を輝かせる。
「ふふふー、お姉さま〜っ♪」
(かくなる上は……!)
吐き気の原因を取り除くべく、両手でハレの手首を掴んだ。
そしてそのまま彼女の指を引っ張りだそうと力を込める。
力を込める……!
全力で引っ張る……!!
……しかしビクともしない。
彼女は恐ろしい怪力の持ち主だった。
あるいは、私があまりにも非力なのか……。
どちらにしても、もう為す術なんか無い。
私にはもうハレが満足するまで必死で嘔吐感を抑えるしかないのだ。
(甘くない、甘くない、甘くない……)
おそらく気休め程度にもならないであろう自己暗示をかけてみる。
甘くない、甘くない。
ハレの親指が、形を確認するかのように一本一本の歯をなぞる。
甘くない……甘いくない。
その途中、一際尖った歯を見つけると、より一層目を輝かせる。
甘いくないいや甘い。
楽しげに八重歯の先をちょんちょんやっている。
甘い甘い甘いあまい……。
ちょんちょん、ちょんちょん……。
鼻歌交じりにずっとちょんちょん。
どんどん唾液が滲み出してくる。
そうして嘔吐感がもう限界を迎えようとした時────。
私はようやく解放された。
甘々しい水音と共に指が引き抜かれると、私は口内に残った甘ったるい唾液をすぐさま吐き出した。
「うぇぇ……ぺっ、ぺっ」
「だいじょーぶですか?」
「……」
口を押えて首を横に振る。
と、今度は右の頬に生暖かい感触が……。
それが何なのか理解した瞬間、私は飛び退いていた。
「いいきなり……な、なにをするの……?!」
次から次へと、何なんだこの子は。
突然人の顔を舐めるなんて絶対におかしい。
咄嗟に距離を取ったからよかったけど、もう少し反応が遅かったら噛みつかれていたかもしれない。
奇抜な行動原理のもと動いていそうな彼女のことだ、そういうことを平然とやってのけるだろう。
「う? ちょっと違う……? んー??」
閉じた口からだらんと舌を垂らして首を傾げるハレはなんだか訝しげな表情をしていた。
この場合、私と彼女のどちらが不審者なのだろうか……。
お互いに過去の行いには目を瞑って、とりあえずこの状況だけを見た場合、変なのは向こうのはず…?
なんかだんだんと自信がなくなってくる。
私の方がずっと不審に思っていたはずなのに、「はっ! もしやあなたはお姉さまじゃありませんね!?」なんて指さして突きつけられると、もうこちらが全部悪いような気さえしてくる。
「私はあなたのお姉さんじゃないわ」
「そうでしたかぁ……」
私がきっぱりと言うと、ハレはがっくりと両肩を落とした。
今度はちゃんと分かってくれたみたい。
誤解が解けてよかったけど、この子にはなんだか悪いことをしたような気がする。
「ときにおねーさん、はれはお姉さまをさがしてます。みましたか?」
「だから私は……いえ、誰を探してるの?」
私への呼称がお姉さまからお姉さんに変わっていた。
一瞬その微妙な変化に気づけなくて、間違いでもないのに訂正してしまいそうになった。
「お姉さまです。せなかにはからーふるなはねてきなものがつきでています。なまえはー……ご、ごー……ごくどう…?」
「えっと、……カラフルな翅…が、生えてるのね?」
「なるほど、たぶんそげなかんじです?」
「……? ごめんなさい。見てないわ」
「そうですかぁーあっ!そうですっ」
「……?」
「ふっふっふー。おねーさんも、だれかをさがしてるとみうけたですっ!」
「別に私は誰も……っ!」
言いかけて気付いた。
私の傍にいるはずの少女がどこにも見当たらないことに。
今の今まで忘れていたなんて、私はなんて薄情なやつなんだろう。
ずっと一緒とまで言ったのに……。
自分の無責任さに呆れるばかりだ。
ササコがいない。
昨日寝る前まではちゃんといたはずなのに、どこかへ行ってしまった。
それならいつまでもこうしてはいられない。
すぐに探しに行かないと……!
「ごめんなさい、私用事を思い出したから!」
そう言ってハレに背を向けその場から立ち去ろうとしたが、袖を摘まれて引き止められる。
振り返って見ると、ハレは神妙な面持ちで静かにこちらを見据えていた。
「おねーさんの……さがしびとはだれですか」
「探し人……」
「ハレはきっと、あなたのおちからになれるはずですよ?」
「…………………。白い髪の子をどこかで見かけなかったかしら?」
「ああ、それなら……」
「あっ、えっとね……その子髪は白いのだけど、全体的に土っぽい色なの。土って分かるかしら?土はね、今あなたが……」
「お姉さん」
「な、何…?」
「むこうにいます」
彼女はあっさりとした口調で告げると、私が向かおうとしていた方とは逆を指さした。
「向こう…に、いるの……?」
「はい! そのおひとなら、みちすがらあっちでめぐりあいましたよ!? おねーさん!」
「そ、そう。……教えてくれてありが──」
「れーにはおよびおませんよっ!」
食い気味に言うと、こちらに背を向ける。
「それではまいりましょー!」
ハレは彼女自身が指さした方へと歩き出した。
わざわざ案内をしてくれる気なのだろうか。
それは助かるといえば助かるのだけど……。
「あなたはお姉さんを探しに行かなくていいの?」
「おぅあ! そーでした」
ハレは歩行速度の割に大袈裟なブレーキをかけて止まると、こちらに振り返った。
「おねーさん、ひじょーにもうしわけにくいのですが……!」
両目を細め眉を下げて、いかにも申し訳ないといった表情を見せる。
私はハレが全てを言い切る前に、言ってやることにした。
彼女が何度も私にそうしたように。
「私はひとりでも平気よ」
「お? ぉぉおお……! さすがはおねーさんですっ!」
何がさすがなのかは分からないけど、こちらの言葉がちゃんと伝わったのならそれでいい。
ハレは少しの間、ぴょんぴょんと地面を跳ねてはしゃいでいたが、やがてそれも収まり……。
「それではおねーさん、はれはそろそろおいとまするとします」
「……そう。お姉さん、見つかるといいわね」
「うぉはい!おねーさんもっ!」
そんなお互いちょっと足りないような言葉を交わして、私達はお別れした。
ハレがたたっと駆け出し、途中で何かを思い出したように足を止める。
そして少しだけ振り返ると、目を細めて笑った。
「またねーっ! おねーさん」
ハレちゃん不思議可愛いけどたしかに虹色の目は不気味…
甘ったるい果実を押し込んできたってことはそういう物が主食の子なんでしょうか?
ヘキサノイックさん、おひささです!
ハレちゃんは見ての通りの元気っ子ですが、ミステリアスな一面もあります(主に容姿)
ちなみに、指が甘いのは食生活のせいというのは大体あってたりします
実はこの子はSSに登場する予定が無かったのですが、色々と考えた結果、ちょい役として出すことになりました
なのでこれ以降出番はありません
でも物語に関わってくる重要人物ではあるので、いつか彼女にスポットを当てたお話を番外編として出すかもしれません
(いくら寝起きだからといっても、イシちゃん色々とスルーし過ぎでは……?)
こちらにもぺたり

雨宿りをする二人です
我儘でいいんだ。
ハレが教えてくれた通りの方向へ向かうと、そこに私の探し人がいた。
「ねぇ……?」
「……ぁ」
ササコが振り返り、目が合うと同時に固まる。
彼女は一瞬だけ引きつった不自然な笑顔を作ると、俯いて黙り込んでしまった。
なぜ目をそらすのかも、一度黙ると声が二度と聞けなくなってしまうのも、理由は全部分かっている。
でもだからこそ、こんな時になんて声をかけていいか分からない。
私がササコと同じ目線だったならいくらでも慰めの言葉が浮かぶのに。
現実は違う。
「心配したのよ?」
「…………」
私はまた何も知らないふりをする。
彼女の本音を引き出してしまうと一緒にいるのが少しだけ辛くなるから。
「おはよう」
「…………おはようございます」
ササコは俯いたままだけど、一応返事をしてくれた。
とりあえず、「あなたとは二度と口をききません」は免れたみたいだ。
「うんうん、おはよう」
しばらくぶりの朝の挨拶なのにこれといった感動を抱くことはなかった。
そのことに一瞬違和感を感じたけど、すぐにそれが当然の事だったと気がつく。
(ああ、そういえば……)
今日初めての「おはよう」はもう済ませてしまってたんだった。
……後ろめたさを感じた。
寝起きの数分間を知らない子と過ごしていて、その間一度もササコのことを思い出さなかった。
その数分間が私に罪悪感を抱かせ、先程のササコ同様に口を閉ざしてしまいそうになる。
「……帰るわよ」
私は未だ俯いたままの少女の手を取った。
────────────────────
翌日、ササコはまた逃げ出した。
その次も、さらにその次の日も。
彼女は決まって私が眠っている時にいなくなる。
その度に私が、どこかへ行ってしまったササコを探して寝床まで連れ戻す。
そんな日が何日か続いたある日のこと。
目を覚ますとまたササコが逃げていた。
私はいつものように彼女を探して、そして見つけだした。
いつも通りの展開だった。
「……まだ…ちょっと眠そうね?」
「ええ、まあ……」
「何でまたこんなとこにいるのかは気になるけど……まあいいわ。早く戻りましょう? 今日は特別に二度寝を許してあげる」
そうまくし立てると、私は一方的にササコの手を取り引っ張った。
今日が昨日までと同じなら、これで大人しく着いてきてくれるはず。
しかしササコはその場から動こうとしない。
「……? どうしたの……? …もしかして歩けないの?」
「…………」
「もう、しょうがない子ね……おんぶとだっこどっちがいい? 私としてはおんぶを選んでくれた方が助かるのだけど……」
「……っ!」
「………………」
ササコを捕まえていた手が突然振り払われた。
彼女の体温を見失った私の手の中にあからさまな拒絶の意思だけが残る。
「……私から逃げたいの……?」
「…………」
「それとも、また鬼ごっこがしたい?」
「……そんなの、────」
「じゃあ今度はあなたが鬼をする? 私が逃げて、あなたが捕まえる」
自分でも何を言っているのかよく分からなかった。
強く拒絶された私は、あくまで平静を装うために僅かに残されたコミュニケーション能力すら投げ棄ててしまったのだろうか。
今ササコに喋らせてはいけない。
そんな身勝手な危機感から、私は自分も含めて誰も望まないような提案をした。
「するの? しないの?」
一言嫌だと言ってくれればいい。
そうすれば、今朝のことは全部忘れて、何事もなく今日を始められる。
「……」
(ほら、早く答えないとまた私の自分勝手な決め付けであなたの気持ちをねじ曲げちゃうよ……?)
……私はどこまでも卑劣だ。
ここ数日で何度目かの自己嫌悪をする。
でもそれで、…私が私を嫌いになるだけで望む結果を得られるのなら、もうなんだっていい。
なんだって…よかったのに……。
「そ、そうですね……。それいいですね。やりましょう……」
「ふーん……じゃあ、やっぱりダメ」
「……どうしてですか…?」
「だって私が逃げた後、あなたそのまま逃げるつもりでしょ? 臆病者の鬼さん。その二本の角は飾りかしら?」
私は挑発的に言い放っていた。
ササコはこちらを見ようともしない。
俯き口を固く閉ざした彼女は、もう二度と私と話してくれないかもしれない。
こんな風に言うつもりじゃなかったのに……。
それこそ、一言だけ「嫌だ」って言えばよかったのに。
提案しておいてやっぱり嫌だって言うのはおかしい? そんなことを気にして、あんな追い込むような言い方をしたの? どちらにせよ私がササコの言葉を無下にすることには変わりないのに? そもそもそれらしい理由さえあれば、傷つけてもいいの?
そんなわけがない。
「ササコ……ごめんね……」
「……」
ササコがゆっくりと顔を上げる。
私の目をじっと、見張るように見つめる。
と、すぐに目を伏せて顔を逸らしてしまった。
逸らす直前に数瞬だけ細められた目は問い詰めているようで、「本当に悪いと思っているんですか」と私に言っているようにも見えた。
「あのね、私は本当に……」
「やりましょう」
「……?」
「鬼ごっこ。今度は私が鬼をやります」
「何を言ってるの……?」
「たしか、十秒数えればいいんでしたよね?」
「……待って」
「では今から数え始めるので、逃げてください」
ササコは私の言葉に耳を傾けない。
こちらの返答を無視して話を続ける彼女は、なんだか怒っているみたいでちょっと怖かった。
……でもそれだけじゃない。
こんな話し方をされると、まるで私の人格そのものを否定されているみたいで悲しい気持ちになってくる。
無視と決めつけがこんなにも相手の心を傷つけてしまう行為だったということを。
そして自分のこれまでのササコに対する無神経な振る舞いの数々を、今ようやく思い知った。
(私は彼女に、ずっと……こんなひどいことをしていたんだ)
同じことをされないと気づけないなんて、なんて馬鹿なんだろう。
自らの愚かさを恨むばかりだ。
「あなたが負けたら……」
ササコはかつて私がしたのと同じように、鬼ごっこの敗者がのまなければならない条件を提示しようとする。
たとえ彼女の言葉のその先がどのようなものであったとしても、私はそれに応じよう。
今はそうすることでしかこの罪を償えないから……。
「もう二度と、私に関わらないって約束してください」
「……」
(そうだよね。……これがあなたの本心なんだよね……)
ササコの望みは分かってた。
多分こうなるだろうって、大体の予想は着いていたのに……。
どうして期待しちゃうかな。
私が奪った彼女の自由は、この足一本程度じゃ償えないらしい。
「…………ええ、わかったわ……」
長い沈黙が終わった時、私はもうササコの顔を見れなくなっていた。
せめて最後くらいはちゃんと見たいのに。
夢でこっそり会えてしまうくらい、彼女のことを記憶に焼き付けたいのに……。
体が言うことを聞いてくれない。
一緒にいられるのはこれで最後なんだ。
だから、だから……。
(やっぱり見れないよ……)
私はササコに背を向けてしまった。
その瞬間から二人の時間は動き出し、十秒のカウントが始まる。
二人が独りに戻ってしまうまであと十秒ちょっと。
私はふらふらと近くの木陰まで歩いていくと、寄りかかるように腰を下ろした。
膝を抱えて、ササコの足元をぼんやりと見つめる。
「……」
ぽつりぽつりと雨の雫が地面に落ちては消えていく。
その様子を見ていると不意に視界が歪んだ。
私は目の中にピンポイントで落ちてきた水滴を拭おうとしたけど、やっぱりやめた。
これなら……このままだったら、ササコの顔をちゃんと見れる。
そう思ったから。
でもやっぱり、ぼやけてよく見えなかった。
鼻がつんとする。
(馬鹿だなあ、私)
自分自身への何気ない罵倒がトドメになって水滴が零れた。
頬に冷たいものが伝い、私は慌てて顔を伏せる。
こんな顔ササコに見せられるはずがない。
見せたら彼女の決意が揺らいでしまう。
だから隠さないとだめ。
もうササコに自分を追い込む選択はさせたくないから……。
(─────ああ、もう終わりなんだ)
気づけばもう誰の声も聞こえなかった。
十秒って、こんなにも短いものだったのか。
逃げる余裕なんて全然ない。
「…………」
もう会えないのなら最後くらい笑顔でお別れをしたい。
そうすればきっと、全部いい思い出だったって思えるようになるから。
だから無理にでも笑うんだ。
負けちゃったかって言って、邪気のない笑みを浮かべて……。
前に練習した時と同じように、……楽しくもないのに笑って……。
そして私は………………また、。
(そんなの嫌だよ……)
臆病者は私の方だ。
「ねえササコ、やっぱり……」
やっぱりやめよう。
そう言おうとした。
顔を上げて、ササコの目をちゃんと見て。
でも、私の見ていたい琥珀色の瞳はどこにも見当たらない。
「ササコ……?」
再び顔を上げた時、私は本当に独りになっていた。
────────────────────
ここは一本の木の下。
広い森に無数に存在する木陰の内の一つ。
「やっと、見つけた……。こんな所で、…何をしてるの……?」
私は雨の中を探し回ってようやく見つけ出した鬼役の少女に向かって聞いた。
「えっと、…あ…雨が降ってきたので……雨宿りを……」
「雨……。そうね……もし私が風邪でもひいたら、あなたのせいよ……?」
「……すみません……あ、隣どうですか」
「え? ……うん…ええ、お邪魔するわ」
ササコが自分の真横に目を落とす。
私は不思議に思いつつも彼女の誘いに乗ることにした。
腰を下ろし、隣り合う少女の横顔をちらりと見る。
すると、視線に気がついたのかササコがこちらを見返してきた。
目が合いそうになって咄嗟に視線を逸らす。
「…………」
なんだか気まずい。
さっきまで私たちは、多分ケンカのようなことをしていたのだと思う。
そしてそれは今も変わらない。
仲直りが出来ていないから。
しかしササコとの仲を修復しようとする行為は、これからも一緒にいたいと彼女に暗に言っているのと同じことなのではないだろうか?
もしそんなこちらの意図を悟られればまた嫌われてしまうかもしれない。
二人で交わした約束を平気で破るようなこと、きっと許してくれないだろう。
「どうすれば勝ちなんでしたっけ」
私が悶々としていると横からササコが言った。
何のことを言っているのか分からなくて聞き返す。
「鬼ごっこです。捕まえるって、具体的にはどうすればいいんですか?」
「ああ、そういうことね。……相手の体のどこかに触れば、それで……捕まえたことになるのよ」
「そうですか……」
言うなら今しかない。
まだ勝負が着いていない今しか……。
「あの約束、やっぱりナシに……!」
「ゴイシシジミさん、逃げてもいいですよ」
「……え?」
「この状態から逃げ切れる自信があるのなら、どうぞ逃げてください」
ササコが目を細めて挑発的に言った。
手を伸ばせば届く距離。
こんな距離感では逃げようにも逃げられない。
もしかして彼女は最初からこうなるのを狙っていたのだろうか。
私が鬼を探し回って疲労状態なのも、その足でのこのこと彼女の前に現れたのも、全部ササコの思惑通りだったとしたら……。
「私の負けね……」
「いいんですか?」
「っ……よくない……」
あっさりと負けを認めてしまいそうになった。
あの約束を何とか取り消してもらうまでは、この遊びを終わらせる訳にはいかない。
ササコが納得してくれるような言い訳がないかと考えていると、不意に音が鳴った。
それは、布が擦れるような音。
音のした方へ目を落とすと……。
「あっ……」
ササコが私のスカートの裾を摘んでいた。
「これで私の勝ちですね」
「……そうね」
こうなってしまってはもう、負けを認めるしかない……。
私たちの仲はこれまで。
……一度は覚悟した事なんだ。
だったら当初の予定通り、笑顔でお別れをしよう。
しないと………………。
「ま、負けちゃったかぁ……」
口角を少し上げて、目を細める。
こんな感じでどうだろう。上手く笑えているかな?
ササコといた数日間の思い出が甦る。
そういえば、ササコが笑っている顔は一度も見たことがなかったな。
その事実が、二人で共に過ごした時間が彼女にとっては苦でしかなかったということを証明していて……。
悲しい気持ちになった。
本当ならここは罪悪感を覚えるべきところなのかもしれない。
でも、悲しい。
笑わなきゃいけないのに、できない。
鼻がつんとしてきた……。
このままではまた泣いてしまいそうだったから、さっきと同様に顔を伏せて凌ぐことにした。
目を瞑りじっと待つ。
こうしていればきっといつかは悲しくなくなる。
それまでずっと俯いたまま生活するのはどうだろう。
辛い現実を見なくて済む。
これはもしかすると、とてもいいアイデアなのでは……?
知らないうちにササコは離れていって、引き止めることもできず、私は独りになったことにすら気づかない。
それはとっても、……幸せなことのはず。
……でも、それでもいつかは顔を上げて、この目で全部見なければならない時が来るだろう。
だっていつまでも俯いてたら首が痛くなっちゃうから。
……………………。
(その頃には雨が止んでるといいな。ああ……でも、一人で見上げる青空は、きっとどんな現実よりも辛いんだろうな……。私にちゃんと受け入れられるかな……?)
────馬鹿みたい。
出来もしないことをつらつらと並べて、勝手に納得して……本当に馬鹿みたいだ。
「────これで、********……」
「……?」
不意に声が聞こえた。
隣でササコが何かを呟いたのだ。
それは誰に向けたというわけではない、独り言のようだった。
どうせこれでようやく自由になれるとか、そんなところだろう。
何もわざわざ口に出すことないのに。
「あーあ、これで*********……」
ササコがもう一度、今度はさっきよりも大きめな声で同じ言葉を繰り返す。
まるで私に聞かせようとしているみたいに、わざとらしく呟く。
もうやめて。何も聞きたくない。
それはこれまでの仕返しのつもり?
謝ったら、赦してくれるの?
「ゴイシシジミさん」
「そんなに私のことが嫌いならもう一緒にいなくていいのよ。さっき、約束したでしょ……? 私はこのままここにいるから……」
抗えない別れを告げられるのが怖かった。
だから私は自分からササコを遠ざけるように言ったんだ。
それなのに……。
「じゃあ私もここにいます」
それなのに……
「……どうして」
どうしてあなたは……
「……だって、ほら……雨降ってますし……それに……」
「……」
「私はあなたに……まだ勝ってません。……負け越してるんです」
「何を言ってるの。……あなたは私に…勝ったでしょ」
「だから! ……これで、一勝六敗……なんです……」
「……どういうこと……?」
「私はあなたに、ゴイシシジミさんに5回も負け越してるんです。だからこのままでは終われません。……再戦を申し込みます」
ササコが言っていることは負けず嫌いな子供みたいだ。
でも彼女がやろうとしていることは、きっとその逆で。
気を使って言ってくれているんだと思った。
自意識過剰かもしれない。
でも、私は彼女の優しさを知っている。
それはいつか彼女自身を滅ぼしかねない、危うさを持った優しさだ。
私は本当にまだササコと一緒にいていいのだろうか。
「でも、あなたは私のこと嫌いでしょ?」
私は唐突で直前の会話の流れからは想像もできないような返しをした。
息を呑む音。言葉を飲み込む音。
なんとも形容しがたい無音だけを残して、ササコが口を閉ざしてしまう。
相手の本心を暴き出そうとするような言動を後悔した。
せっかく気を使ってくれているのに、私は彼女の優しさを無下にしてしまった。
これで彼女はどう思っただろう。
めんどくさいやつだと、愛想を尽かしてしまっただろうか。
「ごめんなさい……」
「…………私は、私のしたいようにします……。だから……あなたはあなたのしたいようにすればいいじゃないですか。ちなみに私のしたいことというのは、鬼ごっこの再戦です」
ササコがあくまで鬼ごっこの再戦がしたいと突き通す。
そんなことしたいはずがないのに、負けず嫌いな自分を決して崩さない。
それはどうして?
それは、……きっと私のため。
こちらの我儘を肯定するためだけに、自らも我儘なフリをしているんだ。
大切な我が身を危険に晒してまで……。
どうしてあなたはそんなにも気にしてくれるの。
私には優しくされる資格なんてないのに。
おさまりかけていた涙がまた滲んでくる。
またササコの心を殺しつつある罪悪感と、この優しさにいつまでも浸かっていたいという我儘とが頭の中で交錯し、色んな感情を巻き込んで混濁していく。
もうどれが自分の本心なのか判別がつかなくて、泣きたくなくて……。
漏れそうになる嗚咽がバレてしまわないよう、私は声を殺した。
「再戦、もちろん受けて立ちますよね……?」
なおも言い続ける。
返事を促すようにやさしいトーンで。
……本当にいいの?
そんなことされたら本当に、私はあなたから離れられなくなっちゃうんだよ?
それでも……いいの……?
………………。
もし、私の我儘が許されるのなら……
「鬼ごっこはもうしないわ……」
「あなたが嫌でも、私が勝手に逃げればやらざるを得ませんよね……。なんだったら今からやりますか?」
ああ、あなたは本当に……
「ぁ……」
私はササコを抱きしめた。
彼女の所在をちゃんと確認せずに伸ばした両手は、確かな体温を見失わなかった。
夢なんかじゃない。
彼女は今もずっと隣にいてくれた。
暖かくて、涙が溢れてくる。
「……気を……使わせ…ちゃった、ね」
「なんですかいきなり……私は別に……」
「ありがとう……ごめん…ね…?」
「だから私は……もう、暑いですよ……離れてください」
「逃げ…ない……?」
「逃げませんから……だから、離してください……」
困ったような声でやさしく拒まれた。
本当はあなたのお願いならなんでも聞いてあげたい。
だけどごめんね、ササコ。
私は我儘だから。
あなたにこんな顔を見せたくないんだ。
だからもう少しだけ待って。
止むまで─────。
────────────────────
十数分後
「もう逃げないでね……」
「それは、……約束はできませんけど」
「次また黙って逃げたりしたら……こ、怖いわよ……?」
「……どうするつもりですか?」
「今度逃げたら、……一生私の腕の中で生活してもらいます」
「それは…怖いですね……」
第5話序文の「鬼ごっこで負けた日」とは、ササコの5回の負け越しが確定して揺るがなくなったこの日のことです。
もうこういうつかず離れず(ついたり離れたり?)がお似合いの二人ですね
互いに全てを明かさなくていい、でもそこまで遠くないような関係がいい………
ありがとうございますー
私は見ててもどかしさを感じるくらいの距離感が好きでして……
でもこの二人の関係はちょっと拗らせすぎかなとも思っていたので、気に入って貰えたのならとても嬉しいです
私はとうに聞き慣れた雨音で目を覚ます。
無数の水の粒たちが木の枝葉を、地面を叩く音。
空を見上げると、そこにはいつも通りの灰色があった。
これで何日目だろうか……。
あの酷く落ち込んだ色をした雨雲は、連日降らせ続けて少しづつ地面を溶かしている。
ひょっとすると永遠にこの雨が止むことはないのかもしれない。
この島の土を全て溶かしきって、何もかもが水底に沈んでも、ずっと。
私は別にそれでも構わないと思っている。
いずれ来る最後の日まで毎日「おはよう」と「おやすみ」が言えたらそれでいい。
これはちょっと我儘が過ぎるかな?
「おふぁよぉ……!」
私は我慢ができなくて、あくびや伸びをするよりも早く「おはよう」を言おうとした。
それが失敗の原因。
気持ちが急いてしまったが故の失態。
朝の日課を怠ったせいで、私はなんとも間抜けな声を出してしまったのだ。
なんだか恥ずかしいくてちょっと後悔する。
世の中にはこんな幸せな後悔があるものなのかと思い、目を細めた。
でもやっぱり恥ずかしい……。
時間の経過と共に増幅されてゆく羞恥心が、とうとう眠気に勝ってしまう。
私は両手で顔を覆うといういかにもなポーズを取ってみた。
なんだこれ、余計に恥ずかしい……。
さらなる羞恥に顔が熱くなった。
笑われるだろうか。
それとも、引かれるだろうか。
今私は、いったいどんな目で見られているのだろう。
見守るような暖かな目?
それか、どう反応すればいいのかという困惑の眼差しかな?
冷めた目でもいいかもしれない。
この後のササコの返しがどんなものであっても対応できるようにと私は身構える。
しかし、先程からの一連の行動を通して見ていた少女に笑われる、なんてことはなかった。
指の隙間から外界を覗く。
すると、ずっとそこにいるであろうと思っていたササコの姿が無かった。
両手を下ろして、ほっと息をつくと、幸い顔の熱は直ぐに冷めた。
冷静になった頭で考える。
つまり私は、数分にわたってずっとひとり芝居をしていたということか。
気づいてしまったら一気に気が抜けた。
そこにやり場のない感情だけが残っている。
ササコに見られなかったことを喜ぶべきか、無人の舞台でひとり踊った間抜けな自分を嗤うべきかを悩む。
仮にどちらを選んだとしても、私の顔には笑みが浮かべられているだろう。
多分その意味合いはだいぶ違うと思うけど。
私は今、とても満ち足りている。
「ふわぁ……くぅ」
改めてあくびと伸びを済ませる。
3日前までの私だったら、きっとこんな心境で朝を過ごせはしなかっただろう。
どんなにひどい夢を見たって、もう全然気にならない。
孤独に怯えることも無くなった。
私が精神的に変われたのは、全部ササコのおかげだ。
彼女が帰ってきたらお礼を言おう。
「ありがとう」って。
これだけを聞いたササコは、私がなんのことを言っているのかわからないだろう。
きっと、不思議そうな顔をすると思う。
その直後には当然の質問も飛んでくるはず。
でも私はそれには答えない。
少しでも長くササコの困った顔を見ていたいから。
意地悪だとは思う。
我儘だとも思うけど、それはあの日ササコが許してくれた。
そしてなにより、ササコが悩んでいる間は、きっといつもより私のことをたくさん見てくれるはずだから。
私はこれ以上の何を望もうというのか。
……とりあえず、今回は「おはよう」を言い損ねた分くらいで妥協することにしよう。
計画と言っていいのか分からないくらいに残念な考えと期待を胸に、私はササコの帰り待つことにした。
「……おはよう」
なんとなく寂しくて、空に向かって小声で呟いてみると、今度はちゃんと発音出来た。
どれだけ完璧なものであっても、一人で口にするあいさつに意味なんて無いけど。
「まだかなぁ……」
──────────────────────
あれからどれだけの時間が経ったのだろう。
数分か、数十分か。
もしかすると一時間くらいは待ったかもしれない。
空を見上げて太陽の位置を確認しようにもあいにくの雨空。
これではどのくらい時間が経過したのかを確認出来ない。
「……遅い」
しばらくの間、ササコの帰りを大人しく待っていたが、一向に帰ってこない。
昨日、一昨日と、目が覚めて一番にササコの姿を見ることが出来ていただけに、今日になって一度も彼女に会えていないという事実に不安になってくる。
今すぐササコを探しに行くべきだろうか……?
もしかしたら、どこかで怪我をして動けなくなっているかもしれない。
そうでなくても、セルリアンに追いかけられたりして帰るに帰れなくなっている可能性もある。
最悪の場合は……
「──っ!」
気がつけば走り出していた。
戻ってきたササコとすれ違いになるかもしれない。
彼女がセルリアンと会敵していたとして、私が行ったところで何かが出来るというわけじゃないことも分かっている。
でも、いつまでもあそこでああして待っていることは出来なかった。
もし今からさらに一時間待っても帰ってこなかったら……?
その時のことを考えると、怖くてたまらなかった。
無駄な心配ならそれでいい。
とにかく今は一秒でも早くササコを見つけないといけない!
私は一層足に力を込めた。
──────────────────────
「こんなところにい、たの……ね」
ようやくササコを見つけられたという安心感は、眼前の光景を見た瞬間、その衝撃にすぐにかき消された。
ササコは無事で、今こうして私の目の前に立っている。
だけど私の最悪な想像は少しだけ当たっていて……。
頭の中がたちまちに真っ白になり、すぐにまた別の色に染め上げられる。
次の瞬間、私は一つの感情に全身を支配されていた。
「なに…してるの……それ、なに……?」
声が掠れて上手く形にならない。
私はこれ以上ないほどまでに恐怖していた。
ササコが、セルリアンと対峙している。
こちらに背を向け、恐ろしい存在と私とを隔てているのだ。
まさか、と思った。
ササコがあれと戦うつもりなのではないだろうかという馬鹿げた考えが頭に浮かぶ。
そんなのは本当に馬鹿げた考えだ。
幸いを最悪に変えてしまいかねない選択を、ササコがするはずがない。
だって、ササコは臆病で…………
"ここで足を失うくらいなら、私は全生命をかけてでも抵抗します"
ふと、いつかササコが言った勇ましい言葉と、彼女と初めて出会った時の全身傷だらけの姿を思い出した。
私の知るササコは臆病な所もあったけど、決して弱くはなかった。
少なくとも私よりずっと勇敢なんだと思う。
彼女はその身を滅ぼすような選択を平気でするから。
だから私は、より臆病者にならざるを得ないのだ。
大切なものが傷つくのが怖い。
二度と会えなくなってしまうのが怖い。
ひとり残されるのが怖い。
罪を背負うのが怖い。
痛いのも怖い。
これで最後になってしまうかもしれないというのに、私の頭の中は自分のことばかりだった。
私が恐れる未来。
そこにはササコと死別した自分がいて、当たり前のように生きている。
何も出来なかったことを後悔して、絶望しつつも、何もしない。
痛みを知ってしまった私は、もう二度と自分の胸を貫いたりはできないだろう。
ずっと一緒にいたいと思った。
それなのに、死んでまで寄り添えはしないというのか。
私は本当に、どこまでも自分勝手だ。
"あなたはあなたのしたいようにすればいいじゃないですか"
「……」
自分の命を危険にさらしてまでセルリアンに挑む。
それがササコのしたいことなのだろうか。
……そんなわけない。
もし、仮にそうだとしても、そんな危ないことを黙って見過ごすわけにはいかない。
私はササコを危険な目には遭わせたくない。
今すぐ彼女の背に駆け寄って、あの手を取って逃げるんだ。
そうすればきっと二人とも助かる。
これがササコの願いに反した行いだったとしても、無理やり連れていく。
それが私のしたいことだから。
「……!」
身長がササコの倍近くあるセルリアンを見上げると、全身におぞましいものが駆け抜けた。
嫉妬の目、憎悪の目、殺意の目。
そのいずれにも当てはまる、恐ろしい眼差し。
そいつが私を見ていた。
あまりの恐怖に体がすくんでしまう。
「こ…こわく…なんか……な…ぃ」
もはや声は意味をなさず、強がることも出来なかった。
ササコの方を見るが、彼女はその場に立ち尽くして動こうとしない。
何か動けない理由があるのだろうか?
あの時みたいに、怖くて動けなくなったのかもしれない。
やっぱり、私がササコの元まで歩いていって、直接連れ出すしかなさそうだ。
迷っている時間はない。
不規則になった呼吸を整えるまもなく、私は一歩を踏み出した。
セルリアンの目を見ないように、ササコだけを視界にとらえて前に進む。
前へ、前へ、一歩、また一歩と慎重に歩を進める。
一定の間隔で聞こえる自分の足音と、少しずつズレていく呼吸音。
その二つだけが、私がいる世界の音の全てだった。
雨の音なんて聞こえない。
心臓の音も、意外な程に聞こえなかった。
もしかすると、私の心臓はあまりの怖さに耐えきれずに活動を止めてしまったのかもしれない。
それは困る。
生きるのをあきらめるにはまだ早い。
ここで生きるのをあきらめるということは、これからのササコとの時間を、場合によってはササコの命までもをあきらめてしまうということだ。
そんなこと、絶対にしてはだめ。
せめてササコを安全なところまで連れて行くまでは。
彼女の手を握って、一人じゃないのだと安心させるまでは。
あの指先に触れて、私の存在に気づいてもらうまでは、諦めるわけにはいかない。
徐々に下げられるハードル。
だんだんと弱気になってしまう。
だって、こんなにも怖いから。
視界が、息が酷く乱れるから。
寒くもないのに身体が震えて仕方がないから……。
それでも、どんなに怖くたって足を止めることは許されない。
ここで止まれば二度と踏み出せないと、本能的に分かってしまった。
だから前へ、前へと、立ち止まることなく進むのだ。
ふと、不安になってセルリアンに視線を移すと、そいつは最初に見た位置、姿のままで微動だにしていない。
相も変わらず、こちらに憎々しげな視線を送ってくる。
だけど逆に言えばそれ以上のことはしてこない。
私がこんなに気が気でないというのに、セルリアンの方は随分と悠長な様子だった。
このまま私が近づくのを待ち伏せるつもりか。
もし本当にそうだとしたら好都合。
ササコに危害が及ぶ前にここから連れ出せる確率が上がる。
ササコ、どこも怪我してないよね……?
無事に彼女の顔を見るまでは安心できない。
私はいざという時に失敗しないように、一度心を落ち着けようとセルリアンからササコへと視線を戻そうとした。
その時だった。
「──?!」
ヒュンッという短い音が聞こえた。
間違いなく足音ではないそれは、呼吸の音とも違った。
それでいて風が吹く音とも微妙に違う。
例えるならそれは空気を切り裂く音だ。
突然の怪音に足が止まりそうになりながらも、無理やり一歩前へ押し出す。
その際、ササコを捉えることに失敗した視線は、自然とセルリアンの方へと戻って行った。
……待って、何、それ?
私の視界には、さっきの音の正体であろう物体が映っていた。
それは、見方によってはナイフのようにも見えた。
ナイフ……? ナイフってなんだっけ。
ナイフは武器。殺害のための道具だ。
いつだったか、私がそう言った。
違う、言ったのは私じゃない。
記憶が、意識が? 混乱している。
私は酷く動揺しているようだった。
それはどうして?
ナイフなんてみんな持ってる。
ササコだって持っていた。
だから、セルリアンが持っていても別におかしくなんかない。
ナイフの柄に当たる部分が長い蔦みたいになってたって、それを自在に操れたって、今この瞬間にそれを振り上げていたって、何もおかしくなんかない。
ねえ、それをどうするつもりなの?
声なんかもう出ない。
だから目で訴える。
でも、とうにセルリアンは私を見てはいなくて。
その視線の先には────
「──ッ!」
息が止まってしまえばいいと思った。
間に合わないのなら、大切なものも守れないのなら、そのまま肺を潰して死んでしまえ。
それが嫌なら……
──もう呼吸なんてする必要は無い。
ばっしゃん!!
大きな水音と共に視界が揺らいだ。
それと同時に、足のつま先にビリビリとした痛みが走る。
右の足か、左の足かも分からない。どっちだっていい。
全速力なんかじゃ足りないから。
もっと速く、速く、
息を吸うのを忘れてしまうくらいに速く!
ナイフなんかよりも鋭く風を切って走るんだ。
かかとを地面に叩きつける度、ササコとの距離がどんどん縮まっていく。
そして、次の瞬間にはもう、ササコはすぐ目の前だ。
あと少しで届く……!
ガッ
「──ッ!?」
その時、不意に視界が傾いた。
全身が不思議な浮遊感に包まれるが、そんなことは意識の外だ。
次の一歩を踏み出すと同時に手を伸ばせば届く距離にササコはいる。
私は最後の一歩を地面につけようとした。
でも出来なかった。
空中に放り出された両足は、着地予定の地点から大きく後ろにズレてしまっている。
私は、また躓いてしまったのだ。
このまま行けば、間違いなく転けるだろう……。
──そんなのだめ!
ここで転けるわけにはいかない。
私は咄嗟に後悔しそうになるのを押しとどめ、右だか左だかの足を思いっきり前へと蹴り上げた。
一瞬後に地面に触れたのは、ぎりぎり靴の底。
ほとんどつま先だった。
それでもなんとか着地には成功した。
ここまでくれば、あとは手を伸ばすだけだ。
取るべき手を確認するために、私はつんのめったままの低い目線から再び前方を見た。
しかし、そこで見えたものは、ササコではなく、既にすぐ目と鼻の先にまで迫ったナイフだった。
ササコがいたのは左斜め前方。
躓いた拍子に進行方向が僅かにズレてしまったのか。
ナイフの軌道は変わらず、ササコへ向かっている。
今更手を引いたってもう間に合わない。
「ク───ッ!」
私は右足を思い切り地面に叩きつけた。
靴底の内側の角を地面に擦りながらブレーキをかけつつ、やや左へと軌道を修正する。
そして、あと一歩
「あああぁッ!!」
私は思い切り腕を突き出した。
──────────────────────
今回長くなりそうなので一旦区切ることにしました
後半部分はまだ書けてないので完成し次第投稿します
(勢いのある文章を書くの難しい……)
私がササコを突き飛ばした一瞬後、目の前をセルリアンのナイフが横切った。
間一髪だった。
すぐそこまで迫っていた風切り音に気がついて咄嗟に身を引き、しりもちをつくことでなんとか致命傷は避けられた。
この攻撃で受けた被害といえば、右手の袖が犠牲になったくらいだ。
ササコは……大丈夫、ちゃんと生きてる。
突き飛ばした時に強く頭を打ったりしてないといいけど。
今はそんな心配をしている余裕はない。
早く二人でここから逃げなければならない。
左手を地面につき、立ち上がる。
その時、妙に右手が重い感じがした。
私は気にせずにササコに駆け寄ろうとしたが、動こうとすればするほど重力が強くなってしまう。
そこには、確かに真下に引っ張られるような強力な重力があった。
そして、それはいつしか体全体に広がっていって。
私はとうとう膝を折ってしまった。
こんなことをしている場合じゃないのに……!
突然の重力の発生源と思われる右手の辺りに目をやる。
そこには、別段変わったものは無かった。
あるのはさっきセルリアンに切り裂かれた服の袖だけだ。
首の皮一枚でなんとか繋がっている袖口だけ。
真っ赤に染まる袖口。それだけしかない。
あれ?
「なん…で……?」
本当ならそこにあるはずのものが、無いことに気づいてしまった。
なんで? いつから?
私の右手がどこにも見当たらない。
「あ……あ……」
まるでいつか見た悪夢のような出来事に、非現実感を覚える。
これが夢なら、このまま覚めるだけ。
夢じゃなかったら……?
ササコ……。ササコをたすけないといけない。
今すぐ立ち上がって、私がササコの手を引いて逃げるんだ。
これはきっと夢なんかじゃないから。
だから、早く立たないと。
もう一度左手を地面について、自立を試みる。
「ふっ……、ん、ぐぅぅ……!!」
でも、どれだけ頑張っても、力なんか入らない。
早く、まだ動けるうちに足を立てないと。
じゃないと、すぐに間に合わなくなる。
私は気づいてしまったから。
これは、酷い怪我。
下手したら今度こそ死んじゃうかもしれない。
それくらいの大怪我だ。
怪我にはその度合いに見合った、当然の痛みが伴うはず。
痛いのがどれだけ痛いのか、私は知っている。
これからだんだんと痛くなっていって、きっとすぐに動けなくなるだろう。
だからその前に……。
私がもう一度左手を地面に這わせた時、目に映ったものを見て、一気に血の気が引いた。
ああ……だめだ。
そこら一体に拡がった、赤色、紅色。
私の内側をひたすらに彩る、本物の赤。
その色はとめどなく拡がっていた。
一度引いてしまった血の気は、二度と戻ってはこないのだろう。
一気に冷めてしまった断面の熱が、次第に痛みを訴え始める。
私はこれ以上熱が逃げてしまわないように、左手で傷口の上あたりを押さえつけた。
でも、上手く力が入らない。
こうしているうちにも、痛みは強くなっていく。
泣きたいくらいに、強くなっていく。
呼吸も、段々と荒くなってくる。
そろそろ……このくらいで、止まったりしないかな……?
私のそんな諦め半分の期待は、すぐに裏切られた。
まだ、もっと痛くなる。
一回脈動する度に、断面に激痛が走り、無いはずの右手が疼いた。
身体中が痛い。
両目から冷たいものが零れ落ちた。
泣いたって、許してなんかくれない。
私はもうどうしようもなくなって、地面にうずくまってしまった。
これは、きっと痛みに耐える体勢。
少しでも早く体勢を立て直して、ササコを連れて逃げる。
そのための体勢なんだ。
そうやって、無力な自分に言い訳をする。
本当は怖かっただけなのに……。
他の誰かが傷つくのを見るのが怖かった。
他でもないササコが、目の前で二目と見れない姿になるのが怖かった。
大切な友達の最期を看取るのが嫌だった。
だから目を背けた。
私は本当に、私は……。
ふいに、声が聞こえた。
それは喉が捻れて裏返ったような、酷く耳障りな音だった。
呻くような声は、歪すぎて何を言っているのか全然分からない。
これが私のものなんだと気づいた時、それとは別の声が頭に響いてきた。
『立って 』
声は言った。一言、私に立てと。
優しい声で、無理難題を押し付けてくる。
こんなにたくさん血を流したら、もう立ち上がるどころじゃないなんてことは、私にだって分かる。
誰だか知らないけど、いい加減な事を言わないでほしい。
私は痛みを理由に、攻撃的な感情をぶつける。
声はそんなのお構い無しに続けた。
『顔を上げて、ちゃんと見て』
見るって、何?
私に何を見せようっていうの?
私はとうとう一人で会話を始めてしまった。
これも現実逃避の手段のひとつだったのかもしれない。
『ササコちゃん。……今も一人で、戦ってる』
ササコが……?
戦ってるって、無事なの……?
『今はね。でも、このままじゃ危ないの』
自分に嘘を吐いてまで逃避させるつもりなら、どうしてここで現実を見せようとするのかが分からない。
でも、だからといって、この声が本当のことを言っているということにもならない。なるはずがない。
だからこれは、きっと私の願望なんだと思う。
僅かに残された可能性に縋り、希望を見出そうとしている。
私はこんな状況に陥ってもまだ、諦めきれていないようだった。
『大丈夫だから、わたしを信じて』
信じるよ。あなたを信じる。
裏切られた時のことなんか絶対に考えたくないから。
私は歯を食いしばり、軋む首を持ち上げた。
目を開き焦点を合わせる。
「─────っ!」
揺らぐ視界の中で、一番に見えたものは、たった一人で強大な敵に立ち向かうフレンズの姿だった。
ササコはまだ生きてる……!
未だ五体満足な彼女の姿を認めた瞬間、私の脈は加速した。
より効率的に、全身に痛覚が伝達されていくのを感じる。
甚大な痛みと焦燥に駆られて、今すぐにでも擦り殺されてしまいそう。
そんな時、私の頭にまた声が響いた。
彼女は落ち着いた口調で問いかける。
『あの子を助けたいんでしょ?』
答えるまでもなかった。
ササコを無事にここから逃がせるのなら、この身がどうなったって構わない。
だけど、そのために自分に何が出来るのだろうか?
一人で立つことすらままならない、今の私に……。
『わたしはあなたを助けたい。だからそのために、あの子を助ける手伝いをするのよ』
次に響いたのは突拍子のない言葉。
声が何を言っているのか、よくわからなかった。
彼女が何者なのかも分からない。
それを私の一部分とするならば、きっと誰でもないのだろう。
ぼんやりと、私の中にいる何か。
それが『自分を犠牲にするようなことは絶対に許さないからね』と一言付け加えた時、私は何となくその正体がわかった気がした。
それは、本能だった。
極限まで追い詰められた主を守るために、外側まで這い出てきたのだ。
彼女が私の本能の一端を担うような存在であるのなら、自分の命を蔑ろにするようなことを許すはずがない。
でもそれなら、どうしてササコを助ける手伝いをしてくれるのだろう。
私みたいな臆病者の本能なんか、きっと自分本位に決まってるのに。
『あの子と一緒にいる時のあなたが好きだから』
本能(?)はそう言った。
どうやら思ったことは口に出さなくても(そもそも今は言葉を話せる余裕はない)伝わるらしい。
にもかかわらず、否定を一切しないところを見ると、彼女は本当に私の本能なのだろう。
『それでね、わたしにひとつ作戦があるの。あなたにはちょっと頑張ってもらうことになるけど、できる?』
本能が言う。
作戦とは、ササコを助けるための作戦だろうか。
自分の中の本能に『できるか?』とか訊かれるなんて、だいぶおかしい気がするけど、私はササコのためならなんだってするつもりだ。
『そっか…じゃあ話すわね。あなた、"わたしのナイフ"はまだ持ってるよね?』
……?
そんなものは持ってない。
自分の持っていたナイフは、とうの昔に何処かに落っことしてしまった。
『無いの…?! ええと、じゃあ……あそこに刺さってる看板でいいか。あれを引っこ抜いて、セルリアンの後ろにこっそり回るの』
看板……さっき転びかけた時に、そんな感じのものがちらっと見えた気がする。
あれのことだろうか。
『そう、それよ。それで、後ろに回ったら看板を叩きつけて、やつの頭をかち割るっ!』
あまりにシンプルな作戦。
看板で頭を……?
そんなこと、本当にできるの?
『ねえ……あいつの頭、けっこう脆そうじゃない? ヒビまで入っちゃって、まるでガラスみたいね』
確かに言われた通り、セルリアンの頭(?)には何本にも枝分かれした大きなヒビが入っている。
そんなこと、言われるまで全然気が付かなかった。
『どう? できそう?』
……できない。
さっきから何度も立ち上がろうとしてるけど、体が全然言うことを聞かない。
『まだ痛いの? それも、立てないくらいに』
痛、い……?
……ああ、そうだ、痛いんだ。身体中が痛くてたまらない。
だからずっと、私はこんなにも耳障りな声で唸っていたのか。
いつの間にか忘れてしまっていたみたい。
そして、忘れたままならなお良かった。
だけどもう遅い……。
『今から私の言う通りにして。そうすれば、少しは楽になるはずよ』
もう、思考をする余裕も無い。
呻き声で返事をする。
『よし! じゃあまず、声を抑えて。できる?』
首を横に振る。
『いいえ、やるのよ。それくらいできてもらわないと、……ササコちゃんを助けたいんでしょ?』
「グゥ……ぅ……」
『そう、その調子。……大丈夫? まだできるかしら』
今度は、縦に……
『いい子ね。次は、ゆっくり息を吸って、吐く。深く深呼吸をするの。ほら、吸って……吐く』
「ゔぅ……ッ……え゙ぇ……」
『辛いわよね……。けど頑張って、ほらもう一度、吸って……』
「ふッ……うぉえぇ…! ゲホッ!」
むせかえるような血の匂いに、吐きそうになりながらも呼吸を続ける。
促されるまま、一回、もう一回と繰り返す。
そうしている内に、最初は呻き混じりだった呼吸は段々と安定していった。
声だったものは熱になって蒸発していき……。
『どう? もう痛くないんじゃない?』
少し良くなったけど……でも、まだ痛い。
『ちょっと血を流しすぎたのかもね。今はもう止まっているけど……動けそう?』
本当に、本当に少しだけ全身の痛みが引いていた。
その差は微々たるものだったけど、今ではかろうじて思考ができる程度にまで落ち着いている。
これなら何とかなるかもしれない。
左の膝を立てる。続いて、右足も。
これだけではまだ足りない。
私は左の手のひらを、ちょうど足と足の真ん中辺りで地に付ける。
そこまでしたところで、今の自分の体勢がどこかおかしいことに気がついた。
これでは足に上手く力が入らない。
いつもはどのようにして立っていたのだろう。
意識すればするほど、正しい体勢がわからなくなる。
少し考えて、私は左足だけを崩すことにした。
そして、左手は足の間ではなく、左手やや前方に置く。
私は各部位が定位置に着いたことを確認し、足と腕に一斉に力を入れた!
視界が少し高くなり、その直後に急降下。
私は右足を前に出して、前に倒れ込みそうになるのを何とか踏みとどまった。
立てた……!
両の足がぷるぷると震えるけれど、私はなんとか自立することに成功した。
『生まれたてのフレンズって感じね……』
それまで黙って私の一挙一動を見守っていた本能が、突然口を挟んできた。
何やらよく分からない喩えをされたが、今はそんなことはどうでもいい。
私は看板が突き刺さっている方を見た。
ほんの数メートルが、とても遠く感じられた。
「くッ……!」
立っているだけで体のあちこちが軋む。痛い。
こんなにも足が重たいのに、体幹は安定せずに視界がふらつく。すごく気持ちが悪い。
戦う前から満身創痍だ。
それでも私はやらなくてはいけない。
人生における数え切れないほどの内の一歩を、今ここで成し遂げるのだ。
私は大岩のように重たい足を、その意思ひとつで持ち上げた。
下へ、強く引っ張られる。
それを一歩分前へ運び、落とす。すると、ガクンと。
耳には聞こえないけど、そんな音がした。
それと同時に全身から力が一気に抜けていく。
一度視界が大きくぶれて、そのまま地面に激突した。
『ちょっと、大丈夫!? どうしたの?!』
──お腹がすいた。
『お腹がって……こんな時に何言ってるの……?』
歩けない。立っていられない。
本当に、辛いの。
『……』
冗談とかじゃなくて、もう、本当に……
『そう……そうよね……』
何かを悟った気がした。
無意識に、心の奥深くに刻まれてしまった定型文を指でなぞっていた。
これでずっと、一緒に……。
「おねが…い、……ササコ……わたし、を──」
『待ってッ!!』
「──っ!」
本能が叫び、我に返った。
私は今、一体何を……。
『お腹がすいたんだよね?』
本能が私の思考を遮るように訊いてきた。
そんなこと、今更答えなきゃいけないの?
空腹のせいかまた攻撃的になってしまう。
『ササコちゃんを助けたいんだよね?』
更に問い続ける。
次から次へと何?
いちいち声に出さなきゃ分からないの? あなたは私の一部なのに。
これらは全部、自分に向けた言葉、自虐のつもりだった。
それなのに罪悪感を感じてしまうのはどうしてだろう。
『だったら──』
本能はそこで一度言葉を区切り、少しの沈黙の後、短く言った。
『それを食べて』
──え……?
「食べる、って……」
目の前に差し出されたそれは、とても見慣れたもので。
私は無意識のうちにそれを握りしめていた。
指を絡めて、手を繋いでいた。
自らの欠損した断片と。
「──ッ!」
そんな、どうして…… なに、これ……!?
私は左手を振り回した。
力いっぱいに、かつての自分自身を拒絶する。
だけど離れてくれない。
手に指に力が入ってしまって離れないのだ。
それを理解していながら、私にはどうすることも出来なかった。
固く結ばれた手は、必要以上にグロテスクに見えてしまったから。
怖い。気持ち悪い。
冷たい手の感触が、消えてくれない。
『……ごめんね』
諦めたような、悲しいような声だった。
その声を聴いた瞬間から、急速に肩の力が抜けて行った。
そして、繋がれていた手が、今再び解かれる。
冷たいものが指の間をするりと抜けると、そのまま地面に落ちて、ぴしゃんと音を立てた。
『そんなこと、……できるわけ、ないわよね……』
そう言ったきり本能は口を閉ざしてしまったけれど、まだ彼女の息づかいだけは聴こえているような気がした。
苦しそうなのに安らかな、聞いていると泣きたくなるような弱々しい息吹を、私は心で感じていた。
「…………」
なんだか彼女の"お願い"を聞いてあげなきゃいけないような気がして。
私はすっかり赤くなってしまったそれを、もう一度、今度は意識的に拾い上げていた。
やっとの思いで手放せたのにな……。
震える手を口元まで持っていくと、胸が締め付けられるような感じがした。
これを食べれば、ひとまず空腹はおさまるだろう。
でも、もしそれをしたとして、私はササコとこれまで通りに過ごすことが出来るのだろうか。
不安だった。
なにか大切なものを失ってしまうような気がして、食べるのを躊躇ってしまう。
私は、たった今も無謀な戦いに身を投じているフレンズを見上げた。
「……」
──ここで大切なあなたを失うくらいなら、私は……。
まだ迷いは消えない。
だけど独りになるのはやっぱり怖いから。
私は目を瞑り、息を飲み込んだ。
指先達が唇に触れる。
今からこれを、噛み砕くんだ……。
固い口を何とかこじ開けて、何れかの一本を押し込む。
口内に入ってきたそれに恐る恐る舌を這わせると、想像通りの血の味がした。
その味や異質な舌触りに一瞬吐き気を感じたが、何とか我慢する。
吐いてはだめ、食べなくてはいけないのだから。
「ゔぅ……」
私は一旦、指を口から引き抜いた。
悠長になんかしていられない。
だけど、これが自分の一部分だったものであるという認識を、どうにか改めないことには、噛み砕くこともままならない気がした。
それならと、すぐさま解決策を考え始める。
……もし、自分のがダメなら、別の誰かだったら。
例えばこれは、ササコの右手首。
そう思い込んでみるのはどうだろう。
『ねえ……』
私はササコのだったら、きっと拒むことなく受け入れられるから。
口に含んだら最後、歯に少しの抵抗も感じさせないまま、噛みちぎれて、そのまま舌の上で溶けていくだろう。
そうなれば咀嚼する手間も省ける。
『何を考えてるの……?』
しかし、一見合理的に思えなくもないこの案には、ひとつの問題点がある。
これら全てが妄想上のことであると前提したとして、その妄想の中では私がササコを食べているのだ。
脅しなんかじゃなく、本当に。
それは彼女を殺すということに他ならない。
死ねば形を完全に失うから。
誰かを食べようとするなら、その時とどめを刺すのは他でもない私ということになる。
…………
……だけどこれは、あくまで気持ちの問題。
別に、実際にするわけじゃない。
想像上の出来事なんて、夢の中で起きる事と大して変わらない。
だから大丈夫。
私は今からササコの血でこの手を汚すことになるけど、本当のササコは絶対に助けるから。
だからどうか許して欲しい。
私は一方的に捲し立てると、物言わぬ幻影を手にかけようとした。
その時だった。
『イシちゃん……』
「──……え?」
殺意を持った手が止まる。
不意に聞こえたそれは、どこか聞き覚えのある響きだった。
知ってるような、本当は知らないような、掠れていて思い出せない記憶の底。
あれ……? どうして……
だって私は、あなたが……あなた、に……。
大切だったはずなのに。
今だって、まだ大切に思ってるはずなのに、彼女のことが思い出せない。
あなたは……誰?
本当の名前すらも分からない。
私は、思っていたよりもずっとたくさんのことが思い出せなくなっていた。
不意に視界がぼやける。
泣いているのだろうか?
それももう分からない。
鼻がつんとする感じも、まつげに水滴が乗る感覚も、何も無い。
ただ、驚くほど頭が軽くて。
身体も、軽くて。
なんだか意識が朦朧としているなあ、と思った。
『わた……が……違ってたみたい……。やっ……り、あな……には……が重かった』
「な…に……?」
部分的には聴こえていたはずだ。
だけどもう、途切れた断片の声を繋げるだけの気力も残されていない。
『あとは、わたしにまかせてね』
遠のく意識の中で、唯一完成された文字列。
その言葉の意味を理解する間もなく、私は深い眠りに落ちた。
まだ続きます
──side A────────────
おやすみ。
イシちゃんが目を閉じてから、わたしはそう言ったけど、多分彼女には聞こえてなかったと思う。
だって彼女はもう眠ってしまったから。
深いかもしれない。浅いかもしれない。
そんな曖昧な眠りの中で彼女が夢見るのは、きっとあの子のことばかりだ。
いいな……。
ちょっとだけ嫉妬してしまいそうになる。
……と、いけないいけない。
彼女は頑張り屋さんだから、きっと直ぐに起きてきちゃう。
だからその前に、全部終わらせてしまわないと。
わたしは目を覚ますべく、そっとまぶたを持ち上げた。
「……っ……!」
強い刺激を目の奥に感じて、咄嗟に光を遮断する。
すごく眩しかった。
視界に入るもの全ての、色かたちともに判別がつかないほどに。
きっと、生まれて初めて目を開けた時も、わたしはこんな痛みを味わったのだろう。
突き刺すような眩しさに、今にもこの目を潰されてしまいそうだけど、こんな程度のことで立ち止まってはいられない。
わたしは覚悟を決めて両目を開いた。
「んー…………」
再び映し出された煌びやかに渦巻く色々。
瞬きを何度か繰り返していると、乱れていた光彩が次第に安定の色を見せ始める。
「よし!」
言った瞬間、そのあまりの声量にちょっとびっくりした。
でもすぐに気を取り直す。
この自分の声がやたらと大きく聞こえてしまう問題も、きっとすぐに解決する。
少し待てば正常になるだろうけど、そんなことより今はすべきことがある。
今のわたしは、イシちゃんの替わりなのだ。
いや彼女そのものなのだ。
ぐへへ……じゃなくて、えっと……。
わたしは地面に視線を這わせる。
そして。
「──あった」
見つけたそれを拾い上げた。
イシちゃん曰く、これはササコちゃんの右手首……。
さっき、彼女がそう認識しようとし始めた時、その心の中はひどく混沌としていて、見るに堪えないものだった。
まさかわたしの一言で彼女をあんな風に追い詰めちゃうなんて、思ってもみなくて。
でも本当はすぐに気づくべきだったんだ。
自分の体の一部を食べろだなんて、そんな猟奇的な提案を受け入れること、"わたしたちに"出来るはずがないのに。
特にイシちゃんは血が濃くなってるはずだから尚更、自傷的なことは許されなかっただろう。
その結果として、わたしはもう少しで彼女の心を殺してしまうところだった。
「……」
イシちゃんはたくさん傷ついて、ようやくここまで戻って来た。
きっと何度も痛い思いをしてきたはず。
でもこれを食べれば、また少しだけ濃くなってしまう。
また、彼女を苦しませてしまう。
そして、また……鬱々とした日々に帰してしまうかもしれない。
やっと大切なものを見つけられたのに。
「…………」
わたしはなんとか立ち上がれないものかと、地面に左手を着いてみた。でもだめだった。
お腹がすいて力が入らない……というより、そこに何も無い感じがした。
体の密度があまりに低くて、空腹すらも感じないのだ。
ふと、さっきイシちゃんが言いかけていた言葉を思い出す。
"「おねが…い、……ササコ……わたし、を──」"
この先に続く言葉がどのようなものなのか、わたしは知っていた。
だから咄嗟に引き止めた。
だけどやっぱり、今のイシちゃんは一人分にも満たないんだ。
このままじゃ彼女は、きっと……。
死にゆく友達をを前にしたわたしにできることは、もう二つしか残されていなかった。
これからするのは、とても重い決断だ。
わたしは心を決めるために、一度座り直した。
「……?」
体勢を変えた際に、左の太ももの辺りに違和感を感じたが、その正体に気づいて口元が緩んだ。
「なんだ、持ってるじゃない」
もう、迷いは消えていた。
さっきイシちゃんがしたのと同じように、右の人差し指を咥えると、もう血の味はしなかった。
これは愛しい友達の味だ。
「ふふ……」
このままでいれば、あなたはあらゆる苦しみから解放される。
でもわたしは、今から自分の都合であなたをもっと苦しめるよ。
「…………」
『ササコちゃん。……イシちゃんを、お願いね』
わたしは思いっきり、顎に力を入れた。
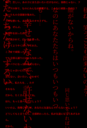
関節部がミシミシと音を立てると、皮が破けて、口いっぱいにイシちゃんの味が拡がる。
そして──
次々と染み出してくるのは、どす黒い感情。
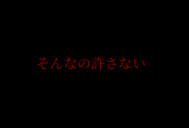
舌をつたって、喉を通って、お腹の底へと落ちていく。
それはまさしく、純度の高い悪意だった。
"わたしたち"が決して抱くことの出来ないくらいの、許容量を遥かに超えた悪意。
少し気を抜くだけで黒い感情に呑まれてしまいそうになるのを、必死に耐える。
こんなものに耳を傾けてはいけない。
自分にそう言い聞かせて、また飲み下す。
何度も何度も、噛んで、飲み込んで。
この単純な作業を繰り返しているうちに、だんだんと身体に震えを感じ始めた。
怖いから震える。これもまた単純な理由だった。
これはわたしの心の中にある怯えなのだろうか。
もしそうじゃないのなら、どうか怖がらないで。
このぐちゃぐちゃしたものは全部、全部わたしが引き受けるから。
わたしのせいで今まであなたをたくさん苦しめたよね。
だからこれはせめてもの償い。
あなたはこれから、ササコちゃんやみんなと幸せに生きるの。
「アンタは黙ってろッ!! 」
やけつくように熱い喉にビリビリとしたものが走る。
絶対に誰にも邪魔なんかさせない。
イシちゃんを繋ぎ止めて、ササコちゃんも助けるんだ!
わたしはもう、何がなんだかわからないくらいに頭に血が上ってしまっていた。
先程まではヤツの悪意に負けじと慎重になっていたが、もう知らない。
わたしは手に持っていたそれを、めちゃくちゃに噛み砕いて、飲み込んだ。
また何やら声が聞こえてきたが、もうそんな戯言に耳を貸すつもりは無い。
もう少しで全部食べ終わる。
そう思った時。
「あの、えっと……」
突然、戸惑うような声が聞こえた。
それは冷たくて腹立たしいあの声とは違っていて。
気になってそちらを見てしまった。
「……?」
わたしの目に映った光景はなんというか、なんだろう。
状況がうまく理解できない。
ササコちゃんが目の前に立っていて、イシちゃんを見下ろしていて、わたしの手には、手には……。
これはなんだ?
もはや原型をとどめないこれは、確か──。
「ぁ……」
全てを理解した瞬間、急速に熱が冷めていくのを感じた。
冷めきってなお、冷える。
わたしは、とんでもないことをしでかしてしまった。
彼女に一番見せてはいけないところを見られるなんて。
どうしてこんなことになってしまったのだろう……。
ササコちゃんの顔がまともに見れない。
目が潤んできて、今にも溢れだそうとしていた。
この涙はきっとわたしのじゃない。
わたしは俯き、目を閉じた。
ごめんね、イシちゃん。
泣かないで。
わたしが絶対に何とかするから。
言い聞かせるように、心の中で呟く。
だけどこの言葉はもう彼女には届かないかもしれない。
わたしの心は既に形を変え始めていたから。
イシちゃんにはわたしだけいればいいとか思ってしまう。
死ななくてよかったわね、じゃあどこかへ行って。
そんな言葉、この口からだけは絶対に言えない。
「ご、ごめんね。……こわがらせ、ちゃった…わよね」
無意識に発せられるのは心にもない言葉。
その涙混じりの声は、まるで遠くで誰かが喋っているみたいに客観的で、耳も遠い。
だめだよ、イシちゃん。まだ寝てないと。じゃないと、あなたはきっと傷ついちゃうよ。
『わたしがいるから。ずっといっしょにいてあげるから……』
もう目を開けることも出来なかった。
意識がだんだんと重くなっていく。
どす黒い液体を吸って、深く深くへと沈んでいくようだ。
この声はもう誰にも届かないのだと悟った時、あの冷たい声の主の気持ちが、ほんの少しだけ分かった気がした。
────────────────────
「ご、ごめんね。……こわがらせ、ちゃった…わよね」
私は我を忘れて、一心不乱に自分の一部だったものに齧り付いていた。
こうしてササコに声をかけられるまで、ずっと。
最初はササコと一緒に逃げるためだったのに、そのササコのことを忘れるほどに血肉を欲していたことが、怖くてたまらない。
だけどそれ以上に怖いのは……。
「ゴイシシジミさん……、」
「そ、そんなことより! ……あなた意外と強いのね。びっくりしちゃった」
本当に、ササコはすごい。
あんなに大きなセルリアンを一人でやっつけて。
未だ……私の前に、立っている。
こんな血まみれの口元を見ても、まだ。
……もしかして、また昨日までみたいに、過ごせるのかな?
まだ、ササコと一緒にいられるのかな……?
もし彼女が何事もなく接してくれたなら、私は元に戻れる?
右手はなくなっちゃったけど、また、いつもみたいに……。
「……!」
「あの、腕……」
「…………私は……あなたと同じフレンズよ」
私が声に出したのは、心にもない言葉だった。
今まで意識しないようにしてきた。
でも、押し込めて隠そうとするほど、それは深く根を張った。
私はきっとササコ達とは違う。
「……」
切り落とされたはずの私の右手が新しく生えていた。
首の皮一枚だった袖も綺麗にくっついていた。
だけど、セルリアンと戦ったササコだけが……傷ついている。
服なんかもう、初めて会った時からずっとボロボロのままで、治る気配もない。
そして今日、ササコはまた……。
俯きながらもかろうじて見える彼女の傷跡。
それは小さな傷だったけど、やっぱり赤い血が流れていて、きっと痛いのだと思う。
私はその赤いのがどうしようもなく見ていられなくて、更に視線を落とした。
そんなことをしたのは、たぶん目を逸らしたかったからだ。
脳裏に焼き付いた真っ赤な両手と、自分と彼女の違いから。
逃げたって何も変わらないのに。それでも直視はできなくて。
すっかり落ち込んでしまった視線の先には、左右で大きく質感の違う履物があった。
ササコの左の足には、ほとんどが砕けてヒビだらけの、鎧っぽいものが。
そして右足には私のとよく似た靴を履いていた。
元々はこっちの方も鎧に覆われていたのかもしれない。
そう思ったら、急に心臓が抉られるような感じがして泣きたくなった。
もう痛くなんかないのに、痛いのはササコなのに。
なのに、なのに…。
背けようのない事実が重くのしかかって、軋む。
私はこんななのに、どうしてこんなにも無力なんだ。
「…………」
未だ私の前に居続ける少女は、もう何も言わなかった。
ただそこにいて、きっと私を見つめていた。
怖いはずなのに。
今すぐに逃げ出したいはずなのに、彼女はまた自分を殺そうと言うのか。
こんなに優しくて、自身の危険を顧みない。
そんなササコに私は何を言えばいい?
逃げてもいいなんてことはもう言えない。
言いたくないんだ。
……だったら、何か弁解するのはどうだろう。
ササコが今夜も安心して眠れるように、私が、この……血塗れの口で……?
信じてもらえるとは思えない。
じゃあやっぱり、こっちの血塗れを後ろ手に隠して、何も無かったって言い張ってみる?
そうしたら……見逃してくれるかな?
それでもダメなら今ここで、ササコの目の前で、この手が生えなくなるまで切り落とせば……。
いや、そんなのは絶対にダメだ。
もしそんなことをすれば、彼女を余計に怖がらせるか、悲しませてしまう。
悲しんで、くれるのかな……。
ろくな考えが浮かばなかった。
足りない頭でいくら考えたって、思いつくのは普通とは程遠い愚案ばかり。
諦めきれない。
でも、ササコの気持ちは無視できない。
いつまで経っても弁解の言葉なんか浮かばないから。
私は彼女に、ササコにこの場の全て委ねることにした。
ずるいかもしれないけど、今の私からはきっと、取り繕うための嘘や誤魔化ししか出てこないから。
目を瞑り、一度浅く深呼吸をしてから、顔を上げる。
すごくドキドキした。
私は鼓動が少し穏やかになるのを待ってから、目を開いた。
「ぅ……」
一瞬ぼやけて鮮明になる。
そうして一番最初に目に入ったのは、ササコだった。
目の前に、ササコがいた。
そんなこと、ずっと分かっていたのに。
でも、どうしようもなく嬉しくて。目頭が熱くなった。
ササコがここにいてくれる。
もう一度、生きて再会することができた。
彼女は俯いていて、どんな顔をしているか分からないけど、今ここにいるのは間違いなくササコだった。
夢じゃないんだよね……?
自分の頬をつねることもせず、私の両手は、自然とササコの方へと伸びていた。
確かめたい。
その手に、髪に、頬に触れて、ササコがここにいることをちゃんと認めたい。
この手で、ササコの体をぎゅっと抱き締めて、確かな体温を感じたい。
もしそんなことをしたら、今度は本当に泣いてしまうかもしれないけど。
だけど止められなかった。
真っ直ぐと伸びていく。
気持ちがはやって、また鼓動が加速する。
もう少しで、届く。
それなのに。
やっぱり、だめだ……。
伸ばしたそれは赤く汚れきっていて、触れるのをためらわれた。
言葉でササコを安心させることも、彼女に触れることも叶わない。
今の私は無力を通り越して無だった。
何も無い、何も出来ない。
ササコはこんなにも、拳を握りしめるほど必死に言葉を探してくれているのに。
地面を睨みつけて、拳をぎりぎりと締めて、その手のひらにはきっと爪の跡がついているのだろう。
そんな彼女の様子を見ていると、自然と笑みがこぼれた。
笑える要素なんかひとつも無い。
だけど私は微笑んでいた。
それは何も出来ない私の……諦めだったのだろう。
20話終了
時間置いちゃうとすぐに文章の作り方が分からなくなるます……
ぼんやりとする。
ずっと、ぼんやりとしていた。
押しては引いていく波打ち際。
私はそこにいて、彼女がそれを見ていた。
「あなたは、夢子……?」
「なぁに、それ」
全体的に白っぽい服を着た少女は、その髪の毛の一本一本も白い。
私やササコと同じ、そしてあの子とも。
眉を下げてどうやら悲しんでいる様子の彼女に、私は何をしてあげられたのだろう。
少女は顔を伏せて、やがて覚悟が決まったのかその名前を口にした。
「わたしは、──────よ」
きっと彼女は否定したかったのだと思う。
目が覚めれば消えてしまう、自分はそんな不確かな存在ではないと、必死になって抗っている。
そんな彼女の声を、私は聞いてあげなきゃいけない。
それなのに、なんだか声が遠いような気がして、上手く聞き取れなかった。
彼女の震えるような寂しい気持ちは、波にさらわれて見えなくなってしまったのだと、そんな風なことを思った。
「わたしの名前、忘れちゃったみたいね……」
「ごめんなさい」
きっと、謝ったって赦されることじゃない。
だけど、それでも……
「ごめんなさい……」
この言葉は彼女に届いているだろうか。
波にさらわれてはいないだろうか。
不安だった。
「ごめんなさ──」
「しょうがないから、赦してあげる」
「……」
「そんなに謝られたら、あなたにこんなに想われたなら、きっとなんだって赦しちゃうわ」
「…………そんなの、」
「それに、別にあなたは何も悪くないもの」
「……違う、私は……」
「──違う」
「…………」
「違う」
「……私が全部、悪かったの」
「違う」
「私があなたを……私さえいなければ……!」
「違うの。わたしの言葉、ちゃんと聴いて」
顔を上げた少女と目が合う。
淡く輝く金色の瞳は、決して逸らさせない。
強い意志を宿して、私を真っ直ぐと射抜く。
それは内に眠る悪夢を取り払うように。
「悪い夢にどんなにひどく言われたって、あなたは決して悪くない」
ずっと欲しかったはずの言葉。
なのに、私は。
「……もうあなたの言葉なんて、信じられないわ」
止められない。これ以上傷つけたくないのに、止まってくれない。
「痛かったじゃない! あんなに痛かったのに、どうして……」
「その話し方」
「……誤魔化さないで」
「………………」
彼女は私から目を逸らして、何かを考え込む。
やがて何かを思いついたのだろう。ゆっくりと口を開いた。
「嘘をついちゃったのは……きっと、幸せだったから。わたしはあなたとの時間を、できるだけ沢山の笑顔で埋めておきたかったの。あなたは知らないこと……あなたの笑った顔はね、実はすっごく素敵なのよ。真っ暗に曇ってしまった心も、一気に晴らしてくれるくらいに……」
「………………」
「だからね、わたしはあなたに笑っていてほしい」
「そんなことで……」
「そんなことじゃないわ。わたしはあなたを恨んだりしない。でも、あなたの笑顔を曇らせてしまうようなやつは許せないの。……たとえそれが、わたし自身であっても」
「……」
「ずっと、聴こえてたよ。わたしみたいになりたい、ならなきゃって。
あなたの気持ち、嬉しかったけど、すごく悲しかった」
「ごめんなさい」
謝ることしか出来なかった。
今は亡き彼女のために泣くことも、もう私には出来そうにない。
そんな資格はとうにないのだ。
自分のしたことを認めておきながら、せめて夢の中でなんて。
彼女の口から赦しを得ようとするだなんて。
本当に救えない。
救われるべきじゃ……ない。
「……ごめんなさい」
「やっぱり、あなたは未だ……夢を見てるのね」
金色の光が揺らぎ、瞬く。
そして再び私の視線をとらえると、網膜を強く焼け焦がす。
鋭くなって、一番深くに刻み込むように。
彼女はその目で言った。
「もう雨には濡れちゃだめよ。また怖い夢を見ちゃうからね。」
「夢……」
「そう、夢。起きても覚めない恐ろしい幻夢。こんなふうに」
彼女はそう言うと、波音の聞こえる方へと視線を流す。
私はその後を追った。
まだ眩しくて、目に光が張り付いているようだった。
金色じゃない、赤い光が視界を覆い尽くすほどに広がっている。
「赤いわね。あれ、なんだと思う?」
それを見るように促した少女が、軽い声色で聞いてくる。
彼女の口元は柔らかく微笑んでいたけど、目は全然笑ってなかった。
「……海」
私が言うと、彼女は曖昧な顔をした。
そして。
「わたしのことは忘れて」
「……え?」
突き放すような言葉。
突然の事で、一瞬その意味を理解できなかった。
じゃあ、一瞬後の今ならどうだろう。
……そんなの、分かるはずがない。
「なん…で、そんなこと、言うの…?」
「言ったでしょ、……許せないって。わたしは太陽なんかじゃないし、あなたの行く先を明るく照らすかがり火でもないの」
彼女はそう言って、こちらへと両手を伸ばしてくる。
ひんやりとした手が頬に触れる。
「ほら、やっぱりわたしはいない方がいい」
「ぇ……?」
頬を伝う水滴の感触。ぼやける視界。気づくと私は泣いていた。
「なんで……」
彼女の言葉が悲しかった。
私が忘れてしまったせいで、彼女のことを、「彼女」としか呼べなくなってしまった。
そのことが悲しくて、申し訳がなくて。でも赦されるはずがなくて。
また涙が流れた。
泣く資格がないとか言っていたのは、誰だっただろう。
何とか押しとどめようと目を瞑ったけど、さっき彼女が言ったばかりの言葉を思い出してしまって、できそうにない。
彼女の悲しい考えを覆せるだけの言葉も、私は持ち合わせていなかった。
それが堪らなく悔しい。
悲しい涙に、悔しい涙。
涙はとめどなく溢れてくるけど、私の顔が水浸しになることは無かった。
こぼれた滴が頬を伝い、途中で途切れる。
その繰り返し。
冷たいものが、添えられた両手に落ちては熱を失っていく。
今まで冷たいと思っていたそれは、彼女の手の冷たさに比べればまだ温かかった。
その対比にまで泣かされそうになる。
ふいに、ぼやけ切った視界の中で彼女が柔らかく微笑んだ気がした。
こんな安心させるような顔を私は知っている。懐かしささえ覚えた。
彼女は一度私のことを泣き虫だと罵ると、指で涙を拭おうとする。
……だけど私はその手を拒んだ。
涙と一緒に、大切なものを取られてしまう気がしたからだ。
「忘れたくない」
「…………」
「忘れたりなんか、できないわ……」
彼女は今、どんな顔をしているのだろう。
目を開けても、瞑っても、映るのは歪んだ悪夢だけだ。
とうにぼやけ切っているのに、視界はまだまだぼやけていく。
とめどなく涙が溢れてくる。
もういっそ、この涙で
溺れてしまいたかった。
最近何だかおかしい。私は今現在、ひとつの悩みを抱えていた。
ここのところ、気づけばササコのことを目で追っている。
それは以前と変わらないようにも思うけど、今はどういう訳か彼女のことが愛おしくてたまらないのだ。
もちろんササコのことは前から好きだった。
でも今はこれまでの比にならないくらいに好きすぎてしまう。
……彼女のことを考えていると、どこか言語能力が怪しくなる。
どうして急にこんな感情を抱くようになったのかは分からない。
だけど、彼女のどこが好きかと聞かれて安直な返答をしてしまうくらいには、ササコが好きだ。
そんな具体性の無い答えではこの気持ちが伝わらないというのなら、私が思う彼女の好きな所をひとつずつ列挙してもいい。
私は目を閉じ、大好きな友人に思いを馳せる。
「…………」
……優しいところが好き。私みたいな子にも優しく接してしまうような迂闊さも含めて好ましく思う。見かけによらず力強いところも好き。まさかあんなに強そうなセルリアンを、たった一人で倒せてしまうなんて。急に彼女にかっこよさを感じるようになってしまった。強くてかっこいい。……好き。だけど彼女の強いところはそれだけじゃなくって。肉体を凌駕する心の強さ。恐怖を感じながらも恐ろしい存在に立ち向かうことは、きっと誰にでもできる訳じゃない。自分が持っていないものを持っていると言うだけでも、惹かれてしまうものなのだと思う、と一人で納得する。やっぱりササコはかっこいい。こんなにもかっこいいのに、かわいさも兼ね備えているなんて……。まるっこい目元は変につり上がってたりしないし、瞳の色は透き通った琥珀色で宝石みたい。それに、繊細そうな唇の奥には尖った牙も見えない。さらには、真っ白な髪はさらさらのもふもふふわふわで、世界に二つとない髪質に違いないと思えるくらい綺麗だ。ちゃんとした服さえ着せれば、きっとどこかのお姫様と間違えてしまうに違いない。
「好き……大好きぃ……」
「……あの、大丈夫ですか……?」
「わひゃぁっ! ……な、なに?」
突然声をかけられて、飛び上がってしまう。
顔を上げるとササコがいた。
今の私に声をかけるのは彼女くらいのものだけど。
だけど、今は、このタイミングで話しかけられるなんて考えもしなかった。
彼女の顔を見た瞬間、そして私に話しかけたのがササコだと認識した時、私の心臓が二度大きく跳ねた。
「す、すみません。なんだかぼーっとしていたみたいだったので。あと顔もいつもより少し赤いような……熱でもあるのではないですか?」
ササコが心配そうに言った。
私は何とか心を落ち着けて、思考を巡らせる。
出来ることなら、愛しい声が紡ぐ言の葉のひとつひとつを。そしてその裏にある彼女の心の全てを理解したい。
だけど私に出来るのは、彼女の思いを乗せた言葉を正面から受け止めることくらいだ。
叶わない願いは早々に諦め、改めてササコの言葉に向き合う。
"「なんだかぼーっとしていたみたいだったので」"
ぼーっとして見えたのは、きっとササコのことを考えていたから。
意識の一番深いところで、脇目も振らず、危機管理をも怠って。
彼女のことだけを考えてた。
"「あと顔もいつもより少し赤いような……熱でもあるのではないですか?」"
言われてみれば、なんだか顔が熱い気がする。
あるのかな、熱。熱……あるのかもしれない。
そう曖昧に考えていると、ふとあることに気づいた。
ササコは私の顔を見て、いつもより赤いと言った。
それを聞いた時、私は焦りながらも喜びを感じていたのだ。
ササコが見ていてくれるのが嬉しい。
些細な(?)変化に気づいてくれるのが幸せだと思った。
……というか、ササコの頭の中には
顔が赤くない平常時の私がいるのか。
こちらにも気がついてしまい、そんなに顔を見られていたのかと思うと、急に言い知れない気恥ずかしさのようなものが押し寄せてきた。
これまでササコが見てきた私は、どんな顔をしていただろう。
彼女の目にはどう映っていた?
変な顔をしてはいないだろうか……?
そんな不安が浮かんでくる。
不安の種を吐き出すためにと、これまでを振り返ったのは間違いだったかもしれない。
今までの私のササコに対するあらゆる言動はどう考えてもまともじゃなかった。
だからきっとそれに伴う表情の方も、普通じゃなかったに違いないのだ。
既に芽吹いてしまった不安事の種は、根を張り茎を伸ばし続ける。
私はその根茎がこの熱を吸い上げてくれることを願わずにはいられない。
もうこれ以上、ササコに変な顔を見せたくはないから。
「ゴイシシジミさん……?」
「…………」
ふいに、意識の外から声が聴こえた。
今度もササコだった。
私はそれっきり思考を打ち切って、無難な返事をすることにした。
「大丈夫よ。…ありがとう」
ササコに不要な心配をかけたくなかった。
極めて平静を装ったつもりだったけど、たった一言を導き出すまでに一体どれだけの時間が流れたのだろう。そしてその無言だった時間で、ササコとどれだけの言葉が交わせたのだろう。
深く考え出したらまた同じことが繰り返される気がしたので、やめておくことにした。
じー……
視線を感じた。疑うような視線を。
「本当に……?」
それは疑わしげな声で、やっぱり疑っているみたいだ。
正直に言うと、私は全然大丈夫じゃない。
こうしてササコに見られているだけで、身体がどんどん熱くなって、溶けてしまいそうになる。
何度も思考に靄がかかりそうになるし、眠くもないのに目が潤んでくる。
熱に浮かされたような気分だった。
これは重症かもしれない……。
「ん……?」
「…………」
今の私は、よっぽど嘘つきの顔をしていたのだろう。
ササコが目を細めて、じっと瞳を覗き込んでくる。
彼女の瞳に写った自分の顔がよく見えて、なるほどこれは熱っぽいなと納得できるくらいに、顔を近づけてきて……。
熱があるかもと疑っておいて、その急接近はどうかと思う。
もし本当に風邪でも引いていたら、これで移ってしまうかもしれないではないか。
それに、こんなにまじまじと顔を凝視されるのは落ち着かない。
見てもらえる事が嬉しいとは言っても、さすがに限度があった。
私は顔を逸らして、ササコの肩に手を置く。
そしてゆっくりと遠ざけた。
「ほんとうに大丈夫だから……ね」
念を押すように言う。
目だけを動かして表情を確認すると……ササコはまだ疑わしげな顔をしていた。
…………………………。
少しの間、刺すような視線を無言でかわし続けていると、向こうの方が根負けしたようだった。
「あなたがそう言うなら……」と、渋々ながら見逃して貰えた。
ほっと息をつく。
「それで、…何が好きなんです?」
「……ぇん?!」
安心したところで不意打ちを食らい、変な声が出てしまった。
みるみるうちに顔が熱くなる。
さっきの"アレ"を聴かれていたのだ。
まさか声に出ていたなんて、と今更になって思う。
それも言葉として認識できて、しっかりと意味が伝わるくらいに、大きい声だったとは……。
愛の囁き(?)が本人に聞かれて、その詳細を問いただされるなんて、……なん…て……。
顔の温度はもうこれ以上上がらないらしい。
今度は頭が熱くなってきた。
今私の額辺りからは湯気が出ている。絶対出てる。自分では見えないけど……。
聞かれてしまった。
……聞かれてしまった……。
熱暴走を起こして止まりかけた思考回路を無理やりに動かすと、事実の確認をするみたいに同じ言葉が何度も繰り返された。
聞かれてしまった。
……声に出してしまった。
次に浮かんできたものは、さっきと微妙に形が違ったけど、結局のところは同じ事実に基づいていて、その二つには大きな意味の違いはなかったはず。
だけど私は"声に"の部分を認識した瞬間、ハッとした。
私は声に出していたのだ。そしてそれをササコに聞かれてしまった。
そんなことは確認するまでも無く、分かりきったことだ。
でも、それは一体どこから……どこまでだっただろう……?
もし最初から最後まで全部声に出ていて、その一言一句を逃すことなく聞かれていたとしたら……。
……ササコは、"何が好きなのか"と訊ねてきた。
わざわざ訊いてくるということは、私の思うような恥ずかしすぎる出来事は起こらなかったと考えるべきだ。
でももし、ササコが全てを知っていてとぼけているとしたら……。
彼女ならそういうこともするような気がする。
少し前までは、彼女に対してそんな風な考えを持つことは無かった。
ササコはどこまでも素直で、言葉をそのままの意味で受け取ってしまう。
出会ってすぐはそんな風に思っていた。
でもそれは違った。
彼女は意外と強かなのだ。
人の言葉を疑いもするし、時には嘘もつく。たまに意地悪を言うことだってある。
それに……。
つい先日のことを思い出す。
前をササコが歩いていて。私はその後ろを歩く。
私の右手を問答無用でひったくったササコが言う。
"「でも良かったです。……こうして捕まえることが出来て。
……また、あなたの手を握ることが出来る」"
あの時は気を使ってくれたんだと、今になって思う。
ササコは気を使うのも上手だった。
だから今回も、わざと聞いていないふりをしてくれているのかもしれない。
もし本当にそうだとしたら、改めて訊かないでほしいけど。
滅多に出ない彼女の意地悪な部分が、ここぞとばかりに出てきてしまったのだろうか……。
「ゴイシシジミさん」
返答はまだかとばかりに、ササコが私の名前を呼ぶ。
やっぱり、ほんの少しだけ意地悪かもしれない。
「えっと……」
言い淀んでしまう。
このまま淀み切ってしまえば、次に口を開く頃には、好きの気持ちごと見失ってしまう気がした。
「あの、ね」
勇気なんか出さなくたっていい。
訊かれたことに答えるだけだ。
ササコが望んだから、それを今から言うんだ。
それだけなのに、鼓動が早くなる。喉が渇いてきて、頭が真っ白になってしまう。
だけど、それでも。
どんなに緊張したって、何も考えられなくなったって、いまさら言うのを止めることは出来なかった。
どんな風に声に出すかは、既に決まっていたから。
「私、は──────」
朝、目が覚めて一番にササコの寝顔を見る。
そして自分が正常であることを再確認した。
「……うん」
ササコの顔をずっと見ていても、激しい動悸や頭が茹だるような熱を感じない。
だから今の私はきっと、"いつもの"私だ。
彼女のよく知る「ゴイシシジミさん」だ。
そう思うと少しほっとした。
今なら分かる。
昨日の私は、本当に風邪をひいていて、熱も動悸も全部その風邪のせいだった。
目を閉じれば蘇る記憶も、薄く蕩けて判然としないものばかりで。
自分がいつ眠りについたのかすら鮮明に思い出せない。
だけど昨日何があって、その後どうなったのかはちゃんと覚えている。
その記憶の所々はぼんやりとしていて、夢でも見ていたのではないかと勘違いしそうになるけれど。
でもあれは間違いなく自分で考えて決めて、この口から発せられた言葉だと言える。
……私は、ササコに「好き」を伝えなかった。
彼女に何が好きなのかと訊かれて、「なんでもない」と答えたのだ。
今思えば、少し素っ気なかったかもしれない。
「あなた」でも、「ササコ」でも、どちらでも言えばそれで良かった。
でも私は口を噤んだ。
その時はそうするべきだと思ったから。
茹だり切った頭で唯一冷静に考えられたのは、今の自分がいつもササコが見ている私じゃないということ。
それだけ解っていれば、もうどうするべきかは考えるまでもなかった。
……でもそれも、熱の冷めた今だから言えることで。
本当のところは、ただ怖気付いただけかもしれない。
「…………」
このままササコの目が覚めるのを待って、いつも通りのおはようを言おう。
そうすればきっと何も変わらない。
二人で朝の挨拶をして、これまで通りの日常を過ごすんだ。
……別に、何も名残惜しくなんかない。
私にとって一番大切なのは今、隣にササコかいることだから。
いつか来る、二人で一緒にいられる最後の日まで。
私はずっと彼女の隣に居続ける。
今ここで、改めてそう心に誓った。
誓いの口付けは必要ない。
私は彼女の騎士じゃないから。
「……私は、あなたの友達になれたのかな?」
投稿頻度が開くことによって発生する問題に、ただいま直面しております
長期間のブランクによる文章の書き方の忘却とそれに伴う文体の変化
より具体的に述べますと、登場人物(主に主人公)のキャラ崩壊が主な問題です
一人称視点で書いているので、地の文の書き方の変化がそのままキャラ崩壊に繋がる恐れがあるわけです(これはもう若干手遅れかも)
そこで、これからは毎日こつこつと進めていく方針に転向しようかなと考えています
最初はこのような方針で進めていましたが、段々と書かない日が続くようになり、今に至ります
このままではいかんですと思い、この度気合いを入れ直すことにしました
今後は、この夏で完走するくらいの心意気を持って進めていきたいと思っています
目標は週一ペースでの更新です