──side A────────────
おやすみ。
イシちゃんが目を閉じてから、わたしはそう言ったけど、多分彼女には聞こえてなかったと思う。
だって彼女はもう眠ってしまったから。
深いかもしれない。浅いかもしれない。
そんな曖昧な眠りの中で彼女が夢見るのは、きっとあの子のことばかりだ。
いいな……。
ちょっとだけ嫉妬してしまいそうになる。
……と、いけないいけない。
彼女は頑張り屋さんだから、きっと直ぐに起きてきちゃう。
だからその前に、全部終わらせてしまわないと。
わたしは目を覚ますべく、そっとまぶたを持ち上げた。
「……っ……!」
強い刺激を目の奥に感じて、咄嗟に光を遮断する。
すごく眩しかった。
視界に入るもの全ての、色かたちともに判別がつかないほどに。
きっと、生まれて初めて目を開けた時も、わたしはこんな痛みを味わったのだろう。
突き刺すような眩しさに、今にもこの目を潰されてしまいそうだけど、こんな程度のことで立ち止まってはいられない。
わたしは覚悟を決めて両目を開いた。
「んー…………」
再び映し出された煌びやかに渦巻く色々。
瞬きを何度か繰り返していると、乱れていた光彩が次第に安定の色を見せ始める。
「よし!」
言った瞬間、そのあまりの声量にちょっとびっくりした。
でもすぐに気を取り直す。
この自分の声がやたらと大きく聞こえてしまう問題も、きっとすぐに解決する。
少し待てば正常になるだろうけど、そんなことより今はすべきことがある。
今のわたしは、イシちゃんの替わりなのだ。
いや彼女そのものなのだ。
ぐへへ……じゃなくて、えっと……。
わたしは地面に視線を這わせる。
そして。
「──あった」
見つけたそれを拾い上げた。
イシちゃん曰く、これはササコちゃんの右手首……。
さっき、彼女がそう認識しようとし始めた時、その心の中はひどく混沌としていて、見るに堪えないものだった。
まさかわたしの一言で彼女をあんな風に追い詰めちゃうなんて、思ってもみなくて。
でも本当はすぐに気づくべきだったんだ。
自分の体の一部を食べろだなんて、そんな猟奇的な提案を受け入れること、"わたしたちに"出来るはずがないのに。
特にイシちゃんは血が濃くなってるはずだから尚更、自傷的なことは許されなかっただろう。
その結果として、わたしはもう少しで彼女の心を殺してしまうところだった。
「……」
イシちゃんはたくさん傷ついて、ようやくここまで戻って来た。
きっと何度も痛い思いをしてきたはず。
でもこれを食べれば、また少しだけ濃くなってしまう。
また、彼女を苦しませてしまう。
そして、また……鬱々とした日々に帰してしまうかもしれない。
やっと大切なものを見つけられたのに。
「…………」
わたしはなんとか立ち上がれないものかと、地面に左手を着いてみた。でもだめだった。
お腹がすいて力が入らない……というより、そこに何も無い感じがした。
体の密度があまりに低くて、空腹すらも感じないのだ。
ふと、さっきイシちゃんが言いかけていた言葉を思い出す。
"「おねが…い、……ササコ……わたし、を──」"
この先に続く言葉がどのようなものなのか、わたしは知っていた。
だから咄嗟に引き止めた。
だけどやっぱり、今のイシちゃんは一人分にも満たないんだ。
このままじゃ彼女は、きっと……。
死にゆく友達をを前にしたわたしにできることは、もう二つしか残されていなかった。
これからするのは、とても重い決断だ。
わたしは心を決めるために、一度座り直した。
「……?」
体勢を変えた際に、左の太ももの辺りに違和感を感じたが、その正体に気づいて口元が緩んだ。
「なんだ、持ってるじゃない」
もう、迷いは消えていた。
さっきイシちゃんがしたのと同じように、右の人差し指を咥えると、もう血の味はしなかった。
これは愛しい友達の味だ。
「ふふ……」
このままでいれば、あなたはあらゆる苦しみから解放される。
でもわたしは、今から自分の都合であなたをもっと苦しめるよ。
「…………」
『ササコちゃん。……イシちゃんを、お願いね』
わたしは思いっきり、顎に力を入れた。
関節部がミシミシと音を立てると、皮が破けて、口いっぱいにイシちゃんの味が拡がる。
そして──
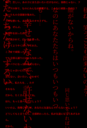
次々と染み出してくるのは、どす黒い感情。
舌をつたって、喉を通って、お腹の底へと落ちていく。
それはまさしく、純度の高い悪意だった。
"わたしたち"が決して抱くことの出来ないくらいの、許容量を遥かに超えた悪意。
少し気を抜くだけで黒い感情に呑まれてしまいそうになるのを、必死に耐える。
こんなものに耳を傾けてはいけない。
自分にそう言い聞かせて、また飲み下す。
何度も何度も、噛んで、飲み込んで。
この単純な作業を繰り返しているうちに、だんだんと身体に震えを感じ始めた。
怖いから震える。これもまた単純な理由だった。
これはわたしの心の中にある怯えなのだろうか。
もしそうじゃないのなら、どうか怖がらないで。
このぐちゃぐちゃしたものは全部、全部わたしが引き受けるから。
わたしのせいで今まであなたをたくさん苦しめたよね。
だからこれはせめてもの償い。
あなたはこれから、ササコちゃんやみんなと幸せに生きるの。
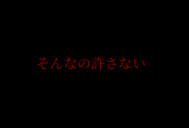
「アンタは黙ってろッ!! 」
やけつくように熱い喉にビリビリとしたものが走る。
絶対に誰にも邪魔なんかさせない。
イシちゃんを繋ぎ止めて、ササコちゃんも助けるんだ!
わたしはもう、何がなんだかわからないくらいに頭に血が上ってしまっていた。
先程まではヤツの悪意に負けじと慎重になっていたが、もう知らない。
わたしは手に持っていたそれを、めちゃくちゃに噛み砕いて、飲み込んだ。
また何やら声が聞こえてきたが、もうそんな戯言に耳を貸すつもりは無い。
もう少しで全部食べ終わる。
そう思った時。
「あの、えっと……」
突然、戸惑うような声が聞こえた。
それは冷たくて腹立たしいあの声とは違っていて。
気になってそちらを見てしまった。
「……?」
わたしの目に映った光景はなんというか、なんだろう。
状況がうまく理解できない。
ササコちゃんが目の前に立っていて、イシちゃんを見下ろしていて、わたしの手には、手には……。
これはなんだ?
もはや原型をとどめないこれは、確か──。
「ぁ……」
全てを理解した瞬間、急速に熱が冷めていくのを感じた。
冷めきってなお、冷える。
わたしは、とんでもないことをしでかしてしまった。
彼女に一番見せてはいけないところを見られるなんて。
どうしてこんなことになってしまったのだろう……。
ササコちゃんの顔がまともに見れない。
目が潤んできて、今にも溢れだそうとしていた。
この涙はきっとわたしのじゃない。
わたしは俯き、目を閉じた。
ごめんね、イシちゃん。
泣かないで。
わたしが絶対に何とかするから。
言い聞かせるように、心の中で呟く。
だけどこの言葉はもう彼女には届かないかもしれない。
わたしの心は既に形を変え始めていたから。
イシちゃんにはわたしだけいればいいとか思ってしまう。
死ななくてよかったわね、じゃあどこかへ行って。
そんな言葉、この口からだけは絶対に言えない。
「ご、ごめんね。……こわがらせ、ちゃった…わよね」
無意識に発せられるのは心にもない言葉。
その涙混じりの声は、まるで遠くで誰かが喋っているみたいに客観的で、耳も遠い。
だめだよ、イシちゃん。まだ寝てないと。じゃないと、あなたはきっと傷ついちゃうよ。
『わたしがいるから。ずっといっしょにいてあげるから……』
もう目を開けることも出来なかった。
意識がだんだんと重くなっていく。
どす黒い液体を吸って、深く深くへと沈んでいくようだ。
この声はもう誰にも届かないのだと悟った時、あの冷たい声の主の気持ちが、ほんの少しだけ分かった気がした。
────────────────────
「ご、ごめんね。……こわがらせ、ちゃった…わよね」
私は我を忘れて、一心不乱に自分の一部だったものに齧り付いていた。
こうしてササコに声をかけられるまで、ずっと。
最初はササコと一緒に逃げるためだったのに、そのササコのことを忘れるほどに血肉を欲していたことが、怖くてたまらない。
だけどそれ以上に怖いのは……。
「ゴイシシジミさん……、」
「そ、そんなことより! ……あなた意外と強いのね。びっくりしちゃった」
本当に、ササコはすごい。
あんなに大きなセルリアンを一人でやっつけて。
未だ……私の前に、立っている。
こんな血まみれの口元を見ても、まだ。
……もしかして、また昨日までみたいに、過ごせるのかな?
まだ、ササコと一緒にいられるのかな……?
もし彼女が何事もなく接してくれたなら、私は元に戻れる?
右手はなくなっちゃったけど、また、いつもみたいに……。
「……!」
「あの、腕……」
「…………私は……あなたと同じフレンズよ」
私が声に出したのは、心にもない言葉だった。
今まで意識しないようにしてきた。
でも、押し込めて隠そうとするほど、それは深く根を張った。
私はきっとササコ達とは違う。
「……」
切り落とされたはずの私の右手が新しく生えていた。
首の皮一枚だった袖も綺麗にくっついていた。
だけど、セルリアンと戦ったササコだけが……傷ついている。
服なんかもう、初めて会った時からずっとボロボロのままで、治る気配もない。
そして今日、ササコはまた……。
俯きながらもかろうじて見える彼女の傷跡。
それは小さな傷だったけど、やっぱり赤い血が流れていて、きっと痛いのだと思う。
私はその赤いのがどうしようもなく見ていられなくて、更に視線を落とした。
そんなことをしたのは、たぶん目を逸らしたかったからだ。
脳裏に焼き付いた真っ赤な両手と、自分と彼女の違いから。
逃げたって何も変わらないのに。それでも直視はできなくて。
すっかり落ち込んでしまった視線の先には、左右で大きく質感の違う履物があった。
ササコの左の足には、ほとんどが砕けてヒビだらけの、鎧っぽいものが。
そして右足には私のとよく似た靴を履いていた。
元々はこっちの方も鎧に覆われていたのかもしれない。
そう思ったら、急に心臓が抉られるような感じがして泣きたくなった。
もう痛くなんかないのに、痛いのはササコなのに。
なのに、なのに…。
背けようのない事実が重くのしかかって、軋む。
私はこんななのに、どうしてこんなにも無力なんだ。
「…………」
未だ私の前に居続ける少女は、もう何も言わなかった。
ただそこにいて、きっと私を見つめていた。
怖いはずなのに。
今すぐに逃げ出したいはずなのに、彼女はまた自分を殺そうと言うのか。
こんなに優しくて、自身の危険を顧みない。
そんなササコに私は何を言えばいい?
逃げてもいいなんてことはもう言えない。
言いたくないんだ。
……だったら、何か弁解するのはどうだろう。
ササコが今夜も安心して眠れるように、私が、この……血塗れの口で……?
信じてもらえるとは思えない。
じゃあやっぱり、こっちの血塗れを後ろ手に隠して、何も無かったって言い張ってみる?
そうしたら……見逃してくれるかな?
それでもダメなら今ここで、ササコの目の前で、この手が生えなくなるまで切り落とせば……。
いや、そんなのは絶対にダメだ。
もしそんなことをすれば、彼女を余計に怖がらせるか、悲しませてしまう。
悲しんで、くれるのかな……。
ろくな考えが浮かばなかった。
足りない頭でいくら考えたって、思いつくのは普通とは程遠い愚案ばかり。
諦めきれない。
でも、ササコの気持ちは無視できない。
いつまで経っても弁解の言葉なんか浮かばないから。
私は彼女に、ササコにこの場の全て委ねることにした。
ずるいかもしれないけど、今の私からはきっと、取り繕うための嘘や誤魔化ししか出てこないから。
目を瞑り、一度浅く深呼吸をしてから、顔を上げる。
すごくドキドキした。
私は鼓動が少し穏やかになるのを待ってから、目を開いた。
「ぅ……」
一瞬ぼやけて鮮明になる。
そうして一番最初に目に入ったのは、ササコだった。
目の前に、ササコがいた。
そんなこと、ずっと分かっていたのに。
でも、どうしようもなく嬉しくて。目頭が熱くなった。
ササコがここにいてくれる。
もう一度、生きて再会することができた。
彼女は俯いていて、どんな顔をしているか分からないけど、今ここにいるのは間違いなくササコだった。
夢じゃないんだよね……?
自分の頬をつねることもせず、私の両手は、自然とササコの方へと伸びていた。
確かめたい。
その手に、髪に、頬に触れて、ササコがここにいることをちゃんと認めたい。
この手で、ササコの体をぎゅっと抱き締めて、確かな体温を感じたい。
もしそんなことをしたら、今度は本当に泣いてしまうかもしれないけど。
だけど止められなかった。
真っ直ぐと伸びていく。
気持ちがはやって、また鼓動が加速する。
もう少しで、届く。
それなのに。
やっぱり、だめだ……。
伸ばしたそれは赤く汚れきっていて、触れるのをためらわれた。
言葉でササコを安心させることも、彼女に触れることも叶わない。
今の私は無力を通り越して無だった。
何も無い、何も出来ない。
ササコはこんなにも、拳を握りしめるほど必死に言葉を探してくれているのに。
地面を睨みつけて、拳をぎりぎりと締めて、その手のひらにはきっと爪の跡がついているのだろう。
そんな彼女の様子を見ていると、自然と笑みがこぼれた。
笑える要素なんかひとつも無い。
だけど私は微笑んでいた。
それは何も出来ない私の……諦めだったのだろう。
20話終了



 <隔月になったらしいぜェ、くーっくっくっく
<隔月になったらしいぜェ、くーっくっくっく