私はとうに聞き慣れた雨音で目を覚ます。
無数の水の粒たちが木の枝葉を、地面を叩く音。
空を見上げると、そこにはいつも通りの灰色があった。
これで何日目だろうか……。
あの酷く落ち込んだ色をした雨雲は、連日降らせ続けて少しづつ地面を溶かしている。
ひょっとすると永遠にこの雨が止むことはないのかもしれない。
この島の土を全て溶かしきって、何もかもが水底に沈んでも、ずっと。
私は別にそれでも構わないと思っている。
いずれ来る最後の日まで毎日「おはよう」と「おやすみ」が言えたらそれでいい。
これはちょっと我儘が過ぎるかな?
「おふぁよぉ……!」
私は我慢ができなくて、あくびや伸びをするよりも早く「おはよう」を言おうとした。
それが失敗の原因。
気持ちが急いてしまったが故の失態。
朝の日課を怠ったせいで、私はなんとも間抜けな声を出してしまったのだ。
なんだか恥ずかしいくてちょっと後悔する。
世の中にはこんな幸せな後悔があるものなのかと思い、目を細めた。
でもやっぱり恥ずかしい……。
時間の経過と共に増幅されてゆく羞恥心が、とうとう眠気に勝ってしまう。
私は両手で顔を覆うといういかにもなポーズを取ってみた。
なんだこれ、余計に恥ずかしい……。
さらなる羞恥に顔が熱くなった。
笑われるだろうか。
それとも、引かれるだろうか。
今私は、いったいどんな目で見られているのだろう。
見守るような暖かな目?
それか、どう反応すればいいのかという困惑の眼差しかな?
冷めた目でもいいかもしれない。
この後のササコの返しがどんなものであっても対応できるようにと私は身構える。
しかし、先程からの一連の行動を通して見ていた少女に笑われる、なんてことはなかった。
指の隙間から外界を覗く。
すると、ずっとそこにいるであろうと思っていたササコの姿が無かった。
両手を下ろして、ほっと息をつくと、幸い顔の熱は直ぐに冷めた。
冷静になった頭で考える。
つまり私は、数分にわたってずっとひとり芝居をしていたということか。
気づいてしまったら一気に気が抜けた。
そこにやり場のない感情だけが残っている。
ササコに見られなかったことを喜ぶべきか、無人の舞台でひとり踊った間抜けな自分を嗤うべきかを悩む。
仮にどちらを選んだとしても、私の顔には笑みが浮かべられているだろう。
多分その意味合いはだいぶ違うと思うけど。
私は今、とても満ち足りている。
「ふわぁ……くぅ」
改めてあくびと伸びを済ませる。
3日前までの私だったら、きっとこんな心境で朝を過ごせはしなかっただろう。
どんなにひどい夢を見たって、もう全然気にならない。
孤独に怯えることも無くなった。
私が精神的に変われたのは、全部ササコのおかげだ。
彼女が帰ってきたらお礼を言おう。
「ありがとう」って。
これだけを聞いたササコは、私がなんのことを言っているのかわからないだろう。
きっと、不思議そうな顔をすると思う。
その直後には当然の質問も飛んでくるはず。
でも私はそれには答えない。
少しでも長くササコの困った顔を見ていたいから。
意地悪だとは思う。
我儘だとも思うけど、それはあの日ササコが許してくれた。
そしてなにより、ササコが悩んでいる間は、きっといつもより私のことをたくさん見てくれるはずだから。
私はこれ以上の何を望もうというのか。
……とりあえず、今回は「おはよう」を言い損ねた分くらいで妥協することにしよう。
計画と言っていいのか分からないくらいに残念な考えと期待を胸に、私はササコの帰り待つことにした。
「……おはよう」
なんとなく寂しくて、空に向かって小声で呟いてみると、今度はちゃんと発音出来た。
どれだけ完璧なものであっても、一人で口にするあいさつに意味なんて無いけど。
「まだかなぁ……」
──────────────────────
あれからどれだけの時間が経ったのだろう。
数分か、数十分か。
もしかすると一時間くらいは待ったかもしれない。
空を見上げて太陽の位置を確認しようにもあいにくの雨空。
これではどのくらい時間が経過したのかを確認出来ない。
「……遅い」
しばらくの間、ササコの帰りを大人しく待っていたが、一向に帰ってこない。
昨日、一昨日と、目が覚めて一番にササコの姿を見ることが出来ていただけに、今日になって一度も彼女に会えていないという事実に不安になってくる。
今すぐササコを探しに行くべきだろうか……?
もしかしたら、どこかで怪我をして動けなくなっているかもしれない。
そうでなくても、セルリアンに追いかけられたりして帰るに帰れなくなっている可能性もある。
最悪の場合は……
「──っ!」
気がつけば走り出していた。
戻ってきたササコとすれ違いになるかもしれない。
彼女がセルリアンと会敵していたとして、私が行ったところで何かが出来るというわけじゃないことも分かっている。
でも、いつまでもあそこでああして待っていることは出来なかった。
もし今からさらに一時間待っても帰ってこなかったら……?
その時のことを考えると、怖くてたまらなかった。
無駄な心配ならそれでいい。
とにかく今は一秒でも早くササコを見つけないといけない!
私は一層足に力を込めた。
──────────────────────
「こんなところにい、たの……ね」
ようやくササコを見つけられたという安心感は、眼前の光景を見た瞬間、その衝撃にすぐにかき消された。
ササコは無事で、今こうして私の目の前に立っている。
だけど私の最悪な想像は少しだけ当たっていて……。
頭の中がたちまちに真っ白になり、すぐにまた別の色に染め上げられる。
次の瞬間、私は一つの感情に全身を支配されていた。
「なに…してるの……それ、なに……?」
声が掠れて上手く形にならない。
私はこれ以上ないほどまでに恐怖していた。
ササコが、セルリアンと対峙している。
こちらに背を向け、恐ろしい存在と私とを隔てているのだ。
まさか、と思った。
ササコがあれと戦うつもりなのではないだろうかという馬鹿げた考えが頭に浮かぶ。
そんなのは本当に馬鹿げた考えだ。
幸いを最悪に変えてしまいかねない選択を、ササコがするはずがない。
だって、ササコは臆病で…………
"ここで足を失うくらいなら、私は全生命をかけてでも抵抗します"
ふと、いつかササコが言った勇ましい言葉と、彼女と初めて出会った時の全身傷だらけの姿を思い出した。
私の知るササコは臆病な所もあったけど、決して弱くはなかった。
少なくとも私よりずっと勇敢なんだと思う。
彼女はその身を滅ぼすような選択を平気でするから。
だから私は、より臆病者にならざるを得ないのだ。
大切なものが傷つくのが怖い。
二度と会えなくなってしまうのが怖い。
ひとり残されるのが怖い。
罪を背負うのが怖い。
痛いのも怖い。
これで最後になってしまうかもしれないというのに、私の頭の中は自分のことばかりだった。
私が恐れる未来。
そこにはササコと死別した自分がいて、当たり前のように生きている。
何も出来なかったことを後悔して、絶望しつつも、何もしない。
痛みを知ってしまった私は、もう二度と自分の胸を貫いたりはできないだろう。
ずっと一緒にいたいと思った。
それなのに、死んでまで寄り添えはしないというのか。
私は本当に、どこまでも自分勝手だ。
"あなたはあなたのしたいようにすればいいじゃないですか"
「……」
自分の命を危険にさらしてまでセルリアンに挑む。
それがササコのしたいことなのだろうか。
……そんなわけない。
もし、仮にそうだとしても、そんな危ないことを黙って見過ごすわけにはいかない。
私はササコを危険な目には遭わせたくない。
今すぐ彼女の背に駆け寄って、あの手を取って逃げるんだ。
そうすればきっと二人とも助かる。
これがササコの願いに反した行いだったとしても、無理やり連れていく。
それが私のしたいことだから。
「……!」
身長がササコの倍近くあるセルリアンを見上げると、全身におぞましいものが駆け抜けた。
嫉妬の目、憎悪の目、殺意の目。
そのいずれにも当てはまる、恐ろしい眼差し。
そいつが私を見ていた。
あまりの恐怖に体がすくんでしまう。
「こ…こわく…なんか……な…ぃ」
もはや声は意味をなさず、強がることも出来なかった。
ササコの方を見るが、彼女はその場に立ち尽くして動こうとしない。
何か動けない理由があるのだろうか?
あの時みたいに、怖くて動けなくなったのかもしれない。
やっぱり、私がササコの元まで歩いていって、直接連れ出すしかなさそうだ。
迷っている時間はない。
不規則になった呼吸を整えるまもなく、私は一歩を踏み出した。
セルリアンの目を見ないように、ササコだけを視界にとらえて前に進む。
前へ、前へ、一歩、また一歩と慎重に歩を進める。
一定の間隔で聞こえる自分の足音と、少しずつズレていく呼吸音。
その二つだけが、私がいる世界の音の全てだった。
雨の音なんて聞こえない。
心臓の音も、意外な程に聞こえなかった。
もしかすると、私の心臓はあまりの怖さに耐えきれずに活動を止めてしまったのかもしれない。
それは困る。
生きるのをあきらめるにはまだ早い。
ここで生きるのをあきらめるということは、これからのササコとの時間を、場合によってはササコの命までもをあきらめてしまうということだ。
そんなこと、絶対にしてはだめ。
せめてササコを安全なところまで連れて行くまでは。
彼女の手を握って、一人じゃないのだと安心させるまでは。
あの指先に触れて、私の存在に気づいてもらうまでは、諦めるわけにはいかない。
徐々に下げられるハードル。
だんだんと弱気になってしまう。
だって、こんなにも怖いから。
視界が、息が酷く乱れるから。
寒くもないのに身体が震えて仕方がないから……。
それでも、どんなに怖くたって足を止めることは許されない。
ここで止まれば二度と踏み出せないと、本能的に分かってしまった。
だから前へ、前へと、立ち止まることなく進むのだ。
ふと、不安になってセルリアンに視線を移すと、そいつは最初に見た位置、姿のままで微動だにしていない。
相も変わらず、こちらに憎々しげな視線を送ってくる。
だけど逆に言えばそれ以上のことはしてこない。
私がこんなに気が気でないというのに、セルリアンの方は随分と悠長な様子だった。
このまま私が近づくのを待ち伏せるつもりか。
もし本当にそうだとしたら好都合。
ササコに危害が及ぶ前にここから連れ出せる確率が上がる。
ササコ、どこも怪我してないよね……?
無事に彼女の顔を見るまでは安心できない。
私はいざという時に失敗しないように、一度心を落ち着けようとセルリアンからササコへと視線を戻そうとした。
その時だった。
「──?!」
ヒュンッという短い音が聞こえた。
間違いなく足音ではないそれは、呼吸の音とも違った。
それでいて風が吹く音とも微妙に違う。
例えるならそれは空気を切り裂く音だ。
突然の怪音に足が止まりそうになりながらも、無理やり一歩前へ押し出す。
その際、ササコを捉えることに失敗した視線は、自然とセルリアンの方へと戻って行った。
……待って、何、それ?
私の視界には、さっきの音の正体であろう物体が映っていた。
それは、見方によってはナイフのようにも見えた。
ナイフ……? ナイフってなんだっけ。
ナイフは武器。殺害のための道具だ。
いつだったか、私がそう言った。
違う、言ったのは私じゃない。
記憶が、意識が? 混乱している。
私は酷く動揺しているようだった。
それはどうして?
ナイフなんてみんな持ってる。
ササコだって持っていた。
だから、セルリアンが持っていても別におかしくなんかない。
ナイフの柄に当たる部分が長い蔦みたいになってたって、それを自在に操れたって、今この瞬間にそれを振り上げていたって、何もおかしくなんかない。
ねえ、それをどうするつもりなの?
声なんかもう出ない。
だから目で訴える。
でも、とうにセルリアンは私を見てはいなくて。
その視線の先には────
「──ッ!」
息が止まってしまえばいいと思った。
間に合わないのなら、大切なものも守れないのなら、そのまま肺を潰して死んでしまえ。
それが嫌なら……
──もう呼吸なんてする必要は無い。
ばっしゃん!!
大きな水音と共に視界が揺らいだ。
それと同時に、足のつま先にビリビリとした痛みが走る。
右の足か、左の足かも分からない。どっちだっていい。
全速力なんかじゃ足りないから。
もっと速く、速く、
息を吸うのを忘れてしまうくらいに速く!
ナイフなんかよりも鋭く風を切って走るんだ。
かかとを地面に叩きつける度、ササコとの距離がどんどん縮まっていく。
そして、次の瞬間にはもう、ササコはすぐ目の前だ。
あと少しで届く……!
ガッ
「──ッ!?」
その時、不意に視界が傾いた。
全身が不思議な浮遊感に包まれるが、そんなことは意識の外だ。
次の一歩を踏み出すと同時に手を伸ばせば届く距離にササコはいる。
私は最後の一歩を地面につけようとした。
でも出来なかった。
空中に放り出された両足は、着地予定の地点から大きく後ろにズレてしまっている。
私は、また躓いてしまったのだ。
このまま行けば、間違いなく転けるだろう……。
──そんなのだめ!
ここで転けるわけにはいかない。
私は咄嗟に後悔しそうになるのを押しとどめ、右だか左だかの足を思いっきり前へと蹴り上げた。
一瞬後に地面に触れたのは、ぎりぎり靴の底。
ほとんどつま先だった。
それでもなんとか着地には成功した。
ここまでくれば、あとは手を伸ばすだけだ。
取るべき手を確認するために、私はつんのめったままの低い目線から再び前方を見た。
しかし、そこで見えたものは、ササコではなく、既にすぐ目と鼻の先にまで迫ったナイフだった。
ササコがいたのは左斜め前方。
躓いた拍子に進行方向が僅かにズレてしまったのか。
ナイフの軌道は変わらず、ササコへ向かっている。
今更手を引いたってもう間に合わない。
「ク───ッ!」
私は右足を思い切り地面に叩きつけた。
靴底の内側の角を地面に擦りながらブレーキをかけつつ、やや左へと軌道を修正する。
そして、あと一歩
「あああぁッ!!」
私は思い切り腕を突き出した。
──────────────────────
今回長くなりそうなので一旦区切ることにしました
後半部分はまだ書けてないので完成し次第投稿します
(勢いのある文章を書くの難しい……)



 <隔月になったらしいぜェ、くーっくっくっく
<隔月になったらしいぜェ、くーっくっくっく
私がササコを突き飛ばした一瞬後、目の前をセルリアンのナイフが横切った。
間一髪だった。
すぐそこまで迫っていた風切り音に気がついて咄嗟に身を引き、しりもちをつくことでなんとか致命傷は避けられた。
この攻撃で受けた被害といえば、右手の袖が犠牲になったくらいだ。
ササコは……大丈夫、ちゃんと生きてる。
突き飛ばした時に強く頭を打ったりしてないといいけど。
今はそんな心配をしている余裕はない。
早く二人でここから逃げなければならない。
左手を地面につき、立ち上がる。
その時、妙に右手が重い感じがした。
私は気にせずにササコに駆け寄ろうとしたが、動こうとすればするほど重力が強くなってしまう。
そこには、確かに真下に引っ張られるような強力な重力があった。
そして、それはいつしか体全体に広がっていって。
私はとうとう膝を折ってしまった。
こんなことをしている場合じゃないのに……!
突然の重力の発生源と思われる右手の辺りに目をやる。
そこには、別段変わったものは無かった。
あるのはさっきセルリアンに切り裂かれた服の袖だけだ。
首の皮一枚でなんとか繋がっている袖口だけ。
真っ赤に染まる袖口。それだけしかない。
あれ?
「なん…で……?」
本当ならそこにあるはずのものが、無いことに気づいてしまった。
なんで? いつから?
私の右手がどこにも見当たらない。
「あ……あ……」
まるでいつか見た悪夢のような出来事に、非現実感を覚える。
これが夢なら、このまま覚めるだけ。
夢じゃなかったら……?
ササコ……。ササコをたすけないといけない。
今すぐ立ち上がって、私がササコの手を引いて逃げるんだ。
これはきっと夢なんかじゃないから。
だから、早く立たないと。
もう一度左手を地面について、自立を試みる。
「ふっ……、ん、ぐぅぅ……!!」
でも、どれだけ頑張っても、力なんか入らない。
早く、まだ動けるうちに足を立てないと。
じゃないと、すぐに間に合わなくなる。
私は気づいてしまったから。
これは、酷い怪我。
下手したら今度こそ死んじゃうかもしれない。
それくらいの大怪我だ。
怪我にはその度合いに見合った、当然の痛みが伴うはず。
痛いのがどれだけ痛いのか、私は知っている。
これからだんだんと痛くなっていって、きっとすぐに動けなくなるだろう。
だからその前に……。
私がもう一度左手を地面に這わせた時、目に映ったものを見て、一気に血の気が引いた。
ああ……だめだ。
そこら一体に拡がった、赤色、紅色。
私の内側をひたすらに彩る、本物の赤。
その色はとめどなく拡がっていた。
一度引いてしまった血の気は、二度と戻ってはこないのだろう。
一気に冷めてしまった断面の熱が、次第に痛みを訴え始める。
私はこれ以上熱が逃げてしまわないように、左手で傷口の上あたりを押さえつけた。
でも、上手く力が入らない。
こうしているうちにも、痛みは強くなっていく。
泣きたいくらいに、強くなっていく。
呼吸も、段々と荒くなってくる。
そろそろ……このくらいで、止まったりしないかな……?
私のそんな諦め半分の期待は、すぐに裏切られた。
まだ、もっと痛くなる。
一回脈動する度に、断面に激痛が走り、無いはずの右手が疼いた。
身体中が痛い。
両目から冷たいものが零れ落ちた。
泣いたって、許してなんかくれない。
私はもうどうしようもなくなって、地面にうずくまってしまった。
これは、きっと痛みに耐える体勢。
少しでも早く体勢を立て直して、ササコを連れて逃げる。
そのための体勢なんだ。
そうやって、無力な自分に言い訳をする。
本当は怖かっただけなのに……。
他の誰かが傷つくのを見るのが怖かった。
他でもないササコが、目の前で二目と見れない姿になるのが怖かった。
大切な友達の最期を看取るのが嫌だった。
だから目を背けた。
私は本当に、私は……。
ふいに、声が聞こえた。
それは喉が捻れて裏返ったような、酷く耳障りな音だった。
呻くような声は、歪すぎて何を言っているのか全然分からない。
これが私のものなんだと気づいた時、それとは別の声が頭に響いてきた。
『立って 』
声は言った。一言、私に立てと。
優しい声で、無理難題を押し付けてくる。
こんなにたくさん血を流したら、もう立ち上がるどころじゃないなんてことは、私にだって分かる。
誰だか知らないけど、いい加減な事を言わないでほしい。
私は痛みを理由に、攻撃的な感情をぶつける。
声はそんなのお構い無しに続けた。
『顔を上げて、ちゃんと見て』
見るって、何?
私に何を見せようっていうの?
私はとうとう一人で会話を始めてしまった。
これも現実逃避の手段のひとつだったのかもしれない。
『ササコちゃん。……今も一人で、戦ってる』
ササコが……?
戦ってるって、無事なの……?
『今はね。でも、このままじゃ危ないの』
自分に嘘を吐いてまで逃避させるつもりなら、どうしてここで現実を見せようとするのかが分からない。
でも、だからといって、この声が本当のことを言っているということにもならない。なるはずがない。
だからこれは、きっと私の願望なんだと思う。
僅かに残された可能性に縋り、希望を見出そうとしている。
私はこんな状況に陥ってもまだ、諦めきれていないようだった。
『大丈夫だから、わたしを信じて』
信じるよ。あなたを信じる。
裏切られた時のことなんか絶対に考えたくないから。
私は歯を食いしばり、軋む首を持ち上げた。
目を開き焦点を合わせる。
「─────っ!」
揺らぐ視界の中で、一番に見えたものは、たった一人で強大な敵に立ち向かうフレンズの姿だった。
ササコはまだ生きてる……!
未だ五体満足な彼女の姿を認めた瞬間、私の脈は加速した。
より効率的に、全身に痛覚が伝達されていくのを感じる。
甚大な痛みと焦燥に駆られて、今すぐにでも擦り殺されてしまいそう。
そんな時、私の頭にまた声が響いた。
彼女は落ち着いた口調で問いかける。
『あの子を助けたいんでしょ?』
答えるまでもなかった。
ササコを無事にここから逃がせるのなら、この身がどうなったって構わない。
だけど、そのために自分に何が出来るのだろうか?
一人で立つことすらままならない、今の私に……。
『わたしはあなたを助けたい。だからそのために、あの子を助ける手伝いをするのよ』
次に響いたのは突拍子のない言葉。
声が何を言っているのか、よくわからなかった。
彼女が何者なのかも分からない。
それを私の一部分とするならば、きっと誰でもないのだろう。
ぼんやりと、私の中にいる何か。
それが『自分を犠牲にするようなことは絶対に許さないからね』と一言付け加えた時、私は何となくその正体がわかった気がした。
それは、本能だった。
極限まで追い詰められた主を守るために、外側まで這い出てきたのだ。
彼女が私の本能の一端を担うような存在であるのなら、自分の命を蔑ろにするようなことを許すはずがない。
でもそれなら、どうしてササコを助ける手伝いをしてくれるのだろう。
私みたいな臆病者の本能なんか、きっと自分本位に決まってるのに。
『あの子と一緒にいる時のあなたが好きだから』
本能(?)はそう言った。
どうやら思ったことは口に出さなくても(そもそも今は言葉を話せる余裕はない)伝わるらしい。
にもかかわらず、否定を一切しないところを見ると、彼女は本当に私の本能なのだろう。
『それでね、わたしにひとつ作戦があるの。あなたにはちょっと頑張ってもらうことになるけど、できる?』
本能が言う。
作戦とは、ササコを助けるための作戦だろうか。
自分の中の本能に『できるか?』とか訊かれるなんて、だいぶおかしい気がするけど、私はササコのためならなんだってするつもりだ。
『そっか…じゃあ話すわね。あなた、"わたしのナイフ"はまだ持ってるよね?』
……?
そんなものは持ってない。
自分の持っていたナイフは、とうの昔に何処かに落っことしてしまった。
『無いの…?! ええと、じゃあ……あそこに刺さってる看板でいいか。あれを引っこ抜いて、セルリアンの後ろにこっそり回るの』
看板……さっき転びかけた時に、そんな感じのものがちらっと見えた気がする。
あれのことだろうか。
『そう、それよ。それで、後ろに回ったら看板を叩きつけて、やつの頭をかち割るっ!』
あまりにシンプルな作戦。
看板で頭を……?
そんなこと、本当にできるの?
『ねえ……あいつの頭、けっこう脆そうじゃない? ヒビまで入っちゃって、まるでガラスみたいね』
確かに言われた通り、セルリアンの頭(?)には何本にも枝分かれした大きなヒビが入っている。
そんなこと、言われるまで全然気が付かなかった。
『どう? できそう?』
……できない。
さっきから何度も立ち上がろうとしてるけど、体が全然言うことを聞かない。
『まだ痛いの? それも、立てないくらいに』
痛、い……?
……ああ、そうだ、痛いんだ。身体中が痛くてたまらない。
だからずっと、私はこんなにも耳障りな声で唸っていたのか。
いつの間にか忘れてしまっていたみたい。
そして、忘れたままならなお良かった。
だけどもう遅い……。
『今から私の言う通りにして。そうすれば、少しは楽になるはずよ』
もう、思考をする余裕も無い。
呻き声で返事をする。
『よし! じゃあまず、声を抑えて。できる?』
首を横に振る。
『いいえ、やるのよ。それくらいできてもらわないと、……ササコちゃんを助けたいんでしょ?』
「グゥ……ぅ……」
『そう、その調子。……大丈夫? まだできるかしら』
今度は、縦に……
『いい子ね。次は、ゆっくり息を吸って、吐く。深く深呼吸をするの。ほら、吸って……吐く』
「ゔぅ……ッ……え゙ぇ……」
『辛いわよね……。けど頑張って、ほらもう一度、吸って……』
「ふッ……うぉえぇ…! ゲホッ!」
むせかえるような血の匂いに、吐きそうになりながらも呼吸を続ける。
促されるまま、一回、もう一回と繰り返す。
そうしている内に、最初は呻き混じりだった呼吸は段々と安定していった。
声だったものは熱になって蒸発していき……。
『どう? もう痛くないんじゃない?』
少し良くなったけど……でも、まだ痛い。
『ちょっと血を流しすぎたのかもね。今はもう止まっているけど……動けそう?』
本当に、本当に少しだけ全身の痛みが引いていた。
その差は微々たるものだったけど、今ではかろうじて思考ができる程度にまで落ち着いている。
これなら何とかなるかもしれない。
左の膝を立てる。続いて、右足も。
これだけではまだ足りない。
私は左の手のひらを、ちょうど足と足の真ん中辺りで地に付ける。
そこまでしたところで、今の自分の体勢がどこかおかしいことに気がついた。
これでは足に上手く力が入らない。
いつもはどのようにして立っていたのだろう。
意識すればするほど、正しい体勢がわからなくなる。
少し考えて、私は左足だけを崩すことにした。
そして、左手は足の間ではなく、左手やや前方に置く。
私は各部位が定位置に着いたことを確認し、足と腕に一斉に力を入れた!
視界が少し高くなり、その直後に急降下。
私は右足を前に出して、前に倒れ込みそうになるのを何とか踏みとどまった。
立てた……!
両の足がぷるぷると震えるけれど、私はなんとか自立することに成功した。
『生まれたてのフレンズって感じね……』
それまで黙って私の一挙一動を見守っていた本能が、突然口を挟んできた。
何やらよく分からない喩えをされたが、今はそんなことはどうでもいい。
私は看板が突き刺さっている方を見た。
ほんの数メートルが、とても遠く感じられた。
「くッ……!」
立っているだけで体のあちこちが軋む。痛い。
こんなにも足が重たいのに、体幹は安定せずに視界がふらつく。すごく気持ちが悪い。
戦う前から満身創痍だ。
それでも私はやらなくてはいけない。
人生における数え切れないほどの内の一歩を、今ここで成し遂げるのだ。
私は大岩のように重たい足を、その意思ひとつで持ち上げた。
下へ、強く引っ張られる。
それを一歩分前へ運び、落とす。すると、ガクンと。
耳には聞こえないけど、そんな音がした。
それと同時に全身から力が一気に抜けていく。
一度視界が大きくぶれて、そのまま地面に激突した。
『ちょっと、大丈夫!? どうしたの?!』
──お腹がすいた。
『お腹がって……こんな時に何言ってるの……?』
歩けない。立っていられない。
本当に、辛いの。
『……』
冗談とかじゃなくて、もう、本当に……
『そう……そうよね……』
何かを悟った気がした。
無意識に、心の奥深くに刻まれてしまった定型文を指でなぞっていた。
これでずっと、一緒に……。
「おねが…い、……ササコ……わたし、を──」
『待ってッ!!』
「──っ!」
本能が叫び、我に返った。
私は今、一体何を……。
『お腹がすいたんだよね?』
本能が私の思考を遮るように訊いてきた。
そんなこと、今更答えなきゃいけないの?
空腹のせいかまた攻撃的になってしまう。
『ササコちゃんを助けたいんだよね?』
更に問い続ける。
次から次へと何?
いちいち声に出さなきゃ分からないの? あなたは私の一部なのに。
これらは全部、自分に向けた言葉、自虐のつもりだった。
それなのに罪悪感を感じてしまうのはどうしてだろう。
『だったら──』
本能はそこで一度言葉を区切り、少しの沈黙の後、短く言った。
『それを食べて』
──え……?
「食べる、って……」
目の前に差し出されたそれは、とても見慣れたもので。
私は無意識のうちにそれを握りしめていた。
指を絡めて、手を繋いでいた。
自らの欠損した断片と。
「──ッ!」
そんな、どうして…… なに、これ……!?
私は左手を振り回した。
力いっぱいに、かつての自分自身を拒絶する。
だけど離れてくれない。
手に指に力が入ってしまって離れないのだ。
それを理解していながら、私にはどうすることも出来なかった。
固く結ばれた手は、必要以上にグロテスクに見えてしまったから。
怖い。気持ち悪い。
冷たい手の感触が、消えてくれない。
『……ごめんね』
諦めたような、悲しいような声だった。
その声を聴いた瞬間から、急速に肩の力が抜けて行った。
そして、繋がれていた手が、今再び解かれる。
冷たいものが指の間をするりと抜けると、そのまま地面に落ちて、ぴしゃんと音を立てた。
『そんなこと、……できるわけ、ないわよね……』
そう言ったきり本能は口を閉ざしてしまったけれど、まだ彼女の息づかいだけは聴こえているような気がした。
苦しそうなのに安らかな、聞いていると泣きたくなるような弱々しい息吹を、私は心で感じていた。
「…………」
なんだか彼女の"お願い"を聞いてあげなきゃいけないような気がして。
私はすっかり赤くなってしまったそれを、もう一度、今度は意識的に拾い上げていた。
やっとの思いで手放せたのにな……。
震える手を口元まで持っていくと、胸が締め付けられるような感じがした。
これを食べれば、ひとまず空腹はおさまるだろう。
でも、もしそれをしたとして、私はササコとこれまで通りに過ごすことが出来るのだろうか。
不安だった。
なにか大切なものを失ってしまうような気がして、食べるのを躊躇ってしまう。
私は、たった今も無謀な戦いに身を投じているフレンズを見上げた。
「……」
──ここで大切なあなたを失うくらいなら、私は……。
まだ迷いは消えない。
だけど独りになるのはやっぱり怖いから。
私は目を瞑り、息を飲み込んだ。
指先達が唇に触れる。
今からこれを、噛み砕くんだ……。
固い口を何とかこじ開けて、何れかの一本を押し込む。
口内に入ってきたそれに恐る恐る舌を這わせると、想像通りの血の味がした。
その味や異質な舌触りに一瞬吐き気を感じたが、何とか我慢する。
吐いてはだめ、食べなくてはいけないのだから。
「ゔぅ……」
私は一旦、指を口から引き抜いた。
悠長になんかしていられない。
だけど、これが自分の一部分だったものであるという認識を、どうにか改めないことには、噛み砕くこともままならない気がした。
それならと、すぐさま解決策を考え始める。
……もし、自分のがダメなら、別の誰かだったら。
例えばこれは、ササコの右手首。
そう思い込んでみるのはどうだろう。
『ねえ……』
私はササコのだったら、きっと拒むことなく受け入れられるから。
口に含んだら最後、歯に少しの抵抗も感じさせないまま、噛みちぎれて、そのまま舌の上で溶けていくだろう。
そうなれば咀嚼する手間も省ける。
『何を考えてるの……?』
しかし、一見合理的に思えなくもないこの案には、ひとつの問題点がある。
これら全てが妄想上のことであると前提したとして、その妄想の中では私がササコを食べているのだ。
脅しなんかじゃなく、本当に。
それは彼女を殺すということに他ならない。
死ねば形を完全に失うから。
誰かを食べようとするなら、その時とどめを刺すのは他でもない私ということになる。
…………
……だけどこれは、あくまで気持ちの問題。
別に、実際にするわけじゃない。
想像上の出来事なんて、夢の中で起きる事と大して変わらない。
だから大丈夫。
私は今からササコの血でこの手を汚すことになるけど、本当のササコは絶対に助けるから。
だからどうか許して欲しい。
私は一方的に捲し立てると、物言わぬ幻影を手にかけようとした。
その時だった。
『イシちゃん……』
「──……え?」
殺意を持った手が止まる。
不意に聞こえたそれは、どこか聞き覚えのある響きだった。
知ってるような、本当は知らないような、掠れていて思い出せない記憶の底。
あれ……? どうして……
だって私は、あなたが……あなた、に……。
大切だったはずなのに。
今だって、まだ大切に思ってるはずなのに、彼女のことが思い出せない。
あなたは……誰?
本当の名前すらも分からない。
私は、思っていたよりもずっとたくさんのことが思い出せなくなっていた。
不意に視界がぼやける。
泣いているのだろうか?
それももう分からない。
鼻がつんとする感じも、まつげに水滴が乗る感覚も、何も無い。
ただ、驚くほど頭が軽くて。
身体も、軽くて。
なんだか意識が朦朧としているなあ、と思った。
『わた……が……違ってたみたい……。やっ……り、あな……には……が重かった』
「な…に……?」
部分的には聴こえていたはずだ。
だけどもう、途切れた断片の声を繋げるだけの気力も残されていない。
『あとは、わたしにまかせてね』
遠のく意識の中で、唯一完成された文字列。
その言葉の意味を理解する間もなく、私は深い眠りに落ちた。
まだ続きます
──side A────────────
おやすみ。
イシちゃんが目を閉じてから、わたしはそう言ったけど、多分彼女には聞こえてなかったと思う。
だって彼女はもう眠ってしまったから。
深いかもしれない。浅いかもしれない。
そんな曖昧な眠りの中で彼女が夢見るのは、きっとあの子のことばかりだ。
いいな……。
ちょっとだけ嫉妬してしまいそうになる。
……と、いけないいけない。
彼女は頑張り屋さんだから、きっと直ぐに起きてきちゃう。
だからその前に、全部終わらせてしまわないと。
わたしは目を覚ますべく、そっとまぶたを持ち上げた。
「……っ……!」
強い刺激を目の奥に感じて、咄嗟に光を遮断する。
すごく眩しかった。
視界に入るもの全ての、色かたちともに判別がつかないほどに。
きっと、生まれて初めて目を開けた時も、わたしはこんな痛みを味わったのだろう。
突き刺すような眩しさに、今にもこの目を潰されてしまいそうだけど、こんな程度のことで立ち止まってはいられない。
わたしは覚悟を決めて両目を開いた。
「んー…………」
再び映し出された煌びやかに渦巻く色々。
瞬きを何度か繰り返していると、乱れていた光彩が次第に安定の色を見せ始める。
「よし!」
言った瞬間、そのあまりの声量にちょっとびっくりした。
でもすぐに気を取り直す。
この自分の声がやたらと大きく聞こえてしまう問題も、きっとすぐに解決する。
少し待てば正常になるだろうけど、そんなことより今はすべきことがある。
今のわたしは、イシちゃんの替わりなのだ。
いや彼女そのものなのだ。
ぐへへ……じゃなくて、えっと……。
わたしは地面に視線を這わせる。
そして。
「──あった」
見つけたそれを拾い上げた。
イシちゃん曰く、これはササコちゃんの右手首……。
さっき、彼女がそう認識しようとし始めた時、その心の中はひどく混沌としていて、見るに堪えないものだった。
まさかわたしの一言で彼女をあんな風に追い詰めちゃうなんて、思ってもみなくて。
でも本当はすぐに気づくべきだったんだ。
自分の体の一部を食べろだなんて、そんな猟奇的な提案を受け入れること、"わたしたちに"出来るはずがないのに。
特にイシちゃんは血が濃くなってるはずだから尚更、自傷的なことは許されなかっただろう。
その結果として、わたしはもう少しで彼女の心を殺してしまうところだった。
「……」
イシちゃんはたくさん傷ついて、ようやくここまで戻って来た。
きっと何度も痛い思いをしてきたはず。
でもこれを食べれば、また少しだけ濃くなってしまう。
また、彼女を苦しませてしまう。
そして、また……鬱々とした日々に帰してしまうかもしれない。
やっと大切なものを見つけられたのに。
「…………」
わたしはなんとか立ち上がれないものかと、地面に左手を着いてみた。でもだめだった。
お腹がすいて力が入らない……というより、そこに何も無い感じがした。
体の密度があまりに低くて、空腹すらも感じないのだ。
ふと、さっきイシちゃんが言いかけていた言葉を思い出す。
"「おねが…い、……ササコ……わたし、を──」"
この先に続く言葉がどのようなものなのか、わたしは知っていた。
だから咄嗟に引き止めた。
だけどやっぱり、今のイシちゃんは一人分にも満たないんだ。
このままじゃ彼女は、きっと……。
死にゆく友達をを前にしたわたしにできることは、もう二つしか残されていなかった。
これからするのは、とても重い決断だ。
わたしは心を決めるために、一度座り直した。
「……?」
体勢を変えた際に、左の太ももの辺りに違和感を感じたが、その正体に気づいて口元が緩んだ。
「なんだ、持ってるじゃない」
もう、迷いは消えていた。
さっきイシちゃんがしたのと同じように、右の人差し指を咥えると、もう血の味はしなかった。
これは愛しい友達の味だ。
「ふふ……」
このままでいれば、あなたはあらゆる苦しみから解放される。
でもわたしは、今から自分の都合であなたをもっと苦しめるよ。
「…………」
『ササコちゃん。……イシちゃんを、お願いね』
わたしは思いっきり、顎に力を入れた。
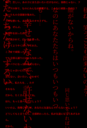
関節部がミシミシと音を立てると、皮が破けて、口いっぱいにイシちゃんの味が拡がる。
そして──
次々と染み出してくるのは、どす黒い感情。
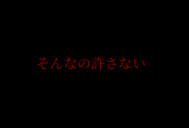
舌をつたって、喉を通って、お腹の底へと落ちていく。
それはまさしく、純度の高い悪意だった。
"わたしたち"が決して抱くことの出来ないくらいの、許容量を遥かに超えた悪意。
少し気を抜くだけで黒い感情に呑まれてしまいそうになるのを、必死に耐える。
こんなものに耳を傾けてはいけない。
自分にそう言い聞かせて、また飲み下す。
何度も何度も、噛んで、飲み込んで。
この単純な作業を繰り返しているうちに、だんだんと身体に震えを感じ始めた。
怖いから震える。これもまた単純な理由だった。
これはわたしの心の中にある怯えなのだろうか。
もしそうじゃないのなら、どうか怖がらないで。
このぐちゃぐちゃしたものは全部、全部わたしが引き受けるから。
わたしのせいで今まであなたをたくさん苦しめたよね。
だからこれはせめてもの償い。
あなたはこれから、ササコちゃんやみんなと幸せに生きるの。
「アンタは黙ってろッ!! 」
やけつくように熱い喉にビリビリとしたものが走る。
絶対に誰にも邪魔なんかさせない。
イシちゃんを繋ぎ止めて、ササコちゃんも助けるんだ!
わたしはもう、何がなんだかわからないくらいに頭に血が上ってしまっていた。
先程まではヤツの悪意に負けじと慎重になっていたが、もう知らない。
わたしは手に持っていたそれを、めちゃくちゃに噛み砕いて、飲み込んだ。
また何やら声が聞こえてきたが、もうそんな戯言に耳を貸すつもりは無い。
もう少しで全部食べ終わる。
そう思った時。
「あの、えっと……」
突然、戸惑うような声が聞こえた。
それは冷たくて腹立たしいあの声とは違っていて。
気になってそちらを見てしまった。
「……?」
わたしの目に映った光景はなんというか、なんだろう。
状況がうまく理解できない。
ササコちゃんが目の前に立っていて、イシちゃんを見下ろしていて、わたしの手には、手には……。
これはなんだ?
もはや原型をとどめないこれは、確か──。
「ぁ……」
全てを理解した瞬間、急速に熱が冷めていくのを感じた。
冷めきってなお、冷える。
わたしは、とんでもないことをしでかしてしまった。
彼女に一番見せてはいけないところを見られるなんて。
どうしてこんなことになってしまったのだろう……。
ササコちゃんの顔がまともに見れない。
目が潤んできて、今にも溢れだそうとしていた。
この涙はきっとわたしのじゃない。
わたしは俯き、目を閉じた。
ごめんね、イシちゃん。
泣かないで。
わたしが絶対に何とかするから。
言い聞かせるように、心の中で呟く。
だけどこの言葉はもう彼女には届かないかもしれない。
わたしの心は既に形を変え始めていたから。
イシちゃんにはわたしだけいればいいとか思ってしまう。
死ななくてよかったわね、じゃあどこかへ行って。
そんな言葉、この口からだけは絶対に言えない。
「ご、ごめんね。……こわがらせ、ちゃった…わよね」
無意識に発せられるのは心にもない言葉。
その涙混じりの声は、まるで遠くで誰かが喋っているみたいに客観的で、耳も遠い。
だめだよ、イシちゃん。まだ寝てないと。じゃないと、あなたはきっと傷ついちゃうよ。
『わたしがいるから。ずっといっしょにいてあげるから……』
もう目を開けることも出来なかった。
意識がだんだんと重くなっていく。
どす黒い液体を吸って、深く深くへと沈んでいくようだ。
この声はもう誰にも届かないのだと悟った時、あの冷たい声の主の気持ちが、ほんの少しだけ分かった気がした。
────────────────────
「ご、ごめんね。……こわがらせ、ちゃった…わよね」
私は我を忘れて、一心不乱に自分の一部だったものに齧り付いていた。
こうしてササコに声をかけられるまで、ずっと。
最初はササコと一緒に逃げるためだったのに、そのササコのことを忘れるほどに血肉を欲していたことが、怖くてたまらない。
だけどそれ以上に怖いのは……。
「ゴイシシジミさん……、」
「そ、そんなことより! ……あなた意外と強いのね。びっくりしちゃった」
本当に、ササコはすごい。
あんなに大きなセルリアンを一人でやっつけて。
未だ……私の前に、立っている。
こんな血まみれの口元を見ても、まだ。
……もしかして、また昨日までみたいに、過ごせるのかな?
まだ、ササコと一緒にいられるのかな……?
もし彼女が何事もなく接してくれたなら、私は元に戻れる?
右手はなくなっちゃったけど、また、いつもみたいに……。
「……!」
「あの、腕……」
「…………私は……あなたと同じフレンズよ」
私が声に出したのは、心にもない言葉だった。
今まで意識しないようにしてきた。
でも、押し込めて隠そうとするほど、それは深く根を張った。
私はきっとササコ達とは違う。
「……」
切り落とされたはずの私の右手が新しく生えていた。
首の皮一枚だった袖も綺麗にくっついていた。
だけど、セルリアンと戦ったササコだけが……傷ついている。
服なんかもう、初めて会った時からずっとボロボロのままで、治る気配もない。
そして今日、ササコはまた……。
俯きながらもかろうじて見える彼女の傷跡。
それは小さな傷だったけど、やっぱり赤い血が流れていて、きっと痛いのだと思う。
私はその赤いのがどうしようもなく見ていられなくて、更に視線を落とした。
そんなことをしたのは、たぶん目を逸らしたかったからだ。
脳裏に焼き付いた真っ赤な両手と、自分と彼女の違いから。
逃げたって何も変わらないのに。それでも直視はできなくて。
すっかり落ち込んでしまった視線の先には、左右で大きく質感の違う履物があった。
ササコの左の足には、ほとんどが砕けてヒビだらけの、鎧っぽいものが。
そして右足には私のとよく似た靴を履いていた。
元々はこっちの方も鎧に覆われていたのかもしれない。
そう思ったら、急に心臓が抉られるような感じがして泣きたくなった。
もう痛くなんかないのに、痛いのはササコなのに。
なのに、なのに…。
背けようのない事実が重くのしかかって、軋む。
私はこんななのに、どうしてこんなにも無力なんだ。
「…………」
未だ私の前に居続ける少女は、もう何も言わなかった。
ただそこにいて、きっと私を見つめていた。
怖いはずなのに。
今すぐに逃げ出したいはずなのに、彼女はまた自分を殺そうと言うのか。
こんなに優しくて、自身の危険を顧みない。
そんなササコに私は何を言えばいい?
逃げてもいいなんてことはもう言えない。
言いたくないんだ。
……だったら、何か弁解するのはどうだろう。
ササコが今夜も安心して眠れるように、私が、この……血塗れの口で……?
信じてもらえるとは思えない。
じゃあやっぱり、こっちの血塗れを後ろ手に隠して、何も無かったって言い張ってみる?
そうしたら……見逃してくれるかな?
それでもダメなら今ここで、ササコの目の前で、この手が生えなくなるまで切り落とせば……。
いや、そんなのは絶対にダメだ。
もしそんなことをすれば、彼女を余計に怖がらせるか、悲しませてしまう。
悲しんで、くれるのかな……。
ろくな考えが浮かばなかった。
足りない頭でいくら考えたって、思いつくのは普通とは程遠い愚案ばかり。
諦めきれない。
でも、ササコの気持ちは無視できない。
いつまで経っても弁解の言葉なんか浮かばないから。
私は彼女に、ササコにこの場の全て委ねることにした。
ずるいかもしれないけど、今の私からはきっと、取り繕うための嘘や誤魔化ししか出てこないから。
目を瞑り、一度浅く深呼吸をしてから、顔を上げる。
すごくドキドキした。
私は鼓動が少し穏やかになるのを待ってから、目を開いた。
「ぅ……」
一瞬ぼやけて鮮明になる。
そうして一番最初に目に入ったのは、ササコだった。
目の前に、ササコがいた。
そんなこと、ずっと分かっていたのに。
でも、どうしようもなく嬉しくて。目頭が熱くなった。
ササコがここにいてくれる。
もう一度、生きて再会することができた。
彼女は俯いていて、どんな顔をしているか分からないけど、今ここにいるのは間違いなくササコだった。
夢じゃないんだよね……?
自分の頬をつねることもせず、私の両手は、自然とササコの方へと伸びていた。
確かめたい。
その手に、髪に、頬に触れて、ササコがここにいることをちゃんと認めたい。
この手で、ササコの体をぎゅっと抱き締めて、確かな体温を感じたい。
もしそんなことをしたら、今度は本当に泣いてしまうかもしれないけど。
だけど止められなかった。
真っ直ぐと伸びていく。
気持ちがはやって、また鼓動が加速する。
もう少しで、届く。
それなのに。
やっぱり、だめだ……。
伸ばしたそれは赤く汚れきっていて、触れるのをためらわれた。
言葉でササコを安心させることも、彼女に触れることも叶わない。
今の私は無力を通り越して無だった。
何も無い、何も出来ない。
ササコはこんなにも、拳を握りしめるほど必死に言葉を探してくれているのに。
地面を睨みつけて、拳をぎりぎりと締めて、その手のひらにはきっと爪の跡がついているのだろう。
そんな彼女の様子を見ていると、自然と笑みがこぼれた。
笑える要素なんかひとつも無い。
だけど私は微笑んでいた。
それは何も出来ない私の……諦めだったのだろう。
20話終了