小説書いておくとこ
下書きのこともあるかも
※私は西尾維新先生をリスペクトしているので、作品も西尾色が強いです。ご了承ください。
進捗とかは自活の方に書くと思います。
『みつりソウル』(完結)
前置き>> 1 本編>> 5 >> 7 >> 8 >> 9
『フレンチトーストの香りとともに(仮)』(現在進行中)
本編 零>> 10 壱>> 11 >> 12 >> 13 弐>> 14 >> 15 参>> 16 肆>> 20 >> 21 伍>> 31 陸>> 32 >> 34
週一ペースで更新します
感想とか気軽にどうぞ(*'ω')
このページの文章・設定等の著作権は全て私(6×6=36)に帰属します。無断転載は御遠慮ください。


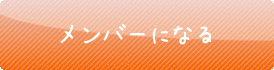





ラストにある曲が合うようにルーズリーフ二枚で小説を書くというリア友内の企画日向瀬 風翔 にクラスメイトの弐栞 みつり が語る、冴凪 高校の怪談とは・・・?迫真の二段組み(原稿が)で送る季節外れの短編小説!
あらすじ
『みつりソウル』(←サブタイ)
ある夏の日、「僕」こと
たぶん明日から更新。
そしてそれが私w
のせてくれてありがとーー!1000万超えの曲です
描いてくれたやつコピーとって返すね~
そして私も小説を、、、
企画 とちまる
d('∀'*)りょ、ありがお
確かに西尾色強いけど好きだわ~
ある曲ってこれ
みつりソウル
「人魂の噂、聞いたことあるかしら?」
昼の休み時間、僕の後ろの席に座る弐栞は、唐突にそう話しかけてきた。
おもむろに振り返りつつそれに応える。
「人魂?何のことだ?」
「やっぱり知らないのね。日向瀬君、そんなことじゃ、すぐに時勢に取り残されるわよ」
余計なお世話だ。
そう思いつつ強引に話を戻す。
「――――学校の七不思議みたいなもんか?僕はそんな話、入学してからこっち、聞いたことないけど」
「そうね。無人の教室で鳴るピアノとか、動く骨格標本とか、そういう類の話、この高校にはまるで無いわよね」
「だよなぁ」
例がベタすぎて、いまいちぞっとしない。
「で、その人魂とやらは別なのか?」
「別――――というか、その怪談のせいで他の怪談が生まれない、という感じかしら」
弐栞も確信を持って話している訳ではないらしく、要領を得ない返答だった。
「えっと――――」
話を整理すると、肝試しをしようと深夜に学校を訪れた生徒――――どこの学校にも少なからずいる人種のようだ――――が、いざ夜の校舎へ乗り込まんと(不法侵入)すると、必ず現れるそうだ。
目の前に、ぼんやりと光る人魂が。
大抵の人間はそこで怖気付き、校舎へ近づかない。それ故に、この学校に七不思議のようなものが存在しない。ということらしい。
人魂。古くから言い伝えられている怪異で、その名の通り、人の魂が体を抜け出したものらしい。人の魂でなく霊だが、鬼火、狐火なども似たものとして挙げられるだろう。
「ね?日向瀬君が気に入りそうな話と思って」
先日、とある事件をきっかけに知り合うことになった黒髪の少女は、そう言って微笑んだ。
確かに、僕としては気にせざるを得ない話だ。
「良かった。それにゃっ」
?
弐栞は下唇を嚙んで悔しげにこちらを睨んでいた。
嚙んだらしい。
「嚙んでなんかいないわよ」
何もなかったかのように、すまし顔でそう言われた・・・。
ここで「失礼。嚙みました」とか言っていたら可愛げがあるのに、なんて思った。
どこか抜けている奴なのだ。例えるなら、3ピースをぴっちり着込んでいるのに、足元がスニーカー、みたいな。彼女のその気質は、随分小さい時かららしいということは既に聞き及んでいる。
三つ子の魂百まで、という奴だ。
この魂は浮遊していないだろうが。
ともかく僕としては、この怪異現象を検証しない訳にはいかない。
そう伝えると弐栞は、
「ふふっ。そう言うと思った。楽しみにしてるわ」
「?」
そう言って、さっきと比べて意味ありげな笑みを浮かべた。
教室の窓から吹き込む潮の匂いのする風が、彼女の前髪を微かに揺らした。
その光景と微笑みがやけにマッチしていてなんだか、僕の心臓を直接撫でられたような心地になった。
次章は後日。
そんな会話から少し時間が過ぎ、太陽が地球の裏側の天上で輝いているであろう時、僕は再びいつもの通学路を歩いていた。
現実的に考えてしまえば、防犯用のライト――――センサーで光るやつ――――とかが真相なんだろうが、それでも、現実でなかった時を考慮しないわけにはいかない。
内心そわそわしながら僕は、僕達の通う市立冴凪高等学校の正門の前に辿り着いた。
少し予習をしてきた。
人魂は、古くは万葉集から存在しており、人の体から魂が抜け出した魂。地域差があるが、あまり高くは浮遊せず、色は青や白、赤色が主で、尾を引くらしい。
代わって鬼火は、人だけでない霊や怨念が現れたもので、青や赤に加え、黄色もあるらしい。
そして狐火は、少し趣を異にしていて、列をなす火であるらしい。
そんな御託はともかく、と僕は頬を張って気を引き締め、そう高くない校門に手をかける。
――――フッ
突然それは僕の前に現れた。
ぼんやりと、しかし確かに、その黄色い灯は遠近感が失せる程に僕の目前に現れた。否、灯った。
次章は後日
思い出したから更新
その姿だけでも、僕に危険を感じさせるには十分だった。
「――――っ」
瞬時に重心を後ろに動かし、右足で跳ねるように跳び退く。
尻を強かにアスファルトに打つが、気にしない。手と脚を接地し、臨戦態勢――――と言うには尻餅をついていてどうにも間抜けだが――――を取り、人魂――――鬼火か?――――を見据える。
否、見据えようとした。
そこには既に人魂の姿はなかった。その代わりに、
「――――クックックッ」
と静かな笑いが響き渡る。
何だ?
「クッ――――フフッ――――ふふふっ」
そこで、はたと気付く。
その笑いは火が灯った校門――――つまり前方――――ではなく、後方、否、僕の頭上から降ってきていた。
「あはは――――愉快ね」
昼間に聞いた声だった。
ひとまずその声を聞いて多少なりとも安堵した僕だった。
全く、傍点まで振った僕が馬鹿みたいじゃないか。
「弐栞。全部お前の仕業なのか?」
僕の頭上で未だに笑っているクラスメイトに、そう問いかけてみる。
「あら。人聞きの悪いことを言うじゃない、日向瀬君。私は人魂に怯える日向瀬君を観察しようと背後にいたけれど、日向瀬君の反応が面白すぎて、ついつい笑いが抑えきれなくなっただけよ?」
「・・・」
人が悪い。
「レディに向かって失礼ね」
心を読まれていた。
「私にかかればお茶の子さいさいよ」
なんだこの一方的な以心伝心。
「ま、ただ日向瀬君の思考を推理しているだけなのだけれど――――それはともかく日向瀬君。もう一度校門に手をかけてみなさい?答え合わせをしてあげるわ」
暗に分かり易い奴、と言われた気もしたが――――もう一度?答え合わせだと?さっきは人魂は自分の仕業じゃないと言わなかったか?
「仕掛け人でなくとも、仕掛けのタネを知ることはできるでしょう。そんなことも分からないとは、残念な脳細胞ね」
「残念って言うな」
こいつの方が成績いいからなぁ・・・。
「ほら、もう一度校門の前に――――もう一度人魂と対峙しなさい。今度は逃げずに、ね?」
「・・・おう」
渋々、立ち上がって再び校門へ歩き、さっき人魂を見た辺りで立ち止まる。
フッ
「――――っ」
また、人魂が現れた。だが今度は退いたりしない。熱さを錯覚するほど目前の人魂に対峙する。
「――――あれ?」
すると、ふ、と人魂が消えた。
困惑していると、再び、ふと人魂が現れた。
「・・・」
ひとまず、観察してみると、どうやら人魂は3秒程の周期で明滅してる様だ。
まるで自分の存在を弱々しくも主張するように。
続きは後で
この小冒険のオチ。
件の人魂は、弐栞の言うところによると、学校から少し離れた岬、そこに建つ灯台の光が、校舎内を上手く反射し、2通りの光となり、校門の前の高さ1.5m程の位置で立体的に交わっている、ということらしい。
2方向から光が入るので、人間の脳は、それを一つの立体と認識し、目の前に人魂が現れるように見える、というからくりだ。
「ん?原理は分かったけど、あの岬の灯台って動いてたっけ?あそこはもう稼働してない廃墟だった気がするし、夜に光ってたら、ここでの生活も短くないし、僕でも気付くと思うんだけど」
「細かいことは気にしないの。それに、全部謎を解いちゃってもつまらないでしょう?」
「そういうもんか?」
「そういうものよ」
「あ、ところで、お前いつから後ろにいたんだ?家から尾行してた訳じゃないだろ?」
「そりゃそうでしょ。誰が好き好んで日向瀬君を尾行するのよ」
さいですか。
「私の家って日向瀬君の通学路の途中にあるのよ。気付かなかった?」
気付いていなかった。
いや、一緒に登下校していた訳でもないし、知らねぇつーの。
「部屋の窓から道を監視していて、日向瀬君が通った時に、窓から外に出て、尾行を・・・あっ」
「尾行してんじゃねえか」
首に手刀が飛んできた。
照れ隠しが洒落にならない女だ。
にしても何故窓から・・・。両親に気を遣ったのかな?ちなみに僕は堂々と(こそこそと)玄関から家を出た。
「とりあえず、一件落着、かな」
「そうね」
長話をしていた自覚もなかったが、僕らの帰路の先には、もう気の早い太陽が姿を見せていた。
薫る風に背を押され、僕らは2人並んで朝の陽へと、明日の日常へと歩いていく。
この後、弐栞は、何故か玄関から堂々と帰宅し、ご両親に大目玉を食らったそうだ。
三つ子の魂は、まだ、生きて漂っているらしい。
――――「みつりソウル」完
『フレンチトーストの香りとともに(仮)』
零
────あの出会いは、偶然か。必然か。
「はぁ・・・」未井幹斗 は疲れを滲ませた溜息を零しつつ、昼下がりの街並みを歩いていた。若干着られている感のある真新しいジャケットを脱ぎ、休息の場を求めて彷徨う。
残暑を感じさせる日差しの中、
念願の刑事部に配属されて早五日。人出が足りないとして組織犯罪対策部にレンタルされている幹斗は、連日聞き込みを手伝わされていた。やけに眩しい太陽の所為か、僕は何部になったんだっけか、と自分の記憶すら曖昧になってくる。
吹き抜けるそよ風が、街路樹のまだ夏の色を残した葉を揺らす。
そこで、ふと微かな香りが、アスファルトの匂いに辟易していた鼻腔をくすぐる。
これまで趣味の時間を多く持ってこなかった幹斗には、その香りが焙煎されたコーヒー豆のものだとは、まるで分からなかったが、その芳醇な釣り糸は確かに迷える魚を手繰り寄せた。
僅かな糸を頼りに、しばらく道を歩いた。
そして香りの源はここだろうと思しき、少し年季の入った煉瓦造りの建物に辿り着き、足元の「Cafe Asanoha 2F」という看板に従って側面の階段をのぼる。赤茶けた段のきぃ、という抗議のような音にも耳を貸さずに、幹斗は、開店を示す小さな看板のかかる木製のドアを開けた。
ドアを開けるとともに、芳醇な香りが奔流となって幹斗を包み込む。
そのささやかな幸せに体を預けるのもそこそこに、幹斗は店内を見やる。
向かって左手のすぐ手前には大仰な機械やコーヒーカップの置かれたカウンター、右手にはいくつかのシンプルな椅子とテーブルが並んでいて、窓に近い席には、二十歳くらいの男が一人窓の外を見るように座っている。
男は、入ってきた幹斗をちらりと一瞥したが、すぐに視線を戻した。短く刈られた頭と濃い赤色の半袖シャツは、落ち着いたこの空間にはやや不釣り合いにも見えた。
そしてもう一人。カウンターの奥にある、他とは違うアンティーク調の肘掛椅子に腰掛け、ハードカバーの本を読んでいる。幹斗とさして変わらない年齢に見えるが、綺麗にアイロンがけされているであろうシャツと、錫色のベストとズボンが誂えたように似合う男だ。
小さめの眼鏡をかけて本を読んでいた彼は、客の来訪に気付くと、一瞬、目を丸くしたが、すぐに本を閉じて立ち上がり、分厚い本を椅子の座面に重ね、柔らかな笑みを浮かべて幹斗に声をかける。
「いらっしゃいませ。お好きな席にお座り下さい」
「あ、はい、コーヒーひとつ」
「かしこまりました。フィルターでよろしいですか?」
「はい」
おざなりに返事と注文をすまし、近くの椅子に座る。コーヒーなど成人してから飲んだ試しもなかったが、とにかく今は、身体が水分を欲していた。
ようやく座って一息ついて、幹斗はたった今自分の注文を受けた男の顔をぼんやりと眺める。
整髪料で適度に撫でつけられた黒髪に、落ち着いた顔つき。細長い両手が、きびきびと器具を動かす。
「どこかで・・・」
彼の顔に要領を得ない懐かしさを感じ、ぼそっと呟いた幹斗の声は、彼がコーヒー豆を引く音にかき消された。
しばらくして、
「お待たせ致しました」
こと、と上品な音を奏でて、白い湯気をたたえたコーヒーカップがソーサーと共に着地する。
「あっ────」
儀礼的に礼を言おうと顔を上げて、固まる。幹斗の脳内に疑問符が飛ぶ。
彼の細長い左腕の先には、コーヒーを机に置いたにも関わらず、まだ白い皿が載っていた。
もう一人の男が何か頼んでいたようにも思えない。そう考え、彼の目を見やると、彼もその視線に気付いたように、
「あぁ、この皿ですね。お疲れのようだったので、不躾ながら軽食を、と思いまして」
そういって皿に載ったフレンチトーストを幹斗に見せる。鮮やかな山吹色の表面に、栗色の焦げ目が控えめながらもよく映えていた。その甘美な香りは、コーヒーよりも強く幹斗の鼻腔を惹きつける。
フレンチトーストは、幹斗の大好物だった。
「余計なお世話でしたら、すぐにお下げします。好物かと思ったのですが、違いましたか?」
幹斗の瞳を見返して、そんなことを口にする。
「えっと・・・あなたは・・・」
「何でしょう?」
「いえ────」
違う。僕がこの人に呼びかける名は、そうじゃない。
柔らかい細目。少し高めの声色。細長い手指。回りくどい気遣いと少し意地悪な笑み。何もかもが懐かしく、幹斗の脳細胞を心地よく刺激する。
意を決して、呼吸を整え、再び彼のチョコレート色の瞳に目を合わせ、できる限りの笑顔をつくり、こう口にする。
「久しぶりだな、白羽 」
白羽と呼ばれた男も、先程の様に柔らかに、しかし先程よりも快活に笑って応えた。
「そうだな、幹斗」
こうして、かつて大親友と呼びあった未井幹斗と白畑 白羽は、10年振りに再会を果たした。
壱
白羽は変わらないな。幹斗はそう思った。実に10年ぶりの邂逅だというのに、白羽も幹斗もまるで10年前、いやそれより前の、同じ教室で机を並べていた頃のように、気負うことなく会話を交わした。荒田利玖 、噂が独り歩きしてる部分があると思いますが、ここに寄せられる相談を受けているのは、私ではなく、主にこいつなんです」
「へぇ。お前が警察か。しばらく見ないうちに立派になったなぁ」
「年明けに会う親戚のおじさんかお前は」
「随分大きくなったねぇ」
「今度はおばあちゃんか。いったい何歳なんだよ。同い年じゃん。つーかお前の方がよっぽど背高いだろ」
「俺は永遠の12歳だよ。ちなみに身長は185ないくらい」
「いい歳して何言ってんだ。やっぱ背高いな────」
幹斗は白羽に会わなくなってからもしばらく成長していたが、それでも白羽に比べて10cmほどの開きがあった。
少し会話に間隙ができたので、今度は幹斗から白羽へ、この店について質問を投げる。
「あー、この店はもともと大学でできた友達のお爺さんの店だったんだけど、継ぐ人がいなくてさ。そこでその友達伝いで俺に話が来て。当時からコーヒー屋で働いてたから、願ってもない話だと思って働かせてもらってたん」
「なるほど。じゃあそのお爺さんは?」
幹斗は言いながら店内を見回してみるが、相変わらずテーブルにスマホだけ置いて、何をするでもなく窓の外をぼんやり見つめている赤い半袖シャツの男以外、視界に入る人物はいない。
「うん、まあ、あそこにいるはいるよ」
曖昧な返答をしながら、白羽はカウンターの奥を指し示す。
「あ・・・」
白羽が指し示したカウンターの奥の棚にある、小綺麗な縁に入った柔らかな顔をした壮年の男性の写真を見て、幹斗は言葉を詰まらせる。
「そう。矍鑠としたお爺さんだったんだが、去年に脳をやっちまってな。それ以来あそこで呑気に笑ってるよ」
「・・・すまない」
「構わんよ。遅かれ早かれ、誰の身にも訪れることだし、そのお陰といっちゃなんだが、それからはこの店は俺がやらせてもらってるからな」
そういって白羽は、一瞬見せた暗い影を落とした顔を、無機質な笑顔で上塗りする。その笑顔は、10年会わなかったといえども大親友である幹斗ですら、一瞬分からないほどに精巧に作られていた。
「えっと────」
「あ」
気まずい沈黙に耐えられなくなって口を開けようとした幹斗を制するように、白羽が声を零して幹斗が先ほど入ってきた扉に目を向ける。つられて幹斗も同じ方向を見やると、扉の奥から、こつんこつん、とのんびりとしたテンポで靴底が階段を叩く音が微かにするのを感じる。
「すまんな、また後で」
そう言って片手で謝罪の形を作ると、足早にカウンターへ戻る。すると、タイミングを図ったように緩やかにドアが開けられ、全体的に地味な色の服を着、重ねた月日の分だけ頭を白く染めた女性の姿が現れる。
「いらっしゃいませ」
自然な笑顔で女性を迎えると、女性もそれに応え、カウンターの席に座りながらなにやら話し始めるが、その控えめな声は、幹斗の耳には、明瞭には届かない。
カウンターの様子を窺うのを諦め、幹斗は思い出したように、目下でまだ湯気をたたえるコーヒーカップとフレンチトーストに目を向ける。なにも考えずにコーヒーを頼んでしまったが、コーヒー飲めないじゃん、と数分前の自分を責める。しかし、大親友が淹れてくれたコーヒーだし、飲めないことは無いはず、と自分を奮い立たせ、白磁のコーヒーカップの取っ手を掴みあげ、勢いよくその中に満ちる艶のある黄櫨染にも似た色の液体を口に含んだ。
「!」
意外にも美味しかった。口を通る液体は、高めの温度と心地のよい酸味と甘み、仄かな苦みを伴って舌を包み込む。やがて飲み下すと、街中で嗅いだ芳醇な香りが再び鼻腔をくすぐりながら通り抜ける。調子の付いた幹斗は、続いて右手をフォークに持ち替え、黄金色のフレンチトーストを食しにかかる。フレンチトーストは、適度なはちみつの甘みがよくパンの味を引き出していて、とても幹斗好みの味に仕上がっていた。パンの程良いしっとり感が堪らなく味覚を刺激する。
流石に、そのフレンチトーストが初めから幹斗のために作られていたと思うほど、幹斗は自惚れていなかったが、その慣れ親しんだ美味と新しい美味は、確かに幹斗の疲労を癒し、五分もしないうちに、ふたつの器は空気を載せるのみとなった。
空腹と疲労を失い、満足感に浸っていた幹斗は、なんとはなしに、再びカウンターの話し声に耳を傾ける。
「────ということなんです。なんとかお願いできませんか?」
「なるほど・・・えっと────」
体力の回復からか、先ほどよりは、明瞭に会話の断片が聞こえてくる。白髪の女性が何かを白羽に頼みこんでいるようだ。白羽は困ったように曖昧な笑みを浮かべている。
がた、と唐突に椅子を無遠慮に動かす音が、静かな店内に響く。音のした方向は、最初から店内にいた半袖シャツの男のいた辺りだ。不思議がって幹斗がそちらを振り向くより早く、男は幹斗の横を通り抜けて、カウンター席に向かい、ふたりに話しかける。横を通る瞬間、幹斗は男が笑みを浮かべていたように見えた。
「すみません、お話、横から聞かせてもらいました。俺が力になりますよ」
「えっ?あなたは・・・?」
男の突然の言動に、女性も驚かされているようだ。そこにやれやれ、といった笑顔で、白羽が助け船を出す。
「こいつは
「そうなんですか!どちらにしろ、孫をお願いします!」
「任せてください!」
「善処します」
素性が分かると同時に、女性は嬉しそうな声で、もう一度ふたりに何かを頼みこむと、「ありがとうございます。お願いします」と重ねて言って、慌ただしく席を立つ。
「ありがとうございました」
白羽はそう言って、帰る客を見送る。女性は再び謝辞を重ねてお辞儀をすると、扉の向こうへと消えていった。こつんこつん、と軽やかな音が遠くなり、再び店内が静かになったところで、幹斗は白羽に今のやり取りについて尋ねた。
「さっきのお客さんのお孫さんが、家出して不良みたいな連中とつるんでるから家に連れ戻してほしいってさ。いつからか、どこかの物好きの所為で、ここは街の人たちの相談所────万屋みたいになってるんだよ」
白羽はそう言って、となりで満足げな笑みを浮かべる男を見やる。
(壱の続き)
「はは、俺のことだな!俺は利玖。ここで居候してて、暇なときは大体ここにいて、人々の悩みや相談に乗る、心優しき────」麻澤 ふゆっていって、この建物の所有者。それとここのマスターの孫だ。アイドルみたいなことやってて、時々テレビにも出てる。この光景はいつもの景色」
「馬鹿だ」
店全体に響くような大きな声で得意げに自己紹介を始めた半袖シャツの男────利玖のセリフに、白羽が被せるように言った。
「ひどいこと言うなよ白羽~。俺とお前の仲だろ」
「最初は近所のお爺さんの家出した猫探しだったんだが、いつのまにか噂が広がって、こんな風に大きめの話まで来るようになった。しかも何故か俺に」
軽口を叩く利玖をスルーして、白羽が言う。普段は人の話を最後まで聞く白羽にしては珍しい行動だ。
「俺としては迷惑もいいところだ。威力業務妨害で訴えてやろうかと思っててな」
「ひぇっ」
辛辣な言葉を並べていても、白羽がそれを本気で言っているのでないことは、その表情を見れば幹斗でなくとも容易に分かるだろう。どうやら、この利玖という男と白羽は随分親しい関係のようだと幹斗は感じた。それを少し面白くないと思う自分を頭の隅へと追いやって。
割り切れない笑みを浮かべる幹斗をおいて、白羽は
「まあでも、そこのコンビニの店長が、不良がたむろするようになったって言う時期と重なるし、多少は動いたほうがいいかもな」
とひとりごちる。
かつかつかつ、と早いテンポで階段を叩く音が聞こえたのは、その時だった。
音がして間もなく、店の扉が勢いよく開く。扉の奥から現れたのは、三人と同じくらいの歳の女だった。肩までの黒髪をストレートに垂らし、髪の黒色と対照的な白を基調とした服を着こなす、整った顔をした小柄な女は、幹斗の目を引き付けるには十分な魅力を持ち合わせていた。
「エチオピアをフィルターでいただけるかしら?」
「かしこまりました。550円になります」
高めの声音で優雅に注文を済ませると、女は流れるように次の言葉を繋ぐ。
「ツケといて頂戴」
「いやどこに」
間髪を入れずに白羽が真顔ででつっこむ。
「いいじゃない、居候させてやってんだからツケぐらい。なんなら私の可愛さに免じてタダにしてくれてもいいのよ」
「こっちも商売なもんで。ちゅーか、なんで値引きを目論む人がそんな上からなんですか」
急に低めの声で女は白羽と会話を交わす。幹斗はひとまず、後からの方が彼女の素だろうということと、彼女がこの建物の所有者、あるいは関係者だろうということを把握した。なんだかんだ言いながら、バッグから財布を出しながら女は応える。
「はぁ。あんたは相変わらずケチね。550円ね────ってぇ!ここのコーヒー、一杯450円でしょうが!なんでさらっと100円多くかっぱらおうとしてんのよ!」
「あ、ばれたか」
「ばれたか、じゃないわよ!まったく────」
言いあうふたりを尻目に、見飽きた光景だと言わんばかりの顔をして、利玖がその場を離れる。自らの席に戻る途中で幹斗の横に止まり、幹斗に話しかけた。
「あの人は
「なるほど。というと、彼女が白羽の大学の友達ですか?」
「いや、それは弟のほう。俺とそいつと白羽が大学の同期。あ、俺バイトの時間近いしお暇するわ。それと、俺ら同い年だろうしタメ口でいいよ、幹斗クン。じゃあな!」
「・・・」
立て板に水にそう口にすると、幹斗に口を挟む隙すら与えず、自席にあったスマホを取ると、まだなにやら言いあっている白羽とふゆと、手持無沙汰な幹斗を置いて、足早に店の出入り口とは違う扉の奥へと消えていった。ここに居候していると言っていたし、自分の部屋に行ったのだろうか。幹斗が呆気にとられていると、
「あなたが白羽のお友達?可愛い顔をしてるわね」
いつのまにか近付いていたふゆが、幹斗に話しかけた。赤っぽい色の目が幹斗を覗く。しばらく男ばかりの職場にいる幹斗は、久しぶりに女性と話すことに緊張しながらも、会話に応じる。
「あ、はい。はじめまして。未井幹斗といいます」
「こちらこそはじめまして。麻澤ふゆです」
綺麗な笑顔でそういうものだから、なおさら幹斗の心臓は早鐘を打つ。
「俺の大切な友達なんだから、食おうとしないで下さいよ」
「そんなことしないって。私のことなんだと思ってるのさ」
カウンターの向こうで食器を動かしながら、白羽が軽口を挟む。
「なんでしょうね?はい、できましたよ」
そう言いながら、てきぱきとした手つきで、コーヒーカップをカウンターに差し出す。
「はぐらかすなよ・・・。カップは後で返すわ」
「了解です」
「幹斗くんも、また会いましょう」
「あ、はい」
呆れたような声でカップを受け取ると、ふたりを一瞥してから、ふゆは利玖が消えていった扉の向こうへ去ろうとする。しかし、ふと立ち止まってこちらを振り返った。
(壱の続き)
「そうだ、さっきおばあちゃんがお辞儀しながらこの店を出るのを見たわ。あんたら、また変なことに首突っ込もうとしてんじゃないでしょうね?」
「ご想像にお任せしますよ」
「────ったく。怪我はしないでよ。いちいちあんたらの治療とか看病すんの、面倒なんだから」
トゲのある事を言っていても、彼女の目はとても優しげで、本気でふたりを心配している事が幹斗にも見て取れた。そこまで言うと、彼女はすぐに前に向き直り、扉の奥に消えた。かつかつかつ、というヒールの音がフェードアウトする。店は、幹斗と白羽のふたりのみとなる。
「すまんな。騒がしくて」
「いやいや、明るいのはいいことだよ」
幹斗は白羽にそう返すと立ち上がり、空になったコーヒーカップと皿を持ってカウンターに歩き、白羽に返す。
「もっと話してたいのは山々なんだが、そろそろ集合の時間なんだ」
左手首に巻いた腕時計の文字盤を見ながら、ペアを組んでいる組織犯罪対策部の刑事の言った、休憩後の集合時間を思い出す。あと15分ほどだった。
「そうか。がんばってな。また来てくれよ」
「ああ、勿論だ」
白羽は幹斗から受け取った食器を洗いにかかりながら、幹斗は椅子にかけたジャケットを腕にかけて、出入り口に向かいながら、会話を交わした。言葉数は少なかったが、ふたりにはこれで十分だった。また会える。また話せる。そのことを思えば、余計な言葉は不要だった。
外に出て、背後で扉の閉まる音を聞き、幹斗は空を見上げる。
鮮やかな色を纏った雲が浮かんでいた。
高い空に輝く太陽は、やけに柔らかな光で幹斗を包んだ。
弐
大親友との思わぬ邂逅から幾日かが過ぎた日の昼間、白畑白羽は自ら切り盛りするカフェで、一人静かに本の世界に浸っていた。ドアの外には開店を示す看板をかけてはいるが、昼前のこの時間に訪れる客はまずいない。カウンターの横にあるアンティーク調の肘掛椅子に深く座り、文字の連なる頁 を捲る。彼の至福のひとときだ。
そこにふと、音もなく栗色の翼を持った常連客が訪れる。ちゅん、という小さな声で白羽は来客に気付く。
「いらっしゃい。今日もいい天気だね」
手をひらひらと振ってみる。問いかけの意味を知ってか知らずか、開け放った窓の枠にとまる小鳥は白羽を見て再び啼く。そのかわいらしい様子に思わず目尻が下がる。
「もう行くのかい。元気でね。また明日」
いつもと変わらない挨拶をすると、小鳥は窓の外に向き直り、色の変わり始めた街路樹の覗く青空へと飛び立った。
かんかんかん、と柔らかい靴底が鉄の段を叩く音が白羽の鼓膜を揺らしたのは、そんな時だった。腿の上に置いた栞を頁の隙間にさし、横目でカウンターのエスプレッソマシンの陰にある、山吹色の物体を載せた皿を確かめる。
きぃ、と控えめな音とともに扉がゆっくりと開けられ、奥からこちらを窺うように、見慣れた懐かしい顔が覗く。
立ち上がって本を椅子に置き、見知った来客に笑顔を見せる。
「いらっしゃいませ。今日は何にいたします?」
「え、えっと…じゃあエチオピアのフィルターで」
「かしこまりました」
自分の前で大人ぶろうとしている幹斗に、ついつい口元が緩む白羽だった。前の時のふゆの注文を真似したのだろう。
「にやにやすんなよ白羽ぁ」
「ふふっ。なんか可笑しくてついな」
恥ずかしそうにこちらを睨む幹斗は、先日とは違い、ラフな黒いTシャツにジーンズ、それに何より目を引く真っ赤なスニーカーに身を包んでいる。
「今日は非番でさ、暇だったから来てやったんだよ」
拗ねたような口調で幹斗は話を逸らす。コーヒー豆を挽きつつ、カップやサーバーを用意しながら幹斗に応じる。
「そうだったのか。相変わらず赤いの好きだな」
「そう。何だかんだ赤が一番好きだな」
「お前が変わってなくて安心したよ」
「そっちも大して変わらないな」
「なら良かった。でも見た目は随分大人っぽくなったよな」
「大人になったんだよ。もう何歳だと思ってるんだ。つーかこの会話前にもしたろ」
「そうだっけか。俺が永遠の144歳って話か」
「なんで数日見ないうちに年齢が二乗されてんだ────」
実に阿呆らしくて楽しい会話だった。そこで出来上がったコーヒーをカップに注ぎ、味見用のカップにも少し注いで、素早く呷って出来を確かめる。満足のいく味に口角を上げ、フレンチトーストの載った皿とともに幹斗のもとへ運ぶ。
「!また気を使ってもらって悪いな」
「ええよ。俺が好きでやってる事だから」
幹斗の両の眼は揃って運ばれてきた山吹色のトーストに釘付けになっている。今にも涎を垂らしそうだな、なんて思った。
「そういえば、何で時々方言っぽい話し方なんだ?地方にでも行ってたのか?」
フレンチトーストにがっつきながらも、白羽に話を振ってくる。自分には無いその自然な気遣いと明るさは幹斗の魅力のひとつだ。特に親しい仲でないでない限りは、用事でもないと自分から他人に話しかけることができない白羽にとっては、とてもその気質は羨ましい。白羽はいつも、自分は他人によく思われていないと意識してしまうので、友人と思っていても、自分からは一定以上に距離を縮めない。それで誤解されることも無きにしも非ずなのだが。
「今読んでる本の登場人物の影響かな。特に好感の持てるキャラだと、方言ってよう伝染るやん?」
肘掛椅子に置いたハードカバーの本を指し示す。
「おぉーん。なるほど」
「お前本読まないやろ」
「失敬な。本ぐらい読むさ、三冊くらい…」
「週に?」
「月に!」
予想通りの反応だ。昔から、白羽は学校の授業中も読書をするくらいに読書家だったが、幹斗は正反対のタイプだった。
「まあ、警察官だとそんな時間ないのか?」
「まあな」
「まだ組対の人と聞き込みしてんのか?」
「そんなところ。悪い人じゃないんだけど、暴力団と日頃相対する人だからさ、なかなか心臓に優しくないんだわ」
「あー、想像できるな」
何人か警察に知り合いがいる身として、組対の人々の異質さを想像するのは難しくない。あくまで想像だが。
「他の部に人借りるほど人手が足りないって、何があったんだ?」
「この辺りの組────なんだっけ?黒龍会?が武器の製造とか輸出をしていて────って捜査情報じゃん」
「おっとすまねぇ。あとそれ白竜会な。黒龍じゃあ国が滅びちまう」
(弐の続き)
危うく機密(?)を漏らしかけた幹斗に雑に片手で謝罪し、懐かしいゲームのネタを交える。止 めるのは得意だ。依然として騒ぐ胸に語りかけ────言い聞かせ、新たな来客のために笑顔をつくる。
「懐かしいな。でもそれなら白羽ひとりで倒せるだろ?」
「いつの話だよ。今じゃ腕が鈍ってて無理だって」
「その昔は何体狩ったんだ?」
「四、五十体くらい?」
「なら大丈夫だな」
「じゃあペアで狩ろうぜ」
「俺以外の人でよろ」
「俺の相棒はお前しかいないぜ!」
そこまで言って、フレンチトーストの最後の一切れを飲み込んだ時に、幹斗は何かを思い出したような仕草をした。
「ん、この前来た時にさ、何か相談してたおばあさんいたよな?あの件どうした?」
「ああ、あれな。丁度いい」
そこで言葉を区切り、意味ありげな(特に意味の無い)笑みを浮かべる。それを受け、何かを察したようにキリッとした顔をつくる。
「今日の夜、その件について動く予定なんだよ」
「ほう。家出少女だったっけ?」
「そうそう。今夜利玖と、件の少女が一緒にいるっていう不良たちの集会に凸る予定だ」
つい最近から町のコンビニの周りにたむろしている不良がいるという噂も耳に入っていたので、飛んで火に入る夏の虫、という具合だ。もう立秋は過ぎているが。
「危ないことにならないか?大丈夫か?」
心配しているのだろう。幹斗が問いかける。
「大丈夫。そんな事にはならんと思う」
「んー、でも心配だから俺も着いてくわ」
「えっ────暴力沙汰も噂される連中だぞ?危ないからよせよ」
「それなら尚更だ。俺も行く」
やれやれ、と白羽は思った。この顔をした幹斗の意思を曲げる────曲げさせるのは不可能に近い。幹斗と同じだけの熱量で言い合う気力は、今の白羽には無かった。よって妥協をする。妥協が良い結果に転ばないことを、白羽はよく知っているが、そこで白羽は妥協を選んだ。
────選んでしまった。
「そこまで言うなら仕方ない。着いてきてもらうか。今夜九時にそこの階段の下に集合でいいか?」
「ああ」
言うと、空になったカップと皿をおもむろにカウンターに返してくる。「ありがとう」と返してシンクにそれらを置き、扉へ向かう幹斗を送るため、カウンターを回り込んで幹斗に近寄る。
「じゃあ、また」
「うん、また夜に」
短い挨拶を交わすと、幹斗は扉の向こうへ歩き、扉が閉まるとともに階段を叩く音も消える。
別れ際の幹斗は固い顔をしていて、何を思っていたか、白羽には伺い知れなかった。白羽は人より、他人の心情を察する能力に長けた男だったが、自分が関わると、途端に相手の心が見えなくなる。何か悪いことをしてしまっただろうか。白羽の胸は俄にざわつく。しかし、そう考え込むのは一瞬だった。再び階段を叩く音が聞こえてくる。幹斗の靴とは違う音だ。思考を止めて、カウンターへと戻る。
大丈夫、思考を
扉がきぃ、と開いていく。
「いらっしゃいませ」
参
白畑白羽と未井幹斗の二度目の邂逅と同日。窓枠に置かれた、紅く色づき始めた丸い葉を携えた多肉植物の鉢植えが、短い影をモザイクタイルの上に落とす頃。幹斗の去ってしばらくした店内には、三人の人間がいた。蒼浪 工場のことか?」
一人は白畑白羽。例のアンティーク調の肘掛椅子に、瞼を軽く落として腰かけている。しかし意識はあるようで、腿に置いた右手の指をゆったりと動かしている。
もう一人は荒田利玖。いつものように目を輝かせ、カウンターの席に座り、隣に腰かける、少し薄めの白髪を整髪料で丁寧に撫で付けた男に体を向けている。
利玖の隣に座る男は、所在なさげに腰の位置を動かしていた。そんな男に、らちが開かないとばかりに、焦れた利玖が話しかける。
「で、何があったって言うんです?」
男は依然として目を泳がせる。
「あの、信じてもらえるか…というか、言ってもいいものか…」
「嘘でわざわざここまで来ないでしょう。それに、信じるかどうかはこちらの問題です。言っていただかないと、何も始まりませんよ」
目を瞑ったままで、白羽が諭すように言う。男はそれでも、数十秒ほど逡巡する素振りを見せたが、やがて意を決したように、口を開いた。
「私の友人に、小さな町工場をやってる者がいるのです」
「隣町の
「その通りです。ご存知でしたか」
「ああ。小規模だが、優れた技術を持っているってどこかで聞いた」
利玖は普段から相手の年齢に気兼ねすることがほとんどないため、敬語を使って話すことは不得手だった。大学を出てからは特に敬語を使う機会が減ったので、相手が年上とはいえ、この態度は致し方なかった。
「私はとっくに仕事を定年で辞めていますが、そいつはまだ工場にいるので。気が向いた時には、工場に顔を出しに行くんです」
男は利玖の口調に気分を害された様子もない。
「それが…今週の月曜日だったかな。いつものように工場を訪ねたら、普段は開いている門が閉まっていたんです」
「でも、たしかその日は祝日でしたよね?」
「普段は祝日でも工場を閉めることはないはずなんです。そして、金曜日にも訪ねました。その時も、門扉は閉まっていた。流石に気になったので、門扉に登って中を覗きましたが、人の姿はおろか、明かりも点いていなかったんです」
男は自分でも不可解という顔をしながら、流暢に話している。確かに不可解な話ではあった。
「休みの日はあるのか?」
「土日と、年末年始やお盆などの時ぐらいです」
「ふぅん…確かに妙だな」
「今日は、この事を相談しに来たんです。なんとか調べていただけませんか?」
助けを乞うような目で、利玖に訴える。
「分かった。調べてみる。他になにか手掛かりはあるか?」
「…あ、そうだ!その日のうちに、そいつの家を訪ねました。本人か、或いは家族が出てくれるかと思ったんですが…」
「────返事はなかったと」
「そうです。こんな老人の足で分かることはほとんど無くて…申し訳ない」
「構わない。それを調べるのが俺の仕事────いや、趣味だ。任せてくれ。あとのことだが────」
もう一人。その会話に耳を澄ませていた者がいた。
なんとはなしに、店と他の階へと続く階段を隔てる扉に背を預けて話を聞いていた麻澤ふゆは、そこまで聞くと、扉に凭れていた体を起こし、自室のある上の階への階段へ歩みを向けた。
かつかつかつ、という彼女のヒールの音は、階段室に静かに反響するのみで、店内の三人の耳に届くことはなかった。
今週おやすみ 来週こそ書きます
がんば!こっちもがんばるよっ
今週おわりそうでやばい。お互いがんばろ
うん!
4月中には投稿したいところ(休校措置がとられているなかで、いろんな人に少しでも喜びを与えたい)
…なんでもないです
そもそも見てくれる人がいるかどうかについては触れないでおこう
私は6×6さんの小説毎回楽しみにしてるけど…ね!
というか、この小説をもっと広めたい。いろんな人に読んでもらいたいなぁ
>> 24そう思ってもらえる人が1人でもいるのありがたい(´︶`)
書くの楽しいから頑張ってね
完結したらpixivにも上げるつもりだけど、読み手いないのは確かw宣伝よろw
宣伝しときますーー
6×6様、この置き場を私の掲示板の説明欄に貼らせていただくことは可能でしょうか?
>> 27願ってもない話です!是非是非。
私の掲示板の説明欄に書いた通り、「Night Park憩いの場」にて紹介します。
ご協力ありがとうございます!
肆
時計の針が頂点でひとつになった頃。夜のそよ風が、黄色く色づき始めた街路樹の葉と、未井幹斗の頬を吹き抜ける。一日に二回もこの道を辿るのは初めての事だった(日付が変わっいるかもしれないが、そこは気にしない)。自宅からは十数分程。薄暗い町に目が慣れはじめると、昼にも訪れた年季の入った階段の下に、ふたつの人影が見えてくる。ひとつは、背が高く細長いシルエット。針金細工にも似た手足を、寒色で無地のセーターに袖を通した白畑白羽だ。もうひとつは、白羽よりも二回りほど小柄でがたいのいいシルエット。肌寒い秋の夜にも関わらず、黒っぽい半袖シャツで動きやすい格好をした荒田利玖だ。
「よう」
「おう」
片手をあげて軽く応答をする。セリフだけを抜き取れば軽薄なムードだが、幹斗は二人の間にある言い知れぬ静かな重みを感じていた。だいいち、前会った時には積極的に話しかけてきた利玖が、おざなりに手を振るだけで、軽口すら叩かない。そう思った時に、
「じゃあ、全員揃ったことだし、出発しますか」
空気を変えるようにぱんっ、と両手を打ち鳴らして、利玖が口を開いた。
「うん。そうしよう」
応える白羽も、先のような重い雰囲気は無い。
「こんな時間に、悪いな」
「いや、行くって言い出したのは俺の方だからな」
そう幹斗に声をかける白羽を見て、幹斗は学生の部活の試合前みたいだな、と感じた。緊張する部分もあるが、それでいてどこかわくわくしている所が二人にはあった。
利玖が「四丁目のコンビニだよな?」と言いながら先導して歩き出す。目的地への道はわかりきっている様子だ。
こうやって白羽と肩を並べて歩くのはいつ以来だろう。小学校の頃は、度々こうして歩くことがあった。しかし中学で道を違えてからは、そんなこともすっかり無くなった。それでも、やはりこの男が隣に居るのはとても居心地がよかった。自然と、同じ歩調で歩ける。
少し過去に思いを馳せていた幹斗の頬を、夜風が再び撫でた時、行く手に闇夜には不似合いな明かりが見えた。
「ひとまず俺らが相手をしてくる。幹斗は後ろで控えていてくれ」
「分かった」
幹斗の承諾を聞くと同時に、白羽は片手をあげる仕草をして、足早に利玖の背を追い抜いた。
きっと、白羽のことだから、不良相手にも上手く言いくるめて穏便に済ますのだろう。そんな風に楽観的に捉えていた。暴力沙汰になどならないと、どこかでそう思っていた。
幹斗は、そんな自分を後に後悔することになる。
片田舎特有の、敷地の広いコンビニ。面積の半分を駐車スペースが占めているが、こんな夜中に車でコンビニを訪れるような変わり者は居ないようだ。敷地の少し奥まった所に、平たい建物が光っている。コンビニの外には、店内の明かりを背に四つの人影。
布陣は変わって白羽が先頭、敷地の僅かに外に待機する幹斗、その中間辺りに利玖がいる形になる。白羽が真っ直ぐに不良達の所へ向かうと、一人が相対する様に歩み寄ってきた。
「なんだいあんた。買い物客、には見えねぇけどよ」
店の明かりから少し離れたことで、多少は造形が把握出来る。粗雑に白羽に話しかけた男は、肩まである髪が、店の明かりを茶色く透かしていた。身長は白羽より頭半個分ほど低いか。
「その通り。面倒な前置きは省いて単刀直入に言わせてもらおう。馬場みおさん、後ろにいるだろう?彼女は家出をしていて、連れ戻して欲しいと彼女の家族に頼まれたんだ。と、言うわけだ。彼女と話させてもらおうか」
本当に端的に要件を述べ、男の横を通ろうとした白羽だったが、男は白羽を通そうとはしなかった。
「ミオは家に帰るつもりはないぜ。そうだろ?」
男が後ろを振り返りつつそう問うと、後ろにいる人影のひとつが頷いた。きっとその人影が件の孫娘なのだろうが、幹斗の位置からでは、逆光でその顔は窺えない。
「────というわけだ。お帰り願おうか」
「そう言われてもねぇ。こちらにも、こちらの事情があるんだ。話くらいはさせてくれよ」
男は凄むような口調で言ったが、白羽は気にした様子もない。音のない睨み合いが続いた。数分、いや数秒だったかもしれない。やがて男の方が口を開いた。
「ちっ…あくまでそのつもりなら、こっちもこっちで考えがある────ぜっ!」
男は一息に拳を振り抜いた。
「────っと。随分気が早いねぇ」
身体を後ろに引いて拳を躱した白羽は依然として余裕を崩さない。そしてそのまま後ろ向きに歩いてくる。
同時に歩き出した利玖と入れ替わるように。
今度は利玖が男と対峙する。手を伸ばせば触れるような間合いに思える。
男は声を荒らげながら利玖に殴りかかる。
「今度はなんだ────っおぉ!?」
次の瞬間、セリフを言い終わることも出来ずに、男はアスファルトに尻餅をついていた。
早すぎる回し蹴りだ。男が殴り掛かる瞬間、利玖は微かに右足を引いていた。恐らくそこから左足を軸に高い回し蹴りを放った。幹斗の目には、利玖と男の頭のシルエットを黒い影が通ったのを見た。しかし、瞬きを終えた頃にはもう右足は最初と同じ位置に戻っていた。
「何してんだてめぇ」
前の男が倒されたのを見て、慌てたように後ろにいた仲間が右手にバットを持って歩み出てくる。
大股で間合いを詰めると、二人目の男はバットを頭上に振りかぶり、袈裟斬りの軌道で利玖の頭を目掛けて振り下ろした。
「────っ!?」
が、その手には何も握られていなかった。男の驚愕の声が、アスファルトに落下したバットの鳴らす軽い音と重なる。
利玖の右足は、とうに同じ位置に戻っている。
今度は前蹴りだった。バットの持ち手を正確に狙った蹴り。しかも、先程のように利玖の身体は微動だにしていないように、後方にいる幹斗には見えた。相当鍛えられた体幹が無ければそんな動きは不可能だ。
再び、利玖の右足が動いた。
「────っう!?」
(肆の続き)
最初と同じ、目で追えないような速度の回し蹴り。頽 れる頃には、利玖の右足は定位置に戻っている。
勿論、男が
二人目の男もアスファルトの地面に尻を付けたのを見て、利玖は、いつものような軽い口調で口を開いた。
「さ、お話しようか」
尻餅をついた二人の表情が安らかでないのは、逆光でも見て取れた。
二人の恐怖の表情を見て、幹斗の中で、嫌悪に似た何か黒いものが生まれた。
いつの間にか幹斗の近くへ寄ってきていた白羽が、顔を前に向けたまま話しかける。
「な、危ないことにはならなかっただろ?後は事情を聴いて、家に返すかどうするか決めるだけだ」
いたって軽い口調で、そう口にする。
────こんなの、ただの暴力による制圧じゃないか。
その言葉は幹斗の心の声か、それとも幹斗の口から発せられたのか、分からない。
ただ、目に映った光景は、自分の望んだ景色ではなくて。
対話する気がない相手にいくら言葉を尽くしても意味が無い。それはもっともだ。たけど…だけど、他に何かあるんじゃないのか?平和的解決が、穏便な結果が。
不可能なのは頭では分かってる。でも、白羽なら、あいつなら、俺が驚くような手際であの場を切り抜けられるんじゃないか。
そもそも俺は、何を望んでいたのだろう?
何を願い、何を、白羽に、押し付けていたんだろう?
幹斗は、走った。
どこへ向かうつもりもなかった。でも、どこかへ行きたかった。逃げたかった。頭に焼き付いた、去り際に視界の端に捉えた親友の表情を振り切るように。
足が縺れる。息が切れる。
やがて立ち止まり、膝に手を付き、肩で息をする。これほど走ったのはいつ以来だろう。ひたすら酸素を貪る。頭が揺れる。視界が揺らぐ。頬を掠める風すら煩い。視界の端を、茶色く乾いた街路樹の葉が、嘲笑うように通り過ぎる。
交番に勤務したこともある。不良の相手をしたことは一度や二度ではなかった。その時も、相手が話し合いを放棄したら闘うことしかできなかった。他に手はないのか、そう思いながら倒れ伏せる不良を眺めたこともあった。
自分が不器用な自覚はあった。だから、自分と違って器用な白羽なら、冴えたやり方を知ってると、そう思っていた。
勝手に期待して、勝手に失望した。
言葉にすればそんなものだった。決して、白羽達が悪かった訳では無い。そう、正当防衛と言える。だけど…
白羽に何を言ったか、覚えていない。でも、何かを言った。言ってしまった。走り出す直前に見た顔は、瞳に光が無かった。もしかしたら、それは、白羽の瞳に映った自分の顔だったかもしれない。
頭を冷やそう。
今日はもう、何も考えたくない。
────こんなことになるなら、会わなければよかった
未井幹斗は、屍のような歩みで、家路を辿った。
空は、厚い雲に覆われていて、地上の微かな光を反射して薄い色を放っていた。
伍
すっかり空は暗くなっている。後ろ向きに歩いてくる白羽とすれ違った時。心地よい温度の夜風が、興奮で少し火照った荒田利玖の頬を冷やす。空を切った 右脚が一秒前と同じ位置に戻る。空振り ができる。
左足を少し前に、剣道の中段構えを左右反転したような足の配置で立ち止まる。目の前、2歩ほど先には自分より少し頭の位置の高い男。利玖は夜目が利く方ではない。なので、コンビニの光で逆光となっている男は、利玖にはシルエットしか見えていない。
だが、問題ない。仄かな興奮に刺激された利玖の全神経が、目の前の男の気配と殺気を明瞭に捉える。居心地のいい空気。意識しなくとも、自然に口角が上がってゆく。
男が近づくことで、二人を隔てる空間が、互いの手が容易に届くほどに押し込まれた時。腰を時計回りに思い切り振り切る。
世界が廻る。右脚は一秒前と同じ位置に置かれている。ふたつの瞳が再び男を捉える。
刹那、置き去りにされた右脚が遅れを取り戻さんと速度を上げて男の顔へ迫る────!
「今度はなんだ────っおぉ!?」
────
一瞬遅れて、男の尻がアスファルトに接地する。その顔には、「恐怖」という文字が貼り付けられているようだった。否、それは恐怖以前の「驚愕」だったかもしれない。
身体の軸をぶらさず、容易に相手の顔面の高さまで足を届かせる回し蹴り。利玖が修得している格闘技、カポエイラの基本的な技「アルマーダ」だ。脚を高く上げる仕様上、近い間合いでも
決して無意味な暴力は使わない。それは昔から、白羽との暗黙の了解だった。血の気が多く闘うことは好きだが、利玖も暴力は好まない。
「何してんだてめぇ」
後ろからもう一人の男が歩いてくる。長めの得物を右手に持っているが、殺気には鈍りがある。先の光景への怯えを、虚勢で誤魔化しているつもりなのだろう。
男は虚勢を振り切るように、バットを振り上げながら大股に迫ってくる。
振り下ろされるバットの手元を直感──本人曰く、野生の勘──で先読みし、両腕と腰を揃えて時計回りに回しながら、上半身とは逆向きに振り上げる右脚の先で手元を狙う。
「────っ!?」
バットを的確に蹴り飛ばしたことを、脚の神経が脳髄に伝えるより早く、上半身と右脚を元の位置に戻す。
得物を手元から失ったことで、男は驚愕の表情を浮かべ、動きを止める。当然の反応だ。その隙は逃さない。
一撃目の勢いを殺さぬように、再び腰とともに上半身を回転させる。
一度の暗転を経て、両眼で数センチ上の相手の顔面を認める。
一度目の蹴りの反動を逃がすように、回りそこねた右脚を相手の顔面に向けて解き放つ。
「────っう!?」
戦闘の興奮で活性化した動体視力によって、右足が相手の目前数センチを通過したのを知覚する。
二人目の男が尻餅を着く前に、空を切った右脚を再び定位置に戻す。
男の表情まで、一人目の焼き直しだった。
前方への蹴り技「メイア ルーア ジ フレンチ」から「アルマーダ」の連携だ。勿論、アルマーダは空振りだし、一撃目もバットを蹴っただけで相手の手には掠りもさせていない。
戦闘とも言えないやり取りではあったが、実戦という緊張感のなかで、「空振り」という当てるよりも難しいことをやってのけたという快感は、確かに利玖の頭に心地よい痺れを与え、自然と利玖の口角も上がり、軽薄な言葉が口を飛び出す。
自覚できるほど緩みきった満面の笑みで、利玖は言う。
「さ、お話しようか」
自分の背後から聞こえた微かな話し声は、決して利玖の耳に届くことは無かった。
街路樹を吹き抜ける深夜の冷たい風が、利玖の頬から熱を奪っていった。
陸
家出少女の一件は無事、平和的解決を見た。あの後、四人の少年少女達と穏便に話し合うことができた。
件の家出少女の家出のきっかけは、ただの親子喧嘩だったと言う。特に大きな事件があった訳ではなかった。家出の勢いのまま、前から少し絡みがあった不良達と合流して一緒に過ごしているうちに(なんと野宿していたと言う。なかなか豪快な子供達だ)引っ込みがつかなくなった、ということらしい。少女も近いうちに帰る気はあったということなので、これを機に家に一旦帰る、と言ってくれた。"一旦"というのが気にならないでもなかったが、そこは利玖達が嘴を挟むべきことではない。
他の三人の不良達にも、家に帰れみたいな説教こそしなかったが、不用意に他人に暴力を振るわないこと、コンビニの店員や客に迷惑をかけないこと、はきつく言い含めた。喧嘩腰から直れば、十分話の通じる青年たちだった。二番目にかかってきたアオイという青年など、淀みなく敬語を話すほどだ。きっと育ちのいい子なのだろう、アオイと会話を交わしながら、利玖はそんなどうでもいい思考を巡らせた。
三人は、前までコンビニから数百メートルほど離れた私有地の一部をたまり場にしていたらしい。ちょっと立派な公園ほどのサイズの私有地で、手入れがまともに行われているようにも見えず、年中樹木が鬱蒼としている小山、というのが地元の人間の認識だ。暴力団の敷地、という噂もあるが、利玖としては半信半疑だ。全体に年季の入ったフェンスが張られていて、入口と思しき場所は、フェンスがかなり奥まっているので、恐らくその空間にたむろしていたのだろう。誂えたように錆びたドラム缶なんかも転がされていた覚えがあるので、適当に駄弁るにはうってつけだろう。
しかし、最近そのたまり場に妙な男達が来るようになった。いや、正確には入口付近のフィールドではなく、入口の奥、森の中に入っていくという。初めは横目で睨まれる程度だったが、やがて来訪者の人数が増えてくると、「この場から消えろ」と怒鳴られるようになった。私有地であることは理解していたので仕方なく、フェンスの破れ目の奥に消える男達に背を向けて、すぐ近くのコンビニに不良達は移動した、ということらしい。
コンビニの店長からしたら迷惑極まりないだろうが、話は理解した。妥協案として、利玖は近くの手頃な空き地を教えてやって、そこに移るよう勧めることにした。いいことではなくとも、違う人間同士、生きていくには妥協──或いはグレーゾーン──が必要というのが利玖の持論だ。ひとまずの解散を少年少女に促し、最後に夜遅くにも関わらずレジに立っていたコンビニの店長にことの次第を報告して、あの場は丸く収まった。
────しかし、丸く収まらない問題もあった。
そう頭の中でぼやきながら、荒田利玖は闇夜の下、背の高いいかにも厚そうな塀を右手に歩いている。
角を折れると、塀が途切れて夜の暗さに紛れるような黒色の門が目に映る。すぐ横には、星の明かりでもよく分かるほど赤錆に塗れた鉄板に「蒼浪工場」の文字が刻まれて、独り塀にくっついていた。門の隙間から中を窺う。更にそこから自分の周囲に視線を這わす。人影は無い。そう認識すると、二メートルほどの門の上部に右手をかけ、右脚を前後に振って勢いをつけてから、身体を振り上げつつ息を吐く。
「ふうっ」
掛け声(掛け息?)に溜息をないまぜにして、一息に門を飛び越える。
硬い床面とお気に入りの赤いシューズがぶつかって、とん、と軽い音を鳴らす。
こういう隠密行動みたいなのは、やっぱり俺向きじゃねぇよなぁ。再び頭の中でぼやきを零して、足元を見やる。お気に入りのシューズの赤が、暗いせいかやけにくすんで見えた。
コンビニでの一件から数日、依頼を受けた例の工場に、利玖は一人で侵入している。本来、潜入のような事柄は白羽の担当だった。しかし、あれ──丸く収まらなかった問題──以来、白羽は生気を失ったように、茫然自失の体となってしまった。それ故、蒼浪工場の潜入(侵入)に、利玖自ら出張ってきているということだ。
あの時自分の背後で何があったのか、未だに利玖は知らない。白羽に詮索することもしなかった。正直、あの場から幹斗がいなくなっていたことからも大方の想像はつく。自分のやり方は、あの純粋そうな目をした男には刺激が強かったのだろう。まぁ、白羽と幹斗の問題だ。それは二人の問題で、二人がどうにかするべき問題だ。普段から人懐っこい人間でいようと心掛けている利玖だが、自分が手を出すのは自分の両手が届くところまで、と決めている。
それはともかく、今は工場の偵察だ。
足音をなるべくさせないようにして(人がいないのなら意味が無いかもしれないが)、工場の大きな扉へ近づく。作るものは多岐にわたる、と聞いていたが、果たしてこんな大きな扉が必要なものだろうか、と思いつつ、手元の閂錠を動かす。
閂を動かして解錠した。閂でない錠をかける所もあったが、そこには施錠されていないようだ。というか、そこに施錠されていたら閂は動かない仕組みらしい。
それなりに鍛えた腕でも力を込める必要のある分厚い扉を、数十センチほど隙間を空けて身体を滑り込ませる。
すぐに扉が閉まる重低音が腹の底まで響き渡る。
残響が途切れた。雑音の聞こえない、静寂。高い位置にあるはめ殺しの窓から射し込む柔らかな星あかりだけが、利玖の瞳に色を挿す。
扉の前で数分立ち尽くしていれば、やがて暗闇に目が慣れる。工場内に、物々しい機械類が所狭しと並んでいるのが見えてくる。
何をどうする機械なのか、工業にはまるで縁のなかった利玖にはさっぱり分からないが、なんとなくのパーツは分かる。一番手近な機械の操作部のような部分に手を這わせる。ボタンや小さなレバーがあるのを指先が感じ取る。
しかし、それだけではなかった。薄い埃が指先にまとわりつく。
いなくなったと思われる日から一週間ほど。それ以来誰もこの機械に触っていないのは確かなようだった。工場内に人の気配が無いことを確かめながら、ゆっくりと工場の奥へと利玖は歩を進めた。
一時間くらい経っただろうか。一応の用心をして、門ではなく塀を乗り越えて外に出る。今度は歩道のアスファルトとシューズのぶつかる音がする。白羽は足音を立てない技術や気配を消す技術、人の気配を察知する技術に秀でている。やはり自分の仕事ではないとつくづく感じる。しかし、白羽が動けないのなら自分が動くしかない、それが今の自分にやれる、自分の手が届く唯一のことだと信じる。文字が書かれていないはずがない 。
大した収穫は無かったが、手がかりならあった。否、手がかりと言うには心許ない。ただの糸なのかもしれない。何処に続いているのか、果たして何かに辿り着けるのか、それすら怪しい一本の糸。
一枚の紙を、街灯に照らさせて内容を読み取る。懐中電灯を持っていれば持ち出さずに済むのだろうが、今回は白羽の流儀に則って完全なる手ぶらで来ていた。結論から述べると、とても後悔した。奴は身軽でいいと言うと思うが、正直懐中電灯はあった方がいい。俺はお前ほど夜目は利かないんだよ。まだ自分の家で落ち込んでいるであろう相棒に悪態をつく。
街灯の光を薄く反射した紙面を見る。専門の用語や記号はまるで分からないが、何かの設計図であることは理解出来た。工場の机の上に一枚だけ置いてあった紙だ。これは重要なモノかもしれないと、野生の勘が告げたので持ってきたが、当たりかもしれない。
黒い(ペンで書いてあれば当たり前だが)四角柱のような物体の周りに、記号や数字が並んでいる。それだけだった。
だが、それはおかしい。記号と数字のみ。漢字はおろか、平仮名も、アルファベットすら書かれていない。もしこれが工場の人々の失踪と無関係な書類なら、
つまり、これは暗号化されているということだ。
確かな手応えを握りしめながら、利玖は帰路へ着く足を早めた。
季節に相応しいつむじ風が、歩道に植わる木々の葉を激しく揺らした。近くの公園に立つ背の高い時計は、逢魔ヶ刻を少し過ぎた時を静かに刻んでいた。
1コメントに書ける量増えた?
気のせいだったわ
50行以内、4000文字以内が制限かな?
そーーなのか!
そう!長文書いていると「行が多すぎます。50行以内に~」とか「文字が多すぎます。4000文字以内に~」って出てくる。
オーナーの管理やな
こっちは12000に増やしてる。
なるほど