陸
家出少女の一件は無事、平和的解決を見た。あの後、四人の少年少女達と穏便に話し合うことができた。
件の家出少女の家出のきっかけは、ただの親子喧嘩だったと言う。特に大きな事件があった訳ではなかった。家出の勢いのまま、前から少し絡みがあった不良達と合流して一緒に過ごしているうちに(なんと野宿していたと言う。なかなか豪快な子供達だ)引っ込みがつかなくなった、ということらしい。少女も近いうちに帰る気はあったということなので、これを機に家に一旦帰る、と言ってくれた。"一旦"というのが気にならないでもなかったが、そこは利玖達が嘴を挟むべきことではない。
他の三人の不良達にも、家に帰れみたいな説教こそしなかったが、不用意に他人に暴力を振るわないこと、コンビニの店員や客に迷惑をかけないこと、はきつく言い含めた。喧嘩腰から直れば、十分話の通じる青年たちだった。二番目にかかってきたアオイという青年など、淀みなく敬語を話すほどだ。きっと育ちのいい子なのだろう、アオイと会話を交わしながら、利玖はそんなどうでもいい思考を巡らせた。
三人は、前までコンビニから数百メートルほど離れた私有地の一部をたまり場にしていたらしい。ちょっと立派な公園ほどのサイズの私有地で、手入れがまともに行われているようにも見えず、年中樹木が鬱蒼としている小山、というのが地元の人間の認識だ。暴力団の敷地、という噂もあるが、利玖としては半信半疑だ。全体に年季の入ったフェンスが張られていて、入口と思しき場所は、フェンスがかなり奥まっているので、恐らくその空間にたむろしていたのだろう。誂えたように錆びたドラム缶なんかも転がされていた覚えがあるので、適当に駄弁るにはうってつけだろう。
しかし、最近そのたまり場に妙な男達が来るようになった。いや、正確には入口付近のフィールドではなく、入口の奥、森の中に入っていくという。初めは横目で睨まれる程度だったが、やがて来訪者の人数が増えてくると、「この場から消えろ」と怒鳴られるようになった。私有地であることは理解していたので仕方なく、フェンスの破れ目の奥に消える男達に背を向けて、すぐ近くのコンビニに不良達は移動した、ということらしい。
コンビニの店長からしたら迷惑極まりないだろうが、話は理解した。妥協案として、利玖は近くの手頃な空き地を教えてやって、そこに移るよう勧めることにした。いいことではなくとも、違う人間同士、生きていくには妥協──或いはグレーゾーン──が必要というのが利玖の持論だ。ひとまずの解散を少年少女に促し、最後に夜遅くにも関わらずレジに立っていたコンビニの店長にことの次第を報告して、あの場は丸く収まった。
────しかし、丸く収まらない問題もあった。
そう頭の中でぼやきながら、荒田利玖は闇夜の下、背の高いいかにも厚そうな塀を右手に歩いている。
角を折れると、塀が途切れて夜の暗さに紛れるような黒色の門が目に映る。すぐ横には、星の明かりでもよく分かるほど赤錆に塗れた鉄板に「蒼浪工場」の文字が刻まれて、独り塀にくっついていた。門の隙間から中を窺う。更にそこから自分の周囲に視線を這わす。人影は無い。そう認識すると、二メートルほどの門の上部に右手をかけ、右脚を前後に振って勢いをつけてから、身体を振り上げつつ息を吐く。
「ふうっ」
掛け声(掛け息?)に溜息をないまぜにして、一息に門を飛び越える。
硬い床面とお気に入りの赤いシューズがぶつかって、とん、と軽い音を鳴らす。
こういう隠密行動みたいなのは、やっぱり俺向きじゃねぇよなぁ。再び頭の中でぼやきを零して、足元を見やる。お気に入りのシューズの赤が、暗いせいかやけにくすんで見えた。
コンビニでの一件から数日、依頼を受けた例の工場に、利玖は一人で侵入している。本来、潜入のような事柄は白羽の担当だった。しかし、あれ──丸く収まらなかった問題──以来、白羽は生気を失ったように、茫然自失の体となってしまった。それ故、蒼浪工場の潜入(侵入)に、利玖自ら出張ってきているということだ。
あの時自分の背後で何があったのか、未だに利玖は知らない。白羽に詮索することもしなかった。正直、あの場から幹斗がいなくなっていたことからも大方の想像はつく。自分のやり方は、あの純粋そうな目をした男には刺激が強かったのだろう。まぁ、白羽と幹斗の問題だ。それは二人の問題で、二人がどうにかするべき問題だ。普段から人懐っこい人間でいようと心掛けている利玖だが、自分が手を出すのは自分の両手が届くところまで、と決めている。
それはともかく、今は工場の偵察だ。
足音をなるべくさせないようにして(人がいないのなら意味が無いかもしれないが)、工場の大きな扉へ近づく。作るものは多岐にわたる、と聞いていたが、果たしてこんな大きな扉が必要なものだろうか、と思いつつ、手元の閂錠を動かす。
閂を動かして解錠した。閂でない錠をかける所もあったが、そこには施錠されていないようだ。というか、そこに施錠されていたら閂は動かない仕組みらしい。
それなりに鍛えた腕でも力を込める必要のある分厚い扉を、数十センチほど隙間を空けて身体を滑り込ませる。
すぐに扉が閉まる重低音が腹の底まで響き渡る。
残響が途切れた。雑音の聞こえない、静寂。高い位置にあるはめ殺しの窓から射し込む柔らかな星あかりだけが、利玖の瞳に色を挿す。
扉の前で数分立ち尽くしていれば、やがて暗闇に目が慣れる。工場内に、物々しい機械類が所狭しと並んでいるのが見えてくる。
何をどうする機械なのか、工業にはまるで縁のなかった利玖にはさっぱり分からないが、なんとなくのパーツは分かる。一番手近な機械の操作部のような部分に手を這わせる。ボタンや小さなレバーがあるのを指先が感じ取る。
しかし、それだけではなかった。薄い埃が指先にまとわりつく。
いなくなったと思われる日から一週間ほど。それ以来誰もこの機械に触っていないのは確かなようだった。工場内に人の気配が無いことを確かめながら、ゆっくりと工場の奥へと利玖は歩を進めた。
一時間くらい経っただろうか。一応の用心をして、門ではなく塀を乗り越えて外に出る。今度は歩道のアスファルトとシューズのぶつかる音がする。白羽は足音を立てない技術や気配を消す技術、人の気配を察知する技術に秀でている。やはり自分の仕事ではないとつくづく感じる。しかし、白羽が動けないのなら自分が動くしかない、それが今の自分にやれる、自分の手が届く唯一のことだと信じる。
大した収穫は無かったが、手がかりならあった。否、手がかりと言うには心許ない。ただの糸なのかもしれない。何処に続いているのか、果たして何かに辿り着けるのか、それすら怪しい一本の糸。
一枚の紙を、街灯に照らさせて内容を読み取る。懐中電灯を持っていれば持ち出さずに済むのだろうが、今回は白羽の流儀に則って完全なる手ぶらで来ていた。結論から述べると、とても後悔した。奴は身軽でいいと言うと思うが、正直懐中電灯はあった方がいい。俺はお前ほど夜目は利かないんだよ。まだ自分の家で落ち込んでいるであろう相棒に悪態をつく。
街灯の光を薄く反射した紙面を見る。専門の用語や記号はまるで分からないが、何かの設計図であることは理解出来た。工場の机の上に一枚だけ置いてあった紙だ。これは重要なモノかもしれないと、野生の勘が告げたので持ってきたが、当たりかもしれない。
黒い(ペンで書いてあれば当たり前だが)四角柱のような物体の周りに、記号や数字が並んでいる。それだけだった。
だが、それはおかしい。記号と数字のみ。漢字はおろか、平仮名も、アルファベットすら書かれていない。もしこれが工場の人々の失踪と無関係な書類なら、


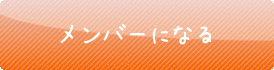




つまり、これは暗号化されているということだ。
確かな手応えを握りしめながら、利玖は帰路へ着く足を早めた。
季節に相応しいつむじ風が、歩道に植わる木々の葉を激しく揺らした。近くの公園に立つ背の高い時計は、逢魔ヶ刻を少し過ぎた時を静かに刻んでいた。