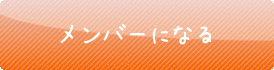『フレンチトーストの香りとともに(仮)』
零
────あの出会いは、偶然か。必然か。
「はぁ・・・」
残暑を感じさせる日差しの中、
念願の刑事部に配属されて早五日。人出が足りないとして組織犯罪対策部にレンタルされている幹斗は、連日聞き込みを手伝わされていた。やけに眩しい太陽の所為か、僕は何部になったんだっけか、と自分の記憶すら曖昧になってくる。
吹き抜けるそよ風が、街路樹のまだ夏の色を残した葉を揺らす。
そこで、ふと微かな香りが、アスファルトの匂いに辟易していた鼻腔をくすぐる。
これまで趣味の時間を多く持ってこなかった幹斗には、その香りが焙煎されたコーヒー豆のものだとは、まるで分からなかったが、その芳醇な釣り糸は確かに迷える魚を手繰り寄せた。
僅かな糸を頼りに、しばらく道を歩いた。
そして香りの源はここだろうと思しき、少し年季の入った煉瓦造りの建物に辿り着き、足元の「Cafe Asanoha 2F」という看板に従って側面の階段をのぼる。赤茶けた段のきぃ、という抗議のような音にも耳を貸さずに、幹斗は、開店を示す小さな看板のかかる木製のドアを開けた。
ドアを開けるとともに、芳醇な香りが奔流となって幹斗を包み込む。
そのささやかな幸せに体を預けるのもそこそこに、幹斗は店内を見やる。
向かって左手のすぐ手前には大仰な機械やコーヒーカップの置かれたカウンター、右手にはいくつかのシンプルな椅子とテーブルが並んでいて、窓に近い席には、二十歳くらいの男が一人窓の外を見るように座っている。
男は、入ってきた幹斗をちらりと一瞥したが、すぐに視線を戻した。短く刈られた頭と濃い赤色の半袖シャツは、落ち着いたこの空間にはやや不釣り合いにも見えた。
そしてもう一人。カウンターの奥にある、他とは違うアンティーク調の肘掛椅子に腰掛け、ハードカバーの本を読んでいる。幹斗とさして変わらない年齢に見えるが、綺麗にアイロンがけされているであろうシャツと、錫色のベストとズボンが誂えたように似合う男だ。
小さめの眼鏡をかけて本を読んでいた彼は、客の来訪に気付くと、一瞬、目を丸くしたが、すぐに本を閉じて立ち上がり、分厚い本を椅子の座面に重ね、柔らかな笑みを浮かべて幹斗に声をかける。
「いらっしゃいませ。お好きな席にお座り下さい」
「あ、はい、コーヒーひとつ」
「かしこまりました。フィルターでよろしいですか?」
「はい」
おざなりに返事と注文をすまし、近くの椅子に座る。コーヒーなど成人してから飲んだ試しもなかったが、とにかく今は、身体が水分を欲していた。
ようやく座って一息ついて、幹斗はたった今自分の注文を受けた男の顔をぼんやりと眺める。
整髪料で適度に撫でつけられた黒髪に、落ち着いた顔つき。細長い両手が、きびきびと器具を動かす。
「どこかで・・・」
彼の顔に要領を得ない懐かしさを感じ、ぼそっと呟いた幹斗の声は、彼がコーヒー豆を引く音にかき消された。
しばらくして、
「お待たせ致しました」
こと、と上品な音を奏でて、白い湯気をたたえたコーヒーカップがソーサーと共に着地する。
「あっ────」
儀礼的に礼を言おうと顔を上げて、固まる。幹斗の脳内に疑問符が飛ぶ。
彼の細長い左腕の先には、コーヒーを机に置いたにも関わらず、まだ白い皿が載っていた。
もう一人の男が何か頼んでいたようにも思えない。そう考え、彼の目を見やると、彼もその視線に気付いたように、
「あぁ、この皿ですね。お疲れのようだったので、不躾ながら軽食を、と思いまして」
そういって皿に載ったフレンチトーストを幹斗に見せる。鮮やかな山吹色の表面に、栗色の焦げ目が控えめながらもよく映えていた。その甘美な香りは、コーヒーよりも強く幹斗の鼻腔を惹きつける。
フレンチトーストは、幹斗の大好物だった。
「余計なお世話でしたら、すぐにお下げします。好物かと思ったのですが、違いましたか?」
幹斗の瞳を見返して、そんなことを口にする。
「えっと・・・あなたは・・・」
「何でしょう?」
「いえ────」
違う。僕がこの人に呼びかける名は、そうじゃない。
柔らかい細目。少し高めの声色。細長い手指。回りくどい気遣いと少し意地悪な笑み。何もかもが懐かしく、幹斗の脳細胞を心地よく刺激する。
意を決して、呼吸を整え、再び彼のチョコレート色の瞳に目を合わせ、できる限りの笑顔をつくり、こう口にする。
「久しぶりだな、
白羽と呼ばれた男も、先程の様に柔らかに、しかし先程よりも快活に笑って応えた。
「そうだな、幹斗」
こうして、かつて大親友と呼びあった未井幹斗と