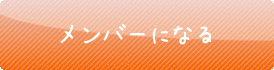参
白畑白羽と未井幹斗の二度目の邂逅と同日。窓枠に置かれた、紅く色づき始めた丸い葉を携えた多肉植物の鉢植えが、短い影をモザイクタイルの上に落とす頃。幹斗の去ってしばらくした店内には、三人の人間がいた。
一人は白畑白羽。例のアンティーク調の肘掛椅子に、瞼を軽く落として腰かけている。しかし意識はあるようで、腿に置いた右手の指をゆったりと動かしている。
もう一人は荒田利玖。いつものように目を輝かせ、カウンターの席に座り、隣に腰かける、少し薄めの白髪を整髪料で丁寧に撫で付けた男に体を向けている。
利玖の隣に座る男は、所在なさげに腰の位置を動かしていた。そんな男に、らちが開かないとばかりに、焦れた利玖が話しかける。
「で、何があったって言うんです?」
男は依然として目を泳がせる。
「あの、信じてもらえるか…というか、言ってもいいものか…」
「嘘でわざわざここまで来ないでしょう。それに、信じるかどうかはこちらの問題です。言っていただかないと、何も始まりませんよ」
目を瞑ったままで、白羽が諭すように言う。男はそれでも、数十秒ほど逡巡する素振りを見せたが、やがて意を決したように、口を開いた。
「私の友人に、小さな町工場をやってる者がいるのです」
「隣町の
「その通りです。ご存知でしたか」
「ああ。小規模だが、優れた技術を持っているってどこかで聞いた」
利玖は普段から相手の年齢に気兼ねすることがほとんどないため、敬語を使って話すことは不得手だった。大学を出てからは特に敬語を使う機会が減ったので、相手が年上とはいえ、この態度は致し方なかった。
「私はとっくに仕事を定年で辞めていますが、そいつはまだ工場にいるので。気が向いた時には、工場に顔を出しに行くんです」
男は利玖の口調に気分を害された様子もない。
「それが…今週の月曜日だったかな。いつものように工場を訪ねたら、普段は開いている門が閉まっていたんです」
「でも、たしかその日は祝日でしたよね?」
「普段は祝日でも工場を閉めることはないはずなんです。そして、金曜日にも訪ねました。その時も、門扉は閉まっていた。流石に気になったので、門扉に登って中を覗きましたが、人の姿はおろか、明かりも点いていなかったんです」
男は自分でも不可解という顔をしながら、流暢に話している。確かに不可解な話ではあった。
「休みの日はあるのか?」
「土日と、年末年始やお盆などの時ぐらいです」
「ふぅん…確かに妙だな」
「今日は、この事を相談しに来たんです。なんとか調べていただけませんか?」
助けを乞うような目で、利玖に訴える。
「分かった。調べてみる。他になにか手掛かりはあるか?」
「…あ、そうだ!その日のうちに、そいつの家を訪ねました。本人か、或いは家族が出てくれるかと思ったんですが…」
「────返事はなかったと」
「そうです。こんな老人の足で分かることはほとんど無くて…申し訳ない」
「構わない。それを調べるのが俺の仕事────いや、趣味だ。任せてくれ。あとのことだが────」
もう一人。その会話に耳を澄ませていた者がいた。
なんとはなしに、店と他の階へと続く階段を隔てる扉に背を預けて話を聞いていた麻澤ふゆは、そこまで聞くと、扉に凭れていた体を起こし、自室のある上の階への階段へ歩みを向けた。
かつかつかつ、という彼女のヒールの音は、階段室に静かに反響するのみで、店内の三人の耳に届くことはなかった。