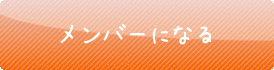弐
大親友との思わぬ邂逅から幾日かが過ぎた日の昼間、白畑白羽は自ら切り盛りするカフェで、一人静かに本の世界に浸っていた。ドアの外には開店を示す看板をかけてはいるが、昼前のこの時間に訪れる客はまずいない。カウンターの横にあるアンティーク調の肘掛椅子に深く座り、文字の連なる
そこにふと、音もなく栗色の翼を持った常連客が訪れる。ちゅん、という小さな声で白羽は来客に気付く。
「いらっしゃい。今日もいい天気だね」
手をひらひらと振ってみる。問いかけの意味を知ってか知らずか、開け放った窓の枠にとまる小鳥は白羽を見て再び啼く。そのかわいらしい様子に思わず目尻が下がる。
「もう行くのかい。元気でね。また明日」
いつもと変わらない挨拶をすると、小鳥は窓の外に向き直り、色の変わり始めた街路樹の覗く青空へと飛び立った。
かんかんかん、と柔らかい靴底が鉄の段を叩く音が白羽の鼓膜を揺らしたのは、そんな時だった。腿の上に置いた栞を頁の隙間にさし、横目でカウンターのエスプレッソマシンの陰にある、山吹色の物体を載せた皿を確かめる。
きぃ、と控えめな音とともに扉がゆっくりと開けられ、奥からこちらを窺うように、見慣れた懐かしい顔が覗く。
立ち上がって本を椅子に置き、見知った来客に笑顔を見せる。
「いらっしゃいませ。今日は何にいたします?」
「え、えっと…じゃあエチオピアのフィルターで」
「かしこまりました」
自分の前で大人ぶろうとしている幹斗に、ついつい口元が緩む白羽だった。前の時のふゆの注文を真似したのだろう。
「にやにやすんなよ白羽ぁ」
「ふふっ。なんか可笑しくてついな」
恥ずかしそうにこちらを睨む幹斗は、先日とは違い、ラフな黒いTシャツにジーンズ、それに何より目を引く真っ赤なスニーカーに身を包んでいる。
「今日は非番でさ、暇だったから来てやったんだよ」
拗ねたような口調で幹斗は話を逸らす。コーヒー豆を挽きつつ、カップやサーバーを用意しながら幹斗に応じる。
「そうだったのか。相変わらず赤いの好きだな」
「そう。何だかんだ赤が一番好きだな」
「お前が変わってなくて安心したよ」
「そっちも大して変わらないな」
「なら良かった。でも見た目は随分大人っぽくなったよな」
「大人になったんだよ。もう何歳だと思ってるんだ。つーかこの会話前にもしたろ」
「そうだっけか。俺が永遠の144歳って話か」
「なんで数日見ないうちに年齢が二乗されてんだ────」
実に阿呆らしくて楽しい会話だった。そこで出来上がったコーヒーをカップに注ぎ、味見用のカップにも少し注いで、素早く呷って出来を確かめる。満足のいく味に口角を上げ、フレンチトーストの載った皿とともに幹斗のもとへ運ぶ。
「!また気を使ってもらって悪いな」
「ええよ。俺が好きでやってる事だから」
幹斗の両の眼は揃って運ばれてきた山吹色のトーストに釘付けになっている。今にも涎を垂らしそうだな、なんて思った。
「そういえば、何で時々方言っぽい話し方なんだ?地方にでも行ってたのか?」
フレンチトーストにがっつきながらも、白羽に話を振ってくる。自分には無いその自然な気遣いと明るさは幹斗の魅力のひとつだ。特に親しい仲でないでない限りは、用事でもないと自分から他人に話しかけることができない白羽にとっては、とてもその気質は羨ましい。白羽はいつも、自分は他人によく思われていないと意識してしまうので、友人と思っていても、自分からは一定以上に距離を縮めない。それで誤解されることも無きにしも非ずなのだが。
「今読んでる本の登場人物の影響かな。特に好感の持てるキャラだと、方言ってよう伝染るやん?」
肘掛椅子に置いたハードカバーの本を指し示す。
「おぉーん。なるほど」
「お前本読まないやろ」
「失敬な。本ぐらい読むさ、三冊くらい…」
「週に?」
「月に!」
予想通りの反応だ。昔から、白羽は学校の授業中も読書をするくらいに読書家だったが、幹斗は正反対のタイプだった。
「まあ、警察官だとそんな時間ないのか?」
「まあな」
「まだ組対の人と聞き込みしてんのか?」
「そんなところ。悪い人じゃないんだけど、暴力団と日頃相対する人だからさ、なかなか心臓に優しくないんだわ」
「あー、想像できるな」
何人か警察に知り合いがいる身として、組対の人々の異質さを想像するのは難しくない。あくまで想像だが。
「他の部に人借りるほど人手が足りないって、何があったんだ?」
「この辺りの組────なんだっけ?黒龍会?が武器の製造とか輸出をしていて────って捜査情報じゃん」
「おっとすまねぇ。あとそれ白竜会な。黒龍じゃあ国が滅びちまう」