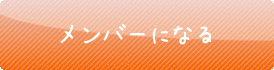壱
白羽は変わらないな。幹斗はそう思った。実に10年ぶりの邂逅だというのに、白羽も幹斗もまるで10年前、いやそれより前の、同じ教室で机を並べていた頃のように、気負うことなく会話を交わした。
「へぇ。お前が警察か。しばらく見ないうちに立派になったなぁ」
「年明けに会う親戚のおじさんかお前は」
「随分大きくなったねぇ」
「今度はおばあちゃんか。いったい何歳なんだよ。同い年じゃん。つーかお前の方がよっぽど背高いだろ」
「俺は永遠の12歳だよ。ちなみに身長は185ないくらい」
「いい歳して何言ってんだ。やっぱ背高いな────」
幹斗は白羽に会わなくなってからもしばらく成長していたが、それでも白羽に比べて10cmほどの開きがあった。
少し会話に間隙ができたので、今度は幹斗から白羽へ、この店について質問を投げる。
「あー、この店はもともと大学でできた友達のお爺さんの店だったんだけど、継ぐ人がいなくてさ。そこでその友達伝いで俺に話が来て。当時からコーヒー屋で働いてたから、願ってもない話だと思って働かせてもらってたん」
「なるほど。じゃあそのお爺さんは?」
幹斗は言いながら店内を見回してみるが、相変わらずテーブルにスマホだけ置いて、何をするでもなく窓の外をぼんやり見つめている赤い半袖シャツの男以外、視界に入る人物はいない。
「うん、まあ、あそこにいるはいるよ」
曖昧な返答をしながら、白羽はカウンターの奥を指し示す。
「あ・・・」
白羽が指し示したカウンターの奥の棚にある、小綺麗な縁に入った柔らかな顔をした壮年の男性の写真を見て、幹斗は言葉を詰まらせる。
「そう。矍鑠としたお爺さんだったんだが、去年に脳をやっちまってな。それ以来あそこで呑気に笑ってるよ」
「・・・すまない」
「構わんよ。遅かれ早かれ、誰の身にも訪れることだし、そのお陰といっちゃなんだが、それからはこの店は俺がやらせてもらってるからな」
そういって白羽は、一瞬見せた暗い影を落とした顔を、無機質な笑顔で上塗りする。その笑顔は、10年会わなかったといえども大親友である幹斗ですら、一瞬分からないほどに精巧に作られていた。
「えっと────」
「あ」
気まずい沈黙に耐えられなくなって口を開けようとした幹斗を制するように、白羽が声を零して幹斗が先ほど入ってきた扉に目を向ける。つられて幹斗も同じ方向を見やると、扉の奥から、こつんこつん、とのんびりとしたテンポで靴底が階段を叩く音が微かにするのを感じる。
「すまんな、また後で」
そう言って片手で謝罪の形を作ると、足早にカウンターへ戻る。すると、タイミングを図ったように緩やかにドアが開けられ、全体的に地味な色の服を着、重ねた月日の分だけ頭を白く染めた女性の姿が現れる。
「いらっしゃいませ」
自然な笑顔で女性を迎えると、女性もそれに応え、カウンターの席に座りながらなにやら話し始めるが、その控えめな声は、幹斗の耳には、明瞭には届かない。
カウンターの様子を窺うのを諦め、幹斗は思い出したように、目下でまだ湯気をたたえるコーヒーカップとフレンチトーストに目を向ける。なにも考えずにコーヒーを頼んでしまったが、コーヒー飲めないじゃん、と数分前の自分を責める。しかし、大親友が淹れてくれたコーヒーだし、飲めないことは無いはず、と自分を奮い立たせ、白磁のコーヒーカップの取っ手を掴みあげ、勢いよくその中に満ちる艶のある黄櫨染にも似た色の液体を口に含んだ。
「!」
意外にも美味しかった。口を通る液体は、高めの温度と心地のよい酸味と甘み、仄かな苦みを伴って舌を包み込む。やがて飲み下すと、街中で嗅いだ芳醇な香りが再び鼻腔をくすぐりながら通り抜ける。調子の付いた幹斗は、続いて右手をフォークに持ち替え、黄金色のフレンチトーストを食しにかかる。フレンチトーストは、適度なはちみつの甘みがよくパンの味を引き出していて、とても幹斗好みの味に仕上がっていた。パンの程良いしっとり感が堪らなく味覚を刺激する。
流石に、そのフレンチトーストが初めから幹斗のために作られていたと思うほど、幹斗は自惚れていなかったが、その慣れ親しんだ美味と新しい美味は、確かに幹斗の疲労を癒し、五分もしないうちに、ふたつの器は空気を載せるのみとなった。
空腹と疲労を失い、満足感に浸っていた幹斗は、なんとはなしに、再びカウンターの話し声に耳を傾ける。
「────ということなんです。なんとかお願いできませんか?」
「なるほど・・・えっと────」
体力の回復からか、先ほどよりは、明瞭に会話の断片が聞こえてくる。白髪の女性が何かを白羽に頼みこんでいるようだ。白羽は困ったように曖昧な笑みを浮かべている。
がた、と唐突に椅子を無遠慮に動かす音が、静かな店内に響く。音のした方向は、最初から店内にいた半袖シャツの男のいた辺りだ。不思議がって幹斗がそちらを振り向くより早く、男は幹斗の横を通り抜けて、カウンター席に向かい、ふたりに話しかける。横を通る瞬間、幹斗は男が笑みを浮かべていたように見えた。
「すみません、お話、横から聞かせてもらいました。俺が力になりますよ」
「えっ?あなたは・・・?」
男の突然の言動に、女性も驚かされているようだ。そこにやれやれ、といった笑顔で、白羽が助け船を出す。
「こいつは
「そうなんですか!どちらにしろ、孫をお願いします!」
「任せてください!」
「善処します」
素性が分かると同時に、女性は嬉しそうな声で、もう一度ふたりに何かを頼みこむと、「ありがとうございます。お願いします」と重ねて言って、慌ただしく席を立つ。
「ありがとうございました」
白羽はそう言って、帰る客を見送る。女性は再び謝辞を重ねてお辞儀をすると、扉の向こうへと消えていった。こつんこつん、と軽やかな音が遠くなり、再び店内が静かになったところで、幹斗は白羽に今のやり取りについて尋ねた。
「さっきのお客さんのお孫さんが、家出して不良みたいな連中とつるんでるから家に連れ戻してほしいってさ。いつからか、どこかの物好きの所為で、ここは街の人たちの相談所────万屋みたいになってるんだよ」
白羽はそう言って、となりで満足げな笑みを浮かべる男を見やる。